【前編】「いじめ」への処方箋 ~いじめ問題を真正面から描いた小説5選~

決してなくならない、いじめ。2013年に制定された「いじめ防止対策推進法」では、いじめは「犯罪」と位置づけられ、2019年に刊行された山崎聡一郎『こども六法』は、いじめられている子どもへ、法律を味方に悩みを解決する方法を示し、話題を呼んでいます。法律のみならず、小説の分野でもいじめ問題に真正面から向き合った作品は少なくありません。いじめを真摯に考える小説を、前編・後編の2回にわたって紹介します。今回は前編の3作品です。
いじめられる方には原因はないと、本当に思っていますか? その建前にきれいごとなしに切り込んだ――川上未映子『ヘヴン』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4062772469
近著『夏物語』において、希望が持ちにくい現代に子を成すことは、「おめでた」などではなく、親の究極のエゴではないかと問題提起し、多くの読者の反響を得た芥川賞作家・川上未映子。川上は、大人になった私たちが蓋をしてやり過ごしている物事に、きれいごとはなしで切り込んでゆくことに定評のある作家で、本作『ヘヴン』では、一般的によく言われる、「いかなる場合も、いじめる方が悪いのであり、いじめられる方に非はない」という建前を再検証する試みがなされています。
本作の主人公は中学生の「僕」。極度の斜視を揶揄するあだ名をつけられたり、チョークやトイレの水を無理に飲み食いさせられたりしている「僕」は、斜視を治す手術を受けるか悩んでいます。これに対し、クラスメートの女子で、不潔だという理由で「生ごみ」呼ばわりされていじめられているコジマは、「僕」が手術を受けることに反対します。
“お父さんは働いても働いてもお金がない人で、お母さんはお金のある人と再婚して、わたしはこっちに越してきたのよ。わたしが汚くしてるのは、(貧乏な)お父さんを忘れないように。お父さんと一緒に暮らしたってことのしるしのようなもの。君は斜視で、そのせいでひどい目に遭っていて、つらいことだけれどでもそれがいまの君って人をつくっているってこともたしかだと思うの。わたしは、君の目がとてもすき。”
いじめられる要因がはっきりしているならそれを改善すればいいという意見に、コジマは
“『自分がされたらいやなことは、他人にしてはいけません』っていうのは、インチキだよ。自分がされたらいやなことなんてみんな平気でやってるじゃないか。肉食は草食を食うし、いつだって強い者は弱いものを叩くんだ。自分がされたらいやなことからは、自分で身を守ればいいんじゃないか”
いじめっ子たちの「弱肉強食」の理論は、多くの人が心の底では認めていながらも、見ないふりをしてやり過ごしている、いわば人間の本質を突く指摘です。「僕」は自分の身は自分で守るため、いよいよ斜視の手術を受ける方向に心を傾けてゆくのですが、それは同時に親友コジマを裏切ることでもありました。コジマは「僕」に訴えます。
“君は、その目を治してわたしから逃げたいと思ってるんじゃないの。でも、わたしは(汚い服を着ることを)やめないから。君もわたしも、弱いからされるままになってるんじゃないんだよ。あいつらの言いなりになってただ従ってるだけじゃないんだよ。目のまえでなにが起こってるのか理解して、受け入れてるのよ。それはむしろ強さがないとできないことなんだよ”
いじめられても仕返しせず、ただ黙ってそれを引き受けるやり方こそが正義だと信じ、自分の考えを貫くコジマ。「僕」は、コジマを見限って、最終的に斜視を治すのでしょうか? それとも、そのままにしておくのでしょうか? どちらを選択することが、「僕」にとっての「ヘヴン(天国)」となるのか、結末は本書で確かめてください。
少女2人はなぜ手をつないで飛び降りなければならなかったのか? 女子特有の陰湿ないじめを描く――井上荒野『あたしたち、海へ』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4104731056/
人間関係の機微を繊細な筆致で描くことに定評のある直木賞作家・井上荒野。本作は、作者が、女子中学生2人が手をつないで飛び降りたという実際に起こった事件に触発されて筆を執ったという意欲作です。
私立の女子校・桐ヶ丘女子中学一年生の、
“そんなのはおかしいと、誰も言わなかった。海だけが言ったのだ。不公平だよ、と。海はくじを引かなかった。有夢と瑤子は引いた。引いたほうがいいよと海に何度も言ったけど、海は頑として意思を曲げなかった。引かないひとは、自動的に選手になってもらおう、とルエカが言った。海は、アンカーに決定、ということになった。全部ルエカたちが決めた。そして誰も反対しなかった。マラソン大会の当日、海は学校に来なかった。ボイコットしたのだ。アンカーはルエカが務めた。翌日から、誰も、海に話しかけなくなった。”
有夢も瑤子も、本当は分かっているのです。ルエカたちのやり方がいかに不条理かということも、海の言うことが正論だということも。けれど、容姿が華やかで運動神経抜群、クラスの中心的な位置を占めるルエカたちに楯突いたら、ここでは生きていけないということも、有夢と瑤子はまた、痛いほど分かっているのです。マラソン大会が終わった後も、海と今まで通り仲良くしようとする有夢と瑤子。2人はルエカに呼び出され、こう問い質されるのでした。
“有夢と瑤子はどっち側の人なの?”
有夢と瑤子は、海には申し訳ないと思いつつも、長い物には巻かれよと、ルエカの側につかざるを得なくなったのです。それから突然、海が桐ヶ丘女子校から20キロ離れた公立中学へ転校することが決まるのでした。するとルエカは、有夢と瑤子に海の転校先を無理やり調べさせ、転校先の校門前で以下のような内容のビラをばら撒いて来るように命じたのです。
“H市立第二中学校のみなさまへお知らせ そちらの学校に転校した野方海は、最低の裏切り者です。クラスが一丸となって、優勝をめざしていたマラソン大会は、彼女の卑怯な裏切りのおかげで、負けました。責任を逃れるために、海は転校しました。とても自分勝手で性格の悪い子です。そちらの学校でも、みなさんにいやな思いをさせるかもしれません。よく気をつけてください。 桐ヶ丘女子学園 中等部生徒一同”
これではまるで、クラスの和を乱した悪者が海で、一致団結を目指して頑張ったルエカたちが被害を被ったように取れてしまいますが、こうした、加害者が被害者になりすます巧妙なやり口にも、女子特有の陰湿さが見え隠れします。ルエカは海に対して暴言を吐くわけでもなく暴力を振るうわけでもなく、いわば、自らの手を汚さずにいじめを遂行したのです。
心根の優しい有夢と瑤子はビラを撒きながらも、海への罪悪感で追い詰められてゆきます。しかし、ルエカに背いたら、今度は自分たちがいじめの対象になることは火を見るより明らかです。数か月後、海が転校先の学校でも不登校になったと風の噂で聞いたルエカは、勝ち誇ったようにこう言うのでした。
“せっかく転校したのにねえ。転校したって海は海だもんね。世界の果てまで行ったって(学校でうまく人間関係を作ることなんて)無理だよね。”
ルエカたちは、自分たちの書いたビラのせいでというよりはむしろ、海自身がもともと持っている性質のためにいじめられたのだと、責任転嫁しています。
有夢と瑤子の様子がおかしいことを、周りの大人たちは薄々感じてはいるのです。しかし、担任の若い女性教師は「気のせいかもしれない」、両親たちは「思春期だから」と、無理やり自身を納得させてやり過ごしてしまいます。そこには、子どもの世界への手出しの出来ない無力さが残酷なまで描き出されるのです。
ルエカの有夢らへの要求は日増しに加速し、遠方の海の学校まで放課後毎日ビラを撒きに行き、証拠写真をスマホで撮ってくるよう指示されます。わずかな抵抗をした有夢らの椅子には、濡れた泥まみれの雑巾が毎日置かれるようになりました。
つらい状況の中で、2人が束の間現実を忘れられるのは、耳にイヤフォンを差し込んで、お気に入りのリンディの音楽を聞いているときだけでした。リンディの新譜「ペルー」を聞いて、2人は、自分たちもいつかペルーへ行きたいと夢想します。ペルーに行こう、というのはやがて2人の合言葉になり、それは現実のペルーという国のことではなく、ここではないどこか、といった意味合いを帯びてゆきます。ここではないどこかへ行くための方法を、2人は模索するようになるのです。
“何度も乗ったことがあるロープウェイだ。瑤子はペルーのことを考えた。ゴンドラのドアをちらりと見る。中からは開かない仕組みになっているのだろうか。ドライバーとか持っていたら、開けられるかもしれない。ふたりきりで乗せてもらわないとだめだけれど。人が乗らないような時間を狙って、ふたりで乗る。ドアをこじ開け、手を繋いで一、二、三で飛ぶ。ペルーへ。”
2人が飛んだ先は、2人が望むようないじめのない世界なのでしょうか? そこで3人は元通り仲良く暮らせるのでしょうか? 少女たちの行動に最後まで目が離せません。
いじめがあるのを知っていて何もしない傍観者は、一番罪深いかもしれない――高橋弘希『送り火』
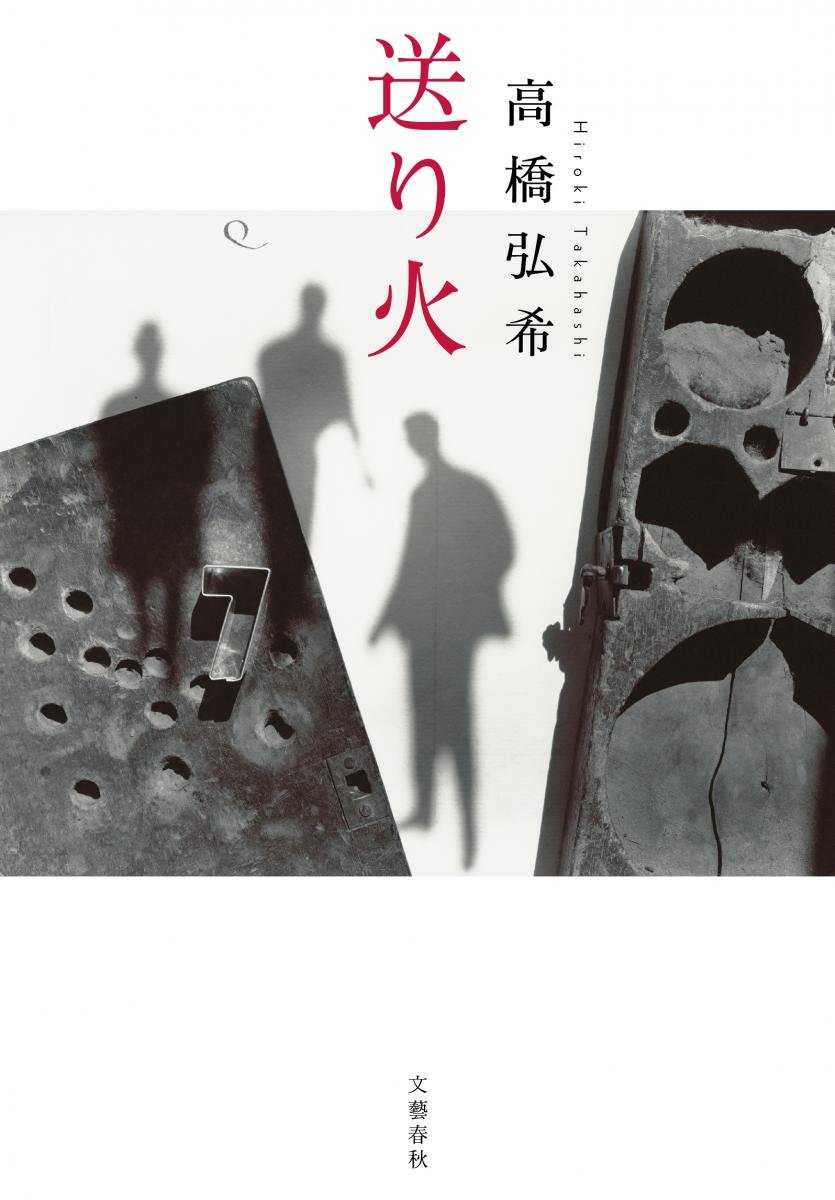
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163908730/
高橋弘希は、本作『送り火』において、田舎の閉塞的な環境で起こる悲惨ないじめを克明に描写し、第159回芥川賞を受賞しました。
本作の主人公は中学3年の男子生徒・
“休み時間、歩は一人の少年に話しかけられた。切れ長の一重瞼、形の良い鼻梁、薄い唇――。初対面の歩に対してはっきりものを言う。彼は学級の中心的人物だと直感した。転校を繰り返したせいか、歩は学級の力関係を把握することに長けていた。”
その中心的人物は晃という名でした。歩はクラスでの立ち回りが上手く、すぐに新しい環境に馴染みます。ある日の放課後、歩は、5人の男子から「
“晃はコンクリートに小瓶を置いた。小瓶には赤字で“硫酸”と記されていた。皆がどよめいた。晃は生きたバッタへ溶液を傾けていく。(バッタは)頭部と胴体が腐食するように焼け爛れていき、やがて絶命した。六本の試験管の一本に、硫酸が混じっている。燕雀でドボンになった者が、どれか一本の溶液を手の甲にかける。”
さすがにこれは危険だと、止めようとする歩ですが、晃に、この学校の伝統に背く気かとにらまれ、郷に入りては郷に従わざるを得なくなるのです。やがて稔へのいじめは加速し、何度も屈伸運動をさせてめまいを起こさせたところへ首を絞めてかかる、ということまで行われます。歩は稔に同情しながらも、本心では、
“面倒はご免だ。自分は残り少ない中学生活を平穏に過ごし、何事もなくこの土地から離れていきたい。高校に入学すれば、どうせ彼らも渡り鳥のことなど忘れてしまうのだ。”
と思っています。いじめを見て見ぬふりをして、何とか一学期の間をしのぐのでした。
“七月二十日、通知表が配られた。歩の“生活の記録”の“公正・公平”の欄にプラスが記されていた。――四月から加わった新しい仲間ですが、上手く学級に溶け込むことができて先生も安心しました。その優れた協調性は、社会に出てからも役立つでしょう。”
教師には問題の本質が全く見えていないようです。いじめを傍観している自分に対し、「公正・公平」と評価する教師を、歩は皮肉交じりに眺めるのでした。歩はこのままずっと第三者的立ち位置をキープするつもりでしたが、そうはさせない事件が起こるのです。夏休み、歩が晃たち5人と集っていると、そこへ中学の卒業生たちがやって来て、「サーカス」なる遊戯をしようと提案するのです。それは、花札で負けた者を後ろ手で縛り、三つ又の農機具で突いたり、大きな球の上へ乗せた挙句バランスを崩させて横転させるといういじめでした。皆の予想通りターゲットにされた稔はしかし、思わぬ反撃に出るのです。
“稔の右手で、銀色の光が瞬いた。何らかの刃物を手にしている。男達は皆、稔から距離を取るように、森の端へと退いた。歩もとにかく距離を取ろうと、立ち上がろうとしたとき、強い力で後方へと押し倒された。降り下ろされた一打は、歩の耳のすぐ横に突き刺さった。「わだっきゃ最初っから、おめぇが一番ムガついでだじゃ!」
稔は歩を殺そうとしている。なぜ自分が稔の標的にされているのか、理解できない。自分は暴力に加担していないし、嘲笑もしていないのに、なぜ――”
稔が攻撃した相手は、意外にも、いじめっ子の晃たちではなく、傍観者の歩でした。いじめをそれと分かっていながら、気づかないふりをして、上手に世渡りする歩に、稔は一番腹が立ったのでしょう。いじめ問題の加害者、被害者、傍観者のうち、「傍観者の罪」に焦点を当てた作品です。
おわりに
前編では3作品をご紹介しました。さまざまな視点から、いじめについて考えさせられる作品ばかりです。後編もぜひ、お楽しみに。
初出:P+D MAGAZINE(2021/03/08)

