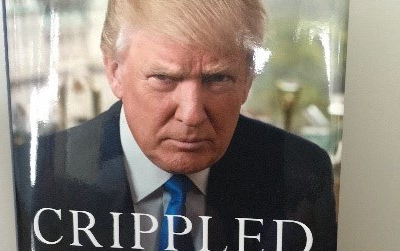デビュー作品完結に10年費やした作家・福永武彦
文壇に、福永武彦の存在を知らしめた長編『風土』。10年の歳月をかけて完成したというこの処女作に寄せて、長男である池澤夏樹氏が、あとがき解説を寄稿しています。どんな言葉が綴られているのか…、ぜひチェックしてみてください。
没後37年経た今でも、叙情性豊かな詩的世界の中に、鋭い文学的主題を見据えた作品の数々で、根強いファンを多く抱える作家・福永武彦。
彼が文壇に、その存在を知らしめた長編『風土』は、1941年に書き始め、完結したのが1951年と、十年の歳月を費やして記された“処女長編作”です。途中、太平洋戦争の激化と戦後の混乱、そして福永氏自身、胸を病んで約7年に及ぶ病院での療養生活という激動の日々の中、何度も中断しながら必死の思いで生み出した”処女作“でもあります。
1923年と1939年という二つの時代を通じ、世界が揺れ動いた時代に、日本という“風土”に生まれ育った芸術家の思索、苦悩、愛の悲劇に迫った作品です。
『風土』あとがきに寄稿された池澤夏樹氏の言葉とは
今回も、『海市』に引き続き、『風土』の復刊に際して、芥川賞作家で福永武彦の長男である池澤夏樹氏が、あとがき解説を寄稿しています。この記事では特別に、その寄稿文を全て、掲載させて頂きます。

写真提供:学習院大学史料館
夏の海辺の議論の小説 池澤夏樹
作家はいつ作家になるのか。
世間から言えば小説を書いた人が作家である。一般的には「書いた」は「出版された」であって、本が出て初めて「あの人は作家だ」と認知される。
しかし本人にすれば小説を書いている段階で既に作家なのだ。いや、小説を書こうと思い立った時から作家であると言ってもいい。結果より意図が大事。
『風土』は福永武彦の最初の長篇小説である。彼はこれを書くのに1941年から1951年まで十年をかけた。着手した二十四歳の時にもう彼には作家の自覚があったと見なすべきだ。
十年もかかったのは戦争や病気などさまざまな障害のせいもあったけれど、それ以上に彼がこの作品に対してきわめて周到だったからだとぼくは思う。いわゆる習作ではなく、その時期の日本で小説として通用していたものの模倣や亜流でなく、真に自分の作として世に提示できるもの。フランスをはじめとする欧米の先端の文学を多く読んだ上で、日本の小説の可能性を広げるような作品。そういう野心が、貧しい病気がちの若い男を促し、困難な営為を持続させ、完成に至らせた。
執筆の方針。
まずは自然主義私小説を排してモダニズムを採用する。
登場人物一人一人の性格や思想をきちんと準備し、彼ら同士の間のやりとりを一段階ずつ緻密に構築する。
行動は少なく会話は多い。それをサロン的と言ってもいいが、そう言うなら小説とは最初からサロン的なものだった。『源氏物語』は宮廷というサロン内のゴシップを、サロンに属する作者が書き、サロンの中に読者を得た。
『風土』は三部から成る。
第一部と第三部の主な登場人物は四名。中年の男、中年の女、少女、少年。幾重にも対称軸が重なる幾何学的な図柄。この安定した構図が枠としてあるからこそ作者は話を奔放に広げられた。
第一部と第三部の舞台は1939年夏の、明記してはないがおそらく湘南海岸。その間に置かれた第二部の舞台は同じ場所ながら、1923年の夏で、ここは登場人物が多い。その中の二人が、若さを失って1939年の主役二人になる。
桂昌三という画家が三枝という家を探してくるところから話は始まる。彼は十六年ぶりに旧知の三枝芳枝をぶらりと訪れた。彼女は桂の親友であった三枝太郎の未亡人で、かつては秘かな恋心の対象だった。
三枝芳枝、旧姓荒巻芳枝は裕福な名家の娘で、外交官である太郎と結婚してパリに渡るが、夫は画家になると言って仕事を辞め、絵を描くうちに交通事故で急死する。
芳枝は道子という娘を連れて帰国し、海岸のこの家でずっと暮らしてきた。実家に支えられて生活に困ることはない。
十五歳の道子は驕慢な美少女で生気に溢れている。
そのイノセントな友だちが早川久邇という同じく十五歳の少年。彼はピアノがうまく、日々修練を積んで、いずれはピアニストないし作曲家になりたいと思っているらしい。
この四人の間には一対一の関係が合わせて六つ成り立つ。三人や四人が居合わせる場面ではもっと複雑かつ多元的なやりとりが生じる。
四人の配置には「男と女」、「中年と未成年」、「芸術家とそうでない者」、「希望がある者と絶望している者」などなどいくつもの対立項があって、そこからたくさんの思いが言葉となって湧いて出る。
「芸術家とそうでない者」は桂と久邇はもちろんだが、なかなかの絵を描く道子もこちらに属するはずだ。
もっぱら桂が仕掛ける会話のテーマもまたさまざまな二項対立の形を取る。いわく、「若さと老い」、「西洋文化と日本文化」、「芸術と世俗」、「希望と絶望」、「文明と未開」……探せばまだまだあるだろう。
二つの時代の間にも対称性を見出すことができる。
1923年には日本人はまだ自国の未来を信じていた。この館に集った若い人々は、個人はともかく、社会の先には明るい未来を確信していた。1939年にはもうそういうものはない。少なくとも桂はそれを知っているし、戦中から戦後に掛けてこれを書いた作者も、また後世の読者である我々も知っている。この十六年の歳月の間に日本という国が元気な青春を終えて疲れた中年期に入っており、その先には敗戦という大きな失敗がほの見えている。

桂がしきりに言うのは、伝統のない日本で西洋流の絵を描くことがいかに困難であるかということ。所詮はなぞるだけにしかならない。ある一線を越えることができない。だからパリに行って先端のアートが沸騰している場に身を置いてみたいと日本の画家は願った。大戦間時代はまたエコール・ド・パリの最盛期であり、その主役はフランス人だけではなかった。ピカソもカンディンスキーもモディリアニもスーティンも外から来たのであって、佐伯祐三やフジタのように日本から参加した者もいた。
その一方で桂はヨーロッパ文明に限界を見てポリネシアに渡ったゴーギャンの例も持ち出す。かつて太郎が購入したコレクションの中にゴーギャンが一点あって、今は道子のものになっているという事実で彼の論点は強調される。
会話が多いところはトーマス・マンの『魔の山』にも似ている。あれも多くの思想を代表する者たちがアルプス山中のサナトリウムに集って議論する話であり、行動が少なかった。この『風土』について言えば、プロットを左右するような行動は、①桂の訪問、②何度か繰り返される海水浴、③ゴーギャンの盗み見とそれを知った道子の逆上、④花火の後のほぼ同時の二組の接吻、⑤桂と芳枝の共寝。これくらいのものだ。
技法の中心にあるのはフランス文学に特徴的な心理小説。登場人物の心の動きを外の視点から精密に書き、人々の関係とその変化をほとんど力学的に辿る。『クレーヴ公の奥方』から『赤と黒』や『ボヴァリー夫人』を経て『ドルジェル伯の舞踏会』に至るまでに洗練された方法。『風土』とほぼ同じ時期に刊行された大岡昇平の『武蔵野夫人』もこれに依っている。
もう一つは「意識の流れ」ないし「内的独白」。一人の心に去来する思いを定文化しないまま綴るもので、J・ジョイスの『ユリシーズ』の最後の章やW・フォークナーの『怒りと響き』が典型だろうか。
福永はこれらの手法をただ新しいから、珍しいから用いたのではない。こういう方法を用いなければ書けない心の領域があるのだ。芳枝の誘惑に抗う桂の心の動きは、あるいはその先の微妙なやりとりの過程は、この方法でなければ表現できない。二人の人間の間の思いはチェスの盤面のように相互の言葉に呼応して変わってゆく。そして、1950年代の日本ではこれはずいぶん大胆な、実験的な小説だったはずで、しかもこの実験は明らかに成功している。こういうことを試みる勇気だけでも賞賛に値する。
福永武彦の作品の系列の中に『風土』を置いてみると、芸術家が官能によって鼓舞される、という主題が再び使われたことがわかる。絵が描けなくなった桂は、ためらいながらも芳枝の肉体的魅力の提示に絵筆を執ることへの促しを認める。芳枝はかつての夫である太郎のモデルを務めて傑作を描かせたことをどこかで思い出している。これは珍しいことではなく、ロダンとカミーユ・クローデルとか、ピカソと一連の恋人たちとか、世に多く例があるわけだし、ゴーギャンとタヒティの女たちだって同じケースと言える。
そして福永は十一年後に『海市』でほぼ同じテーマを書いた。方法こそ異なり、ずっと技巧的に洗練されているけれども、描けない男性の画家を女性の官能的魅力が救うという基調は変わらない。背景が海辺というところも似ている。もちろんどちらの場合もそうことはうまく運ばず、試みは悲嘆のうちに終わるのだけれど。
『風土』の中ではもっぱら絵を描くことを巡って言葉が交わされるが、それはそのまま文学についても言えることだ。桂昌三はパリに行かなければ絵は描けないと考えたが、福永武彦はフランスに行くことなくこの作品を書き上げた。それは絵画と文学の違いであると同時に創作者としての桂と福永の資質の違いでもある。作家は逆境にありながらも画家ほどは疲れていなかったのだろう。
(作家・詩人)

池澤夏樹 Natsuki Ikezawa
1945年生まれ。北海道出身。小説家、詩人。埼玉大学理工学部物理学科中退。1988年「スティル・ライフ」で芥川賞を、1992年『母なる自然のおっぱい』で読売文学賞を、1993年『マシアス・ギリの失脚』で谷崎賞を、2000年『花を運ぶ妹』で毎日出版文化賞を受賞するなど受賞多数。その他の作品に『静かな大地』『きみのためのバラ』『カデナ』『双頭の船』など。作家・福永武彦を父に、詩人・原條あき子を母に持つ。2014年8月より、北海道立文学館館長を務めている。
おわりに
池澤氏が小説を書きだしたのは“父”福永武彦が没した後からだそうです。 現代を代表する作家の一人・池澤夏樹氏の父の“処女長編作への作品解説”は如何だったでしょうか。
福永武彦の小説の世界は、実に十年の歳月を費やして完結した作品『風土』から始まったともいえます。

『風土』芸術家の苦悩を描いた著者の処女長編小説
関東大震災と第二次世界大戦という二つの歴史的大事件に挟まれた16年間――画家・桂が片時も忘れえなかった昔の恋人・三枝夫人との再会と、すれ違った愛の行方を追い求め描いた作品。 世界が激しく揺れ動いた時代、日本という風土に生まれ育った芸術家の思索、苦悩、そして愛の悲劇を通して人生の深淵に迫った力作である。完成までに十年の歳月を費やした福永武彦の文学的出発点ともいえる。
初出:P+D MAGAZINE(2016/07/13)