夏目漱石の孫 半藤末利子おすすめ4選

文豪・夏目漱石を祖父に、昭和史研究家の半藤一利を夫に持つ半藤末利子は、漱石と家族たちの逸話を記した随筆を発表しています。そんな名随筆家によるおすすめ作品4選を紹介します。
『漱石の長襦袢 』漱石の妻・鏡子 の思い出や、漱石文学館設立への道のりなど

https://www.amazon.co.jp/dp/4167801930
著者の祖母にあたる、漱石の妻・鏡子の思い出などを綴った随筆集です。
世間では、料理が嫌い、朝寝坊で夫より後から起きる、夫の門下生が来ても長襦袢のまま寝そべっていた、夫の死後に印税で豪邸を建てた、など悪妻のイメージが定着している鏡子について、
漱石は熊本で結婚して所帯を持つとすぐに妻の鏡子に「俺はこれから毎日たくさんの本を読まねばならぬからお前のことなどかまっていられない」と申し渡した。それを聞いて鏡子は「よござんす。私の父も相当に本を読む方でしたから少々のことではびくともしやしません」と受けて立っている。頼もしいには違いないが、20歳の新妻にしては随分ふてぶてしくも思えるではないか。私の母筆子(漱石の長女)は、鏡子が度外れて豪胆であったからあの漱石と暮らしていけたのだ、と「普通の女の人だったら早々と逃げ出すか、気が変になるか、自分の命を絶っていたことでしょうよ」といつも鏡子を
庇 っていた。
と述べています。英国留学から帰って以来、生真面目すぎる性格ゆえ神経衰弱を患っていた漱石は、妻や娘に当たり散らすこともあったようですが、鏡子は鷹揚に対処します。漱石が胃病のため修善寺で療養中、
漱石の没後、
著者は、父の遺志を引き継ぐかのように、漱石山房の復元計画に携わります。その際、漱石ファンである脳科学者の
漱石山房記念館は、平成29年に開館し、著者は現在名誉館長を務めています。
『夏目家の糠 みそ』漱石が食したとされ、江國香織も絶賛した秘伝の糠漬けとは
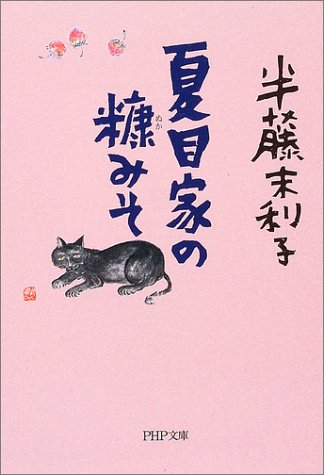
https://www.amazon.co.jp/dp/4569579604/
夏目家に伝わる家庭の味、漱石が愛した食べ物などを綴ったエッセイ集です。
漱石の顔が千円札に登場した時、「お祖父さんがお札になるってどんな気持ち?」とよく訊かれた。母筆子は、「へーえ、お祖父ちゃまがお札にねぇ。お金に縁のあった人とは思えないけど」という感想を述べたが、私にはこれといった感慨は湧かなかった。それは一つには49歳で没したため、私が漱石に抱かれたりした記憶を持たないせいでもあろう。しかし一番の理由は母が折に触れて語ってくれた漱石の思い出が、余りにも
惨憺 たるものだったからであると思う。
漱石没後に生れた著者は、祖父を直接には知りません。けれど、そんな著者が祖父を身近に感じられるのが、夏目家に伝わる糠床だと言います。
祖母が夏目家に
嫁 す時に実家から貰ってきたものを、母が夏目家から持って出て、それを私が貰って今日ここにある。我が家で唯一江戸時代から受け継がれてきたもの。
糠床は、時代を経れば経るほど、そして、かき回す回数が多いほど美味しくなるという著者は、手入れを怠らず、煮物の残り汁などを混ぜて糠床に栄養を与え、茄子、きゅうり、大根、蕪などを漬けています。ある時、それを食べた直木賞作家の江國香織が、「こんな美味しい糠漬けを食べたことがない」と感嘆したとか。
ところで、糠床に関して、芥川賞作家の朝吹真理子は、「人間の手には無数の常在菌があり、おばあちゃんがかき混ぜて育てた糠床には、おばあちゃんの死後も彼女由来の常在菌が混じっている。残された人がそれを食べることは、故人とつながることであり、人間同士はくっきりとした個体で区別されているわけではなく互いに浸食しあって生きている」(2022年5月18日収録 END展開催直前トークイベント「人生100年時代の死生観とは?」より)と考察しています。
その意味で、著者もまた顔を知らない漱石とつながっている、といえるでしょう。
『老後に快走!』漱石ゆかりの糠漬けを、現天皇陛下が召し上がることに

https://www.amazon.co.jp/dp/4569764215/
『夏目家の糠みそ』を読んだ人から、糠床を分けてほしいとの依頼を受けた著者。群馬県川場村で式典が開かれ、株分けすることになります。
2010年川場村に皇太子殿下(現・天皇陛下)がお越しになられた。「ここには夏目漱石も食した、200年以上も昔から継承されてきた糠漬けがございますが、お召し上がりになりますか」と村長さんがお尋ねになると、殿下は「いただきましょう」とお答えになって召し上がって下さった。殿下の素直で気さくなお人柄が
偲 ばれて、私は嬉しくなると同時にすっかり恐縮した。皇族方の善意溢れる、良質な社交性。こんなにもサービス精神旺盛でいらっしゃるとは。
東京農大の調査により、この糠床からは、日本で最も長生きしている植物性乳酸菌が検出されたようです。
わが家の糠みそはすごいのだ! さあ、糠漬けを食べて健康になりましょう。だが待てよ。この漬物は漱石も食べたであろうということで珍重されるわけだが、肝心の漱石は胃弱に悩まされて亡くなった。このことを糠みそと結びつけてどう説明したものか、私にはさっぱり分からない。
とユーモアたっぷりに結んでいます。
他に、母・筆子のことを綴った箇所もあります。
筆子は明治時代の良家(
御大家 ではない)で躾けられた、奥床しい女性であった。言葉遣いの良さに関しては父・漱石の影響が多分にあったと思われる。漱石はぞんざいな言葉が大嫌いで、母達が姉妹間で「あんた」などと呼びあっていると、「あんたなどという日本語はない。あなたと言いなさい」と厳しくたしなめたという。
晩年、認知症が進んだ筆子を自宅に引き取り、介護していた著者。ある時、近所の人が菓子のお裾分けに来ると、「お母様のお許しがないといただけません」と筆子が固辞したというエピソードを紹介して、次のように述べています。
呆けると本性が現れるとよく言われるが、幼い時に叩き込まれたものは、一生骨身に徹するようである。それにつけても明治時代の躾を強要した漱石に大いに感謝せねばならない。因みに漱石は自分の娘がなまじ文学付いたりするのを嫌って、年頃になっても文学書を読むことを筆子に禁じた。筆子はもっとも漱石好みの女性に成長したのかもしれない。
また、夫・半藤一利が、芥川賞作家・川上弘美のファンで、彼女にファンレターを送り、もらった返事の内容も公開しているなど、読みどころが満載です。
『硝子 戸 のうちそと』亡き夫・半藤一利は超愛妻家?
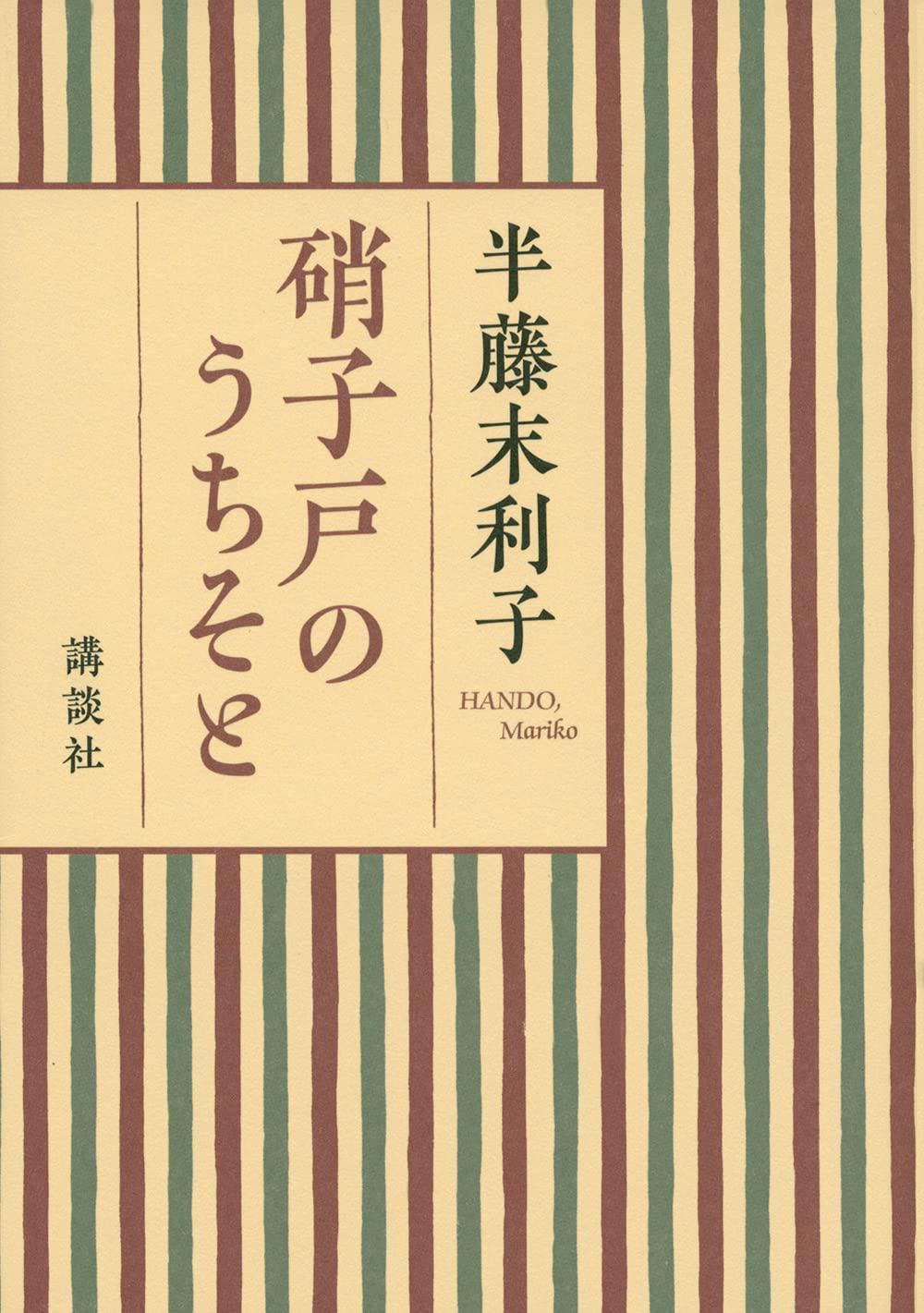
https://www.amazon.co.jp/dp/4065235510/
2021年に逝去した夫との暮らしなどを振り返ったエッセイ集です。
作家の半藤一利が、第63回菊池寛賞を受賞することになったときのエピソードを次のように書いています。
菊池寛賞は、文学、芸能、スポーツなどの分野で、高い業績をあげた人や団体に贈られる賞。かつて大学時代、菊池寛は私の父松岡譲と親友であった。しかし父の恋愛事件をめぐって、父を排斥する立場にまわった。だから私からしてみると菊池寛は私の親の
敵 である。私は仇討ちをせねばならぬ身である。当然私の助っ人になるべき亭主が尻っぽを振って賞をもらう気か、と私が怒り、一時 わが家は内紛状態にあった。亭主は私がけんつくを食わすと、私をテロリストと呼んだ。が「そんなこと言わないで、式には出席してください」と終いにはひれ伏して懇願してきたので、授賞式には私は渋々ながら出席したのである。夫の受賞理由は、「『日本のいちばん長い日』などの著作を通じ、常に戦争の真実を追求し、数々の歴史的ノンフィクションで読者を啓蒙してきた」というものだそうである。驚いたことに、夫は正式の挨拶の中で、「自分の感謝している人を4人あげます」と言って、その中になんと私も含めたではないか。大した女房でもないのに、私のすることなすことをほめちぎるのである。バッカじゃなかろうか! 聴いてくださった方々はさぞや半ちゃんは恐妻家なんだと思われたことであろう。
しかし、実際の半藤一利は、愛妻家だったようです。
彼は夫としては優等生であった。あんなに私を大切にして愛してくれた人はいない。ほんの4日間だけ、下の世話を私にさせたことを、「もったいない」と
嗚咽 を堪えながら、「あなたにこんなことをさせるなんて思ってもみませんでした。申し訳ありません。あなたよりも先に逝ってしまうことも、本当に済みません」と頻 りに詫びるのであった。
著者は阿川佐和子との対談で、夫から「奴隷になります、女神さま」という強烈なプロポーズを受けたこと、生涯妻に丁寧語で話しかけ、妻が地味な格好をするのを嫌ったためピンクの服ばかり、といったエピソードを明かしています。(『週刊文春』2021年5月6日・13日ゴールデンウィーク特大号より)
夫の最期の言葉は、「墨子を読みなさい。2500年前の中国の思想家だけど、あの時代に戦争をしてはいけない、と言ってるんだよ。偉いだろう」というものだったようです。反戦を唱え続けた半藤一利らしく、読者の心を打つのですが、著者はまだ読んでいない、とお茶目に告白しています。
おわりに
「漱石を書く時、私は緊張を強いられることがない。祖父といっても著書を通してと、母筆子が語った漱石しか私は知らない。漱石は私にとっていわば他人に近い存在なので、努力しなくとも客観視できる」(『漱石の長襦袢』より)と述べているように、著者は、身びいきや感傷にとらわれることなく、漱石とその一族のエピソードを軽妙なユーモアをもって描いており、漱石ファンもそうでない人も、楽しめる内容といえるでしょう。
初出:P+D MAGAZINE(2022/08/09)

