【『一人称単数』発売】村上春樹の珠玉の短編3選

自らを長編作家と名乗っている村上春樹ですが、短編小説を書くことは「純粋な個人的楽しみに近い」とも語っており、長編に対する“実験”のような立ち位置だと言います。そんな村上春樹の実験的な作風を楽しむことができるおすすめの短編小説を、最新の作品集『一人称単数』の収録作も含めご紹介します。
1979年に『風の歌を聴け』でデビューして以来、世界的に大きな影響力を持つ作家として活躍を続けている村上春樹。『1Q84』、『騎士団長殺し』といった長編小説が注目されしばしば社会現象ともなる村上春樹ですが、実は短編小説の中にも味わい深い作品が多くみられます。
村上春樹自身は、短編小説を“実験”の場として扱っているとたびたび述べています。
短編小説を書くことは多くの場合、純粋な個人的楽しみに近いものです。とくに準備もいらないし、覚悟みたいな大げさなものも不要です。アイデアひとつ、風景ひとつ、あるいは台詞の一行が頭に浮かぶと、それを抱えて机の前に座り、物語を書き始めます。
──『若い読者のための短編小説案内』より
今回は、そんな“純粋な個人的楽しみ”としてのアイデアや風景、台詞を堪能することができる村上春樹の短編小説から、おすすめの作品を3作品ご紹介します。
『クリーム』(『一人称単数』収録)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163912398/
『クリーム』は、2020年7月に刊行された村上春樹の最新短編集、『一人称単数』の収録作品です。
物語は、主人公である“ぼく”が、18歳のときに経験した奇妙なできごとを年下の友人に語る──というシーンから始まります。当時浪人生だった“ぼく”は、子どもの頃に通っていたピアノ教室の生徒のひとりだった女の子に、突然、ピアノの演奏会に招待されます。特に親しく交流していたわけでもない彼女からの数年越しの誘いに“ぼく”は戸惑いますが、好奇心も手伝って足を運ぶことを決め、招待状を頼りに、神戸の山の上にある会場を目指します。
しかし、招待状に書かれたバス停でバスを降り、指定されたとおりの道を上っていった先にあったのは、鉄の扉にぐるぐると南京錠がかけられた、人気のないホールでした。来た道を引き返し、途中にあった公園のベンチに座って“ぼく”は考え始めます。女の子にかつがれたのかもしれない、けれど一体どんな理由があってこんなに手の込んだ嫌がらせをするのだろう──?
あれこれと考えを巡らせているうちに過呼吸になってしまった“ぼく”の目の前には、気がつけばひとりの老人が座っていました。老人は“ぼく”を心配する様子もなく、突如、こんな言葉を投げかけます。
「中心がいくつもある円や」
「円ですか?」とぼくは仕方なく声に出して尋ねた。相手は年上の人だし、返事もせず黙り込んでいるわけにはいかない。
「中心がいくつもあってやな、いや、ときとして無数にあってやな、しかも外周を持たない円のことや」と老人は額のしわを深めて言った。「そういう円を、きみは思い浮かべられるか?」(中略)
老人は言った。「ええか、きみは自分ひとりだけの力で想像せなならん。しっかりと智恵をしぼって思い浮かべるのや。中心がいくつもあり、しかも外周を持たない円を。そういう血のにじむような真剣な努力があり、そこで初めてそれがどういうもんかだんだんに見えてくるのや」
そういった血のにじむような努力を成し遂げたときに、それはそのまま“人生のクリーム”(とびっきり最良の、人生のいちばん大事なエッセンス)になる──と老人は“ぼく”に告げます。
そんな“ぼく”の回想を聞いていた年下の友人は、“話の筋がもうひとつうまくつかめないのですが、そのとき実際に何が起こっていたのでしょう?”と問いかけます。しかし自分にもそれはわからないと“ぼく”は言い、ただ、人生の中で説明のつかないできごとを経験したときはずっと、その“中心がいくつもあって外周を持たない円”のことを深く考えてきたと語るのです。
人は不条理なできごとに運悪く接したとき、それがなぜ起きたのか、なぜ自分が当事者とならなければならなかったのかということについてしばしば説明を求めます。しかし、本作の主人公にとって“実際に何が起こっていたか”は些末なことであり、むしろ、そのできごとの説明のつかなさについて考え続け、老人の説いた“クリーム”のようなものを得ることこそが人生の本質であると彼は捉えています。本作は、考えることをやめないことの難しさと誠実さ、その意義について、理不尽な時代を生きざるを得ない私たちに警告を発するかのような1篇です。
『独立器官』(『女のいない男たち』収録)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4163900748/
『独立器官』は、2014年刊行の短編集、『女のいない男たち』に収録されている作品です。
本作の主人公は、“技巧的な人生”を歩んできた
内的な屈折や屈託があまりに乏しいせいで、そのぶん驚くほど技巧的な人生を歩まずにはいられない種類の人々
でした。誰にでも感じよく接することができ、ユーモアのある会話も楽しめる渡会医師でしたが、彼は先天的に恵まれすぎているが故に自分のことしか考えていないし、嫉妬や怒りといった感情とは無縁の人物だと谷村は捉えていました。
渡会医師はもともと、結婚している女性ともデートを楽しんだり関係を持ったりすることがたびたびある人物でした。しかしあるとき、渡会医師は人生で初めて、“思いもよらず深い恋”に落ちてしまいます。恋した相手には夫と子どもがいましたが、渡会医師は彼女との関係を切ることができず、あまりにも強すぎる恋煩いに苦しむようになっていきます。
渡会医師がそのようにして深い恋に落ちてしまう直前、彼はナチの強制収容所(ホロコースト)についての本を読み、
もし私が何かの理由で──どんな理由かはわかりませんが──今の生活からある日突然引きずり下ろされ、すべての特権を剥奪され、ただの番号だけの存在に成り下がってしまったら、私はいったいなにものになるのだろう?
と生まれて初めて考えるようになった、と谷村に語ります。自分自身がなにものであるかという疑問を中年にして突如抱き、それをきっかけに生まれて初めての恋を経験してしまった渡会医師がたどる運命は、あまりに切実で残酷なものでした。
本作は、内的な葛藤のない人物がホロコーストという歴史上のできごととひとつの恋を契機に変化していくさまを写実的に描いていると同時に、その人物と対照的な存在である語り手の独白を通して、「物語」というものが人の人生になにをもたらすかを実験的に浮かび上がらせようとしているかのようです。象徴的なのは、ホロコーストについての本を読んだ直後の渡会医師と谷村の会話です。
「失礼ですが、谷村さんはそんな風に考えたことありませんか? もし自分からものを書く能力が取り去られたら、自分はいったいなにものになるのだろうと?」
僕は彼に説明した。僕は出発点が「なにものでもない一介の人間」であり、丸裸同然で人生を開始した。(中略)だから自分が何の取り柄もなく特技もない、ただの一介の人間であることを認識するために、わざわざアウシュヴィッツ強制収容所みたいな大がかりな仮定を持ち出す必要はないのだ、と。
自分のことを“なにものでもない”と捉えている谷村は、ホロコーストの物語を“大がかりな仮定”と呼び、ある意味では自分と距離のあるできごととして捉えています。しかし、渡会医師はその物語を生まれて初めて「自分ごと」として捉えてしまったが故に、物語に魅入られ、ホロコーストの犠牲者たちの死をなぞるような形で破滅していきます。物語というものが人に与える影響や人生にもたらす変化をふたりの人物を通じてグロテスクなまでに描き切っている、奇妙な後味を持った1篇です。
『象の消滅』(『パン屋再襲撃』収録)
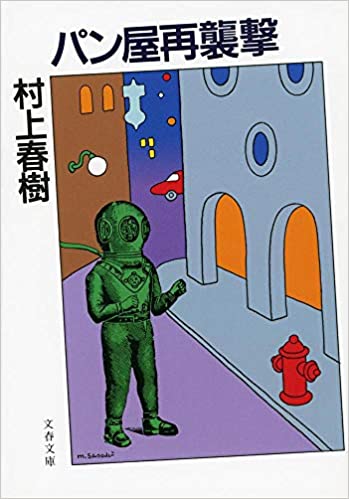
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4167502119/
『象の消滅』は、1986年に刊行された短編集、『パン屋再襲撃』に収録されている1篇です。村上春樹の初期の作品にあたる本作は、軽妙洒脱な会話、“喪失”という村上作品の多くにみられるモチーフ、あっけないほどにシンプルでありながら奇妙な味わいを残すストーリーなど、村上春樹らしさを存分に堪能することのできる作品です。
とある町で、老いた象が、飼育係とともに跡形もなく“消滅”してしまう──というのが本作のあらすじです。象の消滅についての一連のできごとは、理由もなくその象に関心を寄せ続けていた“僕”が集めた新聞のスクラップや、“僕”の視点を通じて語られます。
老齢のその象は、町の外れにあった動物園の閉園にともない、紆余曲折の末に“町有財産”として、古い小学校の体育館に移設された象舎で暮らすことになった気の毒な象でした。象舎の落成式では、象にとっては“完全に無意味”と思える町長の演説や小学生による作文の朗読、象のスケッチコンテストなどがおこなわれましたが、象はそれらすべての儀式に黙って耐えていました。
そんな象が突如姿を消してしまったのは、5月のある日のことでした。象はその日、唯一心を許していた相手である飼育係の老人とともに、忽然と象舎から消えてしまったのです。象の足にはめられていた足枷は鍵をかけられたままそこに残されており、象舎の周りには足跡ひとつ見られませんでした。新聞は町の管理体制の不完全さを糾弾するような記事を書きましたが、それが盗難や脱走ではなく“消滅”としか呼びようのない現象であることは誰の目にも明らかでした。
実は、象と飼育係が消滅する直前、彼らの姿を最後に目にしたのは“僕”でした。象好きであった“僕”は、象舎を上から見下ろすことができる山に登って象の姿を眺めることが時々あり、彼らが消滅する前の晩も、そのようにして象舎を見ていました。しかしその晩、“僕”の目には、象と飼育係の大きさのバランスがいつもと違うように映っていたのです。
「つまり大きさのバランスだよ。象とその飼育係の体の大きさのつりあいさ。そのつりあいがいつもとは少し違うような気がしたんだ。いつもよりは象と飼育係の体の大きさの差が縮まっているような気がしたんだ」
“僕”は、象の体がその時点で小さくなっていたか、あるいは飼育係が大きくなっていたのだろうと推測します。最初は見間違いだと感じた“僕”ですが、彼らの姿を遠くから眺めているうちに、やがて不思議な感覚を覚えます。
それは不思議な光景だった。通風口からじっと中をのぞきこんでいると、まるでその象舎の中にだけ冷やりとした肌あいの別の時間性が流れているように感じられたのだ。そして象と飼育員は自分たちを巻きこまんとしている──あるいはもう既に一部を巻きこんでいる──その新しい体系に喜んで身を委ねているように僕には思えた。
本作の中で、象を巡る“完全に無意味”な社会的儀式と、象と飼育係が育んでいた絆や信頼関係は対照的なものとして描かれています。“僕”が目にした、バランスを崩した象と飼育係の姿は、統一性や機能性を求める社会のシステムから外れてしまった存在の象徴であったのかもしれません。物悲しいけれどどこかさっぱりとした読後感が残る、味わいのある短編です。
おわりに
村上春樹はかつて、短編小説を書くということについて、このようにも述べています。
短編小説というのは「うまくて当たり前」の世界です。それが前提です。その上で何を提供できるか、ということが主題になります。「はい、よく書けました」だけではどこにもいかない。うまくは書けてるけど、どっかで前に読んだことのあるような話だよな、みたいなものでは、書く方には意味があるかもしれないけど、読む方にとってはほとんど意味はない。他の人には書けない、その人でなくては書けない「実のある何か」がそこにくっきりと浮かび上がってきて、今まで見たことのないような情景がそこに見えて、不思議な声が聞こえて、懐かしい匂いがして、はっとする手触りがあって、そこで初めて「うん、こいつは素晴らしい短編小説だ」ということになります。
──『短編小説はどんな風に書けばいいのか』(『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997-2009』収録)より
その言葉どおり、“今まで見たことのないような情景”や“不思議な声”、“懐かしい匂い”が、彼の多くの短編には満ちています。今回ご紹介した3篇を入り口に、村上春樹の作品世界に足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2020/08/04)

