端正で美しい言葉の世界を味わう 堀江敏幸のおすすめ4選

2001年、『熊の敷石』で第124回芥川賞を受賞し、現在同選考委員を務める堀江敏幸は、詩情あふれる言葉で書かれた上質な小説やエッセイが魅力の作家です。そんな著者のおすすめ作品4選を紹介します。
『なずな』――44歳の男性が、生後2ヵ月の姪を預かることになり……。驚きと優しさに満ちた育児小説

https://www.amazon.co.jp/dp/4087452484/
「私」は、地方紙で文筆に携わる独身男性。弟夫婦が不慮の事故に見舞われたため、生後2ヵ月の赤ん坊・なずなを、急きょ引き取ることになります。育児経験のない「私」は大わらわ。幸い、「私」は、「一度でも赤ん坊の顔を見たら、他人事とは思えない」と言う親切な人たちの助けもあり、試行錯誤で育児に励みます。
なずなが来てから私の身に起きた大きな変化のひとつは、周りがそれまでとちがった顔を見せるようになったことだ。こんなに狭い範囲でしか動いていないのに、じつにたくさんの、それも知らない人に声をかけられる。顔は知っていて、たまに言葉も交わしている人たちも、あきらかに親しさの敷居をひとつまたいだ反応をみせる。
育児に神経質になっている「私」に、「数値は数値でしかない」と、鷹揚なところを見せる老先生。「赤ん坊の体調は大人よりバリエーションがある」と教えてくれた看護師。「赤ん坊が近くにいるだけで空気が変わる。肩の凝りがほぐれる」と言ってくれる碁会所の老人。ベビーカーを押して入っても嫌な顔をしない居酒屋のママ。今、1人で育児をしている親のストレスが問題になっていますが、なずなはその反対に、町の皆によって育てられます。
そして、この小説の魅力は、赤ん坊の卓越した描写の仕方です。
赤ん坊というのは、こんなにやわらかく目を閉じられるものなのか。なにものをも拒まない閉じ方だ。光さえも、声さえも……。
他にも、赤ん坊の手を「開いているとも閉じているとも言えそうな指の丸まり」と書いたり、
すやすや眠っている赤ん坊を見て、「世界の中心は、いま、ベビーカーで眠っているなずなの中にある」と思い、この世界には赤ん坊の数だけ中心がある、と思い至った「私」。ミルクをやり、おしめを換えることを繰り返すうち、「きれいと汚いの区別は無意味だ」とまで感じられるようになり、なずなへの愛おしさが芽生えはじめた矢先に、突然の別れが訪れます。その時の、「私」の思いも寄らない心境の変化とは。
育児を経験した人もそうでない人にも読みごたえのある1冊です。
『めぐらし屋』――父の遺品を整理する40代の娘。父が残した「あたたかな謎」とは
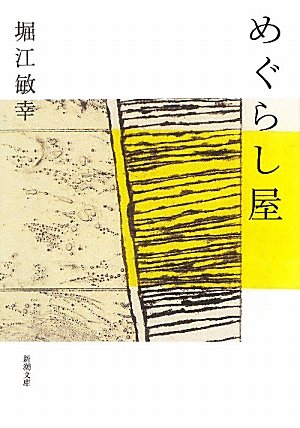
https://www.amazon.co.jp/dp/4101294755/
父と母は、さんざん考えた末に名前を「路子」と決めた。ところが、父ひとりで役所へ届け出に行き、書類に必要事項を書き込もうとしたところ、枠のうえについていた印刷の汚れを役所の男性がカウンター越しに
草 冠 と見まちがえて、ふりがなを書き込むまえに、「ふきこですか、衒 いのない、いいお名前ですなあ」と漏らしたのを聞いて、「みちこ」ですと言い返せなくなってしまったのだという。(中略)蕗子さんは母の十八番 となったこの話を聞くたびに、世の路子さんたちには申し訳ないけれど、蕗子でよかった、と土壇場の父の横暴に感謝した。路がひとをここではないべつの土地へと導いてくれる線だとすると、蕗はその路のわきに生えている草みたいなもの。まっすぐ進むことができずに寄り道ばかりしていても、それが名前なのだと居なおることができる。
思い出に浸っていた矢先、蕗子は、「そちらは、めぐらし屋さんですか」との電話を受けます。父は、蕗子の知らないところで、黒子的な世話役、それも、とりとめもないお願いを引き受ける役回りをしていたらしく、その依頼人は、高齢の母の「願わくば花の元にて春死なん」という望みを叶えてほしいと持ちかけます。戸惑いつつ、「めぐらし屋」を引き継ぐことになった蕗子は、父と生活を共にしていた頃より、今の方が父を近しく思う不思議を感じます。けれど、そのことを突き詰めて考えたりしません。それは、「わからないことは、わからないままにしておくのがいちばん」と父が言っていたから。
蕗子の人物造形も魅力的です。花屋で買う花より、ジャガイモやオクラなど野菜に咲く花が好きだったり、小学校にある百葉箱の「百葉」の由来は、通風口の羽が百枚の葉を重ねたように見えるからなのか、それとも、
ゆったりとした物語のなかに身をゆだねたい、滋味深い1冊です。
『もののはずみ』――物言わぬ、かそけきものたちへの愛惜の念
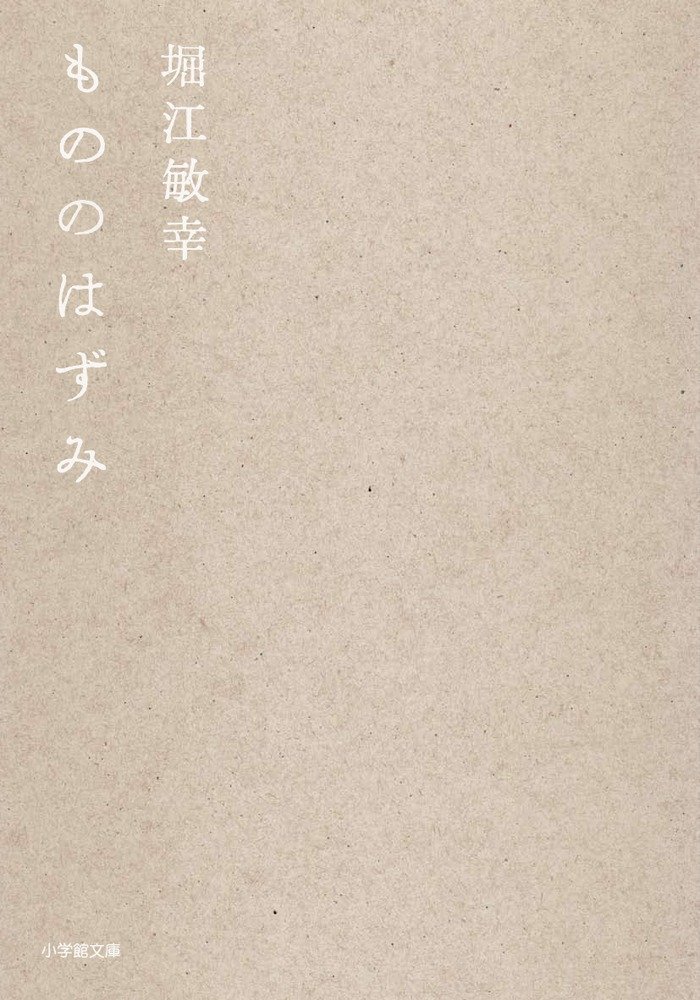
https://www.amazon.co.jp/dp/4094061770/
著者が集めた、とるにたらないけれど捨てられない「もの」に宿る記憶をひもといたエッセイ集です。
通勤用鞄の握りの部分に、小さな熊のぬいぐるみがぶら下がっている。娘がまだ幼稚園に通っていた頃、先生に特別な結び方を習ったと言って、頭部から都合よく2本のびていた紐を、たまたまそこにあった鞄にまんまるい手でくりくりと結んでくれたのである。ほら、と嬉しそうに胸を張っている子どもの前で、どうしてそれをほどくことができようか。青いチェック模様の熊は、そのうち自然にゆるんで取れてしまうだろうとの予想を裏切って、朝夕、私の手もとでゆらゆら揺れつづけた。しっかり結ばれた紐はその頼りなげな熊を人波から保護し、寝不足でふらふらしている私をも支えてくれたのである。
また、仏文学者でもある著者は、フランスの古道具屋めぐりで、様々な「もの」たちに出会います。
ある店で、
脱穀 を済ませた麦の量をはかるための樽 を見つけた。20キロでちょうど一杯になる。形がいいのでごみ箱にでもなるかと買い求めたところ、後日、べつの店で、同型の、もっと小ぶりなものがふたつならんでいるのに出くわした。幼い子どもが棄てられているようで不憫 になり、さっそく連れ帰ることにした。親樽をすでに持っているものですから、と言うと、店主は、その気持ちが大切だ、と誉めてくれた。
物を役に立つかどうかの基準で選別したりせず、
他に、年賀状に子どもの写真を載せることについては、意見が分かれるものですが、著者は次のように考えます。
年賀状に子どものスナップ写真をあしらってくる方々がいて、家族ぐるみのつきあいなどないお宅であってもお子さんたちはみな愛らしいから、こんなふうに毎年きちんきちんと報告が送られてくると、れっきとした親類縁者になったようで、なんだか誇らしい気分になる。(中略)とつぜん大きくなって顔つきが変わっていたりしたときなどはびっくりするより取り乱してしまい、いったいなにが起こったのかと前年の賀状を引っ張り出して比較したりする。
著者の、「もの」への優しいまなざしを感じることのできる1冊です。
『音の糸』――クラシック音楽にまつわる記憶を、音楽的な文章で綴ったエッセイ集
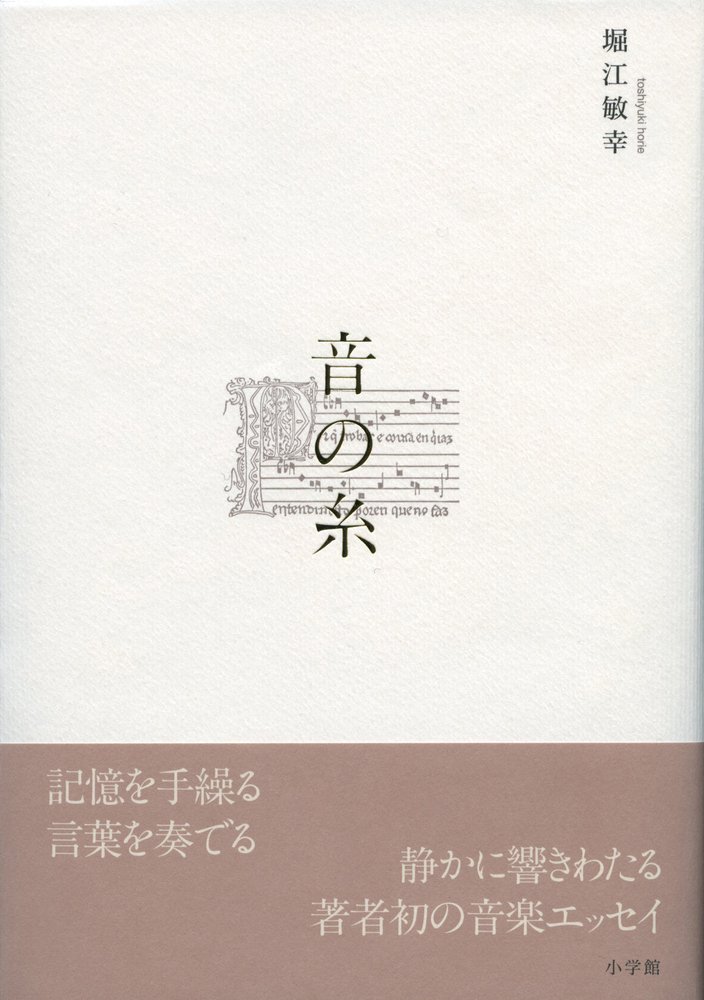
https://www.amazon.co.jp/dp/4093885257/
放課後の音楽室、忘れがたい演奏会など、音楽によってたぐられる記憶の糸をめぐってのエッセイです。
手もとに残っているLPレコードのなかに、大学生協で購入したものが何枚かある。レコードの箱を漁(あさ)る指の快楽はすでに知っていたけれど、好きなだけ買う楽しみとは、経済的な事情でついに無縁だった。円盤を選べば本を我慢しなければならない。本を手に取ってしまえば、円盤は遠くへ飛んで行ってしまう。双方を扱う古書店に入るのはじつに危険なことだった。
音源をネットからダウンロードすることが多くなった現在だからこそ、「レコードの箱を漁る指の快楽」を知っていた世代の読者には、懐かしさを喚起する一節ではないでしょうか。
また、著者は、演奏者のみならず、伴奏者や調律師といった裏方の人達へも賛辞を惜しみません。
弾き込んだ愛器を持ち運ぶのは、望みはしても実現不可能な夢物語であって、ピアニストとは、自分の身体に合った楽器を人前で弾くことの許されない、まことに不自由な芸術家なのだ。演奏会場にある、いろいろな弾き手の癖を取り込んだ共用ピアノを弾くしかない。こうなると、調律師の存在は途方もなく大きいことになる。1台のピアノが、すぐれた調律師の手によって、まったくべつの音を奏でる。彼は表面的な弦の調整をするというより、ピアノの部材の遺伝子操作をして細胞の組成を変えていくのだ。音の細部に対する弾く側の際限なき要求と、限界のなかでそれに応える職人技との真剣勝負には心を打たれる。
美しい文章でつづられ、上質な音楽を聞いているような豊かな気分が味わえる1冊です。
おわりに
堀江敏幸の作品には、思わずどこかに書き留めておきたくなるような、はっとする表現があふれています。お話の先が気になって頁を繰る手が止まらない、というよりは、その美しい言葉と豊かなディティールの世界に浸っていたくて、頁を繰るのが惜しい、といった気持ちにさせてくれる著者の世界を、味わってみてはいかがでしょうか。
初出:P+D MAGAZINE(2022/05/16)

