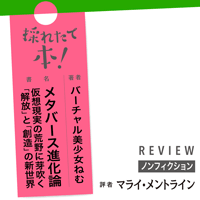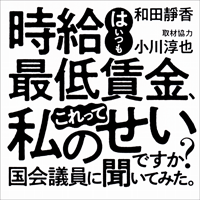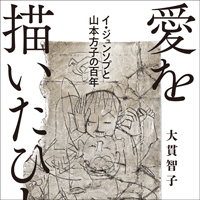今月のイチオシ本【ノンフィクション】

時代とともに変わるものもあれば、永久に不変なものもある。新型コロナ禍の自宅自粛生活で、働き方や教育方法などは大きく変容しそうだ。しかし夫婦や家族の問題は逃げ場がないだけ深刻化したように思える。
そんなとき、誰かのアドバイスが欲しい。誰が答えたかわからないSNSの回答ではなく信頼する人に相談したい。
大正12年生まれの作家、佐藤愛子はいまだに現役バリバリである。2016年に出した『九十歳。何がめでたい』(小学館)は世の中の女性の賞賛を集め100万部を突破した。
その作家を「ソウルメイト」と呼ぶ小島慶子は50歳年下のタレント、エッセイスト。普段住んでいるのはオーストラリアのパース。一か月に一回一週間、日本に出稼ぎにやってくる。なぜそんな不便な暮らしをしているか、その理由が本書には縷々と書き連ねてある。
本書はこのふたりの往復書簡集だ。電子メールでもZoomでもなく手書きの手紙。その始まりは2017年の秋だった。小島さんの手紙は愛子先生の誕生日プレゼントを送った報告とともに自分の家庭の愚痴を赤裸々につづっていた。「夫が働かない」その悩みは確かに深い。
愛子先生の返信は一言でいえば「そんなの、まだまだよ」というところだろうか。夫の会社の倒産に巻き込まれ、来る日も来る日も原稿を書いて借金を返していた日々を思えば、出稼ぎくらい軽い軽い、と私も思う。
夫婦の愛情と家族の絆、世間の義理、そして自分のやりたいこと。これが全部バランスよく日常に割り振られていることなんてまずないだろう。小島さんの愚痴は本人がどこかで見切りをつけるべきことだと、愛子先生はそれを押しつけるのでなく促しているようだ。
酢ダコを好きか嫌いかで人の優劣などつけられない。人の気持ちを慮れというのを「いちいちうるせえ」という愛子先生の啖呵に胸がすっとする。
小島さんは四十代。まだまだこれからだ。全女性の悩みを解決するために、愛子先生には永遠に生きていただきたい。