【書き下ろし 新作怪談つき】本当に怖い、文豪の怪談セレクション

夏といえば“怪談”。夏目漱石から京極夏彦まで、新旧の大作家によるとっておきの怪談をご紹介します。怪談作家・黒史郎さんによる書き下ろし怪談『ピエロ』もお楽しみください。
夏本番。夏といえば、怪談話に花が咲く季節です。
テレビのホラー映像やネット上に蔓延する都市伝説もいいけれど、読書家の皆さまの中には、背筋がゾッと冷たくなるような、でも読み応えのある怪談を読みたい――なんてお考えの方も多いのでは。
そこで今回P+D MAGAZINEでは、日本の大作家が書いた短編小説、ショートショートから、本当に怖い、とっておきの怪談を集めてみました。
記事の最後には、人気怪談作家・
怖いのは姿の見えない「赤帽」? それとも――芥川龍之介『妙な話』

『妙な話』収録/出典:http://amzn.asia/f4vORNm
短編小説の名手であった芥川龍之介。若き日の彼が怪談話の蒐集に凝り、日本に限らず西欧の怪奇小説、幻想小説まで愛読していた――というのは、あまり知られていない事実です。
1910年、日本における民俗学研究の先駆けであるとともに、実話怪談の原点とも言える柳田國男の『遠野物語』が、私家版として数百部限定で刊行されました。当時はまだ文学的評価が高くなかった『遠野物語』。しかし18歳の芥川は、限定版だった同作を早速購入し、愛読していました。友人へ宛てた手紙にも「大へん面白く感じ候」(『芥川竜之介書簡集』より)と綴っています。
そんな彼が、自らも怪談の執筆に傾倒するのは自然なことだったと言えるでしょう。今回は、芥川が1922年に発表した『奇怪な再会』という怪奇小説集の中から、珠玉のショートショート『妙な話』をご紹介。
『妙な話』
ある冬の夜、私は旧友の村上と一しょに、銀座通りを歩いていた。
「この間千枝子から手紙が来たっけ。君にもよろしくと云う事だった。」
村上はふと思い出したように、今は佐世保に住んでいる妹の消息を話題にした。
「千枝子さんも健在だろうね。」
「ああ、この頃はずっと達者のようだ。あいつも東京にいる時分は、随分神経衰弱もひどかったのだが、――あの時分は君も知っているね。」
「知っている。が、神経衰弱だったかどうか、――」
「知らなかったかね。あの時分の千枝子と来た日には、まるで気違いも同様さ。泣くかと思うと笑っている。笑っているかと思うと、――妙な話をし出すのだ。」
村上と近くのカフェに入った「私」は、村上の妹・千枝子が神経衰弱だった時期の話を聞くことに。当時の千枝子は、夫が戦争で地中海に派遣されていたこともあり、村上の目から見ても随分不安定な様子でした。
ある日、自分から「鎌倉へ行く」と出かけていった千枝子は、列車の停車場まで行ったところでおかしな“赤帽”(乗降客の荷物係)を目にし、真っ青になって帰ってきます。見ず知らずの赤帽の男が、千枝子を見るなり「旦那様はお変りもございませんか。」と言った、というのです。
翌日からかれこれ三日ばかりは、ずっと高い熱が続いて、「あなた、堪忍して下さい。」だの、「何故帰っていらっしゃらないんです。」だの、何か夫と話しているらしい
譫言 ばかり云っていた。
千枝子はそのあとも、2年ぶりに帰ってくる夫の同僚を迎えに行った停車場で、「旦那様は右の腕に、御怪我をなすっていらっしゃるそうです。」「奥様、旦那様は来月中に、御帰りになるそうですよ。」とまたもや見ず知らずの赤帽たちから話しかけられ、気味悪がります。
そして翌月、ようやく帰国した夫は、実際に右腕を怪我していました。千枝子が聞くと、夫は地中海で体験したという妙な話をします。
あるカッフェへ行っていると、突然日本人の赤帽が一人、
卓子 の側へ歩み寄って、馴々しく近状を尋ねかけた。(中略)酔っている同僚の一人が、コニャックの杯をひっくり返した。それに驚いてあたりを見ると、いつのまにか日本人の赤帽は、カッフェから姿を隠していた。一体あいつは何だったろう。
――村上がここまで話したところで、カフェに村上の友人が現れ、「私」と村上は挨拶を交わし、別れます。そして物語は、「私」のこんな独白で終わるのです。
私は立ち上がった。
「では僕は失敬しよう。いずれ朝鮮へ帰る前には、もう一度君を訪ねるから。」
私はカッフェの外へ出ると、思わず長い息を吐いた。それはちょうど三年以前、千枝子が二度までも私と、中央停車場に落ち合うべき密会の約を破った上、永久に貞淑な妻でありたいと云う、簡単な手紙をよこした訳が、今夜始めてわかったからであった。…………
不気味な子供を捨てるため、歩き回る――夏目漱石『夢十夜』
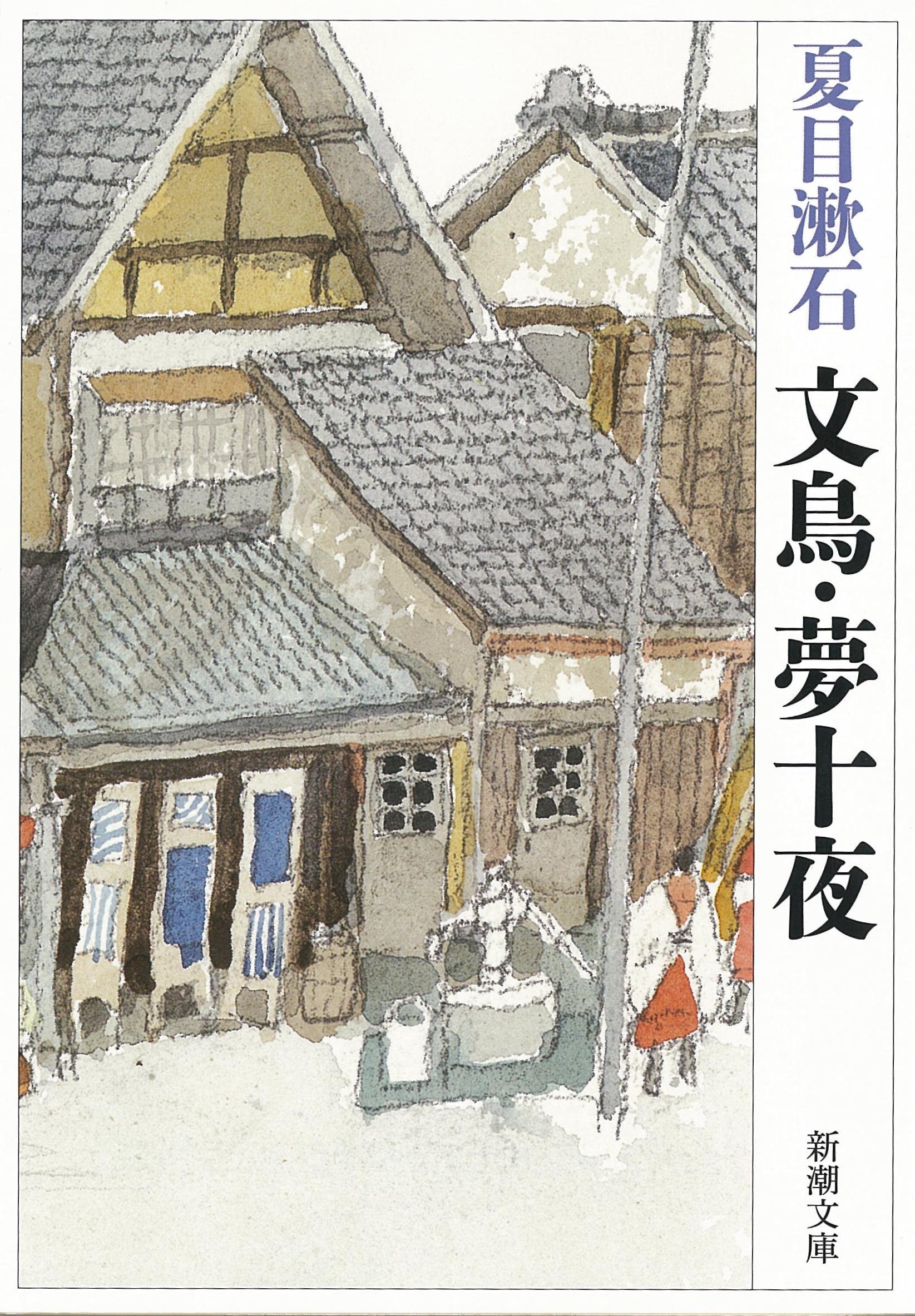
出典:http://amzn.asia/93Eln13
「こんな夢を見た。」という書き出しで有名な、夏目漱石の短編小説『夢十夜』。『夢十夜』はその名の通り、時代も舞台も違う10個の“夢”で構成されています。
文芸評論家としての顔も持つ小説家の伊藤整は、『夢十夜』を「現実のすぐ隣にある夢や幻想の与へる怖ろしさ、一種の人間存在の原罪的不安がとらへられてゐる。この試作的な作品によつて彼はその内的な不安な精神にはつきりした現実感を与へたのである。」(『作家論』より)と評しています。
特に怪談的な趣が強いのは、やはり、ひとりの男が子供を捨てる場所を探して歩き回る第三夜でしょう。伊藤整の評論のとおり、ただ不気味なだけでなく、人間の“原罪”について考えさせられるような物語です。
『夢十夜』第三夜
こんな夢を見た。
六つになる子供を負 ってる。たしかに自分の子である。只不思議な事には何時の間にか眼が潰れて、青坊主になっている。自分が御前の眼は何時潰れたのかいと聞くと、なに昔からさと答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。
「自分」はやがて、目が見えないにもかかわらず、やけに勘の鋭い子供のことが怖くなり、「どこか
あすこならばと考え出す途端に、背中で、「ふふん」と云う声がした。
「何を笑うんだ」
子供は返事をしなかった。只
「御父さん、重いかい」と聞いた。
「重かあない」と答えると
「今に重くなるよ」と云った。
「自分」は子供を背負って田畑の中を歩くうちに、どんどんと嫌な気持ちになってくるのです。
早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。
「もう少し行くと解る。――丁度こんな晩だったな」と背中で独言の様に云っている。
「何が」と際どい声を出して聞いた。
「何がって、知ってるじゃないか」と子供は嘲ける様に答えた。すると何だか知ってる様な気がし出した。けれども判然とは分らない。(中略)「此処だ、此処だ。丁度その杉の根の処だ」
雨の中で小僧の声は判然聞こえた。自分は覚えず留った。何時しか森の中へ這入っていた。一間ばかり先にある黒いものは愼 に小僧の云う通り杉の木と見えた。
「御父さん、その杉の根の処だったね」
「うん、そうだ」と思わず答えてしまった。
「文化五年辰年だろう」
成程文化五年辰年らしく思われた。「御前がおれを殺したのは今から丁度百年前だね」
自分はこの言葉を聞くや否や、今から百年前文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、一人の盲目を殺したと云う自覚が、忽然として頭の中に起った。おれは人殺 であったんだなと始めて気が附いた途端に、背中の子が急に石地蔵の様に重くなった。
雨の日の晩、うずくまる女の正体は――『うずくまる』京極夏彦

『うずくまる』収録/出典:http://amzn.asia/iW9h71m
平成を代表する怪奇小説家、京極夏彦。多作な彼は、妖怪研究家の顔も持つ怪談マニアです。今回ご紹介するショートショートが収録された『旧談』は、江戸時代中期から後期にかけて書かれた書物『
『うずくまる』は、中でも特に怪談らしい、短いながらも上質な物語。その意外なラストには、思わずわっ、と声を上げてしまうのではないでしょうか。
『うずくまる』
Uさんは、私(根岸)の遠縁にあたる、謹厳実直な武士である。
今はもう隠居してしまったが、現役時代はどんな役向きを振られても不平不満を言わず、コツコツと勤め上げるタイプの、所謂真面目人間だった。
そのUさんが、まだ四十代の頃のことだ。
ある暴風雨の夜、Uさんは当番仲間からの緊急の呼び出しを受けて、お供を連れて大雨の中、家を飛び出します。
番町馬場あたりに差しかかった時のことである。
――うずくまっている。
路肩に、女がうずくまっていた。
いや、女だと思ったのだが、女ではないかもしれなかった。
一本道である。雨は益々強く降り注いでいる。提燈で照らして確認する訳にも行かない。
Uさんは咄嗟に、「嵐の夜に道端に女性がうずくまっているというのはおかしい。それなら」と考えます。
Uさんは振り向かなかった。
代わりに伴の侍が振り向いた。
Uさんが幻覚ではないと言ったのは、目撃者がもう一人いたからなのである。
「あのう」
伴侍は言った。
「あれは――何でしょう。その、戻ってよく見てみたほうがいいでしょうか」
「やめなさい」
とはいえ、気になったUさんも来た道を振り返ります。しかし、たったいまうずくまる女を見たはずの場所には、もう誰もいません。
どうにか仕事場の門前についたUさんとお伴の侍は、その瞬間に大変な寒気を感じ、意識が遠のいてしまいます。迎えに出て来た同僚に介抱されたものの、Uさんもお供も、20日もの間、寝込んでしまうのです。
「お供の侍はね、あれは、
瘴癘 の気が雨の中に凝り固まったものだったんです――なんて、いまだに言うんですがね、さてどうでしょうな。」(中略)それよりね、とUさんは続けた。
介抱してくれた同僚は後々、語り種のようにこう言うのだそうだ。
――あの夜あんたたちを見つけた時は、それは驚いたなあ。一瞬、化け物かと思ったよ。なんせ雨の中、門前に二人でうずくまっているんだから。
「うずくまっていたんですよ、私たちも」
Uさんはそう言って、もう一度笑った。
友人の部屋に残る、「変な顔」の落書きを消した跡――黒史郎『ピエロ』

最後にお届けするのは、怪談作家・黒史郎さんの書き下ろし怪談『ピエロ』。
白い顔におどけた表情のピエロを見て、なんだかゾクッとしたことのある方はきっと少なくないのでは。これは、そんなピエロが怖くて怖くて仕方ない、「ピエロ恐怖症」に陥った人をめぐる物語です。
黒史郎
「夜は一緒に散歩しよ」で第一回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞し、デビュー。著書に「幽霊詐欺師ミチヲ」シリーズ、『未完少女ラヴクラフト』『童提灯』など。近刊は『乱歩城 人間椅子の国』。
『ピエロ』
木田さんはピエロが怖い。
あの作り笑いを浮かべる白塗りの顔を見るだけで不安をおぼえ、異常な量の汗をかき、ひどいと過呼吸になることもあるという。実際、ピエロ恐怖症なるものがあるそうだが、ピエロに馴染みのない日本人がこれほど恐れを抱くというのも珍しいケースではないだろうか。
これは木田さんが中学時代に体験した、ピエロを恐れるきっかけとなった出来事である。夏休みの初め、クラスメイトの黒川の家へ初めて遊びに行った。
立派な3階建ての家で、黒川の部屋は3階にあった。その部屋は人に貸していたそうだが、先月、その人が急に出ていったので、今は自分の部屋として使っているのだという。
家具と呼べるものがほとんどなく、広いわりには照明の光が弱くて、部屋の隅が薄暗い。そのせいか、妙に空気が重く感じられ、あまり居心地はよくなかった。
2人でゲームをやっていると、木田さんは部屋の壁に塗り潰したような跡があるのに気付き、あれは何かと訊ねた。「落書きを消した跡だよ」
この部屋を借りていた人が壁に「変な顔」を描いたらしい。
よく見ると、塗り潰した所にうっすらとだが、目や顔の輪郭らしき線が確認できる。
かなりの変人だったようで、黒川の父親に落書きしたことを咎められると「この部屋には幽霊がいる」と妙な苦情をいいだし、その日のうちに夜逃げしてしまったらしい。そんな話をしている途中、黒川は何かを思い出したような顔で、「ちょっとごめん」と部屋を出ていった。
それからなかなか戻ってこず、腹でも痛くなったのかと心配していると、30分ほどしてから戻ってきた。「おまえ、なんだよ……それ」
どこで何をしてきたのか、黒川の顔は真っ白だった。
白い塗料を顔中に塗り、鼻だけを真っ赤に染めている。まるで、できそこないのピエロだ。
困惑する木田さんをよそに、何事もなかったような顔でゲームを再開する。
——なんだよ、これ。笑えない冗談だな。
冗談ならそれらしく振舞ってくれればいいのだが、白塗りの黒川は無表情で、妙に緊張させる空気をまとっている。これでは、せっかくのゲームも楽しめない。
もう帰ろうと立ち上がると、「カエルナヨォ」
部屋に響きわたった声は黒川のものではない。おどけた中年男の声だった。
木田さんを見上げる黒川の顔は、膨張した水死体のように表情の失せ切った、まったく別人のものだった。
「また来るから」と言い残し、逃げるように部屋を後にしたという。夏休みが終わり、学校で再会した黒川は何事もなかったように話しかけてきたが、木田さんは少しずつ距離を置くようになった。そのうち避けられていることがわかったのか、ある頃から話しかけてこなくなった。
気がつけば、木田さんは白塗りの顔を見るだけで身体が拒否反応を起こすようになっていたそうだ。「これはあくまで僕の想像なんですが」
あの部屋で塗り潰されていた壁の絵は、ピエロの顔だったのではないか。
そんな気がしてならないそうだ。
おわりに
新旧の小説家による怪談話セレクション、お楽しみいただけたでしょうか。
暑くて寝苦しい夏の夜は、ゾクゾクするような怪談をお供に、ちょっと夜更かししてみるのもいいかもしれません。
……噂によると、怖い話のあるところには、自ずと怖いものが集まってくるのだとか。ひとりの部屋で怪談を読むときは、扉や窓をぴったり閉めて、くれぐれも後ろは振り返らないようにしてくださいね。
初出:P+D MAGAZINE(2017/08/08)

