虚無を抱えたまま生きる 金原ひとみ おすすめ4選

2004年『蛇にピアス』で第130回芥川賞を20歳で受賞し、注目を集めた金原ひとみ。人間が抱える根源的な孤独感や、やり場のない心情を、ときに繊細にときに生々しく描いてきました。そんな著者のおすすめ作品4選を紹介します。
『デクリネゾン』コロナ禍で更新される、死生観と恋愛観

https://www.amazon.co.jp/dp/4834253619
コロナによる初の緊急事態宣言が出された東京。中学生の娘と2人で暮らす作家の
私たちは広大で、絶え間なく移り変わっていく世界の一瞬を生きる、本来は名前すら持たない生物だ。名前を与えられ、意味付けされ、人間社会に投げ込まれ、繁殖したり労働したりはするけれど、それぞれはただの1つの肉塊だ。そして肉塊だからこそ、私はやっぱり死刑制度には反対だ。すべての肉塊に、生きるべきも死ぬべきもない。少なくともそれは肉塊が肉塊に押し付けるべきものではない。
志絵は、日本政府のコロナへの対応にも疑問を感じます。
苦しんでいる人のことを思いやれ、人の気持ちを考えろと綺麗事と忖度を押し付けられ、あらゆる抑圧の中で自尊心を傷つけられ、苦しむ人は誰かに怒りをぶつけるよりも自死を考えるパターンが出来上がっている日本という国が、どうしても受け入れられない。フランスではお金を出さずにロックダウンなんてしたら国民が暴徒化するに決まってるから休業補償が出たのだし、これまでもデモを繰り返し、弱者を搾取抑圧する政策を可決しようとすれば暴徒化するという事実を裏付けてきた国民がいたからこそ、政府がそれに呼応してきた経緯もあるはずだ。
パリ在住歴がある著者ならではの、日本を相対化してみる眼が光っています。
コロナ禍は、人々の恋愛にも影響を与えます。年下の彼氏がいる志絵は、外出が制限され恋人と会えない日々を過ごすよりは、同棲・結婚に踏み切ろうとしますが、志絵の娘は、外部からウイルスが持ち込まれる機会が増えるからと、難色を示します。危険を冒してでも会いたい人かどうか――コロナを機に関係が進展した人、不倫を精算しなければならない人など、その状況はさまざまで、まさしく「人生の本気度が試されているときだ」と、志絵の担当編集者は言います。
タイトルとなった「デクリネゾン」とは、フランス語で、例えば豚肉なら豚肉の、様々な部位を使った変化に富んだ調理法を指します。たとえ人間が「肉塊」に過ぎなくても、他の肉塊を食べなければ生きていけないのもまた事実。作中に出てくる食べ物の官能的な描写も読みどころです。
『ミーツ・ザ・ワールド』27歳腐 女子 、婚活しないとダメですか?

https://www.amazon.co.jp/dp/4087717771/
「男で孤独が解消されると思ってんの? なんかあんた恋愛に過度な幻想抱いてない? なんかさ、2次元と3次元とか、世の中そういうの細分化しすぎだよ。自分が一緒にいて心地いいものとか、好きだって思えるものを存分集めて
愛 でればいいじゃん」
また、ライを介して知り合ったホストのアサヒからも、セックスはもともと気持ち悪いものなのだから、本当に好きな人ができるまで無理する必要はないと諭され、目から鱗が落ちた由嘉里。普段は関わることのない属性の人々と出会い、由嘉里は本来の自分らしさを取り戻します。そして、一見華やかなライに自殺願望が絶えないことを知ります。自分自身をこの世界から消し去りたいと言うライには、金銭にもグルメにも一切合切に執着がありません。由嘉里は、その原因が過去の失恋にあるのではないかと探りを入れ、力になりたいと思います。けれど、そのことに周囲は懐疑的です。
「そうやって(死にたい)端的な理由を知りたがるの良くないわよ。結局、親が死んだって子供が死んだって、どんなに絶望したって生きてく人は生きてくのよ。親が死ななくても子供が死ななくても、死ぬ人は死ぬのよ。生まれ持った生命力みたいものってやっぱりあるのよ」
「距離感間違えてね? ゆかりんもこの東京砂漠を生き抜いてんだから人との適切な距離感分かるよね? 暑苦しいのとか人情的なのとか恥ず! って感じ分かるよね?」
人に迷惑をかけなければ最大限の多様性が尊重される現代において、なぜ死を自由に選ぶ権利が認められないのか。この点については、平野啓一郎の近著『本心』でも考察されているのですが、日本の若い女性の自殺が増えている現在、看過できない問題です。そんな中、ライが300万円を残して失踪します。不器量なために恋愛に前向きになれない由嘉里に、「300万円あれば整形できるが、その勇気はあるか?」と言っていたライの言葉がよみがえります。
妄想の世界に生きる腐女子と、派手で誤解されがちなキャバ嬢。正反対の2人が出会って開ける新しい世界を描く青春小説です。
『持たざる者』東日本大震災と原発事故後の世界を、粛々と生きる人々の姿
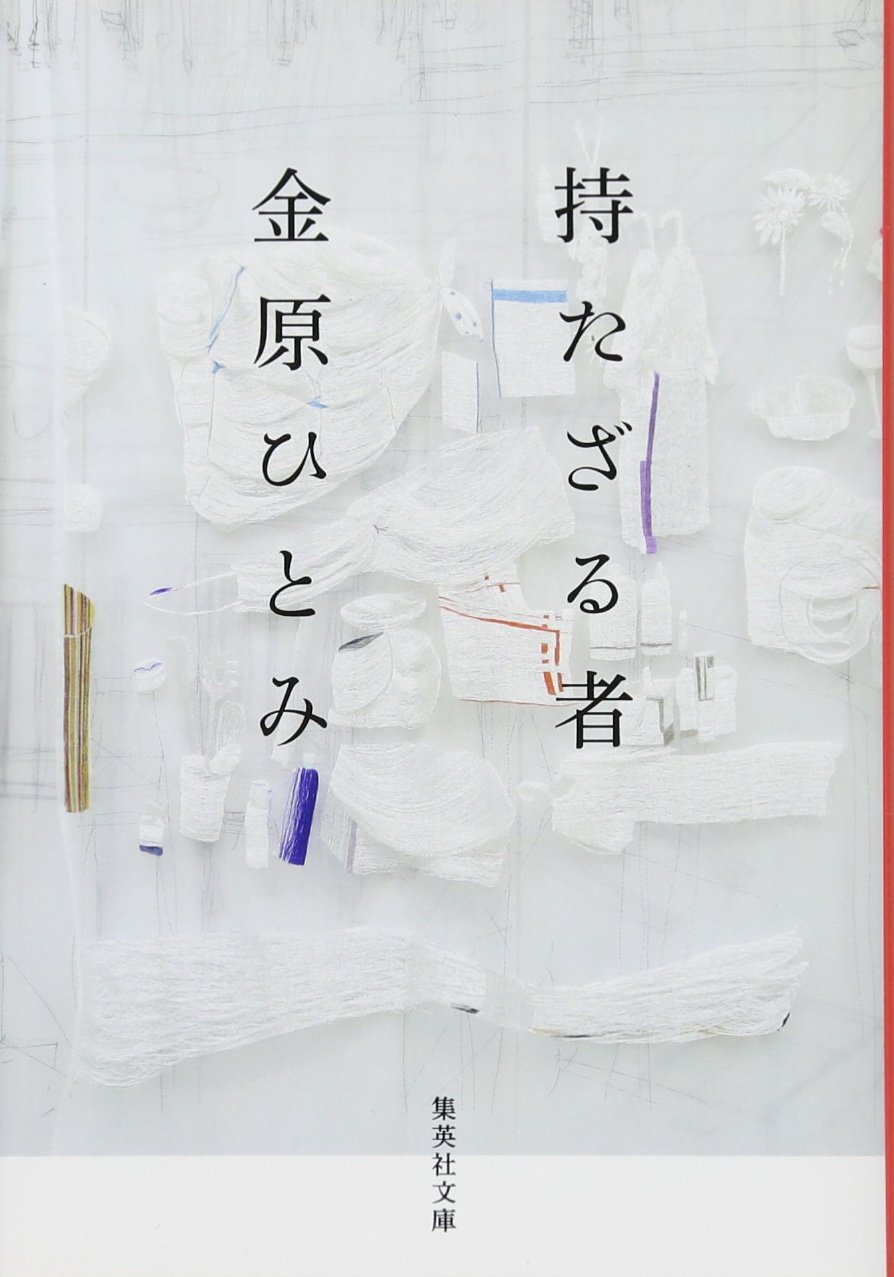
https://www.amazon.co.jp/dp/4087457370/
2011年に起きた東日本大震災から2年後の世界。東京在住だった日本人女性エリナは、福島の原発事故による放射能汚染を恐れ、幼い娘と2人でイギリスに移住します。そのことを行動的で賢いと褒める人もいれば、移住できない人の気持ちも考えろと
私は自分自身の選択でイギリスに来たわけではなくて、そこに自分自身の選択など皆無だった。人生に於ける岐路を自らもまた選択出来ない。岐路が浮上した時点で既に結果は出ている自然現象のようなものであり、その決定事項に私も他人も何ら変更は加えられないのだ。私は一度も選んだことはない。私はただ、決められた一本道をひたすら歩いて来ただけだ。私の意志や努力でつかみ取った道ではない。私の性質と状況との兼ね合いで決まった現実だ。
職業や居住地、パートナーなどは、選んでいるかに見えて、選ばされているだけだという無力感を持つのはエリナだけではないでしょう。
本作では、放射能への対策をめぐって、移住をするか、その場に住み続けるかで意見が対立する家族たちが登場します。放射能という目に見えない脅威は、目に見えないものだけに情報は錯綜し、人々の対応の仕方も様々であるわけですが、中には放射能問題がきっかけで価値観の違いが顕在化して、離婚に至る夫婦もいるようです。
私はもう楽しさの先にある虚無を知っている。人はどうせ生まれて食べて糞して死ぬ。粛々と生きて粛々と死んでいく。どんな人生を送ったってそれしか出来ない。人生の中で、楽しさなんてものはほとんど無意味だ。そんなものに
現 を抜かせるのは若い内だけで、それが無意味だと気づいた瞬間から、長い長い余生が始まる。震災から1年が過ぎた頃、私はふと、唯一無二の存在だと思っていた自分自身が、いつからか多数の人々に埋もれる1つの点になっている事に気がついた。元々、私は点だったはずだ。自分は唯一無二であるという思い込みが打ち砕かれただけだ。自分を唯一無二と思うその幻想は、余裕の象徴なのかもしれない。
「人生はすべてが徒労である」と悟ってしまっても、それでも生を手放すわけにはいかない人々の姿を描いています。
『アタラクシア』人間にとっての「モラル」とは、内発的なものか、外発的なものか

https://www.amazon.co.jp/dp/4087443833/
「他人に対する優しい気持ちも大切にしたいって気持ちも、モラルからじゃなくて抗えない愛情から生じるものであって欲しい。私はモラルから引き起こされる愛情なんて欲しくない。この人を愛するべきだ、なんて思われて愛されるのは嫌だし、モラル的にこの人を傷つけるべきじゃないと思われて、心は離れているのに一緒に居られるのも嫌。結局モラルを人の心の中に求めるのは不可能だから、モラルを外部化しようって流れが主流だと思うよ。人の外にあるルールとして、例えば監視カメラが記録してる、SNSもネットも監視されてる、そういう形で人の生きやすい世界の秩序を管理する世の中になってきてるんだよ。私は世の中なんてそれでいいと思っている」
突然、桂に離婚したいと言い出した由依。その理由は、過去に由依が桂との子供を死産して以来、子供を持ちたくないと思っていたことや、桂に盗作疑惑が持ち上がったこととは関係がありません。むしろそうした分かりやすい理由があればよいのですが、由依の心の内面は、余人の想像の範疇を越えており、双方の親族からも匙を投げられているほどです。それでも桂は由依への執着を手放せません。
「俺も不思議だね。由依は軽薄で、説明能力も欠けてるし、人と分かり合う努力もしない。もっと人の気持ちが分かる人だったらって思うし、実際そうなった方がいいと思ってるよ。でも由依を好きな気持ちはそういうのとはリンクもしていないんだ」
人の心はモラルでは縛れないものですが、結婚生活において、「アタラクシア」(激しい欲望から解放された、平静な心の状態のこと)は、いかにもたらされるのでしょうか。著者は本作で、優れた恋愛小説に贈られる渡辺淳一文学賞(第5回)を受賞しました。
おわりに
金原ひとみの作品は、人生に意味などないということを出発点として、そのなかでの人の生き方の諸相を描いています。そこに安易な慰めや励ましはなく、その救いのない世界にはうちのめされそうになりますが、救いのないことがかえって救いであるのかもしれません。『デクリネゾン』に、「ハッピーエンドの物語を読むと、かえって空しくなると思わない?」というくだりがありますが、それに共鳴できる人は、ぜひ著者の作品を手にとってみるとよいでしょう。
初出:P+D MAGAZINE(2022/09/13)

