小松原織香『当事者は嘘をつく』/性的暴行を受けた被害者の葛藤を語るノンフィクション
自身も性的暴行を受けた被害者であるという著者が、事態とむきあうデリケートな心模様を臨床哲学的な言葉でとらえた一冊。
【ポスト・ブック・レビュー この人に訊け!】
井上章一【国際日本文化研究センター所長】
当事者は嘘をつく
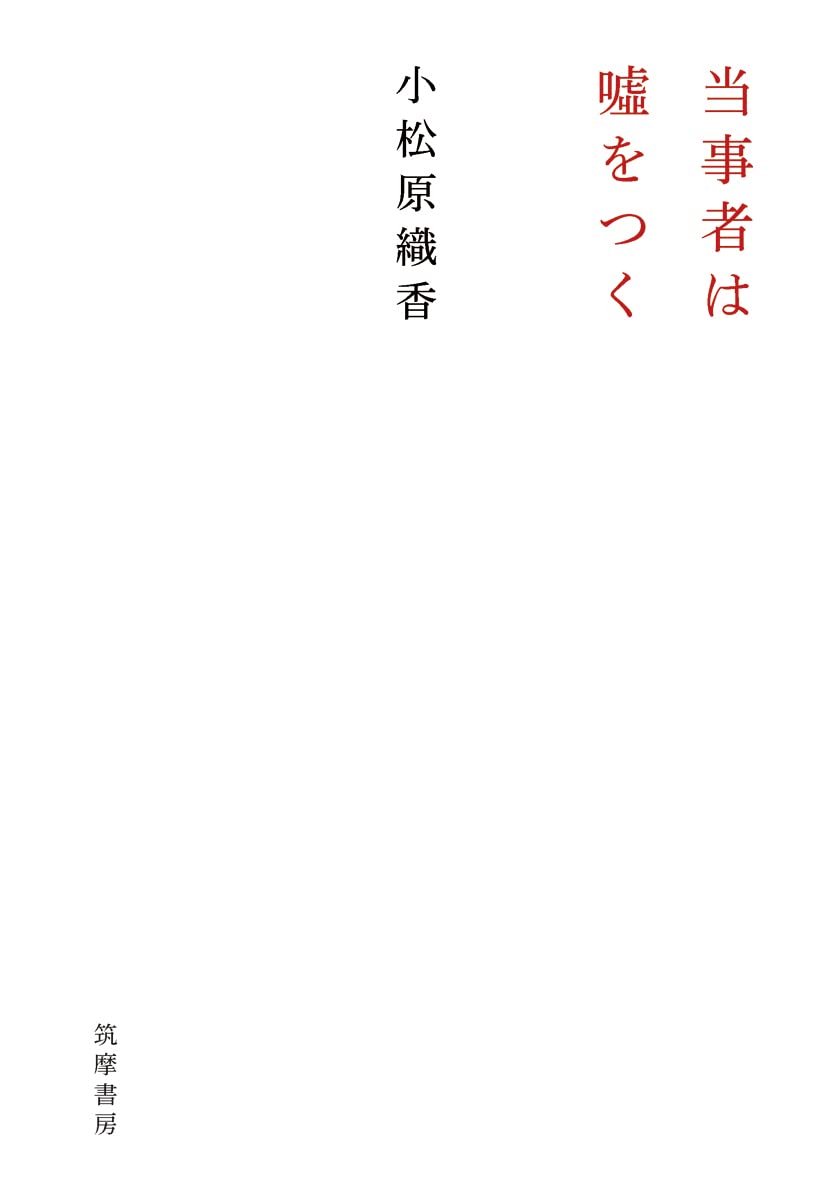
小松原織香 著
筑摩書房
1980円
装丁/鈴木成一デザイン室
むきあうポジションがもたらすデリケートな葛藤
性的暴力をうけた人たちは、その記憶をなくしたいと、よく思う。しばしば脳裏をよぎるその瞬間からは、遠ざかりたいとねがいやすい。そのため、事件をふりかえる言葉も、あいまいになりがちである。被害をわすれて生きのびたいという想いが、そのあやふやさに拍車をかけていく。
彼らを社会的にささえようとする支援者は、彼らなりの言葉で事態をくみたてる。たとえば、法廷闘争むきの弁論へ、おとしこもうとする。そこに、当事者は自己認識との違いを感じ反発しやすくなる。当人じしんの記憶はおぼろげになっていても、支援の言葉がはらむズレは、すぐわかる。あの人たちはわかってくれないと、どうしても感じてしまう。
いっぽう、被害者どうしの語りには、いやおうなく共感をいだく。それらは、サバイバルのために改変された記憶であったとしても、うけいれやすい。回顧の強度が潤滑油になるのだろうか。こうして、他人の言葉は、しばしば自分の言葉にまぎれこむ。あるいは、すりかわる。被害者たちは、生きのこりをかけて、嘘をつくようになっていく。
被害者は、いちばん近くでよりそう支援者を、にくむことがある。支援者たちも、当事者どうしのつながりを、しばしば嫌悪する。そんな壁が、不幸なことだが、両者のあいだにはできているらしい。
著者は性的暴行の被害者であるという。だから、今のべたような違和感をいだきつつ、この問題にあたってきた。
だが、数年前から、いわゆる水俣病ともむきあうようになる。研究課題に、この公害をえらんだのである。性暴力の場合とちがい、自分が被害者になることはありえない。当事者の語りから研究にいかせそうな部分だけを、つまみ喰いしてしまう。そうなりかねない立場に、身をおいた。
事態とむきあうポジションがもたらすデリケートな葛藤を、この本は語っている。その心模様をとらえようとする臨床哲学的な言葉の数々に、感心した。
(週刊ポスト 2022年9.16/23号より)
初出:P+D MAGAZINE(2022/09/14)

