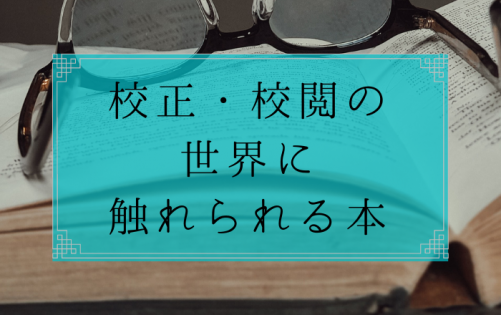ひとつの言葉に徹底的にこだわる。奥深き“校正・校閲”の世界に触れられる本3選
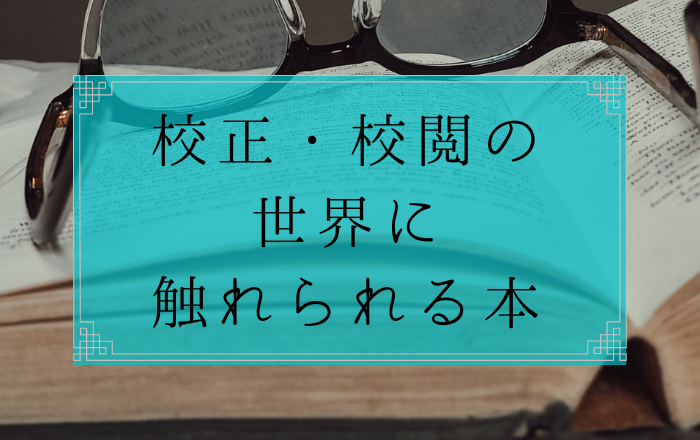
校正者が綴ったエッセイや、校正・校閲をテーマにした本のなかには、仕事上のこだわりや書物への深い愛情が垣間見られる、ユニークなものが多数存在します。今回は、そんな知的好奇心を満たしてくれる、選りすぐりの“校正・校閲本”をご紹介します。
1冊の本を完成させるにあたって欠かせない存在でありながら、普段は“縁の下の力持ち”として、ほとんど表舞台に立つことのない校正・校閲者。誤植や文法上の間違いに目を光らせるのはもちろん、文章中で言及されているできごとの時系列やファクトチェックまで細かくおこなうその姿は、まさに言葉のプロフェッショナルです。
校正者が綴ったエッセイや、校正・校閲をテーマにした本のなかには、仕事上のこだわりや書物への深い愛情が垣間見られる、ユニークなものが多数存在します。今回は、そんな知的好奇心を満たしてくれる、選りすぐりの“校正・校閲本”をご紹介します。
『文にあたる』(牟田都子)
.jpg)
出典:https://amzn.asia/d/2dpT4pr
『文にあたる』は、数々の書籍の校正・校閲を手がける人気校正者、
“人間の脳は優秀で、多少のノイズは無意識に補正して「読める」ようにしてしまうんですね。「読みたいように読んでいる」のだともいえます。校正として読むときはそうではなく、誤りは誤りとしてあるがままに読みたい。だから素読みのときは指先や鉛筆の先端で文字をひとつひとつ押さえ、指さし確認するようにして読んでいきます。文章を「読む」というより文字を「見る」というほうが実感に近いです。”
“読書をしているときには、難しいところを駆け足で飛ばしたり、自分の思考に迷い込んでページをめくる手が止まったりと、読み進むペースがまちまちということもあると思います。校正では、一定の速度を保って読みます。もちろん辞書を引いたり考えたりする時間はありますが、基本的には一文字を見るのに0.5秒なら0.5秒と、すべての文字に同じだけの時間をかけて見る。(中略)歩いて15分かかる道のりを走ったり抜け道を通ったりして5分に短縮するような読み方は、少なくともわたしにはできにくいです。”
集中力と忍耐力が必要とされる校正者の仕事は、書かれていることを“疑う”仕事でもあります。小説の著者本人が目を通したはずのプロフィールに誤植があったり、随筆のなかで触れられている映画のあらすじに大きな誤りがあったりすることは、決して珍しいことではありません。
校正者は物知りだと思われることがあるが、決してそうではない──と牟田は言います。スピードが求められる仕事のなかでも間違いを犯さないよう、典拠となる資料を必死に探して調べ、鉛筆を入れているのです。
“校正者なら誰もが百科項目に通じているわけではありません。知っていることばかりがゲラに書かれているとは限らない。単語ひとつであっても知らなければ辞書を引く。載っていなければ図書館やインターネットを使って調べる。書いているのは専門家だとはいえ、鵜呑みにできないのが校正です。”
本書は、仕事への真摯な姿勢が伝わってくるのはもちろん、時代やシチュエーションによって変わる言葉、“本来は誤り”であっても著者の意図を汲んで活かす言葉など、校正者が一筋縄ではいかない言葉と日々どのように向き合っているかを、その葛藤も含めて知ることのできる貴重な1冊です。
『校正のこころ──積極的受け身のすすめ』(大西寿男)
.jpg)
出典:https://amzn.asia/d/a0i8aDL
『校正のこころ──積極的受け身のすすめ』は、校正者という仕事のあり方について綴られた1冊です。著者の大西寿男は2022年、NHKの人気ドキュメンタリー番組『プロフェッショナル』にも出演し話題となった熟練の校正者で、文芸書の校正を中心に、30年以上のキャリアを持つ人物です。
大西は、校正者の仕事に必要とされる姿勢は、“積極的受け身”だと説きます。
“校正者は日々、じつにたくさんのさまざまな言葉と向きあいます。世の中には人の数だけ言葉がありますから、自分の価値観や感覚とちがっていてもあたりまえ。(中略)そこで校正者は、校正刷(「ゲラ」といいます)を読み進めるなかで、辞書を引き、インターネットで検索し、図書館へ行き、何度も立ち止まり振り返って、そこに書かれてあることを理解し、感じ取ろうと努めます。理解できない限り、この文字が誤字なのか、この表現が適切かを判断することはできません。校正の読みは、読書とはまた異なる、ちょっと変わった言葉との向きあい方、付きあい方です。”
“初対面の人の話に耳を傾け、いろいろ質問して(失礼にならないように気をつけながら)、その人となりを知り、語ろうとしていることを理解し、何が必要かを把握しようとする感じ、といえばよいでしょうか。言葉の理解のために、みずから進んで受け身となる「積極的受け身」の態度がそこにはあります。”
フェイク・ニュースが飛び交い、言葉ひとつひとつの重みが軽視されてしまっているこの時代だからこそ、“言葉が満たされ成就することをめざす校正の態度や考え方は、とても有効ではないか”と大西は問いかけます。
本書のなかで大西は、校正という仕事の歴史を古今東西に到るまで紐解きながら、現代のかたちに合った校正の方法論を説いていきます。駆け出しの校正者や本に関わる仕事をしている人にとっての必読書であるのはもちろん、言葉に真摯に向き合う大西の姿勢は、人とのコミュニケーションを日々模索している現代人にとっても学びの多いものであるはずです。
『カンマの女王』(メアリ・ノリス)
.jpg)
出典:https://amzn.asia/d/dDYO7mV
『カンマの女王』は、アメリカの老舗雑誌『THE NEW YORKER(ニューヨーカー)』のベテラン校正係であるメアリ・ノリスによるエッセイ集です。本書には、著者が校正者としてカンマ記号(,)の位置ひとつに到るまで決して見逃さない、タイトル通りの「カンマの女王」になるまでの道のりや、日々『ニューヨーカー』に掲載される原稿に向き合うなかで考えることなどが、率直な文章とともに綴られています。
日本語話者は、漢字・ひらがな・カタカナという3つの表記法を持つ日本語のことを、しばしば「これほど複雑で難しい言語はない」と評します。しかし、本書を読み進めるうちに、英語には英語特有の難しさがあることが見えてくるはずです。著者は、英語のスペルの複雑さについてこのように語ります。
“英語という言語には、スペルを間違わせようと手ぐすね引いて待ち構えている単語がごまんとあるし、世界にはやかましい方々がたくさんいて、いまにも飛びかかろうとしている。われらが英語は、イタリア語やスペイン語や現代ギリシャ語のように、一定の文字や文字の組み合わせが一定に発音できるとはかぎらない。英語には発音しない「黙字」が多い。そして、起源がごちゃまぜだから、解きほぐすのが恐ろしく難しい。”
“スペルを間違わせようと手ぐすね引いて待ち構えている単語がごまんとある”という表現には思わず笑ってしまいますが、著者は「weird」という言葉がよく「werid」と書き間違えられることなどを例に挙げながら、その油断のならなさを強調します。
また、言葉の誤りを指摘する校正者は、しばしば人に怖がられるものだと著者は告白し、その苦悩を綴ります。
“校正者は魔女みたいなものだとみんなから思われているのをわたしはつい忘れてしまうので、誰かに怖がられるとびっくりする。このあいだも、『ニューヨーカー』の社内を初めて 案内されていた若い編集助手が、わたしの執務室の前に立ちどまり、わたしが校正者だと聞いたとたん、飛びのいた。まるでわたしが真っ赤に焼けたハイフンを突き刺したり、カンマを口に押し込んだりすると思ったみたいに。落ち着いて、と言いたかった。会話でも印刷物でも、わたしは人間を校正する習慣はない──それが出版予定でかつ依頼されないかぎり。つまり、お金をもらわないかぎり。”
そして、校正者とは、“一貫性をがちがちにたてまつる人間”、“他人の間違いを指摘するのを好む陰湿な人間”だと冗談交じりに言いながらも、“ほんとうにすごい書き手は編集のプロセスを楽しむ”ので、間違いや疑問を指摘することを恐れなくともいいのだと語ります。
本書は、英語の校正にまつわる豆知識やよくあるミスを知ることができる本として有用なだけでなく、著者の毒っ気のあるユーモアが遺憾なく発揮された一流のエッセイとしても楽しめます。細かすぎる誤植に気づいたことで作家に感謝され、ゲラ上でプロポーズされたという逸話や、オバマ前大統領もしばしば用いていたという、文法上では誤りではあるものの英語話者に好まれるフレーズなど、読んだら人に話したくなるようなエピソードが満載の1冊です。
おわりに
言葉ひとつひとつに目を光らせる校正者の仕事は偉大でありながらも、スポットが当てられることはほとんどありません。本や雑誌の読者にとっては、言葉は「間違っていないのが当たり前」であり、校正者の存在を意識するのは、出版物のなかに誤植を見つけてしまったときくらいでしょう。校正者は、完璧な仕事をしていても褒められず、ミスを犯してしまったときにだけ非難されてしまう、損な役回りともいえます。
しかし、大西寿男がその著書のなかで指摘しているように、言葉の意味や意義が軽いものになりつつあるこの時代だからこそ、“言葉が満たされ成就することをめざす校正の態度や考え方”を知るのは、非常に大切なことであるように思えてなりません。
初出:P+D MAGAZINE(2023/02/01)