東日本大震災から10年。いまだからこそ読みたい、震災文学3選

2021年3月11日、東日本大震災の発生から丸10年を迎えます。なかには、この10年で震災のことを考える機会が減ったという方もいらっしゃるかもしれません。今回は、震災で失われたものとこれからの未来についてあらためて考えるきっかけとなるような小説を、3作品ご紹介します。
今年の3月11日で、東日本大震災の発生から丸10年を迎えます。すこしずつ復興を遂げてきた場所があることは大きな希望ですが、震災の爪痕はいまだに各地に残っており、10年という歳月があまりにもあっという間に経過してしまったことに驚いている方も多いことでしょう。
2011年から月日を重ねるなかで、震災を直接的・間接的にテーマとして扱った小説作品も多数生まれてきました。震災の直後はリアルタイムすぎてそのような作品が読めなかったという方もいらっしゃると思いますが、節目の年であるいま、あらためて当時のことを考えてみてもよいかもしれません。今回は、いまだからこそ読みたい、震災をテーマにした文学作品をご紹介します。
『想像ラジオ』(いとうせいこう)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B00TX5DLJK/
『想像ラジオ』は、小説家・ラッパー・タレントなどとしてマルチに活躍する、いとうせいこうによる長編小説です。いとうは、本作で第35回野間文芸新人賞を受賞しています。
こんばんは。
あるいはおはよう。
もしくはこんにちは。
想像ラジオです。
こういうある種アイマイな挨拶から始まるのも、この番組は昼夜を問わずあなたの想像力の中でだけオンエアされるからで、月が銀色に渋く輝く夜にそのままゴールデンタイムの放送を聴いてもいいし、道路に雪が薄く積もった朝に起きて二日前の夜中の分に、まあそんなものがあればですけど耳を傾けることも出来るし、カンカン照りの昼日中に早朝の僕の爽やかな声を再放送したって全然問題ないからなんですよ。
物語は、“DJアーク”こと、芥川冬助という人物のこんな言葉で幕を開けます。彼はラジオDJで、人々の“想像力”を電波のようにして自分の声を届けているのです。
読み進めていくと、DJアークは震災の津波による被害で命を落とした人物であり、彼の“声”が届くのは、同じく被災して亡くなった人々であることがわかります。彼の“想像上”の番組には昼夜を問わずさまざまな被災者からの声が届き、DJアークはそのお便りに応答しつつ、さまざまな音楽をラジオに乗せて流します。
彼の“想像ラジオ”はときどき現実の世界と混線し、被災地でボランティアをしている人の耳に聴こえてしまうこともあります。ラジオの音声のようなものが聴こえると訴える人に、ボランティアのリーダー格である若者は、こう言います。
「あのですね、俺らは生きている人のことを第一に考えなくちゃいけないと思うんです。亡くなった人への慰めの気持ちが大事なのはよくわかるんですけど、それは本当の家族や地域の人たちが毎日やってるってことは体育館でも仮設住宅でもいくらでも見てきたじゃないですか。段ボールで位牌作ってでも、皆さんは鎮魂をしています。
その心の領域っつうんですか、そういう場所に俺ら無関係な者が土足で入り込むべきじゃないし、直接何も失ってない俺らは何か語ったりするよりもただ黙って今生きてる人の手伝いが出来ればいいんだと思います。」
正義感の強い彼は、直接被災していない者に死者の声が聴こえるなんて思い上がりだ、被災者の痛みは被災者にしかわからないはずだ──と訴えます。その話を聞いたボランティアに来ている人々は彼の話にうなずきつつも、それでも“聴こえてしまう”ことを静かに告げるのです。
いとうは震災後の無力感のなかで本作を執筆したと語っており、想像すれば絶対に聴こえるはずだ、想像力まで押し潰されてしまったら自分たちには何が残るんだ──という強い気持ちがあったと刊行後のインタビュー等で語っています。本作は震災の被災者たちの苦しみだけでなく、あまりに壮大な喪失を前にしたときに、その喪失体験の当事者ではない人たちが何を感じ、考えることができうるかということについても、真摯に描こうとしている作品です。
『影裏』(沼田真佑)
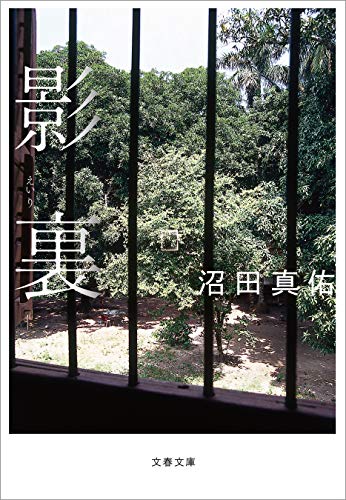
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07WZZMGQG/
『影裏』は、第157回芥川賞を受賞した、沼田真佑による短編小説です。
本作の主人公は、転勤で東京から盛岡市に移住してきた今野という男。人付き合いにあまり積極的ではない彼が唯一親しくなったのが、同じ会社の別部署に勤める日浅でした。彼らは趣味の釣りを通じて親しくなっていきますが、付き合いが1年ほど続いたある日、日浅が退職したということを、今野は同僚から唐突に告げられます。日浅のそんな掴みどころのない性格をどこか快くも感じていた今野は特に気にせず、数か月後にまたふらりと姿を現した日浅と、再び釣りに出かけるのでした。
しかし、3月11日の震災を機に、またもや日浅は姿を消してしまいます。その行方を追う今野は同僚から、かつて日浅に貸していた金が返ってきておらず、問い詰めようと電話した日浅の勤務先の上司に「彼は行方不明だ」と告げられたことを聞かされます。また、日浅の実家をひとり訪れた今野に、日浅の父親は「あれを捜すなど無益だ。おやめなさい」と鋭く言い放ちます。
日浅の父親を含む彼の周囲の人物は、日浅のことを皆、悪し様に語ります。しかし、今野だけは日浅のことを、
そもそもこの日浅という男は、それがどういう種類のものごとであれ、何か大きなものの崩壊に脆く感動しやすくできていた。
日常生活に見聞きする喪失の諸形態に、日浅はすんなり反応してはいちいち感じ入った。それがある種壮大なものに限られる点が、わたしにはなぜだか小気味がよかった。火事ひとつとっても、住宅の一棟や二棟を全焼する程度の火災には、冷淡なほど無関心なのが、数百ヘクタールもの土壌を焼き尽くしてしまう大規模な林野火災となると、一転強い反応を示した。鎮火宣言が発表されるや焼け跡を見に車を出した。ものごとに対し、共感ではなく感銘をする、そういう神経を持った人間なんだとわたしは独り決めにして面白がっていた。
と評価し、慕うのです。日浅というひとりの大きな存在を喪失した今野は、ほかの誰もが彼を捜そうとしないなか、彼の手がかりを掴もうと静かに奮闘します。今野のこのような姿勢は、“大きなものの崩壊・喪失”に感じ入りやすい日浅の姿と対照的に描かれることによって、より切実さを増すかのようです。
本作は、震災の様子やその被害を直接的に描きはしません。しかし、被災者にとって失った人がひとりであっても(そして、相手を失ったことを悲しむ人間がたとえ自分だけであっても)、その喪失感はあまりに大きく、何者にも代えがたいということを繊細な筆致で書ききった作品です。
『ムーンナイト・ダイバー』(天童荒太)

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B07M9N74T2/
『ムーンナイト・ダイバー』は、『家族狩り』や『永遠の仔』などの代表作を持つ小説家・天童荒太による長編小説です。
物語の舞台は、震災から4年半後。主人公の舟作は、震災時の津波で両親と兄を失った経験を持つ人物。ダイビングインストラクターである彼は震災の遺族グループの依頼を受け、放射能汚染の影響で立ち入り禁止区域となっている太平洋の海で、行方不明者の遺品を引き揚げる非合法の仕事をしています。遺族グループと舟作はその行為について部外者に一切口外しない、些細なものであっても引き揚げたものは絶対に持ち帰らない──という固い約束を交わし、こっそりと月夜の晩にだけ、震災後から手つかずのままで残っている海中の“光のエリア”を目指しダイビングをおこなうのでした。
家族を失った舟作は、震災から月日が経ってもなお、なぜ自分だけが生き残ってしまったのか、というサバイバーズ・ギルト(事件や事故の生存者が、自分が生きていることに罪悪感を覚えること)に日夜悩まされ、自問自答を続けます。
なぜあれが起きた? どうしておれが残った? なぜあっちの町がなくなって、こっちの町は平気だ? 誰が選んだ? 何が違うと言うんだ?
そしてそれは、彼に遺品探しを依頼する遺族も同じです。遺族グループのひとりである透子という人物は、震災で行方不明になった夫の指輪を「見つけないでほしい」と奇妙な依頼を舟作に持ちかけてきます。夫の遺体を確認できていない彼女はその死を受け入れることができず、揺れ続ける気持ちをいまだ抱えて日々を過ごしているのでした。海中からかつての生者の手がかりを探そうとする依頼者たちは、皆、震災から止まったままの時間のなかを生きています。
本書の巻末には、天童が刊行に寄せて綴ったエッセイ「失われた命への誠実な祈り」も収録されています。震災からときが経つにつれ、日本の復興ムードが日に日に強まり、肝心の被災地の傷跡には注目がされにくくなっているのではないかと天童は指摘します。受け入れがたい死を真摯に受け入れること、その上で無情にも続いていく生に目を向けることが、本作のひとつのテーマであったと彼は言います。
復興していく街に光を当てること、前を向くことももちろん大切ではあるけれど、失われたものにきちんと向き合うことから逃げてはいけないのではないか──。そんなことをあらためて痛感させる切実な作品です。
おわりに
震災から10年。その喪失感がまだ消えないという方もいれば、なかには震災の被害を受けておらず、当時のことを考える機会が減ってしまったという方もいるかもしれません。
『想像ラジオ』を著したいとうせいこうは、“想像すれば絶対に聴こえるはずだ”と語り、天童荒太は『ムーンナイト・ダイバー』刊行後のインタビューで、“立ち入り禁止区域の海に潜ることができるのは、小説家の想像力だけだ”と語っています。当時の痛みや苦しみを誰よりも知っている被災者の人々はもちろん、たとえそうではなくても、私たちは一人ひとりの喪失体験に対する想像力を持つことはできるのだ、と小説は教えてくれます。
この節目の年にあらためて震災のことを考えることは、いまだ東北の一部地域で続いている堤防や道路の復旧・復興作業について知ったり、遺族や被災者の苦しみに思いを寄せるきっかけになるかもしれません。今回ご紹介した3作品に、ぜひ手を伸ばしてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/03/09)

