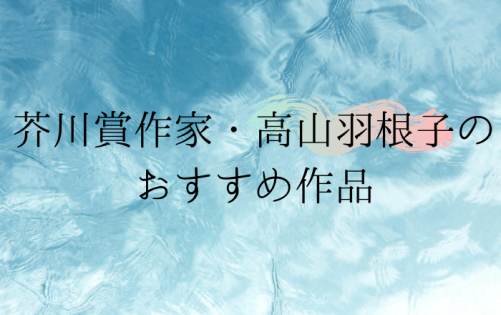【『首里の馬』で芥川賞受賞】高山羽根子のおすすめ作品
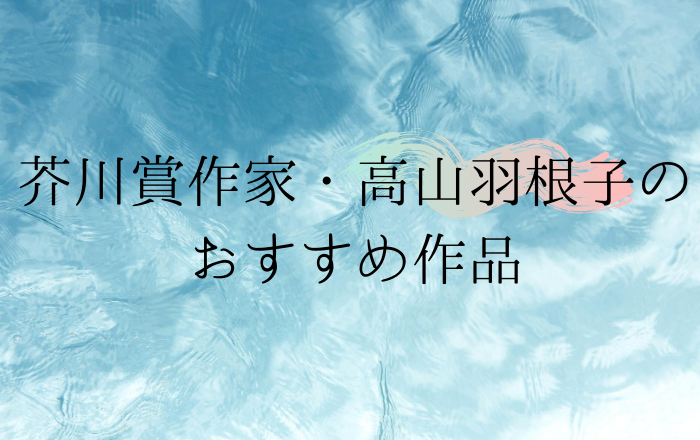
沖縄を舞台にした小説、『首里の馬』で第163回芥川賞を受賞した高山羽根子は、人と物の記憶についての物語を端正な筆致で描く作家です。今回は、高山羽根子のおすすめの作品を3作品ご紹介します。
『首里の馬』で第163回芥川賞を受賞した高山羽根子。SF的な奇妙でおかしみのあるモチーフを多用しながら、端正な筆致で土地や人の記憶、孤独についての物語を書き続け、純文学ファンから熱い支持を集めている作家です。
今回は、これから高山作品に手を伸ばす方のために、『首里の馬』のほか、芥川賞候補作になった『カム・ギャザー・ラウンド・ピープル』など、高山羽根子のおすすめの作品を3作品ご紹介します。
『オブジェクタム』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4022515643/
『オブジェクタム』は、高山羽根子による2018年発表の短編小説。子どもの頃に住んでいた町を大人になって訪れた主人公が、小学生の頃に祖父と自分の間だけの秘密だった町内の“カベ新聞”の記憶を辿りながら、長年借りていた「あるもの」を返そうとする物語です。
子どもの頃、主人公・サトの住む町で、月に一度くらいのペースで町内のさまざまな場所に貼り出されていた謎の“カベ新聞”。町内のスーパーの野菜の傷み率を比較した記事など、その内容は本当にささやかでとるに足らないものばかりでしたが、実際のところその新聞を読んでいる人はとても多いのでした。
インフルエンザで学校を休んだ同級生に届けものをしたある日の帰り道、サトは、祖父が俳句教室に行くと家族に嘘をついて川原に通っていたことを知ります。あとをつけてみると、祖父は川原のススキ畑の中にひっそりと立てたキャンプ用のテントの中で、ひとり手刷りでカベ新聞を作っていました。サトはその日から、祖父の新聞作りを誰にも気づかれないように手伝うようになります。病を患い、弱っていく祖父のことを「ぼけて徘徊している」と家族や町の人たちは捉えていますが、サトは新聞作りという秘密の共有を通じて祖父との絆をひそやかに深めていくのでした。
物語は、主人公の過去の回想と現在の語りを織り交ぜながら進みます。カベ新聞の思い出を中心に、かつて祖父や父が子どもだった時代に町にやってきたことがあるという移動遊園地、サトが神社の裏手で出会った、祖父の古い知人だという手品師の男、祖父が川原でなぜか必死に集めていた“石”の数々──といったさまざまな記憶の断片が、少しずつ重なったり離れたりしながら、いびつではあるものの何物にも代えがたい体験として、サトの、そして読者の目の前に輪郭を持って立ち上っていきます。
作中に、野菜の傷み率に関するカベ新聞を熱心に読んでいたサトの同級生・カズが、こんな情報を知ってなにになるんだ、とサトに聞かれ、
「知らなきゃ気にならないんだろうけど、書かれてるのを読んじゃったから」
と答えるワンシーンがあります。この言葉が象徴するように、本作は、誰にも目を向けられていなければ誰にも知られるはずのなかったささやかな物事やできごとを、一つひとつ丁寧に見つめるように書かれています。小さな記憶の断片の集積体が見せてくれる景色は、虹のようにたとえ一瞬で消えてしまうものであっても、たしかにそこにあったものだということを思わせてくれる力強い作品です。
『カム・ギャザー・ラウンド・ピープル』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4022515643/
『カム・ギャザー・ラウンド・ピープル』は、2019年に発表された作品です。
主人公の「私」はある日、雨宿りのために立ち寄った喫茶店で、イズミという女性に出会います。イズミは、東京のさまざまな記録を映像にしてインターネット上にアップしており、その動画はSNSでも広く拡散されているものでした。イズミの撮った政治的な集会と思しき記録映像の中に、「私」は、バスの車体の上で拡声器を使って何かを主張している、かつての知り合いの姿を見つけます。
茶色い巻き髪に、ピンクのワンピース。スタイルの良いその車上の人にズームする。スマホの光学ズームには限りがあって、どうしてもしっかりとピントが合わない。そのうえ夜なので、投光器で照らされていても手振れがやんでもはっきりしない。でも拡声器の声が聞こえて、そのワンピース姿の人物が男性だということを確信する。
しかも、私はその人物を知っている。
「ニシダだ」
ニシダは、「私」が高校時代に一番仲良くしていた同級生の男子でした。「私」は、映像の中のニシダとの出会いや、亡くなった祖母の背中がふっくらと白く美しかったという記憶、中学時代に聞いた知らない大学生のギターの演奏の記憶などを通じて、心の中で蓋をし続けていたある性被害の体験を思い起こします。
「私」ははじめ、かつて自分が受けた性被害をなかったもののようにして日常生活を送っており、自分の体験を特に社会問題とも結びつけて捉えていない人物として描かれます。彼女にとって“なかったこと”にされていた体験が人や記憶との出会いを通じて“たしかにあったこと”に変化してゆくさまは、切実で痛ましくもあり、とてもリアルです。「私」はその上で、加害者を突き放すことなく、ひとりの人として向き合おうとしていきます。
「私」はつらい体験をしてもなお、社会への拒否感や嫌悪感を内面化させず、失われたものや傷つけられてしまったものに対して常にやさしい視線を注ぐことができる人物です。ある日偶然目にしてしまった人身事故で、亡くなった人が着ていた白いダウンジャケットの羽毛が舞う様子を見た「私」は、
この、白いふわふわを着ていた人の背中が、その人自身が思いもしないくらいに美しいという可能性はどのくらいあるんだろうか。そうしてもし、誰もその背中の美しさに気づいてあげられていないんだとしたら、寂しいなと思った。
と考えます。「私」の一貫したやさしさは、そのまま形を変えず、自らが受けた被害に向き合い声をあげようとするという強さにもなっていきます。ひとりの女性にとって過去に受けた性被害が人生にどんな影響を及ぼすのか、そして、その傷を抱えたままで他者にやさしくすることはできるのかということを、揺れ動き続ける感情を含めて真摯に描き切った作品です。
『首里の馬』
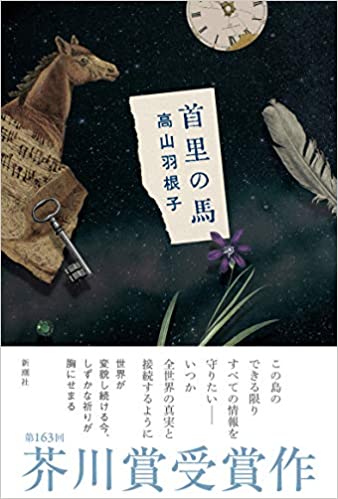
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4022515643/
『首里の馬』は、高山羽根子の最新小説です。2019年に『居た場所』(第160回)、『カム・ギャザー・ラウンド・ピープル』(第161回)で2度芥川賞にノミネートされていましたが、3回目となる本作で第163回芥川賞を受賞しました。
本作の主人公は、沖縄にひとりで暮らしている未名子という女性。未名子は、
「小さな男の子、太った男。──そしてイワンは何に?」
「鴨川、波、造形の影響は、何者へ?」
といった奇妙なクイズを出題するという業務をおこなっていました。
台風が過ぎ去ったある日、未名子の家の庭に、一頭の美しい宮古馬(宮古島で飼育されてきた馬の一品種)が迷い込んできます。未名子は驚きつつもその馬に「ヒコーキ」と名づけ、可愛がるようになります。
個人が作った郷土資料館、知らない人にクイズを出題する仕事、庭に突如迷い込んできた馬と、本作の中では、理由や由来を明かされない不思議なできごとが次々と起こり続けます。これまでの高山作品では、そういった奇妙なできごとの断片がふと現れては説明されないまま最後まで残り、不穏な空気を残す──ということが多かったのですが、『首里の馬』ではそういったSF的な“謎”が完全に解決はされないものの、結末に向かって少しずつ集まり、ひとつの形を作っていくような面白さがあります。
また、
台風があきれるほどしょっちゅうやって来るせいで、このあたりに建っている家はたいてい低くて平たかった。(中略)なるべく風の影響を受けることがないようにと考えるなら、たいていはでこぼこした部分のあまりない、四角っぽく平らな屋根の建物を作る必要があって、それがこのあたりの民家の特徴になっている。さらに古くからのきちんとした家なら、素焼き風の赤銅色をした瓦が吹き飛ばされないようにと、すきまを白い漆喰で埋めてあった。これは強風対策のほかに小獣や鳥、ハブなどが巣を作らないようにという目的もある。このオレンジと白の独特な屋根の色模様が南国特有の景色に溶けこんで、うまいこと風情をかもしだしていた。
といった未名子の住む沖縄の風景の描写もとても緻密かつ美しく、土地の歴史を感じさせるものになっています。台風がくるたびに吹き飛ばされまた再建される家のように、歴史の上でもさまざまな破壊と再生が繰り返され、いまの形になった沖縄という土地。個人の記憶の断片を積み重ねることでその厚みと普遍性、何物にも代えがたい尊さを読み手に実感させる本作は、まさに高山作品の真骨頂です。
おわりに
高山羽根子は、日常の中ではなかなか目を向けられることのない、人や物の些細な記憶に視線を配り、“たしかにあったこと”の重みと美しさを私たちに感じさせてくれる稀有な書き手です。
高山さんは、芥川賞受賞時のインタビューで、
例えば社会がまったく変わってしまって、「文章を書くことはまかりならん」と言われて手首を縛られたとしても、たぶん足で書くと思うんです。
──『文藝春秋』2020年9月号より
と語っています。彼女がこれからも書き続ける物語の中でどんな世界を見ることができるのか、楽しみでなりません。
初出:P+D MAGAZINE(2020/08/15)