【『桜島』『幻化』ほか】戦後派の小説家・梅崎春生の魅力

『幻化』『桜島』といった戦争もので注目され、「第一次戦後派」の中心人物として昭和期に活躍した作家・梅崎春生。今回はそんな梅崎春生のおすすめ作品を、読みどころと共にご紹介します。
第一次戦後派の中心的人物として活躍し、『幻化』や『桜島』といった戦争もののほか、市井の人々の生活をアイロニカルに描いた作品を数多く発表した小説家・梅崎春生。梅崎の小説はどれもはっきりとした筋書きを持たない曖昧模糊としたものでありながら、人間の生死の根幹を見つめるようなたしかな迫力を持っています。
今回は、そんな梅崎春生のおすすめ作品を、あらすじや読みどころとともに3作品ご紹介します。
『幻化』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4061960474/
『幻化』は梅崎春生が1965年に発表した、自身の戦争体験を元にした短編小説です。本作は梅崎の最晩年に書かれ、彼にとっての遺作となりました。
本作の主人公は、精神病院に入院している五郎という中年の男。五郎はある日ふと思い立って病院から抜け出し、羽田発の飛行機に乗って鹿児島に向かおうとします。五郎の病気は作中で詳しくは明らかにされていないものの、彼にはときどき、妙な幻覚が見えるという症状がありました。飛行機の中から窓の外を見ていても、彼の目は同じように幻覚のような風景を捉えています。
白い壁に蟻が這っている。どう見直しても蟻が這っている。近づいて指で押えようとすると、何もさわらない。翼の虫も触れてみれば判るわけだが、窓がしまっているのでさわれない。仮に窓をあけたとしても、手が届かない。
しかし、隣の席に座っていた丹尾という男と言葉を交わしたことによって、その光景は幻覚ではなく、飛行機の潤滑油が流れ出したものだということがわかります。飛行機はなんとか無事に鹿児島に到着しますが、丹尾は着のみ着のままで飛行機に乗ってきた五郎のことが気にかかり、枕崎に向かうという五郎に、ついていくと言い出します。五郎は渋々、丹尾とともに枕崎まで旅をし、そこから坊津へ向かいます。実は五郎は戦時中、特攻隊の発進基地があった坊津で、特技兵として勤務していた過去を持っていたのでした。
五郎がかつての記憶を重ね合わせながら九州をひとりで旅し、何名かの人々と出会うともなく出会い、また別れ、阿蘇で丹尾と再会する──というのが本作のおおまかなあらすじです。五郎の行く先に事件らしい事件は起こらず、物語は最初から最後までおぼろげな輪郭しか持ちません。そこにはまるで、極度の緊張状態に置かれ続けていた戦時中が終わりようやくやってきたはずの“戦後”が、実際には何も持たない空虚なものであった、という梅崎の実感が反映されているかのようです。
梅崎の代表作のひとつとして語られることも多い『桜島』は、『幻化』の前身となる作品です。『桜島』は『幻化』と同じく坊津を舞台にした作品ですが、本作の中には、自殺未遂をする人を見届けていた兵士の言葉として、こんな台詞が登場します。
「人間には、生きようという意志と一緒に、滅亡に赴こうという意志があるような気がするんですよ」
──『桜島』より
『幻化』に登場する五郎や丹尾も、この“滅亡に赴こうという意志”を常に内面に抱えている人物です。しかし、(死ぬときは)「美しく死のう」と繰り返し語る『桜島』の主人公とは違い、死に引き寄せられる強い欲望を持ちながらも、ふたりがどうにか生を選びとろうともがいているシーンで本作は幕を下ろします。茫漠としていながらも、どこか胸に迫るような感動のある一作です。
『ボロ家の春秋』
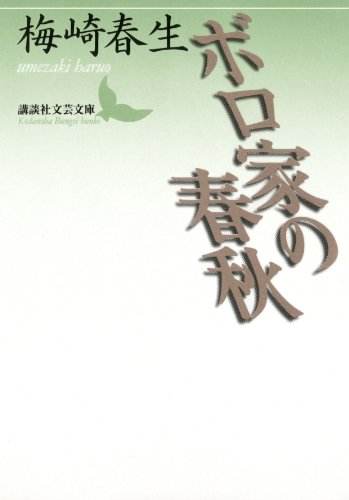
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B00GY19EO2/
『ボロ家の春秋』は、梅崎が1954年に発表した短編小説です。本作は『桜島』や『幻化』のように陰鬱とした空気をまとった戦争ものとは打って変わって、ツッコミ不在のコントのような、ユーモラスな作品です。
物語は、画家の卵である主人公の“僕”がひょんなことから不破数馬という中年男性と知り合い、彼の所有する“ボロ家”を間借りさせてもらうという約束をするところから始まります。しかし、知り合って早々にこの家の持ち主である不破は夫人ともども長旅に出てしまい、その間の留守番として、野呂旅人という人物が“ボロ家”にやってきます。ところが野呂はやってくるなり、不破から聞いていた事情とはまったく違うことを話し始めるのです。
野呂はじろじろと僕を上から下まで眺め廻して、急に言葉がぞんざいになりました。「一体君は何だね。留守番かね?」
「留守番じゃないよ」少々僕もむっとして言い返しました。「留守番は君じゃないか。僕はここの居住者だ」
「居住者?」バカじゃなかろうかというような眼付で、野呂は僕を見た。「何を君は言ってるんだね。この家は僕のものだよ。不破氏から僕が買い受けたんだ。君は早々に出て行って呉れ」
「買い受けただって?」
野呂と話し合った“僕”は、どうやら自分たちが不破から騙されたのだということに気づきます。しかし、お互いに前の家を引き払ってすべての荷物を持ってきてしまっている手前、どちらかが引き下がるわけにはいきません。ふたりは仕方なく、“ボロ家”の西側と東側とに分かれ、奇妙な同居生活を始めます。
“僕”と野呂はどちらも不破の詐欺の被害者という同じ立場であるはずなのに、どうにも折り合いが悪く、常に言い争いばかりしています。不破の関係者を名乗る他の人物に追い打ちをかけるように騙され、家賃を払わされる羽目になってもなお、ふたりは犬猿の仲のままなのです。それはまるで、権力者から搾取される人々が、互いが被害者であることに気づかずにいがみ合い、さらなる搾取を呼び込んでしまうという社会的な構造を戯画化しているかのようです。
批評家の中野翠は、『ボロ家の春秋』で描かれる人間関係の悲喜こもごもを、こんな風に評しています。
深刻趣味の人だったら、その先をえぐって行って、和風で行くなら「業」とか「性」の文学に、洋風で行くなら「実存」とか「不条理」の文学に仕立てるところを、この人は突き放して、ボケたおす。突けば重いものがころがり出すところを、フッと軽くしてしまう。
全編に、ほとんど細心なまでに「美徳悪徳の軽量化」がはかられている。
──『アメーバのように。私の本棚』より
まさにこの“美徳悪徳の軽量化”こそが、『ボロ家の春秋』のおもしろさの正体と言えます。市井の人々の諍いを、徹底的に抑えたトーンで淡々と書き連ねていることが、本作の持つ奇妙な凄みへと結びついています。
『つむじ風』
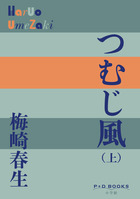
出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352416
『つむじ風』は、梅崎が1956年に発表した長編小説です。『ボロ家の春秋』と同じく市井の人々の姿を戯画的に描いたユーモア小説である本作は、新聞小説として東京新聞に連載され、渥美清主演で映画化もされた人気作です。
自らを徳川家の末裔だと言い張るホラ吹き男・陣内陣太郎が、一見善良そうな雰囲気でさまざまな人々に近づいては、まるでつむじ風のごとく金を巻き上げて去っていくというのが本作のおおまかなあらすじです。
たとえば、車にはね飛ばされた陣太郎を家に連れ帰り、陣太郎をはねた犯人を探し出して金を要求しようという計画を立てた浅利圭介という男は、結局事件の犯人を見つけて金を得られるどころか、陣太郎に家の酒を飲み干されてしまいます。また、ひき逃げ事件の実際の犯人である人気小説家・明治はもちろん、加害者のひとりとして浮上した公衆浴場の主人・三吉までもが、次々と理由をつけられて陣太郎に金をむしり取られてしまうのです。
ナンセンスな笑い話としても完成度の高い本作ですが、細かな点に目を向けると、当時の社会制度や世間の空気に対するアイロニーに満ちていることに気づかされます。陣太郎が徳川家の末裔であるという権力をちらつかせて人々を従えていくことはもちろん、たとえば小説家の明治がつけている日記として引用される、
昼食。野菜入りイタメウドン(粉チーズカケ)野菜どれっしんぐ。果物盛合(おれんじ他)。昼食後仕事。
といった取り留めもない文章のあとに挿入された
もっと歳をとって小説が書けなくなれば、こんな日記を新聞雑誌に切り売りをして生活しようとの算段なのだから、いい気なものである
という一文からは、『断腸亭日乗』などの日記で人気を博した永井荷風など、当時の文壇の大御所への批評性も感じられます。梅崎が向けていた世の中への鋭い目線が伝わってくる、ユーモラスでありながらも鋭い一作です。
おわりに
梅崎春生作品の魅力は、戦争もののようなシリアスな作品であっても市井の人々の生活を描いたユーモラスな作品であっても変わらず根幹にある、人間という存在の善悪の本質を解き明かそうとするような姿勢です。
戦後派の作家の作品に関心がある方はもちろん、吉行淳之介や安岡章太郎といった「第三の新人」の作風が好きな方にも梅崎春生の作品はおすすめです。これまでに梅崎作品を読んだことがないという方もぜひ、今回ご紹介した3冊の小説を入り口に、その作品に手を伸ばしてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2021/05/14)

