渾身の一針はパンクのごとく 過去と未来を縫い合わせて進む 「源流の人」第3回:沖 潤子(刺繍アーティスト)
時代に流されず、 常に新たな価値観を発信し続ける人々を追う、本の窓の連載「源流の人」。第3回は刺繍アーティストの沖潤子。その作品を初めて目にした人は言葉を失う。古い布と糸を材料に使い、まるで血管や筋肉を盛り上がらせたかのような強烈なインパクトを放つ作品の数々。世界的に評価の高い、唯一無二の作品はどうやって生まれてきたのか。
連載インタビュー 源流の人 第3回
時代に流されず、 常に新たな価値観を発信し続ける人々を追う
渾身の一針はパンクのごとく
過去と未来を縫い合わせて進む
沖 潤子
刺繍アーティスト(57歳)

インタビュー・加賀直樹 Photograph: Matsuda Maki
一針、一針、糸を布にくぐらせ、図柄を描き出していく「
相模湾を見晴るかす、緑濃い鎌倉の街並み。丘陵地に居を構える沖は、今回の取材で使用したタブレットの画面から、にっこり笑いながら語り始めた。
「『
美しく、丁寧に。そんな刺繍の鉄則は、彼女には初めから存在しない。ステッチを
「ぜんぶ、表情がある。面白いなと感じます」
思いのほか糸は劣化が早く、湿気を吸うとブチブチ切れてしまうが、それさえも楽しい。太い糸でガシガシ、手が痛くなるぐらい硬い布に挑む日。絶対、普段は使いそうにない色の糸を使ってみたい日。沖は笑って言う。
「何でなのか分からないんです。絵の具と一緒かな」
情熱的で、刹那的で、でも、糸の持つ不思議な力が伝わってくるようで──。一言ではとても表せないその独自の作風が支持され、その作品集にはフランスや英国をはじめとするヨーロッパ各国、米国、台湾、オーストラリアなど、世界じゅうから注文が相次いだ。
今年の四月から来年にかけて、山口県立
「畳に上がらせてもらって、何時間も座ったり、寝っ転がったり。それで気づきました。『ああ、畳には、いろんな人のため息や、時間が降り積もっているんだな』と」
この空間と、沖自身の創作とを
「そうだ、糸だ!」
インターネットを通じて全国から糸巻きの提供を募ってみたところ、根室から那覇に至るまで、じつに約七千個の糸巻きが集まった。母の裁縫箱にあった景色や記憶。便箋に思いのたけを
「結婚した時に、実母が持たせてくれた糸巻きです。あんまりお裁縫しなくて、でも捨てられなくて」
「亡きお
世代や時を超え、津々浦々から集まった一本一本の糸巻き。そのすべてに物語が内包されていることを、沖は思い知った。創作にいそしむ深夜、ふとラジオから聴こえてくる言葉が心に波紋を広げ、潜在意識の階段を駆け下りることがある。亡き祖母や母の影が
「花摘み、花を集めるという意味もあるそうです。これしかない、と」
百年前に世界一周した祖父の気概
絵を描くことに心血を注ぐ学生時代を送った。とりわけ没頭したのは人物画だ。「自画像ばかり描いていました。自分の顔なら、どんなに
結局、美大受験をやめた沖だったが、どこか、その人生については
「たぶん、祖父の存在が大きいと思います」。沖はそう話す。
自由主義の機運高まる大正八年、沖の祖父は日本郵船の船に乗って世界一周の旅に出た。当時、上昇気流に乗っていた繊維業界で会社を起こそうとしたのだった。
「それにはまず、世界を見なければダメだ。船に乗ると決めた祖父は『一等船客じゃなきゃ意味がない』と言って、渡航費用や起業資金を数年かけて用意したそうです」
中国・
「自らの道に全神経を傾け、すべての知恵を注ぎ込む。そして何とかカタチにしていく。祖父の気概を感じます。祖父の存在があるからか、私自身、家族が何をして、何を感じているかが大事に思えるようになったんです」
二十代半ばで、わが国のファッション・イラストレーターの草分け的存在、
「絵では食べていけない。柄じゃないんだな、と」
何をどうしたいのかが分からないまま、とにかく就職しなければと焦りが募り、商品企画会社に勤めた。保育園に通う娘を一人で育てている経緯もあった。保育園と、会社と、自宅とを結ぶ三角形を、いかに小さくするか。それこそが喫緊の課題だった。午後五時半には保育園に迎えに行かなければならない。残業・休日出勤は絶対NG。ただただ、その場で頑張って稼ぐしかない。
仕事の中で記憶に残っているのは、玩具関係の「記念日マーケティング」。大手玩具メーカーを担当し、バレンタインやこどもの日など、記念日のお菓子グッズのパッケージを考え、営業から原価計算、生産・納品管理に至るまでを担当した。当時、ささやかなやりがいも覚えつつ、いつしか心の中に
「仕事に慣れるうち、だんだん『企画が通る仕事』ばかり提案するようになっていった。自分のやりたいことをやりたい。ジレンマが募っていった」
創作への希求は増すいっぽうで、ならば自分に何ができるのかを模索する日々。そんな折、その「事件」は起きた。それは、中学に上がり立ての娘が、亡き母が大事にしていたイギリスの高級生地メーカー「リバティ」の布をジョキジョキ切って、誕生日を迎えた沖のために小さな手提げをプレゼントしてくれたのだ。布にはザックザクの刺繍を添えて。沖はその日のことを楽しそうに振り返る。
「『ええ! 切っちゃったの?』って。そして、大きく心が動きました。これはつくりたいという気持ちだけでできている自由のかたまり。ものをつくるってこういうことだと気づいたんです」
わたしは出る杭をつくりたい
「これ」ができなかったら、もうダメだ。こういう「種」が自分の中から失われてしまったら、もうダメだ。それを娘が気づかせてくれた。それから沖の「本当の創作」は始まった。遺された母の大量の古布を使って、手あたり次第、手提げや娘の着る服をつくる。「片っ端からつくった」という作品群は二〇〇二年、東京・青山のクリエイター祭典に初出展。ブースでは、チクチクと創作活動に没頭する自分自身のアトリエを段ボールに再現した。その後、ほどなくして初の個展も開催。「自分の作品をちゃんと買っていただきたい」。そんな望みが持ち上がったある日、電車で通勤する男性のネクタイに目が留まったという。
「どれも、当たり障りないな、って。ネクタイは『出る
ネクタイを自分でつくろう。そう思った沖は、埼玉・川越市にオリジナルのネクタイをつくる工場があると知り、社長に
「ある大手百貨店の店長はすごく革新的な方でした。『売り場を刷新するために沖さんの作品を置きたい』と」
有名ブランド品が並ぶなか、最も見栄えのする場所に沖の作品を展示してくれた。注目の的となり注文が相次ぎ、沖は嬉しい悲鳴を上げた。そのいっぽうで、今更ながら重大なことに沖は気づいた。それは、自身が究めたいのは作品の量産でなく、新たな美術への探求心だということ。高校生の頃、受験用でない無二の絵を描こうと模索していた、あの頃と変わらぬ思いだった。
そんな沖の思いが、一針の刺繍へと凝縮していったのは──。これもほんの一瞬の偶然がきっかけだった。
「魂をえぐられた」「涙が溢れた」
それはある日、待ち合わせ相手がいつまで
「ネクタイに刺繍していた糸は、いわゆる刺繍糸。この日持っていた糸は縫製用でした。針目を見ながら『あ、これだ!』って。そこからは割り切ったように、単色の表現に変わっていきました」
針目を守ることに
エッセイスト平松洋子も沖の作品に魅せられた一人だ。展覧会で作品と対峙しひとこと「PUNKね!」と感想を述べてくれた。沖は振り返る。「その言葉が、心の奥底に、グッと引っ掛かったんです。PUNKは、わたしとは
二〇一四年に初の作品集、その名も『PUNK』(文藝春秋)を刊行。自身の撮影による一冊となった。
反響は驚くほどで、現在までに四刷を数えている。
変えることができることを変える勇気
鎌倉の家では洗濯や掃除、二匹の猫の世話をした後、午後二時頃から翌朝六時頃まで、創作活動に没頭する。鎌倉の街なかで古道具店の手伝いをしていた頃、モノのもつ力、使い古されて見向きもされないようなモノの価値の存在を知った。電動アシスト自転車に乗り、行ったこともない路地を曲がってみる。妖精のようなおばあさんが路地に座っていたら、ちょっと声を掛けてみる。おばあさんからは時折、思わぬ物語を聞かせてもらえることがある。そんな鎌倉の日々が、いとおしい。

この十年の言葉や形を書きとめたクロッキー帳とノート。作品の発想の源だ。
取材が終わろうとする時、沖が、ふとこんなことを漏らした。信仰を特に持たない沖が、このところ毎朝、祈りを唱えている言葉があるという。米国の神学者・ラインホルド・ニーバーの祈りの言葉だ。
「変えられないことを受け容れる落ち着きと、変えることができることを変える勇気と、それらを見分ける知恵を授けてください」
中学の頃、ただ一人好きだった国語の先生が、生徒たちに、大切にしたい言葉をノートに書かせていた。習慣となり、今もB5判ノートに記し続けている。この言葉もノートにあり、何度も読み返している。沖は言う。「いろんなことをいっぱい考えちゃうんですけど、この言葉は『そこに行き着けば良い』って毎朝思える。声に出すって大事ですよね」
何があっても、手さえ動かしていれば、何かしら跡が残るはず。「これだけやった」。目に見えるものが残るはず。針と布を手放さずに、背筋を伸ばして沖は言う。
「そのためにやっているのかも知れません」
探究の一針、一針。きょうも、明日も紡いでいく。

沖 潤子(おき・じゅんこ)
1963年、埼玉県浦和市(現さいたま市)生まれ、神奈川県鎌倉市在住。2002年より母親が残した布に自己流の刺繍を始め、以後、国内外で展覧会を行う。あえて細いミシン糸を用い、下絵を描かずに刺していく。自己の内面世界を表現し尽くそうともがいているかのような高密度の針目は、刺繍という概念を超え圧倒的な力を放つ。2014年に、沖自身の撮影による作品集『PUNK』(文藝春秋)を刊行、その独自の世界が大きな話題となっている。
個展情報
「anthology」
山口県立萩美術館・浦上記念館「茶室」にて開催中
2021年3月28日(日)まで
● 山口県萩市平安古町586-1
TEL.0838-24-2400
「刺繍の理り」
KOSAKU KANECHIKA
にて開催予定
2020年7月18⽇(⼟)〜8⽉22⽇(土)
● 東京都品川区東品川 1-33-10
TEL.03-6712-3346
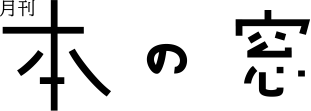
豪華執筆陣による小説、詩、エッセイなどの読み物連載に加え、読書案内、小学館の新刊情報も満載。小さな雑誌で驚くほど充実した内容。あなたの好奇心を存分に刺激すること間違いなし。
初出:P+D MAGAZINE(2020/06/24)

