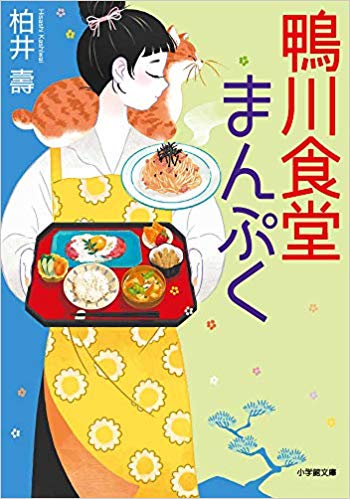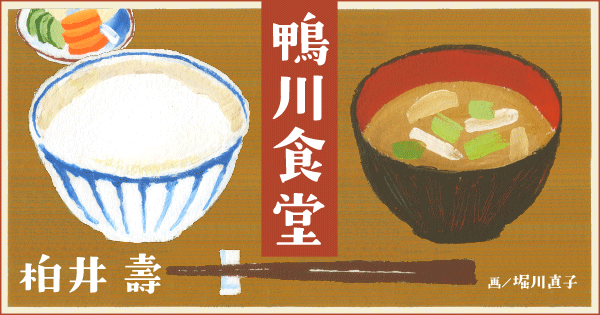「鴨川食堂」第1話 鍋焼きうどん 柏井 壽

第1話 鍋焼きうどん
仏壇を横目で見て、流が頭を下げた。
「流が仕事しとるのをじっと見守ってくれてはるんやな」
膝をくずして、窪山が厨房に立つ流を見上げた。
「しっかり見張られてるんですがな」
流が笑った。
「けど、流が食堂の主人におさまってるとは、思いもせなんだで」
「それを今訊こうと思うてましたんや。どうしてうちの店を?」
流が居間に腰かけた。
「うちの会社の社長はえらいグルメでな、『料理春秋』の愛読者なんや。役員室にもバックナンバーが積んであって、そこに出てた広告を見て、ピンと来た」
「さすが〈マムシの窪山〉ですな。連絡先も何も書いてない、あんな一行広告で、わしの店やと気付いて、ここまで辿り着かはるやなんて」
感心したように、流が首を左右にかたむけた。
「流のことやさかい、何ぞ考えがあるんやろうが、もうちょっと分かりやすい広告にしたらどないやねん。あんな広告でここまで辿り着けるのはわしぐらいやで」
「それでええんですわ。そないようけ来てもろたら困りますねん」
「相変わらずおかしなやっちゃ」
「ひょっとして思い出の味を捜してはるん?」
流の傍らに立って、こいしが窪山の顔を覗き込んだ。
「まぁ、そんなとこや」
窪山が口の端で笑った。
「今もお住まいは寺町の方で?」
立ち上がって、流が流し台に向かった。
「ずっと変わらんと十念寺(じゅうねんじ)のそばに住んどる。毎朝、賀茂川を歩いて出町柳(でまちやなぎ)まで行って、そこから京阪や。会社は京橋にあるさかい便利やで。それにしても正座が辛ぅてな。この歳になると、足が言うことをきかんわ」
顔をしかめた窪山はゆっくり立ち上がり、テーブル席に戻った。
「お互いさまですな。掬子(きくこ)の祥月命日にお寺さんが来てくれはるんですけど、いつも難儀してますわ」
「えらいなぁ。うちなんか何年も坊さんには、拝んでもろてない。ヨメはんも怒っとるやろ」
窪山が胸ポケットから煙草を取り出して、こいしの顔色を窺う。
「うちは禁煙と違うし、かまへんよ」
こいしがアルミの灰皿をテーブルに置いた。
「すんまへん。いっぷくさせてもろても、よろしいかいな」
指に挟んだ煙草を、窪山が浩に向けた。
「どうぞ」
笑みを浮かべた浩は、思い出したように、バッグから煙草を取り出した。
「若いうちはともかく、わしらの歳になったらやめんとあきませんで」
流がカウンター越しに声をかけた。
「いっつも、そない言われとる」
窪山が紫煙をゆっくりと吐き出した。
「再婚なさったんですかいな」
「そのことで、捜して欲しい味があるんや」
流の問い掛けに、窪山が目を細めて、吸殻を灰皿に押し付けた。
「ごちそうさま。カツ丼旨かったです」
カウンターに五百円玉をパシっと置いて、浩がくわえ煙草で店を出て行く。それを目で追っていた窪山がこいしに顔を向けた。
「ええ人か?」
「そんなんと違うわよ。ただのお客さん。近所のお寿司屋の大将」
頬を赤らめたこいしが窪山の背中を叩いた。
「固いこと言うようですがな、秀さん。探偵事務所の所長は、こいしなんですわ。話はこいつにしてやってもらえますか。いちおう事務所は奥にありますんで」
「そうかいな。ほな、こいしちゃん、頼むわ」
窪山が中腰になった。
「ちょっと待ってな、おっちゃん。すぐに準備してくるよって」
エプロンを外してこいしが、厨房の奥へと急いだ。
「流はずっとヤモメを続けとるんか」
改めて窪山が腰を落ち着けた。
「ずっと、てまだ五年しか経ってしません。後添え貰うてなことになったら、化けて出て来ますわ」
流が茶を注いだ。
「そら、まだ早いな。うちは今年でちょうど十五年。そろそろ千恵子(ちえこ)も許してくれるんやないかと」
「そないなりますか。早いもんですなぁ。お宅へ寄せてもろて、千恵子はんの手料理よばれたん、つい昨日のことのように思います」
「ほかはさっぱりやったが、料理だけは天下一品のヨメはんやった」
窪山が小さくため息を吐くと、しばらく沈黙が続いた。
「そろそろ行きまひょか」
流が立ち上がり、窪山がそれに続いた。
カウンター席を挟んで、藍地の暖簾が掛かる出入口と反対側には小さなドアがある。流がそのドアを開けると細長い廊下が続いていた。どうやら探偵事務所に通じているようだ。
「ぜんぶ流の料理か」
廊下の両側にびっしり貼られた写真を見ながら、窪山が流の後を歩く。
「ちょこちょこ違うのもありますけどな」
流が振り向いた。
「これは……」
窪山が立ち止まった。
「裏庭で唐辛子を天日干ししてるとこですわ。掬子の遣り方を見よう見まねで。ええ加減なことです」
「千恵子も似たようなことをやっとった。面倒なことをするんやな、と思うたんやが」
窪山が歩き出した。
「こいし、お連れしたで」
流がドアを開けた。
「面倒やろうけど、いちおう書いてもらえます?」
ローテーブルを挟んで、こいしと窪山が向かい合ってソファに座る。
「氏名、年齢、生年月日、現住所、職業……なんや保険に入るときみたいやな」
バインダーを受け取って、窪山が苦笑した。
「おっちゃんのことやから、適当に書いといてくれたらええよ」
「そうはいかん。これでも元公務員やさかいな」
窪山がバインダーを返した。
「律儀なとこは昔のままやね」
楷書体で埋め尽くされた書類を目で追った後、こいしが膝を揃える。
「どんな食を捜したらええんです?」
「鍋焼きうどんや」
「どんな?」
こいしがノートを広げた。
「昔、うちのヨメはんが作ってくれた鍋焼きうどん」
「奥さんが亡くならはってから、ずいぶん経ちますよね」
「十五年」
「今でもその味、覚えてはりますのん?」
こいしの問い掛けに、窪山はうなずきかけて、思い直すように首を斜めにした。
「おおまかな味やとか、どんな具が入っとったかは、よう覚えとるんやが……」
「それを再現しようと思うても、同じ味にはならへん、ということですか」
「さすが流の娘やな。大した推理力や」
「おっちゃん、まさかそれって、再婚した奥さんに作らせてはるのと違うやろね」
「いかんか?」
「アカンに決まっているやん。ようそんな失礼なことするわ。前の奥さんの想い出の味を再現させるやなんて」
「早とちりするとこまで、流にそっくりやな。なんぼ厚かましいわしでも、そんなことはせん。ただ、旨い鍋焼きうどんを作ってくれと頼んでるだけや。それに、まだ再婚したわけやない。会社の部下で、えろう気が合う女性がおってな、向こうもバツイチで独り身やねん。ときどきうちへ遊びに来て、メシを作ってくれるんよ」
「それで若返りはったんか。恋愛中やねんな」
こいしが上目遣いに冷やかした。
「この歳して恋愛というような甘いもんやない。茶飲み友達っちゅうやつや」
幾らかのテレを含んだ笑いを浮かべながら、窪山が続ける。
「杉山奈美(すぎやまなみ)。皆からはナミちゃんと呼ばれとる。わしよりひと回り以上も歳下なんやが、会社では大先輩や。経理を一手に任されとるし、社長の信頼も厚い。そのナミちゃんとえらいウマが合うてな。映画を観に行ったり、お寺さん廻りをしたりして、楽しいしとったわけや」
「二度目の青春やね」
こいしが微笑んだ。
「ナミちゃんな、今は山科(やましな)にひとりで住んどるんやけど、実家は群馬の高崎やねん。ふた月ほど前に母親が亡くなって、父親ひとりになってしもうた。面倒見んなんさかいに、高崎に帰ると言い出したんや」
「ナミちゃん、ひとりで?」
「一緒に付いて来てくれませんか、と言いよる」
窪山が顔を真っ赤にした。