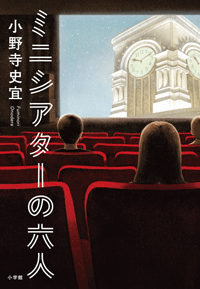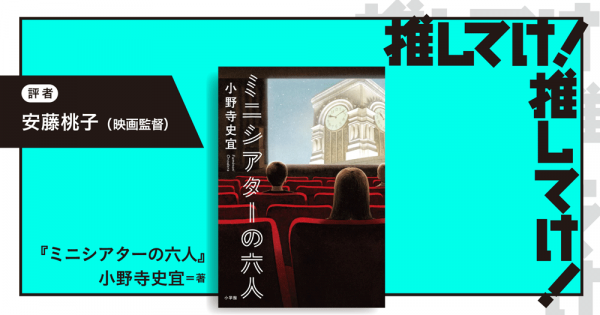「推してけ! 推してけ!」第16回 ◆『ミニシアターの六人』(小野寺史宜・著)
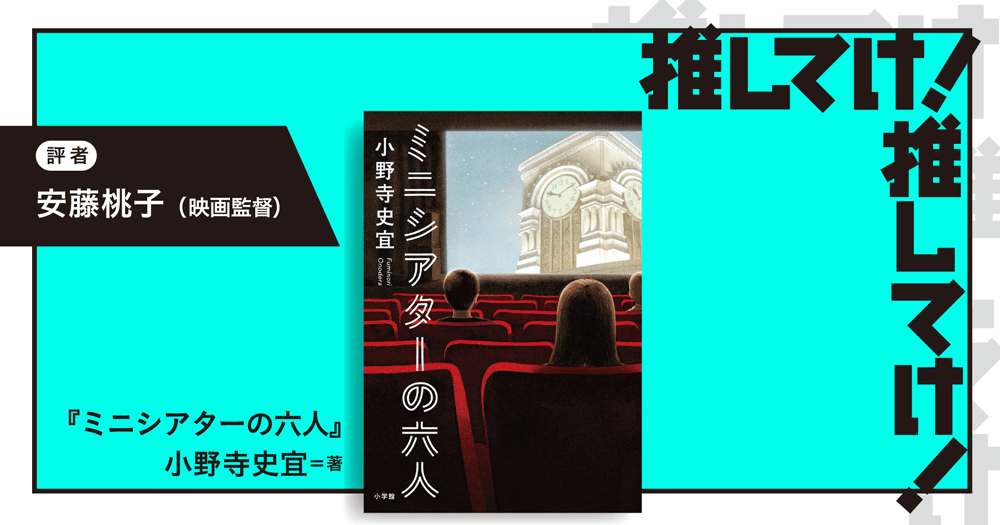
評者=安藤桃子
(映画監督)
パラレルで、ミルフィーユ
「銀座四丁目交差点の角にある和光。その大時計の針が十時十分を指している。映画はそこから始まる」という文章から、『ミニシアターの六人』は始まる。小説の舞台は銀座のミニシアター。2年前に他界した、末永静男という映画監督の追悼上映作品『夜、街の隙間』を観に来た6人の客と1人、それぞれの映画体験と人生は短編集のように独立しているが、絶妙に交差させながら一冊に紡いでいる。映画の内容も同時に描かれ進行していくので、時間軸が縦横、左右、斜め、読み手の感覚はどんどん立体化してゆく。
読み始めて数ページ、リアルな映画描写に思わず小説の中の映画に登場する俳優名を検索したが、そんな俳優は存在しなかった。それほど瞬時に小説内で映画体験へと引き込まれたのだ。そのまま脚本を貼付けたかのように、シーンやト書き、台詞も出てくる。もちろん、小説の登場人物それぞれに引っかかるシーンや共感する映画の登場人物が異なるのだが、観客(登場人物)のスクリーンを観る視点は、読者とシンクロして映画を観ているような状態になる。
小説内にバラバラに出て来るシーンをつなぎ合わせたら全体で一本になるのではないか? 作家、小野寺史宜さんは、一本まるまる映画の脚本を書いてから小説に組み込んだのだろうか? 物語に集中しながらも、脚本が面白くて、そんなことも考えてしまう。映画だと架空の地名やロケーション設定もよくあるが、本作は銀座が舞台なので、ロケーションも楽しめる。リアルなロケーションにすることで、読み手のイマジネーションは固定されるどころか、より一層広がってゆく。この小説の場合、場所を設定することで、時間を超えやすくなったからだと思う。銀座で観る銀座が舞台の映画、映画館という箱と、そこで働く人、観客、交差してゆく6人の登場人物。「末永静男は(中略)細かな細工もうまい」という映画と同じく、本の登場人物達にもちょっとしたつながり、交差がある。
人は映画を観ていると、様々な記憶が蘇るものだ。もちろん、登場人物達も記憶を蘇らせてゆく。ミニシアターで働いていた三輪善乃、中学教師の山下春子、昔、自主映画を撮っていた安尾昇治、無念な男沢田英和、ミニシアター初体験で20歳の誕生日を迎えた川越小夏、映画監督を目指す本木洋央そして、監督と女優との間に生まれた末永立男。映画監督、ミニシアター運営、芸能人の二世、女であり母、ということはもちろん、映画監督を目指していた頃のことも、様々な立ち位置で登場人物にシンクロした。私も閉ざしていた記憶の窓が開き、涙が溢れた。
「ぼくは映画を捨てた。捨てたからには捨てた」「映画は、撮る側から観る側へと戻った」という安尾昇治の言葉が突き刺さる。同時に映画監督を目指す本木洋央が心の炎を燃やすさまに、助監督時代を思い出し、火種がこちらに飛び移った。20歳の川越小夏の映画の見方もとても新鮮で、映画を知らなかった頃にワープした。
「この映画を観て初めて、映画そのものを好きになった。映画というもの自体を少しだけ理解した」、映画に良いも悪いもないのだ。パラレルで、ミルフィーユ。幾層にもなった時間と空間、現実も非現実もないのが映画だ。映画監督、もしくは映画作品そのものに「映画」が在るのではなく、観る人の心のほうに「映画」が在るのだという本質を、一見するとさらっと軽快な運びで描いた小野寺氏は、心から映画を愛しているのだと感じる。
『夜、街の隙間』が映像化されることはない、と思いたい。ここで既に映画化されているからだ。『夜、街の隙間』という名作を観終わった私は、本を閉じた後もその余韻に浸っている。本木洋央が言う「まぶたスクリーンに黒の残像。でもちゃんと浮かぶ」、記憶は掴みきれないというのと同じで、光である映画も掴めない。映画というメディアを、小説で体験させてくれた。和光の大時計が象徴するように、私たちの観念が境界線や限界を作っているだけで、映画館で体感する時間の感覚がそうであるように、時間も空間も本来は自由なものだ。
銀幕の中に生き続ける人たちがいる、その事実の尊さに、実際には存在しない作品にもかかわらず、愛おしさで胸がいっぱいになる。お客の誰かが笑うと、「映画館の空気が少し揺れる」、ミニシアターは魂の装置なのかも知れない。
安藤桃子(あんどう・ももこ)
1982年東京都生まれ。ロンドン大学芸術学部卒。2010年『カケラ』で監督・脚本デビュー。14年、自身の小説『0.5ミリ』を映画化。報知映画賞作品賞、毎日映画コンクール脚本賞、上海国際映画祭最優秀監督賞などを受賞、国内外で高く評価される。父は俳優・映画監督の奥田瑛二、母はエッセイストの安藤和津、妹は女優の安藤サクラ。近著に、家族や映画への思い、移住先の高知での活動のことなどを綴るエッセイ集『ぜんぶ 愛。』がある。
〈「STORY BOX」2022年2月号掲載〉