「推してけ! 推してけ!」第32回 ◆『神無島のウラ』(あさのあつこ・著)
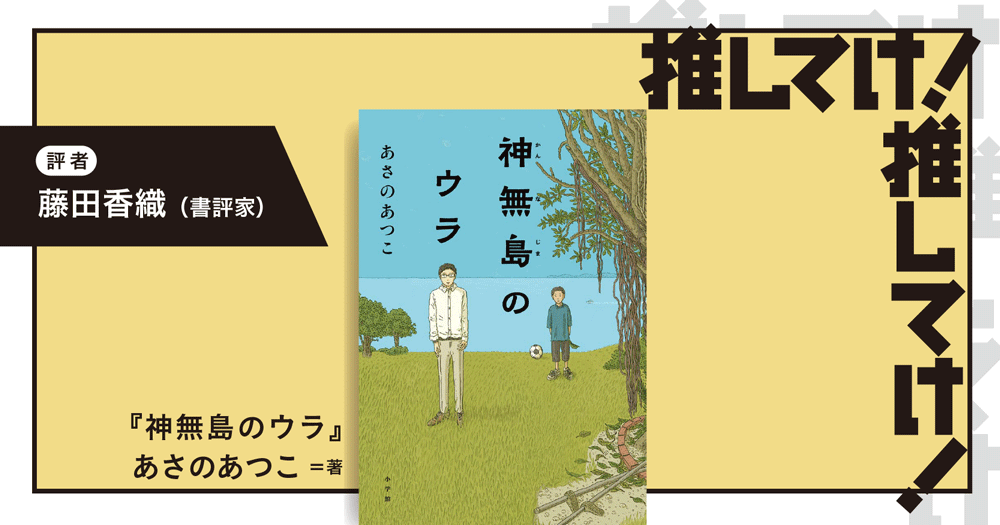
評者=藤田香織
(書評家)
胸に深く突き刺さる〝凄味〟
あぁ、凄い。
読みながら、何度かそう呟いた。
いや、呟く、というより唸るように声が出てしまった。
作者である、あさのあつこの凄さや巧さなんて、もう十分、知っているつもりでいた。
当時はYAと分類されていた出世作『バッテリー』に代表される、ヒリヒリとした、けれど明日を信じさせられる抜群の青春力。島清恋愛文学賞を受賞した『たまゆら』のような、読み手の呼吸を止める描写力。友情の脆さ、尊さ。仕事の厳しさ、楽しさ。戦争の狂気、時代の正義。乗り越えようと歯を食いしばる主人公も、受け入れがたいと足掻く主人公も、その周囲の人々の逡巡や葛藤も、いつだって「あぁ巧いな」と思ってきたのだ。
もちろん、本書も巧みな小説だ。
都会とはまったく違う離島の空気。人々が口にする訛りの強い方言。島に伝わる、子どもたちを守る「ウラ」という神の存在。読み始めてすぐに分かるものごとだけでも、ぐっと惹き込まれるものがある。
でも、それ以上に。胸に深く突き刺さる凄味が本書にはあるのだ。
物語の舞台となる神無島は、鹿児島から週に二便のフェリーで約十二時間。外周わずか十五キロ足らずの人口は百人に満たない小さな島だ。外食できる店はなく、思うように食材も手に入らない。そんな辺境の孤島へ、関東圏の小学校で教師をしていた槙屋深津が、臨時教諭として赴任してくる。
深津は、この島の出身だった。十二歳まで島で暮らしていた彼は、養護教諭の妻と離婚したばかり。とはいえ、離婚の傷を癒すために故郷へ戻ってきたわけではない。
二年半ほど、ひとつ屋根の下で暮らしてきた元妻の彩菜から、深津は幾度となく、あなたのことが分からない、何を考えているのか理解できない、と告げられていた。「わたしに……というより、〝今〟に焦点が合ってないんだよねぇ、深津は」。
〝今〟を見ていないのだとしたら、自分は〝いつ〟を見ているのか。傍からは普通に見えても、深津は自分のなかにある違和感を自覚していた。ときおり、何気ない日常の動作が強張り、ぎこちなくなっていることがある。〈芝居をしているみたいだ。しかも、下手くそな〉。いったいなぜなのか。まずはこの、主人公である深津が抱えているであろう屈託と、寄る辺のなさの正体が気にかかる。
大根役者であったとしても、これまでは、まっとうな教師であり、人間であると彩菜以外の人々の目をごまかすことはできていた。しかし、関係性の濃い島ではそうはいかない。目を逸らし続けることはできず、逃げ場も、ない。
対する人間が、善人か悪人かをじっと見ていれば分かるという、島の神と同じ名をもつ小学四年生の洲上宇良。東京で不登校になり、県の企画で島にホームステイしたことを機に転校してきた中学二年生の高見もも。新学期が始まると同時に急遽転入してきた四年生の清畠莉里と新一年生、流の姉弟。たった十二人の小中学生たち個々の事情と抱えている問題に対峙しながら、深津は自分自身とも向き合っていく。
二十年前、共に島を出た後、深津が十九歳のときに突然姿を消した母・仁海との再会。関係の絶えていた仁海の兄である伯父から聞かされた忌まわしい、けれど曖昧な記憶として残る出来事の真相。「自分から抜け落ちてしまった何か」を回収しようとする深津の痛みが、読み手の胸にも伝わってくる。負くんな、負くんな。必死で立ち上がろうとする生徒にエールを送る深津に、気がつけば同じ言葉を送りたくなっている。
小さな島の、小さな世界で、神に守られているはずの子どもたちが直面している残酷な現実は、決して珍しいものではない。おそらく多くの読者が、まぁよくある話だよね、と思うだろう。けれど同時に、それを「どこか」で起きている話にすぎないと、受け流してきた自分にも気付かされてしまうのだ。
「ごめんなせ。ごめんなせ」、「えずってえずって、身体が動かんかった。深津、守ってやらんで、ごめんなせ」。
恐くて怖くて、身体が動かないほどの暴力は、今、私たちが生きている世界と別の場所で起きているのではない。痛みも憎しみも悲しみも、目を逸らせば無くなるものではないと、繰り返し突きつけられる。
〈島で生きるとは、他人と繋がることだ〉。神無島に限った話ではない。
〝今〟、〝この場所〟で私たちが見ている物語なのだ。
藤田香織(ふじた・かおり)
1968年三重県生まれ。音楽出版社勤務を経て、フリーライターに。著書に「だらしな日記」シリーズ、『ホンのお楽しみ』など。
〈「STORY BOX」2023年3月号掲載〉





