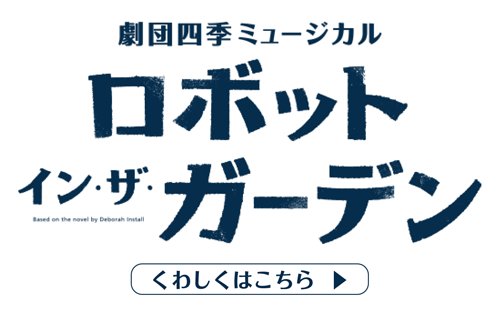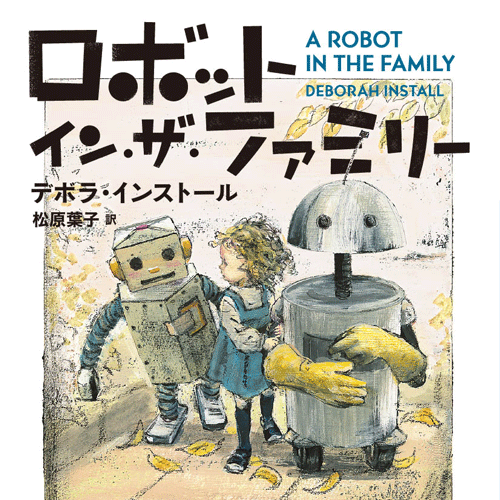劇団四季「ロボット・イン・ザ・ガーデン」上演記念 キャスト特別座談会〈成長しあう喜び〉vol.1

両親を喪ってから無気力な日々を送り、妻にも出ていかれた男ベンが、庭に現れた壊れかけのロボット・タングと世界中を旅しながら人生を再生する――イギリスの作家デボラ・インストールの小説『ロボット・イン・ザ・ガーデン』(松原葉子訳、小学館文庫)が、劇団四季のオリジナル・ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』(台本・作詞:長田育恵、演出:小山ゆうな、作曲・編曲:河野伸)として舞台化されたのは2020年10月のこと。その後、雑誌『ミュージカル』の「2020年ミュージカル・ベストテン」作品部門で第1位に選出されるなど、大きな話題を呼びました。昨年12~今年1月の東京再演からは新キャストも加わり、2月23日には京都公演が開幕(4月16日まで)、5月14日からは全国公演も予定されています。東京公演を終えた1月下旬、ベン役の田邊真也さんと山下啓太さん、ベンの妻・エイミー役の鳥原ゆきみさんと岡村美南さん、二人で一体のパペットを操作するタング役の長野千紘さんと安田楓汰さんに、この作品への思いを聞きました。
お客様の熱量で、「愛される物語」を実感
――東京公演の千秋楽を迎えた感想を教えてください。
田邊
毎日のように新型コロナのニュースが流れていたので、このカンパニーでの公演はどうなるかなといつも不安でした。今は素直に、最後までできてよかったという思いです。
鳥原
去年の初演の時は何回かストップしましたからね。今回は全部上演できたので、天に感謝という気持ちでいっぱいです。
安田
再演が始まった頃は感染者数は少なかったものの、その後急速に感染が拡大しましたからね。
山下
本当に。僕は東京の千秋楽を迎えられたうれしさと、これからまた長い旅が始まるぞ、という両方の思いがあります。

2008年研究所入所。『ライオンキング』で初舞台を踏み、のちにシンバ、『春のめざめ』エルンスト、『アラジン』オマール、『パリのアメリカ人』アンリ・ボーレル等を演じている。『ロボット・イン・ザ・ガーデン』では2022年1月にベン役デビュー。
岡村
こういう状況下で、演劇というのはお客様がいて初めて成り立つものなんだ、作品も私自身も、お客様に育ててもらっているんだと、そう改めて思いました。本番でお客様の空気や反応を肌で感じることで、自分のエイミー像がより立体的に、より進化したのを実感したので。
長野
初演の前半では客席の収容率に制限があり、カーテンコールの時にどなたも座っていない座席が見えると、「ああ、もっと多くの人に見てほしいのに」と思いました。今回は初日から完売で、お客様の熱量も感じて、「こんなに愛される作品になったんだ!」と、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

2011年研究所入所。『サウンド・オブ・ミュージック』リーズルで四季での初舞台を踏み、『桃次郎の冒険』スモモ、『魔法をすてたマジョリン』マジョリン等を演じている。『ロボット・イン・ザ・ガーデン』では初演からタングを演じている。
俳優として表現する喜びに溢れた作品
――この作品が、数ある劇団四季の演目のなかでも高く評価され、魅力的である理由はどこにあるのでしょうか。
田邊
劇団四季には生きる喜びや人生の感動といったテーマ性があって、それはどの作品にも共通しています。ただブロードウェイなどの海外作品を上演する場合は、すでに出来上がったひとつの形を僕らが追うので、セリフの間や立ち位置、心の動きというのはすでに決まっている部分も多い。でも今回のようなオリジナル作品はゼロから作り上げるので、自由度が高いというのは大きいですね。

『クレイジー・フォー・ユー』ボビー、『コーラスライン』ザック、『マンマ・ミーア!』スカイ、サム、『思い出を売る男』『ハムレット』タイトルロール、『キャッツ』ラム・タム・タガー、『鹿鳴館』久雄、『オンディーヌ』ハンス、『アイーダ』ラダメス、『コンタクト』マイケル・ワイリー、『美女と野獣』ビースト、『恋におちたシェイクスピア』マーロウ、『リトルマーメイド』セバスチャン等を演じている。『ロボット・イン・ザ・ガーデン』では初演からベンを演じている。
岡村
私は初演を観た時に、素直に俳優としてうらやましいと感じたんです。舞台に立つ誰もが生き生きと輝いて、表現することの喜びに溢れていて。すごく良い稽古を重ねてここまできたのが伝わってきた。私もこの稽古に関わりたいと心から思って、今回の再演に向けたオーディションを受けました。スケールの大きなお話ではなくて、とても繊細な物語だから、キャラクターをしっかり掘り下げて、リアリティとともにその場ごとに反応していく演技が必要です。稽古や本番を通して、俳優としてこの作品が転換点になったといっても過言ではないと、今はそう感じています。
鳥原
私、今回初めて劇場で観た時に美南ちゃんのエイミーが歌う「Free Free」というナンバーで泣いたんですよ。女性二人で歌う明るい曲で、以前稽古場でうぶちゃん(タング役の一人、生形理菜さん)がこのシーンで泣いているのを見た時は「なんで?」と思ったのに、客席で観た時には「私、泣いてる!」って(笑)。自分が思っていたのと全然違うシーンがふいに心に沁みたりするのがこの作品の多面的な魅力なんだな、と思いました。
岡村
エイミーはキャリアウーマンで、無気力になってしまったベンについていけずに、離婚を切り出すんですよね。

2008年に入団。『劇団四季ソング&ダンス 55ステップス』で四季の初舞台を踏み、『ウィキッド』エルファバ、『夢から醒めた夢』ピコ、『キャッツ』ジェリーロラム=グリドルボーン、『クレイジー・フォー・ユー』ポリー、『ウェストサイド物語』アニタ、『ノートルダムの鐘』エスメラルダ、『パリのアメリカ人』マイロ、『マンマ・ミーア!』ドナ・シェリダン等を演じている。『ロボット・イン・ザ・ガーデン』では2022年1月にエイミー役デビュー。
鳥原
そのキャリアウーマンとして輝いている姿が心に沁みたんだと思います。
山下
僕も初演を観て、それぞれの俳優の技術、熱量、物語の構造も含めて本当にすごい作品だと感動しました。それはもう、言葉にならないくらい。それほど僕にとっては特別で大きな作品です。だから今、自分がベンをやらせていただいているのが信じられなくて。稽古の初日前夜はもう寝られなくて、何かが口からうーっと出てくるんじゃないか、というくらい緊張していました。
鳥原
えっ、全然感じなかった(笑)。
田邊
いつもの啓太だったよな(笑)。
山下
なにしろ真也さんのベンが本当に素晴らしくて。でも演出家の小山ゆうなさんは、真也さんの真似をしなくていい、僕は僕のベンでいいんだ、と何度も何度も言って下さって。
鳥原
同じ役でも稽古が人によって違うんですよね。それが本当にすごいし、それによって生まれたものもたくさんありました。

2006年に入団。『エビータ』で四季での初舞台を踏み、のちにタイトルロール、『ヴェニスの商人』ジェシカ、『ウィキッド』グリンダ、ネッサローズ、『王子とこじき』エドワード王子、『エルコスの祈り』エルコス、『美女と野獣』ベル、『コーラスライン』ヴァル、ディアナ、『サウンド・オブ・ミュージック』マリア、『壁抜け男』イザベル等を演じている。『ロボット・イン・ザ・ガーデン』では初演からエイミーを演じている。
岡村
私にとっては、「芝居の不正解はあるけど、正解はない」と言ってもらえたのが大きかったです。間違ったらきっと指摘してくださるだろうから、それだったらもう思い切ってやろうと。のびのびと挑戦できました。
安田
皆さんが仰ったことに加えて、僕は河野伸さんの楽曲も大好きなんです。耳になじみやすいけれど感動的で、旅をして各地に行く時の曲も、それを聴いただけで国や都市の世界観が伝わるんですよね。
親子、兄弟、友達。ベンとタングの関係性とは
――この物語はベンと壊れかけのロボットのタング、それぞれの成長物語という側面もあります。
安田
僕は初演を観た時、タングしか目に入らなかったんです。それほど印象的で。タングは二人の俳優で操作しますが、「本当に生きてるみたいだ、すごいな」と。でも今回のオーディションでは、ベンを受けるかタングを受けるか締切り直前まで迷いに迷いました。もう一度PVを観て、やっぱりタングだと思って受けたんです。今はそれで良かったなと思っています。
田邊
まだ序盤のシーンしか稽古していない時に、安田君が「手が、手が」と言っていたことがあって。何事かと心配しました。
安田
緊張感や今日はここで決めるぞという思いが強すぎて、初めは強く握りすぎてしまったんです。薬指がピクピクしていて、真也さんが声をかけてくださった時には「手が、手が」と……。

2019年に入団。『オペラ座の怪人』で四季での初舞台を踏む。『ロボット・イン・ザ・ガーデン』では2021年12月にタング役デビュー。
山下
「手がどうしたの?」と、みんなで聞いた(笑)。
長野
私は初演の際はタングの胴体の操作を体験したので、今回安田君が苦労しているのを見て、ああ、男性でも大変なんだ、自分でもよくやっていたなと思いました。今回は私がタングのセリフを話すことが多いので、どうしても私の色になってしまいがちですが、安田君のおっとりしたかわいいところも混ぜたキャラクターにできればと思って、試行錯誤を重ねましたね。
田邊
パペットで表現するって、本当に大変だし、難しいことだよね。
安田
「(相手の話を)聞いてるよ」という感じを込めると、表現が大きくなりすぎてしまうんです。
長野
究極的には瞳のうるうるだけでタングの思いを表現できたらと思っています。これでいいのかなと、いつも俯瞰的に見られるようにしています。
田邊
ベンとタングの関係性でいうと、僕の場合はベンがお父さんで、タングが子供というイメージで組み立てています。僕のセリフのトーンやスピード感は、そういう風に聞こえるだろうなと思います。
山下
僕は、ベンとタングの関係性を台本に沿ってひとつひとつ作り上げていって、最後に絆が生まれるところまで持っていきました。その結果、兄弟というイメージかなと思います。
安田
タング役の自分から見ると、お友達でしょうか。守られている時もあるし、頼られる時もあって、それが場面ごとに違いますし。
長野
タングはベンに対して、「僕のことを守ってくれる、愛してくれる大事な人」という認識は持っていると思います。でもタングは人間ではないし、とはいえ単なるロボットでもない。タングがベンをどんな存在だと感じているか、それは舞台を観てくださる方それぞれの感性で感じていただければと思います。
*たのしい座談会はまだまだつづきます
vol.2へ
(文・構成:鳥海美奈子、撮影:阿部章仁)