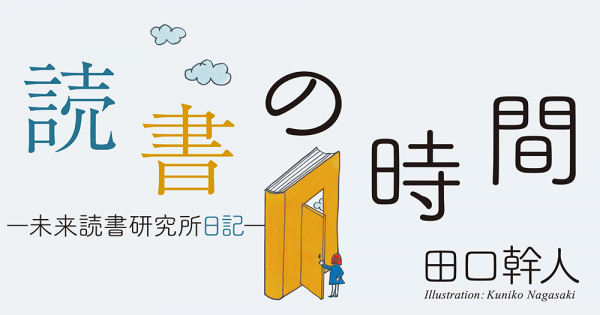田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第12回
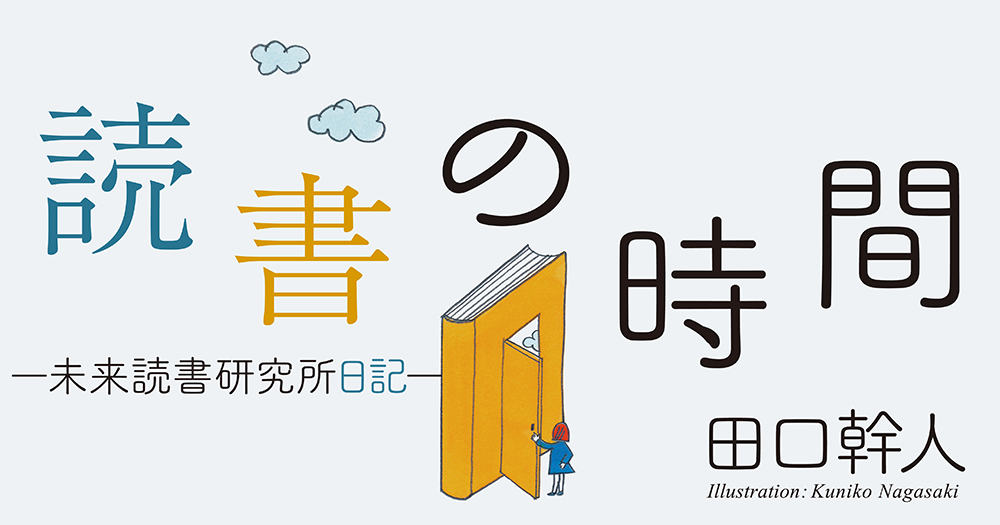
「すべてのまちに本屋を」
本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ
10月20日に神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙「タウンニュース」Web版が、「上町商店街 『小さな本屋』存続ピンチ ひきこもりの就労支援拠点」という記事を公開した。
本屋に関して極めて重要な記事であることから、少し長くなるが一部抜粋してご紹介させていただきたい。
《不登校やひきこもりを支援するNPO法人アンガージュマン・よこすかが運営する「はるかぜ書店」が窮地に立たされている。出版取次と書店をつなぐ仲介業者が資金繰りの悪化で事業停止となり、9月から書籍や雑誌の仕入れが一切できない状況になっている。「ひきこもり当事者が運営する小さな本屋」をコンセプトとする就労支援の事業が揺らいでいる格好だ。》
《ここ数年は出版不況の影響もあり、書店業務は縮小傾向にあり、現時点で研修を受けている人はいない。(中略)「(書店は)社会参加の道筋のひとつであり、商店街の協力を得ながら活動してきたことに大きな意味がある」と島田徳隆理事長。出版取次会社と交渉して書店経営の存続の道を探る一方、時流に合った就労支援事業や受け入れてくれる協力企業の開拓など新たな仕組みの構築も視野に入れる。》
《「社会に出たいけれど、出られない。不安な気持ちを抱えている当事者と家族がいなくなったのであれば撤退できるが、課題の解決には程遠い状況。多くの人に支えられてきた〝小さな本屋〟は大切な場所。簡単にはあきらめない」と島田理事長は力を込めた。》
時を同じくして、ドラッグストアの雑誌コーナーに、「雑誌の仕入先をご紹介いただけないでしょうか」と書かれた紙が掲示されたのを目にした。さらには、病院の売店でも同様の訴えが相次いだ。
その背景にある構図は、はるかぜ書店と同様である。
この記事と出来事を目にすると、「また1つ本屋の灯がまちから消える」ことを伝えている記事のように見えるが、そうではないのだ。書店の閉店や無書店自治体数が話題にされる際、JPO(一般社団法人日本出版インフラセンター)の共有書店マスタに登録されている書店だけが書店であるという建付けの下で語られることが多い。「本の窓」9・10月合併号に書いた「大きな出版業界」と「小さな出版界隈」という2つの円で書店を分けた時、小さな出版界隈に属する本屋は、 JPO の共有書店マスタに登録されていないので、書店としてカウントされていない。
新刊書店と古書店(新古書店)の区別も一般の人には分かりづらい。いずれにしても一般の人にとっては本が買える場所ということの方が大切であり、 JPO の共有書店マスタに登録されているかどうかは意味を持たない。そこに意味があるのは、流通側の都合だけである。現に、無書店地域として仕分けされた自治体から、わがまちには本屋があるという声も多数上がっており、現在発表されているのは、大きな出版業界が把握している無書店自治体数ということになるのだ。
しかし、「大きな出版業界」と「小さな出版界隈」の2つの円は、完全に分かれているわけではなく、重なる部分がある。商品を供給するインフラとしての卸ルートである。本の小口卸売を行っている代表的なものとして、「子どもの文化普及協会」、少部数卸売サービス「Foyer(ホワイエ)」、そして「書店開発」や「湘南ブックセンター」に代表される書店二次卸がある。まちの一般書店が二次卸を担う場合もある。これらの卸ルートで仕入れている書店は、 JPO の共有書店マスタに登録されていないので、公表されている書店数の増減には影響しないが、二次卸が崩壊した2023年は、まちなかでの本とのタッチポイントとなる場の数がダントツに減った1年になってしまったと言える。
今回のタウンニュースの記事は、書店二次卸スキームの崩壊をメディアではじめて取り上げてくれた。それが業界紙でもなく、大手メディアでもなく、〝タウンニュース〟だったことに「大きな出版業界」と「小さな出版界隈」の根付きの違いを実感することができる。
「NPO法人未来読書研究所」は、かねてより書店二次卸スキームの崩壊が、本当の意味での書店閉店に拍車をかけることに対して警鐘を鳴らしてきたが、業界紙や大手メディアは取材すらしてくれなかった。大きな出版業界の会合でも、話題にすら上らない現状に、温度感のズレを感じてしまう。
二次卸とは、商品を卸売業者から仕入れ、次段階の卸売業者や小売業者に販売する中間卸をいう。2023年に入り、この二次卸の業者の破産や廃業、そして事業休止により、小売業者からの相談が相次いでいる。個別具体的な案件は申し上げられないが、概要はこうである。
書店二次卸スキームは、書店が他社の書店開業を支援したり、取次との直接取引が難しい事業者に対して商品を供給することで、異業種の小規模な小売業者を通じて本を販売する事業である。出版業界は、新規参入に対する参入障壁が高く、本を扱いたいが扱えない事業者が多かった。その課題を解決する方法として、書店の二次卸スキームが使われており、本来は出版業界の裾野を広げる意味においても重要なスキームなのである。
直接出店するほどではなくとも一定の売上げが見込めることから、書店二次卸サービスや小口卸売サービスが窓口になって、希望する異業種の小規模な小売業者に対して雑誌を中心に商品を供給していたが、その供給が止まり、小規模な小売業者は各社取次に相談するも取引きすることができず、やむを得ず事業からの撤退という道を選択するケースが多発している。
書店から配達される商品のみを仕入れていたという小売業者も多くあり、業界側の理由で、確実な売上げ(読者)を失ってしまうことを目のあたりにすると切ないものである。二次卸スキームで卸売されているのは主に雑誌である。雑誌の配送は課題が多く、二次卸が商品供給のサポートをしたくてもできないのが実情なのだ。
比較的鮮度の高い情報を取り扱っている雑誌は、より速報性が高いWebメディアやSNS で代替されてしまい、販売額が著しく低下している。
2022年の紙の出版物(書籍・雑誌合計)の推定販売金額は前年比6.5%減の1兆1292億円と、1兆2000億円を下回ったのだが、内訳を見ると書籍が同4.5%減の6497億円、雑誌が同9.1%減の4795億円となっており、書籍以上に雑誌の落ち込みが大きくなっている。(出版科学研究所『出版指標 年報 2023年版』)
雑誌の落ち込みは今に始まったことではなく、出版科学研究所による出版物の推定販売金額調査によると、紙の雑誌の販売額は、ピークだった1996年と比較すると、2022年は実に70%減少、10年前の2012年と比較しても49%減少しており、その減少幅もより大きくなっている。
そもそも、書店に本を届ける出版物流の仕組みは、雑誌を発売日に届けるために組みたてられていて、その物流網を使って書籍を届けている。だからこそ、雑誌の販売額の落ち込みは、出版物流にとっては致命傷となっており、書籍を中心とした物流網への変革が求められているのだが、変革が進んでいるという話は一向に聞こえてこない。
その歪が表立って見えてきたのが、書店二次卸スキームの崩壊なのだ。
書店二次卸スキームは、小口卸売事業で唯一定期誌を卸売することができるスキームであり、極めて重要であることから、早急に対応を検討する必要があるのだが、その動きは見られない。それが今の大きな出版業界の現実なのだと受け止めてはいるが、一抹の寂しさとあきらめを感じている。
田口幹人(たぐち・みきと)
1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。


![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)
![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)