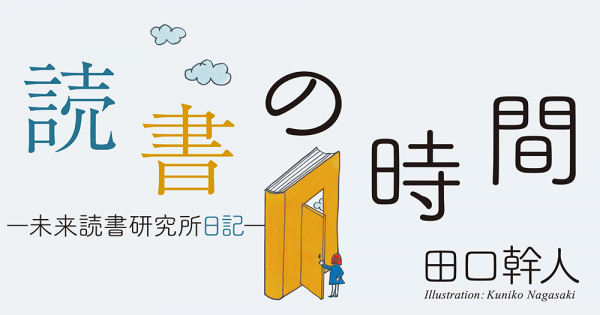田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第13回
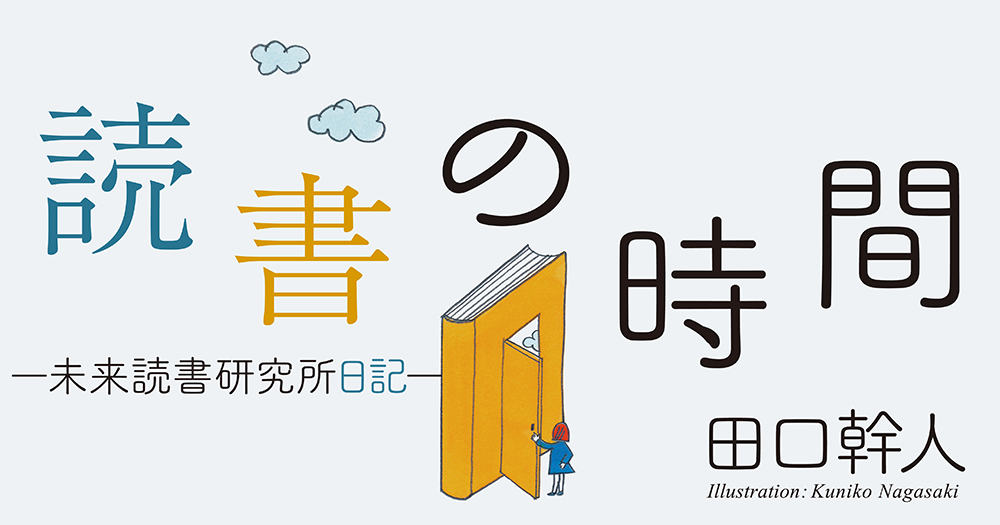
「すべてのまちに本屋を」
本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ
ご縁があって、様々なセミナーや講演会、勉強会などでお話をさせていただくことがある。2023年もそんな機会をたくさんいただいた。
いずれの会場でも熱心にメモをとりながら聞いて下さる参加者の方が多く、ありがたいと思っている。一方で、参加者の方に、その後の実践につながっているのかをお聞きする機会が少ないのだ。講演会後に参加者の方から積極的に連絡をいただき、それぞれの皆さんの活動に伴走させていただくまでに至らないのは、ひとえに登壇する僕の力不足なのだろう。
課題を共有し、何を、いつまで、どのように実施すれば良いのかが明確になれば、人は自然に行動を起こしやすくなると僕は考えている。そこで大切なのは、「思い込み」、「〜しなきゃいけない」、「〜すべき」という思考からの解放だと考えている。そこからの脱却なくして、本当に解決しなければいけない課題が見えることはない。
先日、『「若者の読書離れ」というウソ』(平凡社新書)の著者である飯田一史さんとお話しする機会をいただいた。『「若者の読書離れ」というウソ』のメインテーマの1つは、子ども・若者の読書に関しての誤ったイメージを払拭することにある。現状を把握せず、当事者たちの気持ちに寄り添うことからではなく、我々大人が考えた「こうあるべき」「こうするべき」という「べき論」や「打ち手」(これまでの施策)の評価の話から入ってしまいがちである、という飯田氏の言葉は深く心に残った。
NPO法人読書の時間の活動を通して、様々な学校で多くの子どもたちから直接読書についての率直な意見を聞いてきた僕は、大人が考えた「こうあるべき」「こうするべき」という「べき論」や「打ち手」に対する矛盾を感じていたことがその理由である。
『「若者の読書離れ」というウソ』の第一章「10代の読書に関する調査」は、〝「子どもの本離れ」は過去の話〟であるという文章からはじまる。
えっ? そうなの? と思われるかもしれないが、その通りなのだ。
未来読書研究所で調べたところ、「若者の読書離れ」という言葉がはじめて使われたのは今から46年前の1977年だった。その後、1990年代に入ると、児童書市場の縮小に危機を抱いた業界団体が中心となって読書推進に関する活動がはじまり、その活動が政界を動かし、文部省(当時)が学校図書館を必要とする教育へと方針を転換し、学校図書館整備等五か年計画策定に至った。その後も、官民一体となり子どもたちの読書環境の整備を進めてきた結果、2000年代には小学生の平均読書冊数はV字回復し、中学生の平均読書冊数も増加傾向にある。それは2022年の「学校読書調査」(全国学校図書館協議会)でも変わっていない。
では、高校生の平均読書冊数はというと、1970年代から2022年まで横ばいであり、ここ数年ではわずか0.3~0.5%ではあるが上昇しているのだ。
たしかに1970年代から1980年代までは、読書離れが進んでいることはデータ上把握することができることから、「若者の読書離れ」は進んでいたと思われる。しかし、現在はどうだろうか。「若者の読書離れ」と謳うからには、顕著に減少しているデータを示す必要があるが、そのようなデータは存在していないのだ。
では、なぜいまだに「若者の読書離れ」が進んでいると思われているのか。それは、出版物推定販売額の右肩下がりの現状があるからである。とくに雑誌の落ち込みが大きく、2022年と1996年の雑誌の販売額を比較すると、3分の1以下にまで落ち込んでいるのだ。官民一体となって取り組んできた読書推進活動は、「書籍」が中心であり、「雑誌」を対象外としていたことが大きいのかもしれない。1990年代の子どもたちの多くは「雑誌」を購読していた。それが少子化や、娯楽や情報ソースとしての役割が Web へと変化することで「雑誌」の需要が著しく落ち込むことになったのが現状である。
言い換えると、雑誌の推定販売額の大きな落ち込みが、「若者の読書離れ」という言葉に置き換えられているのではないかと考えられる。
「本を買う行為=読書」ではない。
近年の出版業界団体の読書推進活動の柱は、「読書」ではなく、「本を買う行為」や「本を買うことができる場所を保護する」ことが目的となってしまっていることに違和感を覚えている。
73年続いた毎日新聞社の『読書世論調査』は2019年が最後の調査だった。単年度の数値ではなく、経年変化を見られる毎日新聞『読書世論調査』は非常に大切な調査だったこともあり、調査終了の知らせを聞いた時の落胆は大きかった。その分、2023年8月から9月にかけて、読売新聞社が「秋の読書推進月間」に合わせて世論調査を実施したという報道を目にしたときは嬉しかった。
が、読書月間のはじまりに合わせるように読売新聞の紙面で公表された郵送全国世論調査「読書月間」の質問と回答を拝見し、出版業界団体の読書推進活動の柱は、「読書」ではなく、「本を買う行為」や「本を買うことができる場所を保護する」ことが目的になっているのだと痛感させられた。
「地域の書店を保護する」という言葉を見るたびに暗い気持ちになる。世論調査には、なんの違和感もないかのようにこの文言を冠にした設問も設けられている。しかし、「あなたは、主にどのようなきっかけで、読む本を選びますか。いくつでも選んでください。」という設問の選択肢には、公共図書館が入っていないのである。年間6億8421万5千冊(2019年、出版科学研所調べ)もの本との出合いを提供している公共図書館が、本設問の選択肢にないことに違和感を覚えるのはおかしなことなのだろうか。
その後も、ことごとく書店が必要かどうかというテーマの設問が続いていた。紙面には限りがあるのだろうが、毎日新聞『読書世論調査』が行ってきたような、読書に関する経年変化に関する調査も行われていたと信じたい。とりあえず調査結果をまとめた報告書の出版を待つことにしたい。
長々と脱線してしまったが、話を講演に戻そう。
「百聞は一見に如かず」ということわざがある。百回聞くより、一回自分で見ることのほうが大切であるという意味で使われる故事成語(出典『漢書』「趙充国伝」)である。
このことわざには後世の創作と思われる続きがあり、「百見は一考に如かず」「百考は一行に如かず」「百行は一果に如かず」「百果は一幸に如かず」「百幸は一皇に如かず」がよく知られている。
「百回見るより、一回自分で考えることの大切さ」「百回考えるより、一回自分で行動することの大切さ」「百回行動するより、一回自分で結果や成果を出すことの大切さ」「百回結果や成果を出すことより、一回自分の幸せにつながることの大切さ」「百回幸せにつながるより、一回自分がみんなのために行動することの大切さ」を教えてくれることわざである。
僕は、百回考えるより、一回自分で行動するほうが大切だという「百考は一行に如かず」が好きである。
知り、考え、行動に移す。
この行動に移すことが難しいのであるが。
読書月間がはじまるこの季節は、すごく楽しみな講座がある。ここ数年間は、コロナ禍の影響でリモートでのオンライン配信だったが、今年はリアル開催ということもあり、講座の開催を楽しみにしていた。
「JPIC読書アドバイザー養成講座」である。JPIC読書アドバイザー養成講座は、一般財団法人 出版文化産業振興財団(JPIC)が、読書を通した国民の生涯学習推進・読書活動の推進のため、1993年から続けている講座である。毎期カリキュラムを更新し、常に「本」と「読書」の魅力を掘り下げる多彩な講座を提供しており、受講生には「編集から印刷」「出版と流通」「電子書籍」「著作権」「読書推進運動」等、各分野の第一人者である講師陣のもと、スクーリングとレポートの組み合わせで体系的な学びを提供している。
受講した皆さんはその後、自己の教養を高めるとともに、「読書の効用」を活かし、企業における社員教育の一環として、あるいは地域での活動として、創造的に読書推進を実践されているのが特徴である。
未来読書研究所は、数年来「読書推進運動」のパートを担当させていただいており、講座修了後、本講座の受講生の皆さんからご連絡をいただき、様々な形で各地の読書推進活動の伴走をさせていただいている。
受講後、これだけ多くの実践につながるセミナーや講演会、勉強会はJPIC読書アドバイザー養成講座以外に思いつかない。参加者には公共図書館・学校図書館関係者、出版社、取次、書店等出版業界関係者も多いが、出版業界に興味を持つ学生や一般の方々も多く参加されている。
JPIC読書アドバイザー養成講座テキスト「①本が手に届くまで」の「はじめに」にこんな記述がある。
「多様化し複雑化する社会の中で、本と読者がつながりにくくなっていることも事実である。だからこそ、いま、特に本の世界と読者をつなぐ人材が求められています。これまで本に触れてこなかった人が感じている読書へのハードルをとりはらうのも、読書アドバイザーだからできることです。ただ、忘れてはならないことが読書アドバイザーにはあります。様々な方法で本と触れ合う場が増えてきていますが、それは著者がいて、出版社があるからこそ可能なことだということです。個人と個人が本を交換したり、不要になったものを提供したりすることで本が好きになり、次の読書活動につながることは大変重要で意義のあることです。しかし、そればかりでは出版社に収益が生まれず、著者に還元されません。それが続けば、新しい本が発売されなくなり読書活動自体が困難となります。」
冒頭、作り手と読み手がいる世界を維持する重要性を明確に打ち出しているのは、大変重要なことである。
「本を買う行為=読書」ではないのだが、作り手と読み手がいる世界を維持させるために、共栄共存できる環境づくりが必要なのだ。
JPIC読書アドバイザー養成講座を通じ、このような学びと気づきをされた皆さんだからこそ、その後の実践につながることが多いのだろう。
田口幹人(たぐち・みきと)
1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。


![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)
![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)