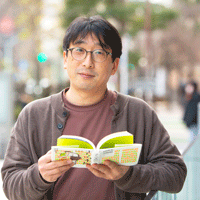田口幹人「読書の時間 ─未来読書研究所日記─」第33回
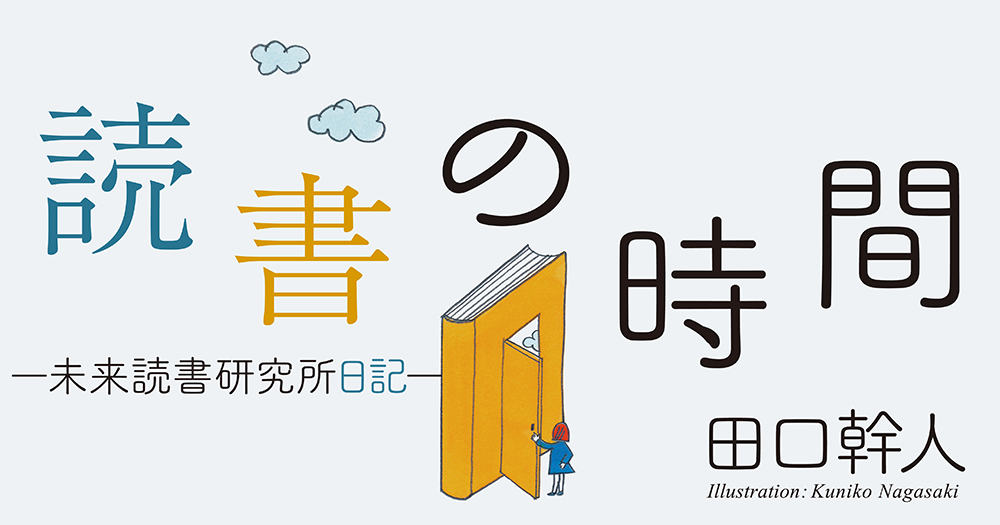
「すべてのまちに本屋を」
本と読者の未来のために、奔走する日々を綴るエッセイ
昨年、政府の経済財政運営の指針となる「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)」に初めて、「書店と図書館等との連携促進等を含む文字活字の振興」が盛り込まれてから、「NPO法人読書の時間」には、各自治体の図書館・学校図書館関係団体から、図書館と書店連携についての講演依頼が増えた。「書店と図書館の連携」というキーワードが語られ、各地で「何をしたらいいのか」と勉強会や、これまでの成果を語り合うイベントが頻繁に開催されたことは有意義だったが、具体的に何をどう連携するか以前に考えるべきことがあるのではないだろうか、という思いが強く残ることが多かった。
7月23日に開催された福島県高等学校司書研修会県大会も学校図書館と地域の書店との連携が主なテーマだった。県下の高等学校から60名の司書が、地域の書店さんから15名の書店員が参加し、学校司書と書店員が一堂に会しての開催だった。書店員が参加しての開催は今回が初めてということで、全国的に書店と図書館との連携を模索する動きが広がっていることを実感した研修会だった。
前半は、僕から書店と図書館が連携することで何を目指すのかのビジョンを明確にすることの必要性をお話しさせていただいた。まずは、地域の書店と学校図書館がそれぞれの強みを活かし、弱みを補い連携することで生徒の皆さんにどういうメリットを与えることができるのかを、議論して決めていくことが必要であり、今回がその機会となることを期待しているということをお伝えさせていただいた。
また、日本出版インフラセンター(JPO)に登録している書店だけが書店なのではないことを説明し、近年の「小さな出版界隈」の広がりと、小さな出版界隈の書店と地域の学校との連携事業の例を紹介させていただいた。福島県下においても、JPO登録のない書店が14軒存在している。
福島県西白河郡矢吹町の「self space しおりば」もその一つだ。人の存在を感じる適度な雑音の中で、本を読んだり、勉強したり、物思いにふけったり、そして、何か話したくなった時に、話を聞いてくれる大人がいる場所をコンセプトに、電車の待ち時間やちょっとした空き時間に、寒い日や暑い日、ちょっと疲れた時やちょっと嬉しいことがあった時、そんなちょっと特別な日に使ってほしいという想いで運営されている。
駅前の空き店舗を活用して本屋をはじめたい、と相談を受けた時のことを今でも覚えている。当時の計画から少し修正はあったように見受けられるが、今は地元の中高生だけではなく、様々な方に利用いただいていると聞いている。
矢吹町は無書店自治体リストに挙げられている。しかし、実際には「self space しおりば」のように本のある空間があり、そこで本が購入できる場所は存在しており、地域に根差し始めている。無書店自治体リストを公表し、書店の減少を嘆く前に、まずは「大きな出版業界」的な書店がなぜその地から撤退を余儀なくされたのか、そしてその後に芽生えた小さな出版界隈の書店がどのような活動をしているのかを知るべきである。「NPO法人読書の時間」が書店連携についてさせていただくお話は、このような問題提起が軸となっている。
論点がズレたので話を戻そう。
今回の福島県高等学校司書研修会県大会には書店の立場から、福島県下の老舗6書店に加え、昨年新しくオープンした「はなみずき書店」さんも参加されていた。
「はなみずき書店」は、元福島県立美術館学芸員の店主が、本を通じて何かと何かがつながって生まれたり、育ったりしていくのを応援していきたいという想いで立ち上げた書店である。芸術、文学、哲学、社会学、心理学、 民俗、自然、生活、児童文学、絵本など、人文系の新刊書と古書を扱っていて、リアル書店では主に新刊書を販売し、オンラインストアでは古書の販売と新刊書の企画販売をしている。
福島県下の書店さんと縁がなかった僕が、唯一会場で面識があったのが「はなみずき書店」店主の荒木康子さんだけだったのだが、ここでお会いできるとは、と嬉しくなってついつい話し込んでしまった。まだ書店をはじめたばかりの私にまで声をかけてくださって、嬉しかったです、とお話しされていた荒木さんだが、大きな出版業界の書店だけではなく、小さな出版界隈の書店も書店としてお声がけされていた福島県高等学校司書研修会県大会の実行委員の皆さんの想いが伝わる瞬間だった。
講演に続いて、各書店がこれまで学校図書館と書店の連携で実施してきた「高校生による読み聞かせ会」や「わたしの推し本POPコンテスト」などについて、岩瀬書店・遠藤拓弥さんと西沢書店・松本照実さんから事例報告があった。
また、福島県立福島東高等学校の阿部先生による紙上事例報告「福島東高校地歴公民科新入生課題図書50冊」は非常に興味深い考察だった。課題図書50冊を、A・Bふたつの書店でフェア展開していただき、A・B両書店で特設コーナーがあることを伝えた上で新入生にリストを配布したところ、課題提出時のアンケートによると、240名中126名はA・B書店のいずれかで入手し課題を提出したという。アンケートではA・B書店以外の書店で購入したとの回答もあり、地域の書店に足を運ぶきっかけを作ることができたのではないか、との報告があった。僕にとっても、若い世代を書店へ誘うきっかけを作る重要性について改めて考えさせられるアンケート結果だった。
課題図書にリストアップされた50冊の中に選ばれている書籍に岩波書店発行の書籍があった。書店側から見た時、岩波書店は原則返品不可であるということで、取り扱いに差が出てしまうなど課題も見つかったというが、今後は、書店とも相談しながら、地歴・公民科以外の科目でもチャレンジしていきたい、と締めくくられており、これまでの書店の取り組みを報告するだけではなく、より緊密な連携の必要性を訴えられていたのが印象的だった。
続いて、8班に分かれてのワークショップでは、司書の皆さんが抱えている悩みや取り組みたいけど実現できない読書活動について率直な意見が多数挙げられ、それに対して書店員がそうであればこんなことができるのでは、という議論が活発に行われていた。なかでも、文化祭で生徒が本屋を開けないか、その仕入れを書店の店頭に出向いて行えないか、その際仕入れについてのアドバイスを書店員の皆さんにサポートしてもらったらどうだろうなど、「面白そうじゃないですか」という案や、福島県下高校の美術部などに、ブックカバーや紙袋のデザインを募集して、ブックカバー大賞のような企画ができないかなど、本を読むことだけではなく、本屋を楽しんでもらう企画など非常に興味深い施策について議論が進んでいる班もあり、今後の連携の行方が楽しみでならない。
互いに膝を突き合わせて話し合い、互いの強みを認め合い、そっと互いの弱みを語り合い、そして互いに補うことで、子どもたちと本との接点を創っていく施策が生まれるのかもしれない、という可能性を感じる研修会だった。
学校図書館に限らず、このような場が全国に広まってほしい。
田口幹人(たぐち・みきと)
1973年岩手県生まれ。盛岡市の「第一書店」勤務を経て、実家の「まりや書店」を継ぐ。同店を閉じた後、盛岡市の「さわや書店」に入社、同社フェザン店統括店長に。地域の中にいかに本を根づかせるかをテーマに活動し話題となる。2019年に退社、合同会社 未来読書研究所の代表に。楽天ブックスネットワークの提供する少部数卸売サービス「Foyer」を手掛ける。著書に『まちの本屋』(ポプラ社)など。

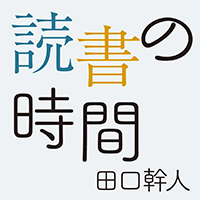
![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[後編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/10/honmado202211SP_t.png)
![特別対談 田口幹人 × 白坂洋一[前編]](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2022/08/honmado202209SP_t.png)