吉川トリコ「じぶんごととする」 5. NYで夢を捨てる【アップタウン編】
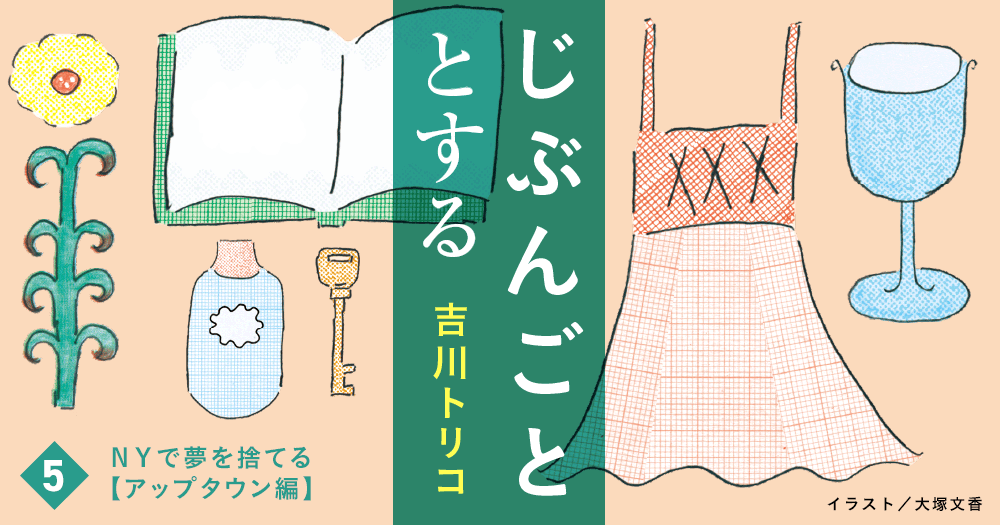
はじめて観たオードリー・ヘップバーンの映画が『ティファニーで朝食を』だった。中学の夏休みに友人とふたりで行くあてもなく町をぶらついていたときに、ひまつぶしに図書館の視聴覚ブースで映画を観ることにした。岡崎京子や『Olive』やMILK、彼女からはいろんなものを教わったけれど、オードリー・ヘップバーンもそのうちのひとつだ。
ユニオシの描き方が典型的なアジア人差別だったり、映画を観た原作者のカポーティが激怒したとか、ホリー役はオードリーではなくマリリン・モンローをイメージしていたとかいったいわくつきの作品だけれど、やっぱり私はこの映画を嫌いになれない。なんといってもオードリー・ヘップバーンの魅力が爆発していて魔法がかっているし、悪評高いラストの展開も改めて見直してみると、「家父長制を愛と呼ぶ男」VS「家父長制を檻と呼ぶ女」の様相を呈しており、ポールのたたみかける台詞のほとんどが、家父長制に首までどっぷり浸かったモラハラ男の説教でしかなく、いやこれぜんぜんハッピーエバーアフターじゃないよね、っていうかこの女たぶん一ヶ月もしないうちに猫と男を置いてどこかへ消えるよね!? という余韻を残していてめちゃくちゃスリリング! そう思って観ていると、なんとなくオードリー・ヘップバーンの演技も絶妙にロマンスの気配を排除したバランスな気がしてくる。
時代の流れや価値観のアップデートにともない、過去に愛していた作品を愛したままでいられなくなるという悩みをこの数年あちこちで耳にするようになった。私にも似たような経験があるが、過去に愛していた作品をこんなふうに(やや強引に)読み換えることで愛を延長させることだってできるのだ(ちゃんと批判的な目を持ちながら愛し続けるというのがいちばん困難で正しいやり方だとは思うけど)。
オタのひいき目や積極的擁護の姿勢を抜きにすれば、映画版『ティファニーで朝食を』は「ここではないどこかへ焦がれ、でも結局どこにもいけないまま愛という名の檻に閉じ込められて終わる女の物語」といったところが適当だろう。この世にごまんとあふれる、夢見がちな女の翼を手折り、地に足をつけさせて終わる異性愛主義的なハッピーエバーアフターの物語。そりゃカポーティも激おこしちゃうはずである。どこまでも自由に翼を広げたホリーがいまもどこかを「旅行中」の原作とは真逆の話になっているんだから。
前回とりあげた吉田秋生が初期に描いていた少女の物語は、どれも少女の不可能性が色濃くあらわれていて、いずれは結婚して家庭に入り、妻となり母となる運命から逃れられないことを予感させる。だからこそアッシュや小夜子が、少女たちのヒーローたりえたのだろう。





