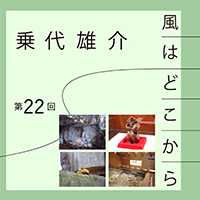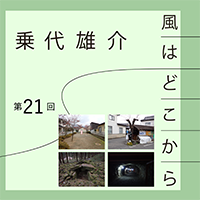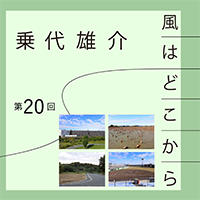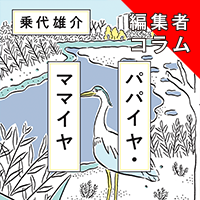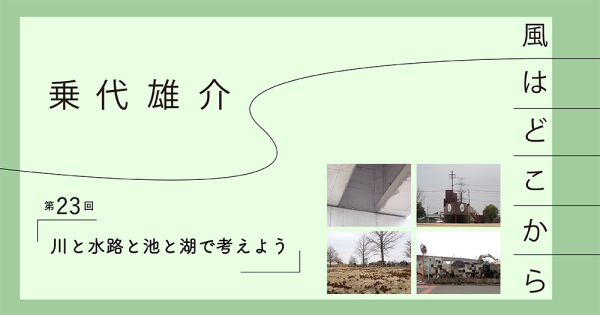乗代雄介〈風はどこから〉第23回
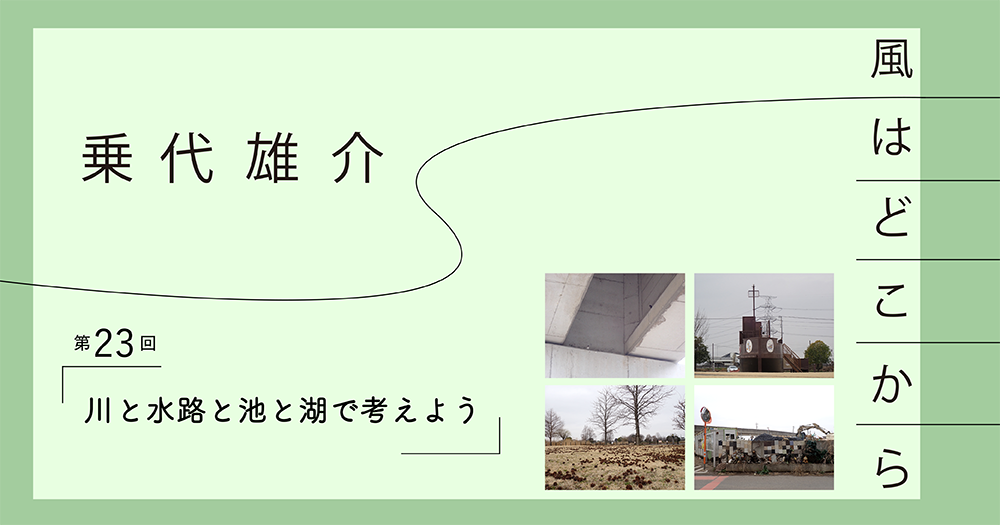
第23回
「川と水路と池と湖で考えよう」
家からそう遠くないのにまだ埼玉県のことを書いていなかったなと思って、通勤ラッシュの満員電車とガラガラの電車を乗り継いで、久喜駅までやって来た。ずっと寒かったのがぽっと暖かくなった日で、衣服の内と外の空気が隔てられていない感覚を久々に思い出し、心地が良い。東口から出て、新幹線の高架沿いに北の方へ歩いて行く。
退屈な道などないと知ってはいても、ちょっと退屈な道かなと思っていたが、10分もすると、工藤静香「つぎはぎのポートレイト」を聴いているイヤホンの外から鳥の鳴き声がひっきりなしに聞こえてくることに気付いた。ほとんどスズメのようだが、それにしても多い。にしては姿をちらほらとしか見かけない。こういう時は歩いているのがよくないので、高架下の公園のブランコに腰かけて観察することにした。すると高架の裏、重厚なコンクリートが縦横に行き交う隙間のあちこちから、スズメが顔を出したり引っこんだりしている。鳴き声は引っこんでもやまず、そうと気付けばそこから聞こえてくるようだ。
1年を72等分してその時季の出来事を名付けた七十二候に「雀始巣」がある。3月20日から24日の頃をいうので、今から1週間後というところだ。なるほど、スズメたちが4月の子育てに向け、ヘビも登れず猛禽類も入りこめない安全な高架の隙間で、巣作りをしているのだろう。

歩いても歩いても長大な長屋のようにスズメの出入りが続くので、高架の橋脚ごとに立ち止まっては写真を撮っていたら、暇そうな速度で自転車をこいで来たおじさんが、何も言わずに私の隣にギッと止まった。二人でスズメらを見ている時間が続き、さすがに気まずくなったので「いっぱいいますね」と言ったら、おじさんは「糞だらけ」の一言を残して行ってしまった。
そんな……と思いつつも考えてみれば確かに、高架橋の営繕という観点から見れば鳥の営巣はあまり歓迎すべきことではないだろう。逆に、この一帯の修繕の時期が繁殖期と重なれば、多くのスズメが巣作りの場所を改めて探さなければいけなくなるが、それを考慮して工期を決めることもないはずだ。堤防の草刈りについて河川事務所で話をうかがった時も思ったけれど、こういう人間の都合との案配は、ある程度自然の強さを信頼しなければ事が進まない。生き物の方でも強かに人工物を利用しているのだから、お互い様という感じだろうか。
というわけで、まったく退屈せずに2キロの道を2時間くらいかけて歩き、調整池のある弦代公園に着いた。周囲1200メートルというまずまず大きな池を見渡して思ったのは、もう春だということだ。目につくのはカルガモとカワウで、ともに留鳥。冬鳥はもう渡っていってしまった頃だ。池に横倒しで半分沈められたコンクリートの柱のようなものは、おそらく動物たちのためにあるのだろう。その目論見通りに、カワウとアオサギとカメがうじゃうじゃ並んでいるのはなかなか見応えがある。
半周歩いて、すぐ近くにある沼井公園に移動。もう少し小さな池があり、こちらはビオトープ化されている様子で、自然観察デッキもあった。小窓からアオサギを堪能したが、そこの掲示に紹介されている冬鳥はやはりもういない。
池とその奥に立ち並ぶ集合住宅を眺めながら、ポール・マッカートニーの「Winter Bird / When Winter Comes」をぼんやり聴く。私は中学の頃に同じ誕生日と知って以来のポール派で、この曲は2020年発表のアルバム『McCartneyⅢ』収録である。ただ、「When Winter Comes」は90年代に作ってお蔵入りになった曲で、ポール自身が発見して収録したらしい。夏鳥や冬鳥に人生の季節や自分を重ねる歌なので、こういう時期によく思い出して聴いている。
テニスコートではスクールレッスンが行われていた。バックハンドの練習で十秒ごとに山なりに返ってくるボールがフェンス際に一つずつたまっていくのをひとしきり眺めたあと、公園のハシゴということで、倉松川に沿うようにして東にある千塚西公園に向かう。コンクリート護岸の細い川の北側を歩きながら、グーグルマップを見て向こう岸にも調整池があると知る。

それでようやく、倉松川という名をニュースで何度か耳にしたことがあることに気付いた。千塚西公園手前の道路上にはちょうど、権現堤の桜並木と共にに「ようこそ幸手市へ!」と書かれた看板が現れた。幸手市は水害の多い町で、その中でも倉松川の氾濫のことをよく聞いた気がするのだが、こうして歩くと川は地面のだいぶ下、フェンスから覗きこむほど水位も低い。調整池だっていくつもあるし、「地下神殿」として特集されたりする首都圏外郭放水路も2006年に完全通水したとのことだが、私が氾濫のニュースを見たのはたぶんそれ以後のことで、どういうことなのかと不思議に思う。
千塚西公園のベンチに座って、砂場に忘れ置かれた荷台付きのブルドーザーみたいなものを横目にスマホでいろいろ調べていると、東二丁目のあたりが床上浸水の頻発地帯らしい。ハザードマップでも「近年の道路冠水か所」として一帯がマークされている。こういうのは行ってみないとわからない。なんとなく予定していたルートとは逆方向だが、足をのばしてみることにした。
さっきの道に戻って倉松川に沿って下流へ歩いていき、中央通りから離れると川は緑のフェンスに挟まれる。幸手市立西中のところで道は一度川を離れ、戻ると水面がずいぶん近い。幸手駅を西口から東口に出て川を追い、川沿いのフェンスと家並みの間の細道を行く。県道65号が通る志手橋を過ぎ、次いで国道4号が通る幸手橋を過ぎたところでがらりと様子が変わった。法面が緩く広がり、その上の新しそうな歩道も嵩上げされて堤防の一部となっている。そして、やはりというか、ここからが東二丁目のようだ。
ストリートビューで調べると、2022年6月の段階では工事前である。現在との比較に夢中になっていっぱい写真を見ていたら自分で撮るのをすっかり忘れていたのだが、色々と考えることがあって忙しかった。例えば、橋にある河川名の銘板に「大中落し」と書いてあったこと。これによって、私が川に沿って歩き始めた千塚西公園のあたりは、正確には倉松川ではなく「大中落悪水路」という名称であることを知ったのだが、幸手駅のあたりからが倉松川であるそうだ。そうなると、銘板が今なお「大中落し」である幸手橋はだいぶ古い橋なのだろうかと思ったりして、グーグルマップばかりぼんやり見ていてはわからないことがあるものだ。ちなみに、「落」というのは田よりも低い位置にある水路すなわち農業用排水路のことで、それに同じ意味の「悪水路」までついているので、相当に悪そうである。
そんなこんなを考えながら、自分の中で名前の変わった水の流れを遡り、千塚西公園まで戻って来た。北の方から出て畑を突っ切る細道を抜け、遠くに見える清掃センターの煙突を目印に、その奥に流れている中川を目指す。
解体業の宮坂興業さん脇の細道から堤防の天端に上がると、今日初めて遠くまで見渡せる道となった。何度か深呼吸して、イヤホンから流れてきた B’z の「イルミネーション」を聴きながら歩く。去年の紅白を思い出す。
のどかな川沿いの道はそのまま高須賀池公園に突き当たった。これもその名の通りに池のある公園で、ぐるりと一周してまた川沿いに戻れそうだ。柵で区切られている池の周りはきれいな芝生で、舗装された小径には、ゴミどころか枯葉1枚ない。春を待つ裸のモミジバフウが何本か植わっているところに差しかかると、落ちた実のとげとげした丸い殻だけが大量に芝生に転がっている光景に出くわした。この実はどこでも目立つものだが、ここまで純度が高いと異様な迫力がある。舗装路には一つも落ちていないから、掃除をする際、芝生の方に集めたのだろう。木道の「ゴミは持ち帰りましょう」の看板がきちんと三点止めしたいがために縦書きなのに横向きになっていたり、変に几帳面な公園だった。

そのまま中川沿いを行くと、今度は権現堂公園に突き当たる。有名な桜堤の西端である。堤の上のソメイヨシノにはまだ早いが、河川敷に並ぶサトザクラはたなびく雲のように桜の霞を連ねて見頃である。それを見に来た人々で、比較的にぎわっていた。ナノハナやネモフィラなど、春の盛りにはさぞかし綺麗になる予定の原っぱを通り過ぎ、冬でも愛嬌を振りまいてくれるヤギを見る。小屋があって、ヤクシマヤギが何頭も放し飼いにされているのだ。だいぶ人慣れして寄ってきてくれるのがうれしい。
権現堂公園は、中川と権現堂川の合流地点である一帯に広がっている。私がいるところがメインの権現堂公園らしく、外野橋で中川を渡ってみた対岸には、権現堂3号公園とあった。さらに続けざまに行幸水門橋で権現堂川を渡ると権現堂2号公園である。こちらは権現堂川の右岸に沿って南北に広がっているが、この水域は権現堂川でありつつ、水門を閉めれば調節池にもなるため行幸湖という名前も持つ。水の流れをあれこれすると色々とややこしいのだなと、今日一日で何度も考えさせられたことを改めて痛感する。
遊具の多い2号公園内を権現堂川に沿って北上していく。園内マップを見ると、川の対岸に大きく「茨城県」と書いてあり、県境でもあるらしい。埼玉側にいたオオバンが、私を警戒して川に入り、茨城方面へと逃げていく。舟渡橋を過ぎたところで野良猫たちに遭遇しエサをねだられたが、くれないとわかるやすぐ次の人間へ突撃してかわいい。
埼玉県のマスコットであるコバトンを描いた船の遊具があり、甲板の柵の向こうに小さな男の子がいるのに気付いた。彼の頭上、柵の中ほどには望遠鏡みたいなものが設置されているのだが、届かなくて諦めているのか単純に気付いていないのか、その下、柵の間からじっとこっちを見ている。手を振ってみても反応はなく、やがて踵を返して姿を消した。

大平橋まで来たところで、川を離れて南栗橋駅に向かう。たまっている仕事をしなければいけないので、まだ明るいけれどもう帰り道だ。一面茅色の畑にハトの群れがいて、船の外板でにこにこしていたコバトンを思い出しているうちに一斉に飛び立った。
写真/著者本人
乗代雄介(のりしろ・ゆうすけ)
1986年北海道生まれ。2015年「十七八より」で第58回群像新人文学賞を受賞しデビュー。18年『本物の読書家』で第40回野間文芸新人賞を受賞。21年『旅する練習』で第34回三島由紀夫賞を受賞。22年に同作で第37回坪田譲治文学賞を受賞。23年『それは誠』で第40回織田作之助賞を受賞し、同作の成果により24年に第74回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。ほか著書に『最高の任務』『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ』『パパイヤ・ママイヤ』『二十四五』などがある。