武塙麻衣子「一角通り商店街のこと」3. おにぎり徳ちゃん
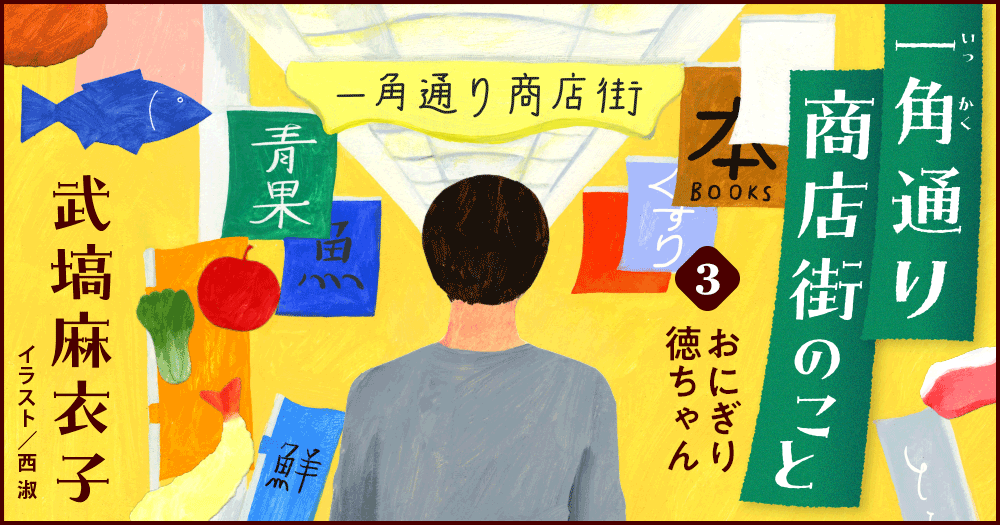
お待たせしました、とカウンターに置かれたおにぎりの皿に雄士は目を奪われた。きゅっと海苔が巻かれた方のおにぎりは、つやつや光る米の上に牛肉の甘辛炒めがどっさりと盛られ、もう一方はとろろ昆布が大きなおにぎりをふんわり柔らかく包んでいる。
「いただきます」
添えられた小皿のたくあんもしっかり熟成されているのか渋い茶色が食欲をそそる。隣で、シゲさんがこれこれ、と言いながら卵黄醤油漬けおにぎりを食べはじめた。負けじと雄士もまずとろろ昆布に手をのばす。大きくかぶりついたおにぎりは、そのどっしりとした見た目に反して、ほろほろと口当たりが良かった。
「あ」
雄士が飲み込んで思わず声を出すと、徳さんがいたずらっぽい顔をしてみせた。
「どうですか」
「美味しいです」
とろろ昆布おにぎりの中身は、おかかをまぶしたチーズだったのである。
「これ、実家だと当たりなんです」
「当たり?」
シゲさんが不思議そうな顔をして、ふたつめのおにぎりに手をのばした。
「おにぎりに当たりなんてあるのか」
雄士は、大きく頷いてみせた。
大きなおにぎりをふたつ食べると、かなりお腹がいっぱいになった。
「ごちそうさまでした」
雄士が頭を下げると、シゲさんと徳さんがにやりとする。
「これで終わりじゃあないんだな。徳ちゃん、今日は何?」
「なめこと豆腐です」
はい、どうぞとお椀が雄士の前に置かれた。蓋を取ると、ふんわりと優しい味噌の香りが溢れる。
「わぁ」
思わず声を漏らし、いただきますと手を合わせるのももどかしく、雄士はお椀に口をつけた。
「美味しいです」
全身から余計な力がすべて抜けて、胃がほこほこと温まるのがわかる。東京に引っ越してから、家で食事をする時はフリーズドライの味噌汁を飲んでいた。種類が多いので飽きがこないしお湯を注ぐだけでよくて簡単だからとりあえずはそれでいいと思っていたのだ。
「全然違うなぁ」
驚いたように雄士が言うと、シゲさんが隣で頷きながら味噌汁を飲んだ。
「うん。旨い」
「お味噌汁はね、そんなに難しくないんですよ」
徳さんは、流しで洗った手を真っ白な布巾で拭いて言った。
「出汁をしっかりとるのがやっぱり一番ですけど、でも家でならそこまで気にしなくてもいいんです。かつお出汁が面倒だったら、とりあえず昆布だけでもいいと思う。昆布を一晩水に浸けておくだけでも十分なんですよ。浸け終わったら刻んで肉か何かと焼いても佃煮にしたっていい」
徳さんはそう言うと、引き出しから袋を取り出し、中から一枚の昆布を抜き取った。
「これ良かったら試しに持って行ってください」
「え、でも本当にちゃんと使えるかどうかわからなくて」
「大丈夫ですよ」
ビニール袋にすとんと昆布を落とすと、徳さんは、はい、とそれを雄士に渡した。
「あといいものがあります」
徳さんが冷蔵庫から取り出したのは、手のひらにちょこんとのるくらいの何やら丸いものだった。
「たこ焼きパーティーは面白かったね」
ユンくんがそう言って、床にバッグを置いた。
「うん。あ、そっちのテーブル座って」
雄士は、指差しながらやかんを火にかけた。実家から持ってきた小さなテーブルは、大学の課題をしたり、ちょっと座って飲んだり食べたりするのにちょうど良い。腰をおろしたユンくんを見て、迷ったけれど椅子を二脚持ってきて良かったなと雄士は思った。
「ユンくんが持ってきてくれたキムチも美味しかったけどさ、あれ」
「ああ、納豆?」
「そうそう。焼いてる時はかなり匂いがすごかったけど、食べたら美味しかったからびっくりした」
具を参加者全員でいろいろ持ち寄るたこ焼きパーティーというのが先月あり、雄士は迷いに迷って結局、ちくわとチーズを買っていった。それらを入れて雄士が焼いたものは、普通に美味しいというのが皆の感想で、ユンくんが持ってきたキムチは絶賛。それを上回る人気があったのが、中島というクラスメイトが持ってきた納豆だったのだ。
「ポン酢で食え」
中島はそう言って、納豆をたっぷり詰めた生地を器用にくるくるとひっくり返して次々に焼き上げ、青ネギをちらした。普段は納豆があまり得意ではないという子でさえ、おおおと歓声をあげるほど、中島が焼いた納豆焼きは、カリッとした表面とトロトロの中身にポン酢の爽やかさが合ってとても美味しかったのだ。
「たしかにあれは美味しかった」
「あそこまで美味しいかどうかはわからないけど、今日はこれを食べてみてよ」
お湯を注いで味噌を軽く溶いたお椀をふたつとお皿一枚を、とんとテーブルに出した。
「おにぎりとお味噌汁? いい匂い」
おにぎりは、いざ自分でにぎるとなかなか難しかった。とてもではないが綺麗な三角形になど仕上がらず、雄士は諦めて途中から丸いおにぎりに方向転換したのだ。
「ごめん、不格好で」
全然、とユンくんが首を横に振った。
「このまわりは何? 海苔じゃないね」
「とろろ昆布。実家から送ってもらったんだ」
へぇ、と一瞬不思議そうにした後、ユンくんはすぐにおにぎりに手をのばした。
「いただきます」
たこ焼きパーティーの時、それ、本当に美味しいの? と皆が引き気味だった納豆のたこ焼きを一番に食べて「美味しい!」と言ったのはユンくんだった。雄士は、そのことを思い出し、なんだかユンくんにとろろ昆布のおにぎりを食べてもらいたくなったのだ。
「ふわふわだ。面白いね」
ユンくんは、おにぎりを手にうんうんと頷いた。
「こっちも良かったら飲んでみて。韓国ってお味噌汁ある?」
「あるよ。テンジャンチゲというちょっと辛いやつ」
そう言いながら、ユンくんはお椀に口をつけた。
「うん、美味しい」
「でしょ? 俺が作ったんじゃないの、それ」
雄士はへへっと笑って自分も味噌汁を一口飲んだ。あの日、徳さんがくれたのは昆布一枚とそれから徳さん手作りの味噌玉だったのである。
「この味噌玉はお椀に入れてお湯を注ぐだけで完成です。使っている味噌もそれぞれ違うし、入っている具もいろいろだから、それは飲んでからのお楽しみということで」
好きな具や好みの味の味噌がわかったらそこから自分で味噌汁作りを始めるのもいいと思います。徳さんはそう言って何種類かの味噌玉をくれたのだ。
「せっかくだからユンくんにも一杯飲ませてあげようと思って」
ユンくんが美味しいと言いながら味噌汁を飲み、おにぎりを頰張っているところを見るのがなんだか無性に嬉しい。美味しさを誰かと共有するというのはひょっとするとかなり大事なことなのかもしれないな、と雄士は思った。次の週末は、徳さんからもらった昆布で出汁をとってみよう。その前にどんな味噌を買おうかな。
1980年神奈川県生まれ。『諸般の事情』『驟雨とビール』などのZINEを発表後、2024年『酒場の君』(書肆侃侃房)で商業出版デビュー。
Xアカウント@MaikoTakehana
- 1
- 2




