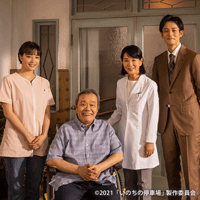現役医師・南 杏子の新刊『ヴァイタル・サイン』 冒頭ためし読み!
正看護師と准看護師は、業務の範囲や許される医療行為に差があるわけではない。しかし、保健師助産師看護師法は准看護師について、「医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて」業務を行う──と規定している。つまり准看護師は法律上、正看護師の補助員という立場に位置づけられている。
准看護師の資格は中学卒業後、各都道府県の准看護師養成所や看護学校に進み、二年間の学習後、試験に合格することで取得可能だ。
女子の高校進学率が低かった時代に看護職員を増やす狙いで創設された制度だが、修学期間が短くて済むことから、近年は社会人経験者が資格にチャレンジするケースも多い。
中学卒業後に十七歳で准看護師になった田口主任は、故郷の山梨県で十年の実務経験を積んだ後に通信制課程で学び直し、正看護師の資格を得たと聞く。文字通りの苦労人だ。
「だって、元准看は事実じゃないすか」
素野子のとがめる表情に気づいたのか、桃香はそう繰り返した。
苦い気持ちのまま、残りの業務を片づける。元は准看であろうが何だろうが、田口主任は一生懸命に業務をこなしている。一緒に働く仲間であるのに、自分も同様に学歴差別されているのだろうかと思うと、素野子は居心地が悪く、息苦しささえ覚える。
その日は夜遅く、自由が丘で翔平と会った。
イタリアン・バルでいつもより多めに赤ワインを飲んだ。まったりとした時間に、ふと桃香のことを思い出した。
「桃香っていう後輩がいてね、おしゃべりで困るのよ」
「相手にすることないよ」
翔平があっさりと答える。
「そんな単純には行かないのよ。忙しくてちょっと返事ができなかっただけで、嫌われてると誤解する子もいるんだから。へたしたら、パワハラって言われるし」
「黙って仕事しろ──って、誰かが言ってやらないと。俺が行く?」
素野子は思わず噴き出す。
「うれしいなあ。翔ちゃんに分かってもらえるだけで、ほっとするよ」
投げキッスをすると、翔平がデへへと笑った。
「桃香は大卒ナースを鼻にかけて、主任のことを准看あがりのくせにって言ったりするんだよ。専門学校出の私もバカにされてるんだろうなあ」
「素野ちゃんが美人だから、ひがんでるんだよ」
「まさかあ」
「その桃香って看護師、どんな子か分かんないけどさ。まあ、もともと医療の世界って、ヒエラルキーが強い世界だからな」
「ヒエラ……?」
「ドイツ語で位階制の意味だよ」
「難しいね、ドイツ語。診療録や病状説明なら分かるけど」
翔平は素野子の答えに笑みを見せ、嘆くような口調で続けた。
「医師と歯科医師をトップに、放射線技師や臨床検査技師、薬剤師、それに素野ちゃんたち正看護師がいて、その下に准看、看護助手……。しかも、正看の中には大卒ナースだ、短大だ、専門卒だって。まるでヒエラルキーのミルフィーユだ」
「そのヒエラなんとかで、給料も違ってくるんだよ」
翔平の言うところのヒエラルキーは、看護師の給与に直結する。二子玉川グレース病院の場合、正看護師の基本給は大卒で二十一万七千円、短大卒と専門学校卒はともに一万七千円安い二十万円、准看護師はさらに一万八千七百円安い十八万三百円と定められている。
「翔ちゃんはドクターでいいなあ」
翔平は肩をすくめる。
「同じだよ。医局では教授、准教授、講師、助教、研修医っていう具合で、こっちもヒエラルキーのミルフィーユ。しかも『給料はいらないから、勉強のためにオペさせてほしい』なんて言う無給医までいる。俺も拘束時間はめちゃめちゃ長いし、時給に直せばコンビニのバイト以下かもしれない。それでも腕は上げたいから、執刀医か第一助手に選んでもらえるように、雑用でもなんでもやってさ。これでもしのぎを削ってるんだぜ」
愚痴を聞かされたのは初めてだ。
「そうなの……」
「いやごめん、こんな話はやめるよ。今は素野ちゃんと、もっと楽しい話がしたい」
翔平の表情が、さっと笑顔に切り替わる。
「そうだね」
素野子もほほ笑み返した。けれど、本当はもっと聞きたいくらいだった。楽しいことだけじゃなくて、嫌なことも共有できるのは、より親密になれた証拠だと思うから。
ただ、よりによって桃香のことを話題にしてしまうなんて、自分はどうかしている。翔平との大切な時間なのに。
「なんだか甘いミルフィーユをバクバク食べたい!」
酔った勢いのせいで、そんな言葉が飛び出た。
翔平は素野子をしばらく見つめたかと思うと、「素野ちゃんらしい」と大笑いする。
店を出て、自由が丘駅の南口に続く静かな舗道を歩く。桜の咲く四月とは言え、夜気はまだ肌寒い。信号のある交差点に立つと、奥沢駅に続く道を示す標識が目に入った。
確か田口主任は、駅前のマンションに住んでいると聞いたことがある。
今日、勤務が終わる直前にあった出来事が浮かんできた。
翔平との大事な時間に、また病院のことを思い出している。素野子は考えを追い払うように頭を振る。けれど、主任の姿は決して消えようとしなかった。
夕方五時の日勤が終了する間際だった。素野子は田口主任に捕まり、仕事を命じられた。ポスター貼りのような単純な雑用とは違い、時間と神経を使う仕事だ。
「堤さん、急だけど今から新しい患者様が入るからね。あんたが担当よ。四一八号室、お名前は猿川菊一郎様。いい? 早いとこナースステーション行って!」
新しい患者の情報収集は、簡単には終わらない。名前や年齢、疾患の確認に始まり、病状、既往歴、アレルギーの有無、処方内容、食事の好み、特別な生活習慣などを漏れなく聞き取る必要がある。血圧や体温、脈拍数などのヴァイタル・サインをチェックし、体の表面に異常がないかを確かめる。それらの情報を記録にまとめ上げ、次のシフトの看護師に申し送りをした。
それで今日はデートに遅刻したのだ。翔平は「あるあるだね」と、笑って許してくれた。
「素野ちゃん、この曲聴いて」
帰りの電車は混んでいた。ドア横のポジションに立つ。翔平がイヤホンを片方だけ貸してくれた。
♪さあ がんばろうぜ!
オマエは今日もどこかで
不器用にこの日々と
きっと戦ってることだろう
翔平の好きなロックバンドの曲だった。自然に口元が緩んでくる。
目が合うと、翔平は親指を立ててうなずく。電車の揺れが強くなっても、素野子は平気だった。翔平がさっきからずっと背中を支えてくれていたから。
翔平とつきあっているのだと素野子は実感する。疲れているのに、安心感で満たされる。うれしくてめまいがしそうだった。
ただ一点、嫌な予感を除いて──。
(つづきは書籍でお楽しみください)
【好評発売中】
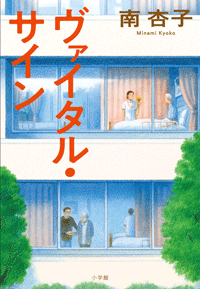
『ヴァイタル・サイン』
南 杏子