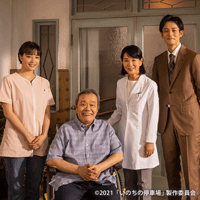現役医師・南 杏子の新刊『ヴァイタル・サイン』 冒頭ためし読み!

プロローグ
「脈拍一二〇、血圧七八─五〇、体温三七度二分、呼吸数二四、意識混濁。どんな状況を想像しますか?」
皆、口をつぐんでいた。問いかけの内容を理解していないのだろうか。あるいは興味がないのか。もどかしさを感じながら、次の質問を投げる。
「では、この血圧について言えることは?」
一人の手が上がった。
「ショックです」
いつも答えてくれる優秀な子だった。
「そうですね。ショックの定義は何でしょう? 彼氏に振られることではありませんよ」
皆が一斉に笑う。
「血圧が急激に下がることです」
「その通り。医療の場で言うショックとは、大幅に血圧が低下してしまい、その結果、いろいろな臓器の機能が落ちることです。脳の血流が不足して酸欠状態になるため、意識障害を引き起こします」
それぞれがノートにメモする様子が見えた。
「すみません、この患者さんは何歳でしょうか?」
「もっともな質問ですね。脈拍一二〇といっても、若い人と高齢者とでは意味合いが全く異なります。そして、このデータは八十三歳、男性です」
向こう側の空気が揺れるのが分かった。
「先生、その年齢だと命の危険があると思いますが……」
いい反応に励まされる。
「血圧が足りない状態に体が反応して、一気に脈拍数を上げ、呼吸数も増えている状態だと読み解くのはいかがでしょうか」
飲み込みがいい学生もいる。ちょっとうれしくなった。
数字からも、患者の状態を洞察する──それが看護の基本である。
「ここで皆さん、もう一度ヴァイタル・サインの基本を復習しましょう。まずは自分でヴァイタルを測定してください」
血圧計や体温計に手が伸びる。ざっと見渡したところ、手技は悪くなさそうだ。
そのタイミングで、正常値を示す。
【ヴァイタル・サインの基準値】
●体温 三六〜三七度
●血圧 収縮期一三〇mmHg未満、拡張期八五mmHg未満
●脈拍 六五〜八五回/分
●呼吸 一二〜一八回/分
●意識清明
「皆さんの中で基準を外れている方はいませんか? 居眠りしていると意識状態は落ちますよ」
くすくすと笑い声が返ってきた。
「ヴァイタル・サイン、つまり生命兆候に関しては、常に敏感に対応しましょう。無視するのは大変危険です。たとえ健康な人であっても……」
第一章 日勤
──二〇一八年四月二日
「ご退院おめでとうございます」
病院の正面玄関で看護師長がバラの花束を差し出した。
「いやあ、お世話になりましたな」
車椅子に乗った白髪の男性はどこか英雄の風格を漂わせつつ、深紅のブーケを優勝杯のように胸に抱いた。ゆっくりと鼻を近づけて、大きく息を吸う。
患者の妻と息子、真新しい制服姿の孫娘二人も頭を下げた。孫たちは、今月そろって高校と中学に入学するという。
月曜日の午前九時前、青空の下で桜はすでに満開だ。風は暖かく、玄関脇の植え込みにも春の息吹がいっぱいに感じられる。
「ほお」
笑みを浮かべた車椅子の主は体を傾け、植栽から脇へ伸びる一本の茎を手折った。
「もうあなたったら」
妻が夫のやんちゃな行為をたしなめる。
「まあ、いいじゃないか。これは一番お世話になった看護師さんへ、心ばかりのお礼です」
玄関に並ぶ何人もの看護スタッフを見渡した男性は、師長の前を通り過ぎ、堤素野子にその一輪を差しのべた。鮮やかな黄色い花の、たんぽぽだった。
「鼓草──あなたの名前の花ですよ、堤さん。長いこと、ありがとうございました」
二十一歳で看護師となり、十年がたつ。この病院で長く高齢の患者を看護してきたが、このように元気で退院できるケースはそう多くない。しかも師長ではなく、一職員の素野子にあいさつをしてくれるような患者は初めてだった。
「ご退院、本当におめでとうございます」
素野子は、あふれる思いで黄色い花をもらい受けた。続いて握手を求められる。手を差し出すと、意外なくらい強い握力が返ってきた。患者が元気になった証拠だとうれしくなる。けれど、いつまでも手を離さない患者に戸惑い、頬が熱くなった。
「たんぽぽや 日はいつまでも 大空に」
「え?」
「中村汀女の俳句です。いつまでも、今のこの幸せな気持ちを感じていたい。それがまさに僕の心境です。本当に、ありがとうございました」
東急田園都市線と大井町線が乗り入れる二子玉川駅の西方。そこだけ武蔵野の緑を残す昔ながらの公園と多摩川を眺める位置に病院は建つ。
岸辺から飛び立ったのだろう。何羽もの水鳥が、背後に高層マンションの迫る空を行く。
幸せな患者と家族を乗せた車を、素野子はいつまでも見送った。
高い空を見上げ、植栽の花たちのように太陽を体いっぱいに浴びる。自分が輝かされているのを感じた。
「白衣の天使」なんて言葉は、好きではない。
甘ったるい言葉の響きが、何というか自分の現実に合わない。
医療と看護の現状や、勤務の実態にもそぐわないと思う。
けれど、やりがいは感じる。
「この仕事が好きだ」
あえて言葉にしてみた。今のすがすがしい気持ちがこぼれてどこかに行ってしまわないように。
医療法人社団賢生会・二子玉川グレース病院の朝は、こうして過ぎていった。
「堤さん、かなり目立ってましたよ。やばくないすか? 師長の顔、こわばってましたよ」
病院の四階にある東療養病棟のナースステーションに戻る直前、同僚の大原桃香が素野子の耳元でささやいた。「さすが専門卒。患者対応がお上手ですね。でも一応、親切心までに」と付け加えつつ。
いつものことだが、桃香の「親切」な一言には、心を逆なでされる。弾んだ気持ちが泡のように消えていった。
二十七歳の桃香は自分より四歳若い。名門の中央医科大学出身、いわゆる大卒ナースだ。
かたや素野子は、都立の看護専門学校卒である。
そのことにコンプレックスを感じる必要はないと思っている。だが、上から目線の皮肉な言い回しにはしばしば違和感を覚えた。
桃香は、素野子の胸の内などお構いなしという表情で去っていく。
ナースステーションでは、いつもツンとすました顔で過ごす彼女。ぞんざいな言葉は、同僚たちばかりか患者やその家族にも向けられる。看護師らしからぬ派手な厚化粧をし、髪も顔にかかるようにセットされている。
二子玉川グレース病院は、東京都の第二次救急医療機関に指定され、救急患者の受け入れを行っている。しかし、総ベッド数二百六十の約四〇パーセントに当たる百床余は療養に振り向けられており、高齢の患者が多い病院だ。
成城、自由が丘、田園調布などの高級住宅地に近いという場所柄、来院する患者や家族は裕福な層が多い。病院の外観やロビーは、患者層にあわせてセンス良くまとめられている。
素野子の働く東療養病棟も、フロアには細やかな気配りが行き届いていた。廊下に掲げられた大きな絵画は明るく躍動感にあふれ、コーナーごとに色とりどりの生け花が飾られている。
「みずみずしい生花と、死に行く高齢患者の組み合わせって、なんか皮肉なコントラストですよね」
後期高齢者が集中する療養病棟は、死亡退院の比率が約七割と高い。厳しい現実を桃香はそんなふうに揶揄した。
死と隣り合わせの患者が多い病棟であっても、患者は枯れていく花などではないと素野子は思う。人生の終末期を生き生きと過ごせるよう、精一杯、患者のために尽くしたい。
今朝は患者に救われた。
霊安室からの退院が日常化した日々。今朝のように明るい気持ちで患者を見送ることができるのは特別なケースだ。
たんぽぽをくれた患者は、残された日々を家族に囲まれて過ごしたいと自宅療養の道を選択した。そして、家族もまたそれを望んだ。患者と家族の笑顔を見て、素野子の心は何とも言えない喜びで満たされた。
ナースステーション中央のテーブルに向かい、素野子はカルテや資料に目を通す。
午前中の業務が迫っていた。つかの間の集中だが、患者の状態をしっかりと把握するためには貴重な時間だ。
「堤さん、ちょっといい?」
「はい」
看護師長の草柳美千代から声がかかった。
まさか桃香が口にしたような「目立ちすぎ」などという小言ではないだろう。けれど、声の調子が低いことに不安がよぎる。
【好評発売中】
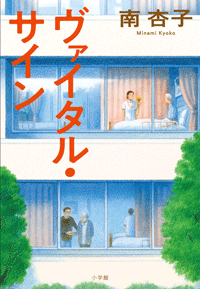
『ヴァイタル・サイン』
南 杏子