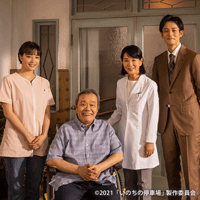現役医師・南 杏子の新刊『ヴァイタル・サイン』 冒頭ためし読み!
部屋に入ったとたん、介護スタッフが顔をしかめる。
美土里の部屋は、いつものように強い香水の香りがしていた。自分の体の臭いや排泄物の臭いを封じ込めようと考えているらしい。ケアをするたびに美土里は必ず香水を振りかけてほしいと希望した。
「いい香りの中で、きれいに死なせて」
それが彼女の口癖だった。
死を前にすると、思うように清潔を保つのが困難になる。誰もが元気なときと同様にずっと身ぎれいではいられない。美土里は認知機能が保たれていることもあって、羞恥心を強く感じるのだろう。素野子は心が痛んだ。
スタッフの視線を感じたが、気づかないふりをした。余計な会話をして患者を傷つけたくはなかった。
「上條さん、お昼ごはんですよ」
美土里の半身をゆっくりと起こし、ベッドの上にテーブルをセットする。
「こちらに置きますね」
介護スタッフも詮索は無用だと理解してくれたようだ。いつもの日常業務の表情に戻り、昼食のトレーをテーブルに置いて部屋を出て行く。
素野子は美土里のベッド脇に座った。トレーに並んだメニューも皆と同じだった。ただし美土里のために、噛まなくても喉を通るように、うなぎはふっくらした身の部分だけ、白和えの野菜は刻まれ、かぼちゃはペースト状になっている。
「どれから食べましょう」
返事はなかったが、美土里の視線からかぼちゃだろうと目星をつけた。スプーンで濃い黄色のペーストをすくい、美土里の唇に近づける。
美土里は無言で口を開いた。そこにスプーンをそっと運び入れる。口が閉じられ、ペーストはゆっくりゆっくり咀嚼された。
美土里の口の動きをじっと見つめる。やがて、のど仏が上下し、飲み込めたのが分かった。
「ああ、おいしい」
美土里はそう言ってほほ笑んだ。
「次はうなぎにしましょうか」
美土里がかすかにうなずく。素野子はふわふわのうなぎを取り、再び口に運んだ。
飲み込むのを待つ間、スプーンの上におかゆを載せて待機する。美土里の食事介助は何度も経験していた。濃い味の次には必ずおかゆを欲しがるのだ。
「おかゆさんです」
うなぎを飲み込んだタイミングで、次を差し出した。三口目もスムーズに食べてくれた。
「お野菜です。ビタミンたっぷりですよ」
きのことほうれん草の白和えを口元に運ぶが、美土里は口を閉じたまま首を左右に振った。気がすすまないのか、もうお腹がいっぱいになったのか。
「じゃあ、デザートはいかがです?」
ブドウのゼリーをすすめてみる。けれど、美土里はやはり口を開かなかった。
「終わり」
そう言って美土里は目を閉じ、一つ深呼吸した。
食事量はわずか三口──少ないが、仕方がない。無理やり口の中に詰め込めば、むせて誤嚥させてしまいかねない。
「じゃあ、あとでおなかが空いたらおやつを出しますね」
軽くうなずくと、美土里は素野子の顔を見上げて言った。
「午後はね、お客が来るの。悪いけど、その方の分のおやつもお願いできないかしら?」
見舞客がほとんどいない美土里にしては、珍しいことだった。
病院食を患者以外に出すのは禁じられている。だが、久しぶりに聞いた美土里の願いを簡単には切り捨てられなかった。美土里はもう、お客のために売店へ食べ物を買いに行きたくてもできない体なのだから。
「……分かりました。でも、師長にはナイショですよ」
そう答えると、美土里はうれしそうな笑みを見せた。
「その人ね、売り出し中の写真家なの。あたし、きれいにしていないと」
素野子は膳を下げ、次の患者の食事介助に向かった。
その後も、他の患者の食事の摂取状態や量を確認して下膳し、介助が必要な患者のマウスケアを行う。これらを午後二時に始まるミーティングの前までに終了させるのが、昼どきのミッションだった。
看護師たちはこの間に、交代で一時間の昼休みに入る。
休憩入りは、正午からの「早昼」チームと、午後一時からの「遅昼」チームにあらかじめ分けられていた。
素野子は今日、午後一時からの遅昼チームだった。けれど、担当患者の食事介助はまだ終わらない。自分がうまく進められなかった作業の残りは、早昼を終えて仕事に戻ってくるスタッフの負担になってしまう。段取りよく進まないときは気が引ける。
四人部屋の四〇七号室に入ったところで、時間を確かめようと思った。素野子は胸元のシルバーに手をやった。
「あれ?」
隣のベッドで患者の食事介助をしていた桃香が声を上げる。
「かわいいですね、その時計」
桃香はすぐに気づいたようだ。妙に目を細めて視線を向けてくる。
「あ、うん──。フォブウォッチだよ」
素野子のナース服のポケットの縁には、短いチェーンつきの時計がぶら下がっていた。別に珍しいものではない。腕時計は手洗いのたびに取り外さないと、ベルトの当たる部分などにウィルスや雑菌が残ってしまう。体位変換やさまざまな介助の際には、腕時計のバックルやリューズが患者の肌を傷つけてしまうリスクもある。フォブウォッチは、この仕事の特質をよく考えた時計だった。
翔平がくれたのは、飾り文字をあしらった銀色のアナログ時計がついている特別なデザインのものだった。
先週金曜日、誕生日の夜が鮮やかによみがえる。
「いつも忙しい素野ちゃんの仕事に、ちょっとでも役に立てばいいな」
翔平はそう言ってプレゼントしてくれた。
ここ数年、誰かから贈り物をもらったことなどなかった。喜びと同時に、じんわりと幸せが訪れる予感に包まれた。そのあたたかな感情は、まだ少しも消えていない。
「もしかして彼氏さんから?」
思わず口元が緩む。
「いいなあ、堤さん」
桃香が、素野子に初めて羨望の表情を見せた。
幸福感が桃香にも分かるくらい漏れ出ているようだ。そのことに気づいて素野子は恥ずかしくなる。一方で、自分は本当に幸せなのだと実感もする。
これを握りしめると、頑張れる。
睡眠不足にも耐えられるし、認定看護師に挑戦する勇気もわいた。
フォブウォッチは、翔平からの応援歌、いや、愛の象徴だ。
桃香の視線が外れるのを待ち、素野子はもう一度襟元に手を伸ばす。
普通の懐中時計と違って、フォブウォッチは時計本体の「六時」の部分にチェーンが取り付けられている。胸に垂れ下がっているときは文字盤が逆さになるが、持ち上げると正しい向きで時刻を確認することができる。
金属の冷たい感触が火照った指に心地よかった。
銀の重みを感じつつ、時刻を確認する。午後零時五十七分──あと三分で休憩時間だ。
急いで下膳を済ませ、マウスケアを開始する。桃香も隣の患者のマウスケアに入った。
「そういえば堤さん、最近きれいになりましたよねえ」
桃香に、のろけ話をせがまれるのは嫌だった。翔平の話をすると、何か大切なものが壊されるような気がする。
「大原さん、あのこと聞いた?」
話題を変えようと、素野子は今朝、ナースステーションで草柳師長がチラリと口にした情報をほのめかした。
「え? 何ですか、何ですか」
桃香はすぐに乗ってきた。
「うちの病院内でもWi–Fiが使えるようになるんだって。今月中に」
「マジ! ようやくネットがつながるんだ。やったあ!」
新しいサービスの提供は費用がかかる。少しでも利益の確保を優先したい病院の経営陣は新規の支出に消極的だったのだが、「ニコタマ・グレースにネット環境がないなんて」という患者や家族からのネガティブなクチコミを恐れて、今年度からの導入を決めたという。
「堤さんの学費支給よりは、万人のためのWi–Fi導入の方が優先度が高かったってことよ」
草柳師長と認定看護師の資格取得に関する話をしたとき、そんなふうに病院の台所事情を説かれた。
素野子はもう一度フォブウォッチに目をやる。その瞬間、突然の叱声が飛んできた。
「堤さん、大原さん、なにやってんの! 患者様の介護をしながらムダ話はやめなさいっ」
草柳看護師長の補佐役、看護主任の田口雅江だった。
主任は、小柄な体を反り返らすようにして怒鳴り声を上げる。
「大原さん。あんたこの紙、貼ってきて。各病室とホールの目立つとこにね」
そう言って主任は、何枚ものB4判のポスターを桃香に突きつけた。二人で話題にしていた件の案内文書だった。
上部に「無線LAN(Wi–Fi)接続サービス開始のお知らせ」と大書され、「当院では患者様・ご家族様のご満足度を高め、サービスの充実と利便性の向上を図るため……」と続いている。
昼食の休憩入り直前に主任から雑務を命じられ、桃香は頬を膨らませた。
「大原さん、これから休憩入りでしょ? ちょうどいいじゃない。誠実に仕事してる看護師なら、こんなこと普通は喜んでやるものだけどね」
誠実──田口主任が得意とする看護哲学だ。
「なによ。准看あがりのくせに」
田口主任が二人のもとを立ち去った直後、桃香が吐き捨てた。
「大原さん、それは……」
素野子はざらりとした違和感を覚えつつ、「失礼よ」という言葉をのみこんだ。
世間で言われる「看護師」の資格は、制度の上で二種類に分かれている。
厚生労働大臣が国家資格として免許を発行する「正看護師」と、都道府県知事が認める「准看護師」だ。
【好評発売中】
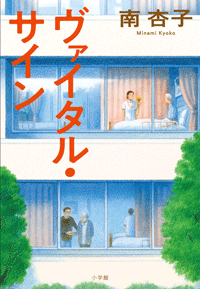
『ヴァイタル・サイン』
南 杏子