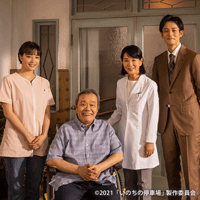現役医師・南 杏子の新刊『ヴァイタル・サイン』 冒頭ためし読み!
三人目の患者、下村里美を連れてきたのは桃香だった。
四〇八号室の里美は、末期の糖尿病患者だ。目が見えず、足が指先から壊疽しかかっている。体重が六十八キロもあるため介護負担も大きく、入浴介助は三人で担当するようにしている。
桃香も素早くTシャツ姿になった。
「はい、あったかいお湯に入りますよー」
里美が横たわる入浴台を湯に沈めている最中に、桃香が顔を寄せてきた。
「聞こえましたよ、さっきの師長とのハ・ナ・シ。堤さん、キャリア・アップ狙ってるんすね。抜け目ないっつうか、さすがですやん」
なぜ桃香が知っているのか。
「あ……」
草柳師長と話をしていたときに聞こえた、バチンという金属音がよみがえる。あれは、休憩室のロッカーを桃香が閉めた音だったのか。桃香は化粧直しのため、しばしばロッカーを使用する。休憩室はナースステーションのすぐ隣にあり、簡単に区切られているだけなので会話は筒抜けだ。
「いや、まだ決まったわけじゃないし」
「堤さん、正解ですよ。こんな療養病棟で、ボケたジジババを相手に雑用ばっかしてもキャリアにならない。年食うばっかで、やってられないし」
あんまりな言い方に絶句した。少なくとも目の前に患者がいるのに口にするセリフではない。耳が遠いから聞こえていないとは思うが、それも分からない。聞こえないふりをしているだけかもしれない。
桃香はその辺りのことを一顧だにしない様子だった。患者の里美は目を固く閉じている。勇子は「またか、やれやれ」という顔で黙々とシャワーを操っていた。
「大卒、上位校出身だと、なおさらその辺を感じちゃうんですよね」
愚痴とも自慢ともつかぬ、桃香のいつもの話が始まる。
中央医科大看護学科の偏差値は六一。当人から何度となく聞かされ、素野子の頭に刷り込まれた数字だ。
看護師の資格を取得するための道は、いくつかある。高校卒業後に看護専門学校や看護短期大学に進み、三年間の専門課程を修めて看護師国家試験を受けるのが最も早いルートで、素野子は専門学校を選んだ。けれど近年では桃香のように、四年制の看護大学や看護学科で学んだあとに国試に臨むケースが激増している。大卒ナースは今、国試受験者の約三〇パーセントを占めている。
桃香は、中央医科大と難易度がほぼ同じ新宿医科大学にも合格したという。実家は多摩地区のどこかの市なので、新宿の方が通学しやすかったはずだが、進学先は港区にある中央医科大を選んだ。理由は学部の名称だった。中央医科大が「医学部看護学科」であるのに対して、新宿医科大は「保健学部看護学科」。医学部という看板の響きに、ブランド力を感じて入学を決めた。これも桃香が得意げに語る話題だった。
「大学であんなに勉強したのに、それが何の役にたっているのかなって。はあ、むなしい」
素野子が専門学校卒だということを桃香は知っている。入浴介助のみを任されているパートの勇子に至っては、資格がないことも。そういう人たちと自分は違うのだと言わんばかりに桃香はため息をつく。
桃香は国家試験に合格したあと、中央医科大学附属病院の総合母子健康医療センターで看護師のキャリアをスタートさせた。ところが目の回る忙しさに数か月でドロップアウトした。その後は、ほどよい働き方で暮らしていけそうな病院を転々として、一年前に二子玉川グレース病院にたどり着いたのだ。
「偏差値六〇超えのナースがやる仕事じゃないですよ、ここって」
ここを選んだ理由も、「おしゃれな街」というイメージにあることは、素野子にも想像がついた。どこまで見栄を求めれば気が済むのかと思う。
「下村さん、お顔の色がよくなりましたよ」
入浴を終えた患者に、素野子はことさらに明るい声をかける。早く仕事モードに戻ろうよ、という気持ちを込めて。けれど桃香はふてくされたような表情を改めようとしなかった。専門学校出の素野子に指導を受けている状況も不満なのかと、こちらまで不愉快になりそうだ。
「お疲れさまでしたー」
ネガティブな気持ちを振り払いたくて、素野子は患者にとびきりの笑顔を向ける。桃香は下村里美を乗せたストレッチャーをぐいと押し、無言のまま出ていった。
眉を上げた勇子と目が合った。素野子も苦笑いでうなずき返す。すでに脱衣所では次の患者が待機していた。
午前九時半から始まり、十人の入浴を終えたときには十一時半になろうとしていた。
手と足がすっかりふやけている。鏡を見ると、額の傷そのものは小さかった。だが、傷の周囲に皮下出血ができており、たんこぶのように膨らんでいる。
「痛っ」
少し触れただけで、患部がうずいた。その瞬間、四〇六号室の蜂須珠代の「やめろ! 人殺し!」という叫び声がよみがえる。
この日の入浴者十人のうち、介助に「抵抗」したのは珠代を含め四人を数えた。それでも全体の半分以下で、まだ少ない方だが、へとへとだった。
勇子も脱衣所の床にへたり込み、濡れた眼鏡を拭き直している。
「虐待する側の気持ちが分かる──なあんて言ったら、誤解されますか?」
灰色の壁に背中をぐったり預け、勇子がそうつぶやいた。
「怒鳴りつけたくなっちゃうこともあるんですよねえ。大人しくしろって」
ぎょっとした。勇子の言葉のひどさに、ではない。素野子の胸にも同じ思いがよぎったからだ。
素野子は何も言えずに額の傷に薬を塗る。
「堤さん、ベランダから入居者を投げ落とした男、ついに死刑判決が出てたよね」
勇子の話は、府中市の介護付き有料老人ホームで、入居していた高齢の男女五人を男性職員が相次いで転落死させた事件のことだった。
「府中の老人ホームですね」
事件の発覚から判決まで何度となく世間を騒がせた介護施設は、同じ多摩川の上流に立つ。
「あの犯人、警察の取り調べでゲロったんだって。入居者がなかなか風呂に入ってくれず、困っていた。入浴を介助しようとしても何度も拒まれた。うまくいかずにストレスを感じた──だとさ」
勇子は眼鏡を何度もかけ直しながら言った。フレームがひどく曲がり、いくら手で調整しても、きちんとフィットしない様子だった。
「あたしたちの仕事って、とんでもないんだわ」
絞り出すような声を出す勇子の指先で、眼鏡の鼻当てがポロリと取れた。
「あっ!」
思わず声が出た。勇子は黙って手元を見つめている。
だが次の瞬間、勇子は、暗い顔を一転させた。
「あしたから、うんと安いのをかけてくるわよ」
勇子が「あしたから」と言ったことに、素野子はほっとする。
「今日はちょっと大変でしたね。本当にお疲れさまでした」
勇子は入浴介助だけのパートなので、これで業務終了となる。
けれど素野子は続いて昼食介助に入らなければならない。Tシャツからナース服に着替え、浴室を出た。
日勤の看護は、午前中に業務が集中する。
普段は午前九時から各病室をラウンドして回るのだが、素野子はこの日、退院患者のお見送りに始まり、入浴介助の当番に当たっていたため、少し変則的だった。他の看護師は、患者一人一人の状態を把握しつつ、検温や血圧測定、おむつ交換や洗面、医師の診察介助や採血検査、点滴などを進めている。
さまざまな業務メニューは、病棟の看護師たちが代わる代わる、あるいは共同でこなしてゆく。自分の業務が終了すれば、すぐに他の看護師が行っている業務に合流する。大縄跳びの中に、スムーズに入っていくように。
間もなく十一時半、昼食準備の開始だ。
素野子もエプロンを付けて、ホールへ向かう。ちょうど食事を載せたワゴンが到着する時間だった。これから午前最大のイベント、昼食の配膳と食事介助が病棟内で一斉にスタートする。
定刻の午前十一時半きっかりに、地下厨房から大型の温冷配膳車がエレベーターで運ばれてきた。この配膳車は、患者一人一人に届ける料理をトレーに載せて収納し、温かい食材は温かく、サラダや果物は冷たいままサーブできる給食システムのスグレモノだ。
ピンク色のエプロンをつけたスタッフが配膳車を押してやってきた。
この瞬間、病棟内の空気が一変する。
医師や看護師の白衣は、患者に特段の福音をもたらさない。ところが、配膳スタッフのエプロン姿は、確実に楽しいことが起きる予感を周囲にまき散らす。しかも二子玉川グレース病院は、世間に向けて「おいしい病院食」を売り物の一つにしていた。
それまでホールでぼんやりとテレビを観ていた患者たちが、配膳車とピンク色のエプロン姿を認め、一斉に目の色を変える。食べ物の力は偉大だ。
今日のおかずは、うなぎの蒲焼きに、きのことほうれん草の白和え、かぼちゃのそぼろあんかけだ。メニューは共通だが、患者の病状によって食材は三段階の硬さに分かれている。
あちこちの患者から、声が上がる。
「早くしろお」
「こっち、まだ来てないよ」
「遅いわね、まだなの」
認知症を患い、順番を待つことが難しい患者も少なくない。
「順番にお配りしていますので、少々お待ちください」
看護師や看護助手、時には手の空いたリハビリテーションのスタッフまでもが声をからして弁明に追われる。しかも、その一方で「看護師さん、トイレへ連れて行ってください」という患者の対応にも当たらなければならない。
ホールでの配膳が終わると、病室のベッド上で食事をする患者の配膳に移る。こちらの患者は多少遅れても文句を言わないから助かる。ホールが見えないせいで食事のサーブが始まったと気づかないのと、むしろ食事をしたがらない患者が多いためだ。
病院食は、料理を配って終わり、ではない。
患者の状態に応じて食事の介助が必要だった。手の力が弱い患者や、震えてうまく食事動作ができない患者には、食べ物をスプーンで口元まで運んであげるのだ。そうすると、やっと口を開け、飲み込んでくれる。
素野子は若い介護スタッフとともに、個室の四一七号室に入った。
患者の名は、上條美土里。東療養病棟では比較的若い六十五歳だ。認知症はない。ただし子宮癌が全身に転移しており、いつ亡くなってもおかしくないターミナルの状態だった。肺へも転移があるため、呼吸が十分にできず、常に酸素を吸入している。意識はあり、会話もできるが、手に力が入らず、先週から食事介助が必要になった。
【好評発売中】
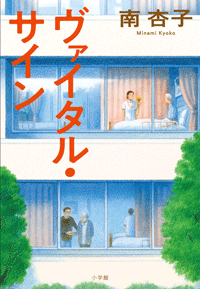
『ヴァイタル・サイン』
南 杏子