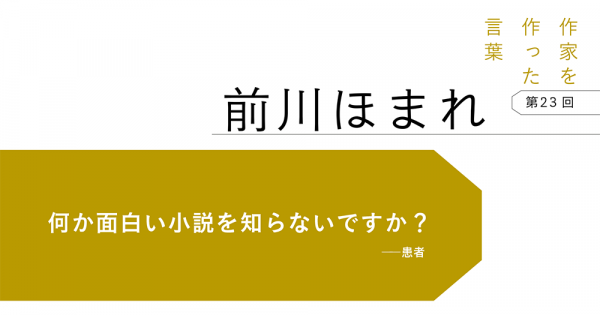作家を作った言葉〔第23回〕前川ほまれ
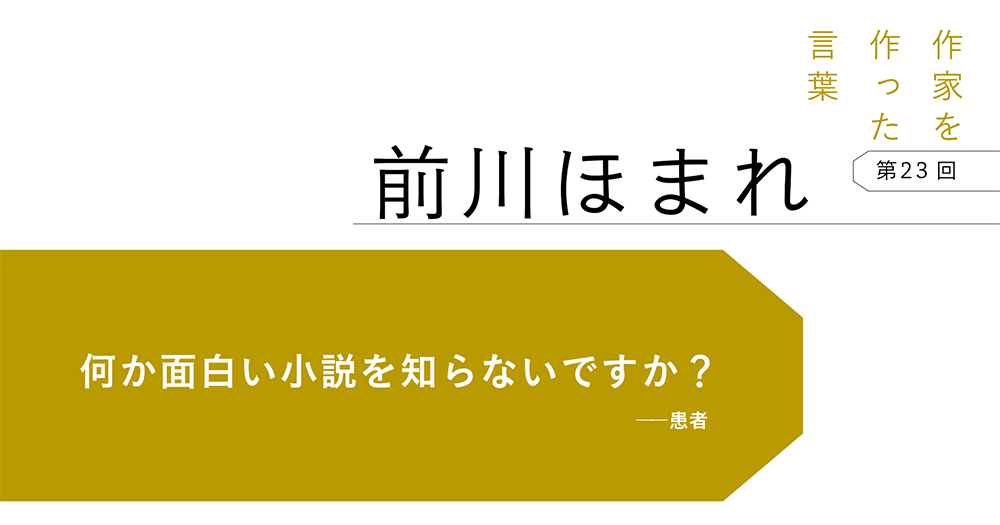
私は現在も、看護師として勤務しながら執筆を続けている。だからと言って、片手間で小説を書いている訳ではない。どの作品にも心血を注いでいるし、書いた物語の責任を負う覚悟もある。しかし兼業であるが故なのか、それとも元来の猫背の影響なのか、背筋を伸ばして自らを作家と強く意識したことは無かった。まだコロナ禍の影響が色濃く残っていた昨夏までは。
世間にコロナウイルスが蔓延すると、患者たちの入院生活は一変した。面会や外出泊は禁止となり、スマホやPCの画面越しでしか家族とは会えなくなった。院内散歩や集団リハビリも中止となり、病棟内でも四六時中マスクの着用を義務付けられた。そんな、息苦しい日々が続いた昨夏。担当患者から「何か面白い小説を知らないですか?」と、訊かれた。病棟に持参したゲームに飽きて、久しぶりに読書でもと思い立ったらしい。私は兼業作家であることを伏せ、個人的に面白かった小説を三冊ほど貸す約束を交わした。
自宅に帰ると、早速本棚を眺めた。悩みながら二冊まで選び終わった時、カポーティの『冷血』が目に留まった。この本を初めて読んだのは、ちょうど二十歳だった。あの頃は全てが上手く行かず、拗れた劣等感のせいで他人と関わることを避けていた。当時は勿論コロナ禍ではなかったが、常に独りでソーシャルディスタンスの日々。そんな鬱屈した二十歳の青年が、意味深なタイトルに惹かれて『冷血』に目を通した。夢中になるまでに、時間はかからなかった。当時は六畳間に住んでいたが、ページを捲っている間は『冷血』の舞台であるカンザス州に何度も降り立った。日常の面倒ごとや卑屈な劣等感すら忘れ、濃密なストーリーに浸ったのを憶えている。カポーティは確かに、二十歳の孤独にひと時だけ寄り添ってくれた。
不意に残りの一冊は、私が書いた小説を渡すことに決めた。こんな状況下であるからこそ、物語の力が必要だ。本棚の前で、自然と背筋が伸びた。私はカポーティにはなれないが、一人の作家にはなれると強く想いながら。
前川ほまれ(まえかわ・ほまれ)
1986年生まれ、宮城県出身。看護師として働くかたわら、小説を書き始める。2017年『跡を消す 特殊清掃専門会社デッドモーニング』で、第7回ポプラ社小説新人賞を受賞しデビュー。『藍色時刻の君たちは』が第14回山田風太郎賞を受賞。