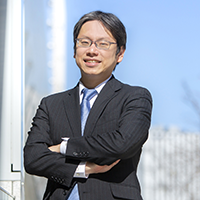源流の人 第44回 ◇ 宇髙景子(能面師)

六百有余年の歳月を経て続く幽玄世界を次代へと繋ぐ能面師
能楽の世界には、いくつかの流派がある。京都に生まれ育った宇髙は、そのうちの「金剛流」の流れをくむ。宇髙の亡き父は、能楽師であり、同時に能面師でもあった宇髙通成。宇髙の弟・竜成、徳成徳成各氏も、能楽師として活躍中だ。
インタビューの日、彼女は6つもの面を持参してきてくれた。うちのひとつが、「顰」という面。目にした途端、その表情の険しさに思わず言葉を失った。
200種類あるという能面の中で、おそらく最も激しい表情。
深いしわを刻んだ額。吊り上げた眉。大きく開いた口には金色の牙。
目も金色。鈍くも強い輝きを放つ。
「大江山」や「土蜘蛛」、「羅生門」といった能の演目で鬼神に用いられる。
この「顰」の面を前に、宇髙は語り始める。

「2013年につくったものです。この面が、わたしにとってターニングポイントになりました」
大学卒業後、ずっと父のもとで能面制作に明け暮れていたが、ある日、ふたりは激しいケンカになった。そもそも宇髙と父の関係性は曖昧で、完全なる「師匠と弟子」でも「父と娘」でもなかった。家でも稽古場でも、どっちつかずの間柄だったという。
ヴィジュアル系バンドにハマった高校生のときに髪を染め始めてから、古風な父からは見た目のことでいろいろ言われてきた。能面制作の仕事に就いてからは、能面を通じてのみ、ふたりは言葉を交わしてきたという。
そんなある日に起こった大ゲンカの様子を彼女は振り返る。
「その時は師匠として弟子に怒っている、というわけでもなく、親子ゲンカの延長のような、よくわからないケンカだったんです。だけど、破門という言葉こそ使わなかったものの最後には『出ていけ!』と言われて。こっちも感情的になって、関係が決裂してしまいました」

そんな状況の時に、大きな出来事が起こる。よりによってそのタイミングで、事情など知らない関係者から、大きな制作オファーが舞い込んだのだ。それは、京都文化博物館の「羅生門」をテーマにした企画展。能の演目「羅生門」に登場する面をつくってほしい、という依頼だった。
さんざん迷った。断ることもできた。
でも……。
これが最後のチャンスかもしれない。
せっかくだからやってみるか。
当然、父には指導を仰げない。ひとりですべて制作手順を決め、仕上げないといけない。これまでは最終チェック段階で父に見てもらい、手直しして面を完成させてきたが、それもできない。でも、とにかく前に進まないといけない。
工房を追い出された宇髙は、自宅片隅の作業場で試行錯誤し、面をひたすら打ち続けた。
「よし! 私はまだやれる」
特に、このおそろしく険しい「顰」の表情を作るのはとても難しく、宇髙を悩ませた。
「他の平面的な能面に比べると凹凸が非常に多いので、彫り進めるにしても細かな作業がずっと続くんです。エッジ(角)がいくつもあるので、処理を丁寧に表現していかなければいけない。ここまで複雑なものはやったことがなかった」
もうひとつ、彼女を悩ませたのは、「顰」に関する資料の少なさだった。
「第一線でお能に使われているお家元の面や博物館にある面は実際に手に取って、間近で見られる機会はほとんどありません。ガラスケース越し、あるいは舞台で見るだけです。それを借りて横に置いて作業することなどはできません。作業は写真や記憶に頼らざるを得ませんでした」

いったい、どこをゴールに定めればいいか。全工程において迷い続けながらも、黙々と制作に打ち込んだ。そうして約2か月経ったある日、彼女の言葉で言うところの「面が現れた」瞬間が訪れる。宇髙は回想する。
「彩色作業の途中で鮮やかな赤色をかすかに混ぜて塗ったとき、全体のバランスが締まった感覚を覚えたんです」
布で磨き、ツヤ感が出た瞬間、「よし! 私はまだやれる」と。悩み、考え続け、手を動かせば、面は必ず現れる。自分のやり方でやっていいんだ。そうわかった瞬間、宇髙は「能面師」を続けることを心に決めた。そんな宇髙の姿を黙って見守り続けた父・通成は2020年、亡くなった。それから現在まで、宇髙は約40の面を世に送り出している。
手作業だからこそ
能面は、20~30年の歳月をかけて乾燥させたヒノキから切り出された角材でつくっていく。京都市にある工房内で宇髙は座り込み、その大きな角材を足袋越しにダイナミックに挟み込みながら、鑿を当て、ハンマーで打っていく。
制作作業は大きく分けると「彫り」と「彩色」の2つがある。その2つの制作には、まったく別の種類の技量が必要とされる。最初の「彫り」には3つの工程があって、四角いブロックから輪郭や鼻、額のフォルムへと大きく落とす「荒彫り」、眼、鼻、口の場所がわかる程度に進める「中彫り」、より明確にその部分を形にする「こなし」の順に進んでいく。そしてさらに細かい表情へと仕上げていく。
「彫り」が一通り済んだら、ようやく「彩色」が始まる。貝の粉を砕いた胡粉に、鹿の膠を湯煎し液状にしたものを混ぜて面全体を真っ白に塗る下塗り、次いで、岩絵具でうっすら色を加えた胡粉を重ねる上塗り。それから「色付け」。墨を入れ、紅を入れ、「毛書き」をして、全体バランスを整えて仕上げていく。宇髙は言う。
「顔料を単色で使うことはほぼなくて、3色ぐらい混ぜて、色を出すんです。ちょっと赤みが強いな、と思ったときには、反対色としてグリーンやブルーを入れて」

着色には、筆をほとんど使わず、布を使いながら指で染み込ませていく。ポンポンとタッピングしながら、グラデーションを生み出していく。
「いかにリアルな感じで影をつけて立体感を出していくかが肝になるんです」
一連の制作過程は、すべて手作業だ。一度だけ試しに、エアブラシを使って塗ってみたことがあった。塗料の粒子がひじょうに細かく、均一に塗れるのが特長のエアブラシだが、これが能面の場合、逆効果だった。プラスチックみたいな平坦な感じに仕上がり、綺麗すぎて不自然だったという。
「人間が手作業でやること。ムラができるのが大事なんですね。それが人間味を表現するものなんです。機械にはそこまではできません」
心のうちは面に出る
能面制作を続けるうち、ある発見を宇髙はしたという。それは、制作過程で、よくも悪くも自らの精神状態が面に投影されてしまうことだ。


「たとえば、苦悩の表情が印象的な『中将』の面は、自分が苦しみながらつくっていても、それが良さに繋がる気がする。いっぽう、『小面』や『増女』といった穏やかな女面は、あまり悩んだり、苦しんだりしてつくってはいけない、と」
女面でも苦しみを抱える「十寸神」は、「中将」と同様に制作の苦悩が移ってしまったが、結果としてそれが似合う形となった。この面で演じる、水面に映る自分を見つめる場面では、影がさし、おでこの窪みが浮き出て、それによって苦悩や悲しみ、絶望の心を表現する。ところが、光の当たり方によって窪みが目立たなくなると、なんとも穏やかで綺麗な表情になる。「十寸神」の面を手にしながら、宇髙の表情も柔和になる。

「不思議ですよね。見える角度によって表情が違う。横顔の雰囲気もとても好きなんです」
レプリカと創作のはざまで
翁、老人、鬼神、女、怨霊、男──。各流の家元らに伝承されてきた、流儀の基準となる優れた面を「本面」と呼ぶ。多くは室町時代につくられ、国宝級のものも多く、芸術的に高い評価を受けている。そんな「本面」をお手本に、「写し」として新たに面を制作することが能面師にはある。そのときに大切にする意識が、自分の中で変わってきたと明かす。
「以前は、写しが絶対、本面がゴールなのが当たり前で、できるだけ近くつくれたら満足という気持ちでやっていたんです。傷まで再現して制作していました」
でも、貴重な「本面」を真横に置いて作れるわけではない。写真を見ながら作っても絶対的な違いがある。
「作った実際のものを見たら愕然とするんです。どうしても越えられない壁がある。立体物をそっくりそのまま写すっていうのは、3Dプリンターでもない限りは無理。『必要なのは形をそのまま写す、ってことではないんだろうな』って、だんだん考えが及んでくるようになって」

傷を写す行為は、考えようによっては、特徴的なものさえ押さえておけば、「本面の写し」だと認めてもらえる逃げ道、という捉え方もできる。そうではなく、むしろ形が違ったとしても、受ける印象や迫力がそのまま写し込まれるのなら、それこそが本来の「写し」ではないか。こんな思いに、宇髙は変わってきたという。
いま宇髙が制作中の新作の能面「曲見」も同じだ。中年女性、母の役に使う面だ。子どもがさらわれたり、行方不明になったりして、生き別れ、絶望のなか狂乱状態に陥っていく。子を思うが故に、目も落ち窪み、その絶望、虚しさが、面から滲み出るようにつくらなければならない。
「脳内補完能力」との戦い
制作に入れ込むなか、宇髙は意識していることがあるという。
「それは面を俯瞰して眺め直すことです。ものすごく大事だと思います。人間の脳みそって優秀で、部分的に隠しても、何となく形がわかる。特に人の顔は、目と鼻と口のどれかを隠しても、誰なのかがわかるじゃないですか。そんな『脳内補完能力』のせいで、ずっと面を見ていると見慣れてきて、よく見えてくる。これって、ひじょうに厄介なことなんです」
制作がうまく進み、「めちゃくちゃいいのできたんちゃうか!」という気分の日の翌日に改めて見ると、「えっ!」と驚くことが多々あると宇髙は笑う。だからこそ、距離を意識的に取ってみる。鏡に映してみる。ときには逆さまに向けてみる。何となく遠くに置いて、パッと見てみる。脳内フィルターを意識的に外し、騙されないように俯瞰していく。完成が近づくにつれ、そんな時間を意識的に設けているという。

「自分の顔も毎日、鏡で見て、化粧するじゃないですか。『何かちょっと今日、いい感じにメイクができたな』って思っていても、たとえば電車に乗っているとき、不意に窓ガラスに映った自分に愕然とする瞬間がある。それって、フィルターなしの実際の姿だと思うんです」
時代にそぐわないからこそ「能」
宇髙の制作の日々は、朝も夜もない。それに加え、能面制作の教室を、京都と東京・代々木で開いている。毎週木曜日の京都教室では、先代・父の頃からのお弟子さんもやってくる。海外からの弟子も増えており、年齢層はさまざまだ。最近は、小学5年生の女の子が通い始めたそうだ。宇髙は目を細めて語る。
「漫画で能面の存在を知り、好きになったそうです」
ヒノキの角材の段階から面を完成させるまでの、全工程を教えているのだという。
「体力的にも、大人と違いますし、手もまだ小さい。『形がちょっと出来上がっているところからスタートすることもできるけど、どうする?』って聞いたら、彼女は『最初からやりたい』って」

頼もしい「後輩」が、すくすくと育っていく。
日本の伝統芸能を担う大切な存在でありながら、全国の能面師、能楽師たちは皆、あがいていると宇髙は話す。ファン層が高齢化し、上演場所も決して多くはない。なかなか、能の仕事一本で暮らしていくことはままならない。能楽の普及のため、宇髙をはじめ、彼ら、彼女らのなかには、SNSを駆使し、YouTube で配信したりしながら、「どうにかしないと」という焦燥を抱き続ける者も多い。
「でも一方で、そもそも時代にそぐわないという魅力が『能』にはあるんですよね」。そう宇髙は訴える。
「今は、わかりやすいものが受ける時代。時短で、説明をたくさんしてくれるものが好まれる。『お能』はその正反対にある」

舞台上での説明はほぼない。動きはミニマム。時間もかかる。それが「能」。それこそが「能」。
ただ、と彼女は付け加える。
「恋愛の話だったり、おかれた状況のなかで何とか自分を保ち、幸せを模索する話だったり、じつは現代社会とそう変わらない題材も多いんです。『能』は時代とそぐわないのが魅力とは言いつつも、そこから知恵や、生き方のヒントを教えてくれるお能もある。発信していく力をもっとつけたい」
女がつくれば般若はこんな顔じゃない
室町期から続いている「能」だが、女性が舞台に立つようになったのは戦後間もなくからという。まだまだ女性が少ない世界だ。でも、これからもっと増えれば、それが新しい潮流を生む可能性はある。
「物語も面も、男性がつくってきた、男性視点の世界観のものです。『般若』だって、男性によってつくられた、嫉妬に取り込まれた女性の面です。もしこれを女性がつくったら、こんな表情にはきっとならないと思うんですよね。いっぽうで、嫉妬にまみれた男性だっているはず。この先、女性の価値観が採り入れられた面がつくられたらどういう顔になるのか。おのずと変わっていくかもしれません。男性の『般若』、見てみたくないですか?」

声の高低のトーンなど、物理的に女性にとって表現の難しい部分もあるだろう。でも、むしろ、今後そこから解放され、女性のトーンでもできる「能」のムーブメントが起こるなどすれば、また新しい世界が拓けるかもしれない。そこから新たな支持が拡がるかもしれない。そんな未来を宇髙は夢想する。
能面つけてみました
6つの能面を前にしたインタビューの最後、おそるおそる宇髙に切り出した。
「能面、可能ならばちょっとつけさせてもらえないでしょうか」
一瞬の沈黙の後、彼女は快諾してくれた。
「能面を触るときのお作法、みたいなのがありまして。この紐穴のところだけを触って、持ってください」

おそるおそる手に取る。
裏面は漆で塗られ、黒光りしている。
軽い。意外なほどに軽い。
「だいたい200グラム前後です」
そして、目の穴から覗いてみる……が、見えない! 狭い、狭い。
まったく見えない!
「たとえば障子に穴をあけて覗くときは、すごく障子に近づいて見るじゃないですか。でも、面の場合は、クッションによって距離ができるので、焦点が合わないんです」
面と顔の距離がひじょうに近く、声がこもる。顔のサイズや、頬骨の高さは役者によって違うため、額と頬のあたりに「面あて」というクッションを入れるのだそうだ。その高さや大きさで、角度を調節し、口元に隙間を作る。能面は、顎が少し出ている位置で留めないといけないルールがある。そうすると、面と目の間に隙間が生まれ、そこから外を見るのは「実質、ほぼ不可能」であることがわかった。宇髙は語る。
「ここまで視界が狭いとなると、もう、勘というか、空間の把握能力にかける感じになっていくんですよ。それもあって舞台では摺り足なんです。『摺り足で何歩』っていう感覚。舞台にある四本の柱のうち、特に『目付柱』といわれる柱を認識しながら演じています。能楽師は皆、身体に染み付いていると思います」
幽玄の世界の深淵に、ほんの少しだけだが近づけたかもしれない。「舞台に出かけてみたくなりました」、心から感じたのでそう告げると、宇髙は快活な笑みを浮かべた。

(写真左下)茶色の粒は絵具を接着させるための膠
(写真右)丸刀の柄には、大ファンであるヴィジュアル系ロックユニットLM.Cのサインが
宇髙景子(うだか・けいこ)
1980年京都生まれ。京都市立芸術大学美術科卒業。幼少期に能の子方(子役)を経験し、大学卒業後は、父・金剛流能楽師・故・宇髙通成のもとで能面制作に励む。2007年、文化庁国際芸術交流支援事業「宇髙会欧州公演」の能面展に参加、監修。22年、世界に1億人以上のユーザーを有する「Apex Legends」の人気キャラクターのマスクを手掛け話題に。翌年にはサントリー100周年記念 短編ドキュメンタリーシリーズのうち、ローマン・コッポラ監督作品でキアヌ・リーブスと共演、ファッションブランド Miu Miuとのコラボレーションなど、古典の枠を超えて活動している。