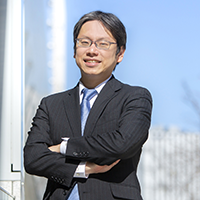源流の人 第42回 ◇ 周東美材(社会学者、学習院大学教授)

日本の音楽文化の根底にある「未熟さ」への愛
芸能史を通じ見えてきた社会構造
『「未熟さ」の系譜』で周東は、童謡の研究から筆を進め、宝塚、ジャニーズ、昭和時代を風靡した番組「スター誕生!」などに論考を広げていく。少し長い引用になるが、その論旨を記してみたい。
近代以降の日本社会は、さまざまなメディアの変容に直面しながら、「未熟さ」を基調とするポピュラー音楽を繰り返し生み出してきた。レコードによる新曲創作の気運を築いていったお伽歌劇と童謡、都市とコミュニケーション空間の変動のなかで花開いた宝塚、米軍基地を後景にしてテレビ芸能界の主役となったナベプロやジャニーズ、(中略)そして、業界再編と消費社会化の只中で「スター誕生!」のカメラの前に立った少年少女たちというように、日本のポピュラー音楽は、メディアの変容に晒されるたびに、幼く未完成で、茶の間のマスコットとなるキャラクターを繰り返し生み出し、家族の理想像に寄り添って来たのである。
(同書 261ページ)
ここで周東が強調するのは、「未熟さ」、それから「幼く未完成」といった言葉だ。周東はこのパワーワードにたどり着いた経緯について語り始めた。
「童謡について大学院で研究し始めた時、最初に重要なキーワードだと思ったのは、『家族』。いわゆる『近代家族』のことでした」

サラリーマンのお父さんと、専業主婦のお母さん、子どもが1人か2人いる家族。子どものことを「大事に守り育てましょう」「子どもが人生の生きがいです」という家族。周東は続ける。
「でも、これって、これまでの日本では特殊な現象。歴史的に調べていくと、そういう『家族のあり方』はずっと前からあったわけではない。明治、大正以降です。江戸時代、一部の武士などは、たしかにそんな生き方をしていたかもしれないけれど、農民は違います。商家の女将さんは、自分だって働きます。子どもが大切にされる場合でも、明確な序列があって、長男だけ別格扱いでした。『家族のあり方』の歴史的な多様性を見た時、『近代家族的な生き方』が、歴史の中で『作られてきたもの』だということを最初に知りました」
そんな周東が最初に研究対象として取りかかった「童謡」は、もともと1910年代の終わりから1920年代にかけて、爆発的に流行した歌謡だった。いわば洋楽。つまり、いにしえの邦楽をもとにした「わらべうた」とは異なり、童謡は西洋文化が入ってきたあとに起こった「流行現象」だった。その事実に、まず多くの現代人は驚かされるだろう。しかも、はじめは雑誌メディアが中心になって創作しており、その後、レコードやラジオ、戦後にテレビへと創作の場が拡大していった。つまり最初の童謡には、旋律さえついていなかったのだ。周東は自著でこう記している。
童謡の展開を考えるにあたって見逃せないのは、童謡が日本のレコード産業の成り立ちとポピュラー音楽の生産体制の確立に深くかかわっていたことである。
(同書 20ページ)
その詳しい経緯や過程、周東の考察については同書を手に取ってもらうとして、気づかされるのは、子どもに対する特別な愛情・情念や「保護するべき」という感覚の醸成と、「子どもを商品にしていく」という意識が、この国では自然とマインドとして高まっていった、ということだ。そして、子どもだから歌が上手くなくても許された。プロではないのだから、愛嬌があるぐらいの評価で、そのクオリティは問われない。西洋とは違う日本的価値観といえる。周東は語る。
「子どもを生きがいにする、人生の中心という価値観や、結婚しないと幸せになれないという考え方。この呪縛って、ものすごく強いなと思ったんです。それ『以外の』生き方のバリエーションが軽んじられている。無視され、抑圧されている。そういうものを抑圧していく社会の仕組みと、音楽のあり方とを一緒に考えていこうと思いました」

ベースとなる論文を2014年に発表してから、周東は1章につき1年をかけて、じっくり書き綴って1冊にまとめた。過去に周東自身が宝塚やジャニーズを「憧れの対象」として眺めたことはないという。
「ただ、私が中学生の一番多感な時期、クラスの女の子たちの多くは SMAP やデビュー前の KinKi Kids が好きでした。『こういう男性像が理想だ』みたいなことをどこか刷り込まれてはいるような気はします。ああいう感じのものを目指さなければいけないんだな、みたいな。そういう影響は受けたと思います」
宝塚は、今でこそ歌と踊りの華麗なパフォーマンスの印象が定着しているが、周東によるとこれは1930年代以降につくられたもの。それより以前の宝塚は「少女歌劇」と呼ばれ、学芸会に似た演目を上演していたという。設立当初の宝塚は「未完成」であることの魅力を打ち出していた。
1920年代、第一次世界大戦の後から、新中間層が形成され、「近代家族」のジェンダー意識やセクシュアリティのあり方、大衆的なメディア文化が形づくられていく。その構造的な土台は、1920年代と、100年経った現在とで「じつはあまり変わっていない」と周東は明かす。
「日本社会が変わってこなかった理由は、一つには日本は高度経済成長を遂げたことで(実質的に)『帝国』のままで、経済危機や民主化運動のような大きな行動変容のきっかけが起こらなかったことです。これだけネット社会になっても、いつまでもテレビ中心。世界的にもジェンダーギャップ指数が下から数えて何番目、という状態で、過去に引きずられたまま変われない社会なんですよね。ずっと同じようなものが100年間、再生産され続ける。例えばジャニーズ問題が、こういう形で噴出はするけれども、『元に戻そう』とする力がものすごく強い」
メディアの変化とジャニーズのターニングポイント
ジャニーズが世に出てきたのは、1964年。東京五輪の年だった。ジャニー喜多川氏が亡くなったのが2019年。メリー喜多川氏は2021年。いわゆる「ジャニーズ問題」が明るみになったのが2023年。ふたつの東京オリンピックに挟まれた約60年を一つの区切りとして考えた時、彼らが「国民的アイドル」に上り詰めたのはちょうど全体の活動期間の半分の30年前、1990年代後半からだった。周東は言う。
「1995年に起こった阪神淡路大震災の後、ジャニーズでは『J-FRIENDS』という応援活動がありました(関西出身メンバーがいる事務所所属ユニット3組による、震災チャリティー活動)。あの頃から、ジャニーズは国民的な人気を得るようになっていきます。SMAP の『世界に一つだけの花』(2003年)が、文化庁と日本PTA全国協議会が選定した『日本の歌百選』に選出されたり、教科書で採用されたり。大河ドラマの主演を務めるとか、『NHK紅白歌合戦』の司会を中居正広がずっとやるようになるとか」

そのピークから30年経った2020年前後に、創業者が亡くなり、「国民的人気」からの転換が始まった。1964年の東京五輪で始まったジャニーズが、2021年の東京五輪を過ぎ、一つの節目を迎える。ここで周東が着目したのが、彼らが国民的人気を得たターニングポイントにあたる、1995年だ。彼は言う。
「ジャニーズ前半の30年が『国民的なアイドル集団』になっていく大きな山だとすれば、1995年は、インターネット元年。『Windows_95』の年です。そのタイミングで、ネット社会化していくメディアの大きな分水嶺がありました。その時に、テレビや雑誌の多くは変革よりもジャニーズにしがみついたわけです」
没落していくメディアであったテレビや雑誌が、ジャニーズの人気にあやかり、なんとか視聴率や部数を維持していく。いつチャンネルを変えても、ジャニーズが映り、書店に並ぶ表紙を飾る世界を築き上げてきた。こうしてジャニーズは1995年から2023年ぐらいまで、老舗メディアと結びつき、インターネットを排除し続けた。ジャニーズアイドルの顔が、ネット上で公開できない状況が続いた。
ただ、ネット普及の波には抗えず公開に転じ、そして性加害が明るみになり、その先に事務所自体がなくなってしまう事態にまでに。それでも、と周東は言う。
「結局は、元に戻していきましょう、っていう流れは依然として強いように思います。『会社名も変わったし、被害補償も始まった、それでいいじゃん』っていうような。CM契約の終了などの動きもあるものの、事務所は会見を開かないままで、今のところ大きな変化の兆しが見えません」
新グループが毎年のように誕生し、その都度、新番組が生まれて──。そこまでの勢いは取り戻さないかもしれない。それでもメディアは、今後もしがみつかざるを得ない。まるで、日本社会全体が「謝ったから良いじゃないか」という思考回路を持っているかのように、またいつの間にか、スライムのように元の形に戻っていくのでは。周東はそう予測している。それにしても、日本社会はどうしてドラスティックに変わっていくことを拒むのか。そう問うと、周東はこう説明してくれた。
「戦後の日本社会の中で、味わってきた経済的な成長、繁栄、その中で培われてきた国民的な文化とか、そういうものへの執着。つまり、『成功体験』が忘れられないのでしょう」
安心して観ていられる「コンテンツ」としての「アイドル」
未熟さ、という言葉についてもう少し掘り下げたい。
「ジュニア」時代から成長が見守られるジャニーズ。
「音楽学校」時代から目をかけられる、宝塚。
「未熟さ」それ自体が、至極のエンタメと化している理由とは、いったい何なのか。
「戦後は、高度経済成長期で、新中間層が爆発的に増えます。それと深く結びついたのはテレビだと思いますけれども、「未熟」とはテレビを見る視聴者たちがコンプレックスを感じないっていうものだと思うんです」

観ていて、肩が凝るような、あまりにも立派過ぎるものではなく、観ている側がコンプレックスを感じずに親しめる偶像こそ、愛したい。彼は続ける。
「『昭和の歌姫』美空ひばりでさえ、もちろん歌は上手ですけれども、子役タレントからデビューして、みたいなこともある。『ひばりちゃん』と呼ばれていたり。それは日本社会が、少なくとも戦後のある時期までは、高い理想を掲げるよりも、自分たちが上から目線で安心して観ていられるものが良い。そういうコンテンツをつくり続けたのだと思います。現在、これだけ新中間層が没落し、生き方が多様化しても、そこだけはなかなか変われない」
映画に出る俳優は「銀幕のスター」と呼ばれ、遠い世界の人たちだった。それに対し「アイドル」は、ぐっと距離が縮まった。身近な、コンプレックスを感じさせない人たちを観られる文化が加速していった。
「お茶の間のブラウン管に、あまりにもグラマラスな女性が出てきたら、家族が一緒に観るのには好ましくない。ほどほどの清潔感が求められたんです。『歌のお姉さん』もそうなんですよ。歌があまりにも『上手』過ぎても、『美人』過ぎても駄目。かといって、見るに堪えないのも駄目。観ている側がコンプレックスを感じない。これは、テレビの特性だと思うんです。家族全員が安心できるお茶の間の延長上にないといけない」
テレビの発達が、「アイドル」を後押ししていった。このようにテレビの文化と結びついた、最初の存在が、じつはいるという。
「正田美智子さん(上皇后・美智子さま)。テレビの普及に大きく関わっています。ご成婚を見たいと、テレビの売り上げが大幅に伸びたのがこの時期です。当時の雑誌で、美智子さまは、『青春の偶像(アイドル)』などと書かれたりしています。戦後最大のアイドルは美智子さまです」

メディアを通して、はぐくむ「アイドル」への思いは、ときとして「変わらないでほしい」「私が育てているんだ」という情念が沸き起こり、道を間違えると強い負の感情に化けてしまうこともある。そういえば、「推し」という言葉がすっかり一般的になったが、ここにもどこか「上から目線」を感じてしまう。周東は語る。
「『推し』という言葉には、私はある側面では良い部分もあると思うんですよ。その前にあった『萌え』という言葉には、どこかセクシュアルなニュアンスで年長男性が年少女性に使っていたところもあると思うんです。(これに対し)『推し』は、応援する、自分がそのアイドルを広めていく、みたいな意味合いですから、性的ニュアンスや、『男性から女性へ』というパターン以外でも使える。多様性を持ったという意味では貢献はあると思います」
ただ、と周東は続ける。
「ただ、まさに『上から目線』で、応援してあげなきゃいけない存在だと思っている。単なる崇拝ではなく、『神輿に担いであげているのは私たちだからね』っていう、どこか傲慢なところも感じられますね」
センターにしてやったのは、俺がCDを何百枚買ったからなのに。
私たちが全国の公演に足繁く出かけ、支えてきたのに。
そんな思いをこじらせると、何かの拍子に、ファンは手のひらを返す。「飼い犬に手をかまれた!」とわめく。ときにそんな危険要素をはらみつつ、「アイドル」を「推す」。
ジェンダーの意識をどう変えていくか
ところで、周東が最初に研究を進めたのは「童謡」だった、と前に記した。
「子ども」に焦点を定めたのには、彼なりの思いが二つあったという。
「一つはまず、一部のコアな人たちだけが知っている、といったことはやりたくなかったんです。多くの人に知られているものを研究対象として取り上げたい。みんながなんとなく知っている、みんなに届くもの。そういうものを研究していきたいなと思っていました。
もう一つは、音楽の研究者って、特に評論もそうですけど、大体が男性なんです。中高年男性。特定分野やジャンルに人生を捧げて、とてもマッチョな世界。『どっちがより詳しい』とか競い合うレースからは、外れていたい気持ちがあったんです」
マウントの取り合いに対する嫌悪感を抱く周東は、ならば、マッチョな彼らが「見ようとしないもの」は何かを考えた。そしてたどり着いたのが、「子ども」の世界。あるいは「女性・子ども」の世界。そういうものを研究対象にしていきたい。彼の研究の原動力になっていった。
周東はこれまで、日本社会の音楽文化の構造を研究してきた。「近代家族」という概念が共有され、それを中心とするジェンダー、セクシュアリティ、人々の生活の基本的なあり方。その構造のあり方がどう生まれたのか。構造の解明を続けてきた。もう一つ、彼が今後の中心点としていきたいことがあるという。周東は言う。
「この構造をどうやったら解体できるかという研究を一方でやっていきたいと思っているんですね。『構造の解明』と『構造の解体』の両方をやる必要があって、解明をまずはしなきゃいけないので、まずはそちらをやる。一緒に、もう一つの中心点は解体です」

この構造が支えられてきたのは、「家族」「男らしさ」「女らしさ」、そうしたジェンダーの意識だったと周東は語る。「固定観念」、もっと言えば「思い込み」と言い換えても良いだろう。
「ジェンダーの、変わらない意識をどう変えていくか。構造の解体を私は中心的な仕事にしなければいけない。ジェンダーの制度や意識の歴史を問い直すことによって、『解体』とまではいかなくても、『揺さぶり』ぐらいをかけられるんじゃないかと思っているんです」
ある研究者が、そんな周東にヒントを与えてくれたという。
「タレントやアイドルは、家族の理想像を演じながら、当の本人自身は家族の生活から最も遠い人生を歩んでいる。例えば、子役タレントは忙しくて学校に行けない。アイドルは恋愛を禁じられている。不倫でもしようものなら、一気にバッシングされる。そんなヒントを教えてくれたんです」
いわゆる「ハレとケ」の「ハレ」を演じる芸能人が、一般的な価値観から遠く外れた人生を送りつつ、家族の理想像を演じている。演じなければいけないことに、激しい抑圧感をずっと抱き続けていく。例えば歌手・梓みちよが「この歌は大嫌い」と思いながら、理想的な家庭の母子を描いた「こんにちは赤ちゃん」(1963年)を歌い続けさせられたように。周東は言う。
「梓みちよさんは、『こんにちは赤ちゃん』が持ち歌になってしまって、でも、そういう縛りから何とか抜け出したくて、『二人でお酒を』(1974年)という大人の歌を歌い始めたわけですね。そういう営みをしてきたアーティストは、いっぱいいるはず。そういうものを研究したい。その『解体』や『揺さぶり』、『攪乱』することを考えています」
攪乱。それは、ただ波風を立てるだけではない。
あらゆる属性の人が生きやすくなる素地をつくる。
呼吸できる領域を拡げることに繋がる。
そんな社会へ近づけるために、周東は舵を切っていく。
始まりは書店主の父による一押しだった
周東は、群馬県桐生市に生まれた。
実家は小さな書店を営んでおり、一軒家の1階を店舗にして、2階部分に家族6人で暮らしていた。周東は3人兄弟の次男だ。
「いわゆる『街の本屋』で、コミックや雑誌の売り上げが大半を占めました。店の手伝いをやらされて、『ドラえもんの新刊が出ます』とか『今日は少年ジャンプの新刊が出ます』とかいった日には、立ち読み防止のビニール袋に本を詰める作業を、ひたすらやりました」
早朝から雑誌の付録を詰める作業をする時には、手がかじかみ、よく紙で指を切ったという。
「あれ、すごく痛いんです。今、話しながら、その感覚が蘇ってきました(笑)」

書店を手伝いながら、彼は音楽家になることを夢見ていた。小学校に上がる頃からクラシックピアノを習い、中学生になると、さらに難曲をこなせるように上達した。校内の合唱イベントでは、全校生徒の前で伴奏を披露し、ステージに立つ高揚感を経験した。高校生になっても、鍵盤と向き合う行為はやめなかった。
「芸大や音大に進みたい」
そう申し出た周東に、父親は首を強く横に振り、こう告げた。
「現時点で、桐生市の中で一番うまくなきゃ、ピアニストになれないよ」
周東は思った。
「そりゃそうだよな」
せめて音楽に一番近い分野は何だろう。たどり着いた彼なりの結論が、文学や芸術を学問として学ぶ道だった。早稲田大学第一文学部の受験に合格し、進学先が決まった。父親は、一冊の分厚い注文カタログを、周東に渡したという。
「このなかから、これからお前の行く学校の教員の本を探して、面白そうな本を好きなだけ注文しろ」
入学前年度の早大のシラバス(講義要項)と照らし合わせ、周東は、音楽と関係する講義と著書を調べていった。そのなかから出合った一冊が、音楽学者・小島美子の『音楽からみた日本人』(日本放送出版協会)。周東は、インタビューに合わせ持参した本をパラパラとめくり、振り返る。

「日本音楽史研究や、民俗音楽の大家で、小島先生が成し遂げたものはとても大きいんです。いわゆる民謡、わらべうた、地域のお祭りとか、三味線の先生たちの音楽的な生活上の営みから、音楽的な感覚やルーツ、リズム感を探っていく」
いーけないんだ、いけないんだー
先生に言ってやろうー♪
たとえばそんな、子どもたちが日常で歌う歌にも、私たち日本人の音楽的なセンスや感覚が生きているという。ハ長調にあてはめた時に「ファ」と「シ」の音のない日本の「ヨナ抜き音階」は、こんにちの J-POP にもたくさんある。
「この本を読んでから、私なりに考えたのは、踊りのことです。牧畜民は強弱のリズム感を持つ、狩猟民はビート感のあるリズム感を持つ。船に乗る習慣を持つ地域では、波に乗るようなリズム感を持ちます。その船も、縦長の船だと上下するスウィング感を持ち、横に大きい形の船だと横揺れのスウィング感が形成されると書かれています」

では、日本の踊りはどうだろう。
「水田稲作農耕を中心に生活をしてきましたから、泥の中にしっかり足をつけ、腰をずっと下に据えていると言われます。ですから、重心が低い位置にあり、ましてや着物を着るから、揺らぐとか、腰を振る踊りってしにくいんですね。サンバみたいにお尻を揺らすことがない。その代わり、能や日本舞踊などの静かな起居振舞への美意識が形づくられてきた、と。」
たとえば、2019年に誕生した音楽ユニット YOASOBI が、「ヨナ抜き音階」を効果的に使用しているのと同様に、「パラパラ」や「オタ芸」といったダンスも、腰の位置をほとんど動かさずに踊る。世界に一つだけかもしれない、オンリーワンの日本の踊りの文化を形成していく。
「そんなことをいろいろ考えるのが楽しかった」
そう言って周東は微笑んだ。
日本の音楽文化と向き合い、その核心を浮き彫りにしていく研究者・周東の背中を最初に押したのは、書店主である父親だった。
書店は現在、店を畳んだ。2006年に父親が他界したからだ。「美材」という名前は、今は亡き父親が、『古今和歌集』に載った平安時代の歌人 「小野美材」 の名をとってつけたという。
「よく考えてみれば、今、私自身、文学や音楽の研究をしていますから、繋がりはもしかしたらあるのかな。そんな気もしないでもないですね」
穏やかな語りのまま、周東は目を細めた。

(写真右)ブックカフェ「オカマルト」の店主・マーガレット氏が所有する膨大なLGBT関連の書籍類。その資料的価値を見出し、データベース化作業を手伝っている
周東美材(しゅうとう・よしき)
1980年、群馬県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。東京大学大学院学際情報学府修了。博士(社会情報学)。専攻は社会学、音楽学。東京大学大学院特任助教、日本体育大学准教授、大東文化大学准教授を経て、現在、学習院大学法学部教授。著書に『「未熟さ」の系譜―宝塚からジャニーズまで』(新潮社)、『童謡の近代―メディアの変容と子ども文化』(岩波現代全書、第46回日本童謡章・特別賞、第40回日本児童文学学会奨励賞)、『カワイイ文化とテクノロジーの隠れた関係』(共著、東京電機大学出版局、2016年日本感性工学会出版局)など。