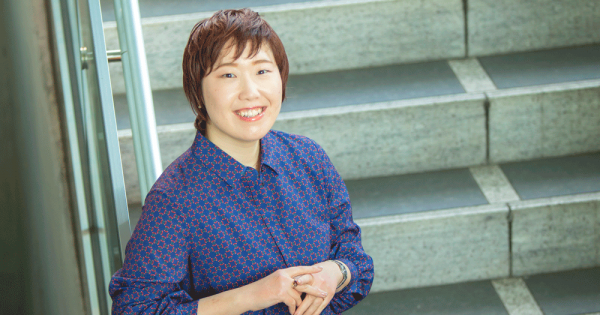源流の人 第19回 ◇ 長田育恵 (劇作家、脚本家、「てがみ座」主宰)
言葉と真正面から向き合い磨き上げ、人物の活きる演劇空間を紡ぐ劇作家
物語は運命に翻弄され流転しながらそれでも光の射す方へと観衆を導く

芝居、ミュージカル、テレビドラマ。気鋭の脚本家は舞台の枠を超えて等身大の「人間」を描き出す。
この人の紡ぐ台詞は、一言たりとも聞き逃したくない──。劇場通いを日課とする筆者が敬愛する、気鋭の劇作家のインタビューが今回叶った。長田育恵。たとえば太平洋戦争期を舞台にした戯曲では、日本、そして当時は日本「だった」植民地に暮らした人々の息遣い、悲哀を克明に描いてきた。あるいは熾烈なスペイン内戦を題材とした戯曲では、戦禍を生き抜くためにもがく者たちの葛藤を詳らかに掬い取ってきた。詩人や思想家ら先達の生きざまに触れながら、「ひととしての矜持」を刻み記した戯曲もある。どの作品においても、登場人物は運命に翻弄され、思いもよらぬ岸辺に流れ着く。そのたびに、観る者の心は揺さぶられる。ただ、最後の場面では、光の射す方角へと姿勢を正し向き直す描写を、かならず織り込んでくれる。生きることの意味、尊さを、客席で思い知ることになる。真冬の日、都内でインタビューに応じてくれた長田は、劇作の源泉について語り始めた。
「心が明るい方へと目指していく。そんな人間の強さを描きたい思いは常にあります。物語がどうなろうと、書きたいのはそれなので、上物は取り替え自由。どのジャンルでも、そこさえ一致していれば何でも大丈夫という感じです」
長田によって生み出される登場人物は、研磨された言葉によってどんどん存在感の光を放つ。誰もが好もしく、もしくは誰ひとり徹底的に憎めない人物として、観る者の記憶に刻まれる。まさに「人間」を描く劇作家が長田である。とかく「ハードルの高い、内向き(内輪受け)の芸術」と見られる演劇だが、長田の戯曲はいかなる人でも共感を生むはずだ。
普遍的なメッセージを
劇団「てがみ座」を主宰し、数々の戯曲で栄えある賞に輝き演劇界を席巻するいっぽうで、長田は「老舗」と呼ばれる多くの劇団とタッグを組み、精力的に作品を発表している。この二〇二二年初めから、さっそく公演が目白押しだ。一月は劇団四季「ロボット・イン・ザ・ガーデン」(原作=デボラ・インストール、小学館文庫)が公演中で、二月には劇団民藝との合作で「レストラン『ドイツ亭』」(原作=アネッテ・ヘス、河出書房新社)の公演が控えている。長田は老舗劇団との共同の意義について語ってくれた。
「劇団の持つカラーに応じ、思い切り(脚本を)書けるのがいま、とても楽しい」
たとえば劇団四季。彼らの普遍的なテーマは「生きることを全力で肯定すること」であると長田は評する。
「だから、真っ直ぐの視線で人生を見つめる物語を、迷わずに書ける。小劇場や現代演劇がフィールドだと、ちょっと恥ずかしい(笑)。けれど、劇団四季では思いっきりできる」

「キャッツ」「オペラ座の怪人」など、海外ミュージカルの輸入作が多い印象の劇団四季は、新たにオリジナル作品の代表作を生み出すべく、劇団内に二〇一八年、専門部署を新設し、創作体制を改組した。長田を今回招き入れた劇団四季の社長・吉田智誉樹は、「僕自身が長田さんの作品の大ファンなんです」と絶賛している。
戯曲「ロボット・イン・ザ・ガーデン」は、壊れかけのロボットと、人生を諦めかけた男との出会いを契機に転がり始める物語。英国人による原作を読んだ時、長田は、英国の風土を写したウイットに富む文体の空気感を楽しく感じつつ、舞台の脚本にするうえで数々の工夫を施した。たとえばロボットを最初から「可愛いキャラクター」として成立させず、主人公との交流を通して自我が芽生えていく描写にするように心血を注いだ。それから、原作にない設定も足している。特筆すべきは、原子力発電所のあった街を描く場面だ。
「人間だけがいなくなった街の描写は、震災を経験したわたしたちにとっては記憶に新しいこと。登場人物の心象風景に深く組み込み、ストーリーに、大切な要素として入れました」
いっぽう、劇団民藝は、幅広い年齢層のファンがおり、人の営みの機微を描くことで定評のある劇団だ。重厚な歴史劇や海外作品の上演も数多い。戯曲「レストラン『ドイツ亭』」は、一九六三年にドイツで開廷されたアウシュビッツ裁判(ホロコーストに関わった強制収容所の幹部らがドイツ人自身によって裁かれた)が題材だ。若いドイツ人が辿る成長と葛藤の軌跡を描く。善良な人間が真っ当に暮らそうとして、虐殺の「一パーツ」に組み込まれていく。長田は語る。
「最初は、裁判を傍聴するようなつもりで入っていきます。途中は、こんなに酷いことがあったのかと証人たちに同情し、打ちのめされながら進むけれど、最後には、被告人の立場に自分が立たされる。すべて追体験できる。どの時代であれ、ひじょうに普遍的なメッセージだと思います。現代における戦争を考える機会になればと思っています」
長田の劇作はこんなふうに、「戦争」が一つのテーマとなっている。その源流を遡ると、彼女の幼い頃の記憶に行き着く。
「同居していた祖父が満州(現中国東北部)に行っていたらしいことは、わかっていました。でも、満州ってどういうところなのかを聞いても、祖父は何にも語りませんでした」
長田が中二の時に、祖父は他界した。その後、かの地がどんな歴史を辿ったのかを長田は知ることになる。
「祖父は、わたしの問いかけに答えないまま亡くなりました。『答えない』という選択を、祖父はしました。わたしは『答えなかった』祖父の後ろ姿を知っている。劇作していくなかで、祖父の背中に手を伸ばさなければいけない」
そんな祖父と共に長田が生まれ育ったのは、東京・大田区の馬込界隈だ。かつて川端康成や萩原朔太郎、佐多稲子など多くの文士や芸術家が移り住んだ「馬込文士村」のほぼ真ん中に、長田家は居宅を構えていた。そんな「文学の磁場」で、長田はどんな幼少を送ったのか。
「入院している時間が多かったんです。身体が弱かったり、すぐ骨を折ったり。母親が本を読んでくれる時間が長かった。外で遊んだ記憶よりも、本を読む時間が長かった」
小五の頃、こんどは母が膠原病という難病に罹り、長い入院生活を余儀なくされることとなった。長田の多感な十代は、会社員の父親と、二歳下の弟との三人で、母親の入院生活を支えて過ぎた。いっぽうで、家族間のコミュニケーションツールとして機能していたのが、まさに長田が現在紡ぐ「物語」だったという。長田は笑顔で語る。
「父はファンタジー小説が大好きでした。『ロードス島戦記』とか『宇宙皇子』、あとは『風の大陸』。『これ、面白かったよ』って父から渡されて、読むんです。弟は弟で、「週刊少年ジャンプ」系の漫画を買っていました。家のなかでの共通会話が、本と漫画だった」
東京都港区にある中高一貫校・普連土学園に進んだ長田は、百巻以上もある小説『グイン・サーガ』を読みふけった。授業の一、二時間目で一冊。三、四時間目で一冊。そして五、六時間目で一冊。計三冊を消化していく。放課後は剣道の部活動に明け暮れ、部長まで務め上げた。想像しがちな文学少女像とは、少々異なる毎日を長田は送った。
小説家になりたい
「物語を読むこと」が好きな長田が、「物語を書くこと」を夢に描くように変わったのはなぜか。尋ねると、長田からは「決定的な瞬間がありました」との言葉が返ってきた。
「小説家って職業になろうと思ったのを、はっきり覚えているのが、湯本香樹実さんという作家の『夏の庭 The Friends』という小説を再読した時のことです。最初に読んだのは中二の頃でしたが、二度目に読んだのは高三でした」
物語では、小学生の少年たちが、おじいさんとの交流を通じ、ちょっと大人になっていく様子を描いている。大学受験を控えた夏に再読したところ、これまでの人生にないほど、長田は泣きじゃくった。当時を振り返る。
「祖父の死とか、母の入院とか、いろんな時間を経たからでしょうか。同じ小説なのに、もう何か、あんなに人生で泣いたことないってくらい大泣きしたんです。一人で」
涙を流すほど心を動かされ、物語の持つ力について思い知った。本ならば、人生のいかなる時に出会っても、そこから先の長い人生に何度か取り出してもらえる。そのたびに何度も寄り添うことができる。一冊の本があるということは、何と素晴らしいことなのか。長田は振り返る。
「まるで肉眼で見たように、本のなかの光景を視覚的に覚えています。その光景が、焼き付いている」
小説家になろう。指針が定まった。多くの作家を輩出する早稲田大学第一文学部(当時)の文芸専修に進学した。
ところで、それまで剣道に没頭してきた長田は、その反動からか「ジャズダンスをやりたい」という夢が膨らんでいた。ダンスを踊ってみたい。でも、当時の早稲田はヒップホップ全盛期。そんな時、長田が目にした光景があった。
「第一文学部のキャンパスに入るスロープの下に、ミュージカル研究会の部室を見つけたんです」
ミュージカルならジャズダンスを踊れるかもしれない。そんな軽い気持ちで研究会の門を叩いてしまった長田に、試練が待ち受けていた。それは「脚本を投稿すること」だった。
演劇の経験もない長田が、見よう見まねで書いたファンタジーミュージカルの脚本が、なんと本公演に採用される。同学出身のラサール石井が設定した伝統あるミュージカル研究会の「掟」として、脚本を書いた学生が演出も担当しなければならなかった。焦った長田は片っ端から卒業生に電話した。
「今年入った一年生なんですけど、演出をやらなきゃいけなくなりました。演劇について教えてください!」
照明、音響の仕事に就いた先輩のもとに駆け込み、舞台設営の作業を手伝わせてもらい、その深淵に触れた。舞台のことをもっと知りたい──。初めてお金を払って東京・新宿の紀伊國屋ホールで観た作品に、長田は息をのんだ。
「最後のシーンで、言葉が一切なかった。それにもかかわらず、登場人物が何を考えているかが、客席にいながら、手に取るように伝わってきた」
小説家志望の彼女にとっては、人間のいかなる感情も言葉で書き表せる小説こそ、文芸の最大の美点だと思っていた。ところが、この演劇作品の最終場面までの時間に使われてきた「演劇の言葉」は、すべての時間がいわば言葉のない瞬間のための滑走路のごとく使われていた。長田は語る。
「言葉がない時間に、ありありと言葉を響かせる。『これが、演劇の脚本なのか』って。目から鱗が落ちるようでした」
言葉を駆使して、言葉の「ない」空間を書き表す。響かせる。戯曲って、なんて面白いんだろう。その境地に挑むことがどれほど醍醐味のあることか。明確に突きつけられ、長田が演劇の世界にのめり込んだ瞬間だった。
井上ひさしからの言葉
早大を卒業後、社会人として生活を送りながら、長田はミュージカルの脚本執筆に携わり続けた。ただ、現代演劇への渇望は冷めない。劇作家として、自分の名で世に出す仕事をしたい……。そんな焦燥感を抱いたある日、日本劇作家協会が「戯曲セミナー」を行っているのを知った。二〇〇七年、その門を叩く。現代演劇がどういう仕組みでできているのかを、長田は一から知りたかった。
劇作家・斎藤憐が講師として教壇に上がった。斎藤は、教室の最前列に座っていた長田に尋ねた。
「戯曲で一番重要なことは何だと思う? 言ってみろ」
しばし考える。一番重要なこと? こう返答した。
「メッセージ性とか、テーマとか、ですか……?」
斎藤は首を振った。
「違う。戯曲で重要なのは、『登退場だ』」
いわく「情報を持った人」が登場し、ストーリーが動き、何かがあったら、その人が去っていく。舞台はその連続でのみ書かれている。斎藤はそう説いた。長田は驚いた。
「考えたことがなかった。お話を書きたいという漠然とした思いの地続きで、ずっと来てしまっていた。生身の俳優が演じるということを、わかっているようでわかっていなかった」
セミナー受講中に書き記した戯曲が認められ、翌年、劇作家の巨匠・井上ひさしの個人研修生として長田は選ばれた。その日々を、長田は笑ってこう言い表した。
「『追っかけしてもいい権利』を与えられました」

井上が地方で講演をする時、自腹でついていく。講演会が始まる前には、楽屋に同席させてもらう。開演前、ついたて奥で本にサインをする井上に声を掛ける「権利」が長田に与えられたという。長田がついたて越しに声を掛ける。
「こんにちは」
すると、井上はサインをする手を止めぬまま、矢継ぎ早に長田に話し掛け始めるのだった。
「この間の提出作品なんだけどね、あそこの場面が……」
(ええっ? 今??)
その場で井上がおもむろに始めた「ダメ出し」のアドバイスを、長田は直立不動で聞くしかなかった。アドバイスが終わるや客席に走った。さきほど聞いたことを懸命に思い出しながら、メモに書き写す。そんなことをしているうちに、「客電(客席の照明)」が落ち始め、演目が始まる──。
そんな「研修生生活」の最後の日、井上から言われた言葉が、長田は今も忘れられない。
「今日一日を、あなた自身の心の力で、良い方向に向かわせなさい」
長田はこう語る。
「作家として生きるようになって、つらい時、この言葉をフッと思い出します。一生作家でいるための秘訣を教えてくださった」
研修の二年後、井上は逝去した。井上のアドバイスを受けた研修生は、長田が最後になった。
「てがみ座」旗揚げへ
東京・王子の小劇場。
「戯曲セミナー」の研修が終わる頃、当時、三十歳になった長田は、この芝居小屋に向かっていた。
「東京の劇場って、一年後の予約をしないといけない。劇作家には早くなりたいけれど、どうすれば良いかがわからない。だから、自分の作品をプレゼンしなきゃ、と思ったんです。(俳優や裏方の)メンバーが揃ってから予約に行ったとしたら、さらに一年かかっちゃう。だから、まずは劇場だけは押さえに行こうと思って」
書き上げたばかりの脚本が手元にはある。劇場に提出する一冊と、自分のぶんの一冊。その二冊だけを持って、長田は劇場の支配人に、直談判した。
「演出家もいません。出演者も誰もいません。だけど、一年後にはどうにかしますから、劇場だけ貸してください!」
支配人は、その荒唐無稽な依頼に心底驚き、さすがに心配そうな表情を浮かべながら、長田にこう告げた。
「今日、ここで上演する劇団さんが、上演後にお茶会をするって言っているから、観ていけば?」
そうして長田が客席で観た芝居が、じつにすばらしかった。終演後、感動した彼女はさきほどまで舞台上にいた俳優に、持参した脚本を渡してお願いした。
「来年ここで旗揚げしたいんです。出てもらえませんか?」
すてきな舞台美術を手掛けていた美術担当者にも、同様にアピールした。すると彼からこんな言葉が返ってきた。
「僕は、旗揚げ劇団の美術をやっていないんだ。でも、現物のホン(脚本)があるのなら、読んでみるよ」
その彼から数日後、連絡があった。天文に関して書いた長田の脚本を読んだ彼の兄は、偶然にも天文学者だった。
「引き受けなきゃと思ったから、だから、僕、やるよ」
その彼の名は、杉山至。劇作家の重鎮・平田オリザとは盟友で、二人三脚で数々の作品を手掛ける、大ベテランの美術家である。
奇跡はまだ続く。王子の劇場で脚本を渡した俳優は、扇田拓也。のちに演出家として長田と長年組むことになる人物だ。……と、すると、その日、王子に行っていなければ、「劇作家・長田育恵」の人生は始まっていなかった? そう尋ねると、長田も頷き、こう語った。
「その日に王子で観たのは『風琴工房』という劇団でした。主宰は詩森ろばさん。最近手掛けたNHKドラマ『群青領域』の脚本を、リレー執筆で一緒に書きました」
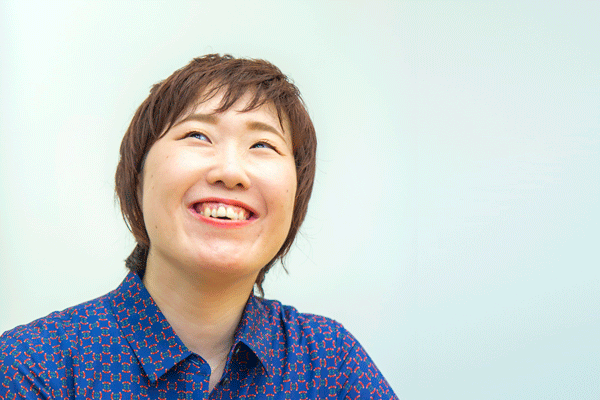
すべてが奇跡的に繋がっている。運を掴み縁を繋ぎ、物語を紡いでいく。一年後、こうして「てがみ座」は旗揚げした。
「とても美しい本だね」
二〇一四年、戯曲「地を渡る舟」が岸田國士戯曲賞候補作に、そして二〇一六年には、戯曲「蜜柑とユウウツ─茨木のり子異聞─」が鶴屋南北戯曲賞に輝いた。傍から見れば劇作家として華麗な道を歩き出したように見受けられるが、その頃に前後し、長田は大きな試練を経験していた。
「自分にとってはトラウマの時期でした。商業演劇に初めて関わり出したのが、そのあたりでした」
言葉を選び抜いて書いた脚本が、演出家によって突き返され、役者の力量に即した台詞へと置き換えられていった。俳優が少しでも喋りにくい台詞があれば、その部分は皆、ほかの言葉に置換されていく。書き替えられた言葉は、およそ演劇空間の強度に耐えかねる、やわな言葉だった。
「次に脚本を書く時に、これまで自分が何を根拠に、台詞を書いていたのか、わからなくなってしまった」
自分が信じている、「善かれ」と思う台詞。その「正解」が俳優の中にしかないのなら、劇作家はただ、俳優が言えそうか否かを推理し、言えそうな言葉のみで書かないといけない。自分は俳優ではない。これから組む座組の俳優のことも知らない。他人の生理を推測して言葉を書くなんて、物語に対する誠実さがない。長田は当時の苦悩を振り返る。
「『おはよう』って書いて良いのかさえ、わからなくなってしまった。最初の一言に何を発するか。わたしは本当に今まで何を書いていたのか……」
それでも締め切りはやってくる。どうにか書き上げたのが、「蜜柑とユウウツ」だった。演出は、劇作家でもあるマキノ ノゾミ。マキノは最初に長田の脚本を読んだ時、こう語りかけた。
「ああ、これは、とても美しい本だね」
詩人・茨木のり子を題材にした作品だ。マキノは続けた。
「この脚本を全部通して、彼女が残した一編の詩になるように、全ページ、岩清水のごとく磨き抜いていこう」
全ページ、磨き抜く。美しいものをつくる。この一言に長田はどれほど救われたかわからない。試行錯誤しながら、「善かれ」と思う台詞を必死で書いてきたことが、間違ってなかったと背中を押された。作品は絶賛され、名誉ある賞を受け、長田の最大のターニングポイントとなった。
「これまでは机上だけで考えていた言葉が、俳優の肉体を通じ演劇空間を駆けめぐりました」。そして演出家の緻密な研磨によって、言葉は昇華する。同作以降、さまざまな演出家と組む際にも、やるべき仕事が明確になった。
戯曲「豊饒の海」では、英国人マックス・ウェブスターが演出にあたった。彼は「物語は目に見えないんだ」と明確に告げたという。では、観客は何を見ているのか。彼は「目前の俳優の関係性の変化しか見てないよ」と言った。長田は語る。
「さらに書くことが明確になっていきました。あらすじのために登場人物が動くのではなく、登場人物が『活きる』ところから、筋が生まれてくることを知りました」
劇作家としての矜持を保てるようになってから、長田はハイペースで戯曲の発表を連ねていく。筆者が特に記憶に強く残るのは、二〇一八年の「海越えの花たち」。韓国・慶州にある在韓日本人妻の収容施設「ナザレ園」をモチーフに描いた作品だ。恥ずかしながら紀伊國屋ホールで観た筆者は号泣し、ロビーにいた長田をドン引きさせた。長田は言う。「祖父のことがあってから、ずっとアジアの中の日本がテーマになっています」
アジアについて最初に書いたのは、宮沢賢治をモチーフにした戯曲「青のはて」(二〇一二年)。賢治が樺太(現サハリン)に行った旅を追った。「汽水域」(二〇一四年)では、フィリピンから日本に出稼ぎに来る青年を描いた。「地を渡る舟」(二〇一五年)は、民俗学者が植民地政策に駆り出されていく話だ。「ゲルニカ」(二〇二〇年)ではスペイン内戦を通じ、暗喩として日本の戦争観、平和観を描き出している。長田は語る。
「こんどの『レストラン「ドイツ亭」』では、ドイツの国民が自分たちの過去を市民レベルで検証しています。それに対し日本は被害者としての意識が強く、市民レベルでは落としている視点もあると感じます。(文化面では国家をまたいで)共同で良い作品を作ろうというモチベーションを皆、持っている。そこから交流、理解が生まれていくと良いと思っています」

ときに偉人の評伝劇を手掛けることもある。ただ、あらすじとしての評伝は書く必要がないと長田は考えている。
「現代を生きる自分たちも観て、共感できる主人公につくり変え、その心の軌跡を追うことで、自分なら何を選択するかを、現代のわたしたちが考えられる演劇にしています」
ひとが前に向かって生きる力を描き出したい
最近はテレビ地上波にも活躍の幅を広げている。演劇とはまったく感触が違うため、長田は戸惑う場面があった。
「舞台で最も気にするのは、いかに空間強度を作るか。俳優を見ながら観客が目にするのは物的緊張の強度ですから」
舞台では、表面上は当たり障りのない言葉で喋り合っていても、劇的な緊張が潜ませてある。空間全体で見た時に、「一対一」で対峙する人間同士の、演劇的な緊張感がある。
「その劇場空間をどう描くか。空気の琴線を操る言葉を書くのが演劇です」
ところが、テレビでは、まずサブテキストでの会話はない。画面は観客(視聴者)とごく近い視点にある。「特に最近はアップが多いですから。半径二十センチの言葉を書くことに驚きました。距離感がまるっきり違う」
演劇空間で威力を放つ言葉は、テレビの至近距離では嘘くさく、信じてもらえない。この近さで響く言葉とは。信頼される言葉とは。長田の試行錯誤は続く。
「演劇は、お金を払ってその空間に閉じ込められに行く人たちが観るもの。打ちのめされたい。けれどもテレビは、まったく違います。ドラマにおける作家性を、どう出したら良いのか。修業中です。これまで一所懸命注力しようとしてきた言葉の訓練が、何も役に立たない」
執筆オファーが引きも切らぬ今、「物語に関わって生きていく」夢は実現した。コロナ禍で配信系の視聴が増えたことは、人々が改めて「物語」を求めていることを証明している。
「ひとが前に向かって生きる力を、物語の枠を借りて描き出したい」
媒体は何でも構わない。舞台、映画、テレビ、小説。どんなメディアでも、物語をつくることを続けていきたい。
アメリカン・コッカースパニエルの「ルノ」と暮らす。ルノはフィンランド語で「詩(Ru no)」を意味するのだそうだ。ルノは朝八時に長田を急かして起こし、朝ごはんを摂る。午前十時から午後四時までが長田の執筆のコアタイムだ。午後四時、ルノは再び訴えるという。
「『もう耐えられない、散歩に連れてけ』って(笑)」
ルノと共に散歩に行き、夕ごはん。夜は資料を読み込む時間に充てているが、長田がやめられないことがある。
「漫画や、小説、何でも良いのですが、お風呂の中でタブレット端末で読まないといられない(笑)。Kindle は罪ですね。寝る時間が二時、三時になってしまうこともあるんです」
そうして束の間の休息の末、翌朝八時、ルノが新しい朝が来たことを(なかば強制的に)知らせてくれる。それが嬉しい。平穏な日々の連なりが、登場人物の一人ひとりが輝きを放つ、うつくしい「長田戯曲」を生んでいく。
インタビューの最後、彼女はこんな言葉で締めくくった。
「必ず、観客の心にも覚えがあるものを届けようと思っています。描いている人物一人ひとりが、観客席にいる人たちと一緒でもある。特別な人を描いていない。それが、自分にとって大きなことだと思っています」
観客席に「任意で」座るひともまた、登場人物になりうる一人である。そのひとを舞台に上げた途端、物語は始まる。そう思いを馳せながら、長田は物語を紡いでゆく。

公演スケジュール
劇団四季ミュージカル
ロボット・イン・ザ・ガーデン
台本・作詞=長田育恵
演出=小山ゆうな
2022年5月14日(土)〜
劇団民藝+てがみ座 公演
レストラン「ドイツ亭」
長田育恵(おさだ・いくえ)
東京都生まれ。1996年、早稲田大学第一文学部に入学。2007年より、戯曲の執筆にも取りかかる。08年、井上ひさしの個人研修生として同氏に師事。09年、「てがみ座」旗揚げ。16年、戯曲「蜜柑とユウウツ─茨木のり子異聞─」で第19回鶴屋南北戯曲賞。18年、てがみ座「海越えの花たち」、劇団青年座「砂塵のニケ」、PARCOプロデュース「豊饒の海」戯曲にて第53回紀伊國屋演劇賞個人賞。20年、PARCOプロデュース「ゲルニカ」で第28回読売演劇大賞優秀作品賞。昨今はNHK「流行感冒」「旅屋おかえり」などテレビドラマの脚本も手掛けている。

(インタビュー/加賀直樹 写真/松田麻樹)
〈「本の窓」2021年2月号掲載〉