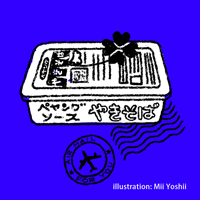思い出の味 ◈ 古谷田奈月

運転中、セブン-イレブンの看板が目に入ると、父は必ず「メロンシェイク飲むか?」と言った。私と兄が子どもの頃、セブン-イレブンがカウンターでシェイクを売っていた頃のことで、飲む、と私たちも必ずそう答えた。すると父は上機嫌になり、そうかそうか、お前たちが飲みたいんじゃあしょうがない、という感じでハンドルを切り、少しも億劫がることなく寄り道を決行した。
車を停めると、お前たちは待っていろ、と言い置いて、父はいそいそと降りていく。そうしてしばらくの後、三つのメロンシェイクとともに戻ってくる。父から手渡されたカップにストローを通し、キュウキュウと吸い上げると、ひんやり冷たくほんのり甘い、思ったよりも緑色の薄いシェイクが、それでもたっぷりとメロンの香りを漂わせて口の中に入ってくる。私たち三人はしばらく黙々とシェイクを飲み続けるが、やがて父がストローから口を離し、「お父さんはな」と大事な教えを授けるような口調で言う。「このシェイクが大好きなんだ」
そんなこと知ってるよ、と私と兄は言わなかった。つまらない返事で興醒めさせるより、最高だよね、と調子を合わせ、父を自動メロンシェイク供給マシーンとして利用し続けるほうを選んだのだ。
しかし、つい先日、それにしてもセブン-イレブンはなぜメロンシェイクなどという色物フレーバー一本で勝負していたのだろう、とふと疑問に思い、調べてみて驚愕した。セブン-イレブンのシェイクはメロンだけではなかったのだ。バニラがあり、ストロベリーがあり、ヨーグルトまであった。もっと色々な味を楽しめたのに、父は私たちを車に残すことで情報を遮断し、自分好みのメロンシェイクだけを与え続けたのだ。
私はどれほど兄に電話し、「私たちはメロンシェイク・ファシズムの犠牲者だ!」と訴えようかと思ったが、踏みとどまった。死後四年、父を糾弾するにはもう遅すぎたし、自分たちも文字通り甘い汁を吸っていたことを思い出したのだ。