岩木一麻著『がん消滅の罠 完全寛解の謎』が描く驚きのトリック・著者にインタビュー!
第15回『このミステリーがすごい! 』大賞・大賞を受賞した作品。医学ミステリーとして緻密に描かれたストーリーには思わず引き込まれます。果たして、がんは完全に消失し完治するのか?がん治療の世界で何が起こっているのかに注目する一作の創作の背景を、著者にインタビュー!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
治るはずのないがんが消え去る驚きのトリックとは――第15回『このミス』大賞受賞作!
『がん消滅の罠 完全寛解の謎』

宝島社 1380円+税
装丁/高柳雅人
岩木一麻
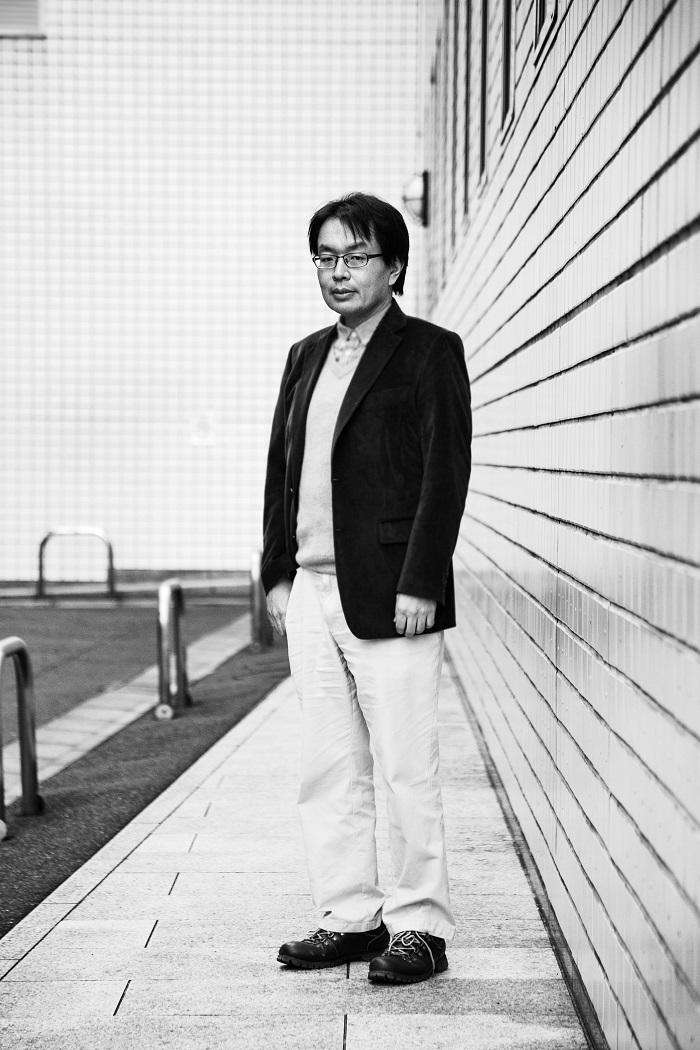
●いわき・かずま 1976年埼玉県生まれ。神戸大学大学院自然科学研究科修了。国立がん研究センター、放射線医学総合研究所で研究に従事。「がんセンターではモンシロチョウ由来の抗がん蛋白質を研究していました。ユニークな特性を持つ、実用化には至っていない抗がん剤候補の一つです」。現在は医療系出版社に勤務。昨年本作で第15回『このミステリーがすごい!』大賞受賞。172㌢、70㌔、A型。
医学の進歩が実現可能にした「魔法」のような技術を生かすも殺すも人間次第
これまで消失トリックで消える物といえば、凶器や死体が専らの対象だった。 しかし本書で描かれるのは〈不可能状況下でのがんの消失事件〉。日本がんセンター呼吸器内科に勤務する〈夏目典明〉は自らが余命半年を宣告した末期患者の4人中4人が、生命保険の生前給付を受けた後に〈完全寛解〉に至る、前代未聞の事態に遭遇するのだ。 『がん消滅の罠』で第15回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞した岩木一麻氏自身、かつては国立がん研究センターに勤務。夏目や、〈天才研究者探偵〉を自称する同僚〈羽島悠馬〉と同様、がんと向き合ってきた元研究者でもある。 羽島が〈殺人事件ならぬ活人事件というわけだ〉と言うように、本来、寛解は歓迎すべきこと。だがその背後には〈救済〉を騙った恐るべき計画が見え隠れし、人が人命や運命すら支配しようとする時、医療は禍々しいまでの毒を帯びる。
*
「執筆動機は2つあって、1つはこの方法でのがん消滅のトリックを研究者時代に思いつき、それをトム・クランシーやマイケル・クライトンのような手に汗握る小説に書きたかったこと。もう1つは、日本人の2人に1人ががんになる時代なのに、多くの方はがんのことをよく知らないからです。
医学の進歩で、長期間の延命も、痛みのコントロールも可能になってきているのですが、がん=悲惨な死というイメージを持つ人はいまだに多い。もっと正確な情報をミステリーとして読めれば少しは状況も変わるかもしれません」
物語は冒頭、夏目が抗がん剤による延命治療を勧めた30代女性の肺門部原発扁平上皮がん、ステージⅣが、某教団の自然療法とやらで寛解し、それを認めた彼の名前が広告に使われた顛末から始まる。実はこの1件、夏目が見せられたのは彼女の〈双子〉の画像だったのだが、その種明かしを序盤早々に回した経緯が面白い。
「治るはずないがんが治る、さては双子だなって、ミステリー好きならピンと来るくらいベタですよね(笑い)。その先入観を長引かせてもよかったんですが、本筋はあくまでがんの消滅ですし、肝心の4人に双子はいませんと明言した上で、面白く読める話を目指しました」 この時、なぜがんは消えたのかという一事に囚われ、まんまと偽造の痕を見逃す夏目ワトソンに、〈密室トリックだと見せかけて実はアリバイトリックだった、みたいのがあるじゃない〉〈あれと似た感じなんだけど〉と絶妙のヒントを出す羽島ホームズ。この2人に、夏目の妻〈紗希〉、大手生保の調査部門にいる友人〈森川〉、その部下の〈水嶋瑠璃子〉も加えた5人組が、本書では酒席も交えて推理を展開。本件はリビングニーズ特約を悪用した保険金詐欺の疑いもあり、生保にとっても死活問題なのだ。
その後、4件の活人には独自の〈オーダーメイド医療〉で実績を上げ、各界の実力者を多く集める〈湾岸医療センター〉が関与し、その理事長は夏目たちの元恩師〈西條〉であることが判明。だが10年前、大学を辞めて何をするのかと質す夏目に、〈医師にはできず、医師でなければできず、そしてどんな医師にも成し遂げられなかったことをです〉と答えた西條が悪事に加担するとは思えない。
がんの話はなぜか タブー視される
一方湾岸側では呼吸器外科医〈宇垣玲奈〉が西條を師と仰いでいた。初期の肺がんが見つかった厚労省官僚の手術を終え、摘出したがん細胞を次なる作業者に渡して彼女は思う。〈自分たちは正しいことをしている。でも、それは明確な犯罪行為でもある〉と。
謎の計画を巡って物語が二転三転する間、本書ではがん治療の最新情報や抗がん剤の治験や認可の問題、患者側の〈ゼロリスク信仰〉の壁などが、極力わかりやすい形で解説されてゆく。 「最近では樹木希林さんが全身がん宣言をなさったり、『がんと共に生きる時代』を迎えている。ただこれはある患者さんの感想ですが、『それほど一般的ながんの話がなぜか職場や公の場ではタブー視され、真正面から扱う小説もなかった』と。 だからこそミステリーの核そのものにがんを据える必要があると私は思ったし、現段階で理論的には実現可能な技術は悪用もできなくはないという危うさも同時に描いておきたかった。現に医学の進歩は魔法にも近い技術を実現しつつあって、その魔法を生かすも殺すも、結局は人間次第なんです」
実際、がんを操ることで人を操る西條の計画も彼なりの正論には根ざし、その目的と手段の捻じれにこそ、魔は潜んだ。そうした医療と倫理の一線について考える時、目を引くのが夏目たちの〈花見〉だ。瓶や火気は持ち込み禁止の上野公園で、ペットボトルに入れた極上の酒を、生石灰と水の発熱作用を利用した〈自作の燗付け器〉で楽しむ彼らは、〈駄目なもんは駄目〉と普通に言える人々なのだ。
一方で、〈人はどんな時に神に近づこうとするのか〉と夏目を慄かせる西條自身、過酷な運命に苦しんでいた。 「臨床心理士の友人によれば、過去に重大な喪失経験を抱え、暴走してしまった西條は『基底欠損による自我の肥大』と診断されるらしい。私は彼の行為をむろん肯定はしませんが、人間、条件さえ揃えばどう転ぶかわからないとは思います」
西條がソクラテスや太宰を例に挙げつつ、ある心理研究に言及し〈憂鬱な気持ちは人々の独創性を増加させるのです〉と言う場面がある。〈幸福だけを至上とする社会では苦悩や不安は一種の病として扱われます〉〈昔は違いました。苦悩や不安、死と滅びは日本文化に宿命として取り込まれ〉〈日本人独特の情緒が形成されていったのです〉と。
「この独創性に関する研究報告は実在します。独創性も発揮の仕方はその人次第だと思うのですが、とりあえず私は辛いことや気分が沈むようなことがあった時は何か新しいことを考えるチャンスだと思うようにしています」
ちなみに次回作は個々の症例は希少でも種類の多い、希少疾患を扱う予定だとか。 「これも母数が少ないだけに新薬開発が進まないなど、がんとは違った意味で深刻な病気の一つ。そんな中でも見方を変えると既存の薬が意外に流用できたりする現状を、私はあくまでスリリングで面白いミステリー小説にしたいんです」
見方一つで視界は変わる。そんなミステリーにも通じる真理と医学の今を、今後も両輪に書いていきたいと、40歳の新人作家は誓う。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト2017年2.24号より)
初出:P+D MAGAZINE(2017/04/30)

