【生誕100周年】小説家・阿川弘之のおすすめ作品3選

戦争文学や記録文学の分野で数多の名作を残した小説家・阿川弘之は、2020年12月に生誕100年を迎えます。『雲の墓標』などを始めとする阿川弘之のおすすめ作品をご紹介します。
2020年12月24日に生誕100年を迎える、小説家の阿川弘之。近年ではエッセイストの阿川佐和子の父として、破天荒で苛烈な性格の持ち主であったというエピソードが語られることの多い阿川弘之ですが、太平洋戦争時の海軍での経験を元にした戦争文学や記録文学を中心とするその作品群は、いまでも非常に高い評価を受けています。
今回は、そんな阿川弘之の作品を初めて読む方におすすめしたい3つの作品を、そのあらすじと読みどころとともにご紹介します。
海軍に入隊した若者の青春と苦悩を率直に綴る──『春の城』
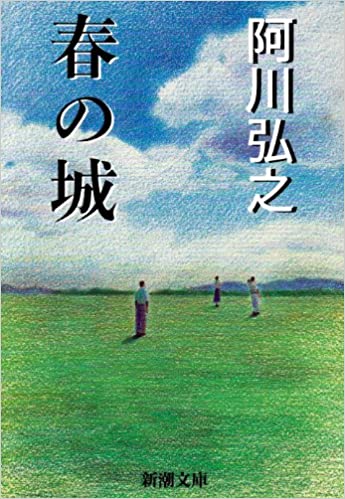
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101110018/
『春の城』は、阿川弘之が1952年に発表した長編小説です。阿川弘之は本作で1953年に第4回読売文学賞を受賞し、小説家としてのキャリアを本格的にスタートさせました。
物語は、1941年から始まります。広島の田舎町で育った主人公・小畑耕二は、すこしずつ近づいてくる戦争の足音を感じながらも、東京で大学生活を送っていました。耕二は、年上の幼なじみ・伊吹幸雄の妹である智恵子に淡い恋心を抱きつつ、心の底では“何でもいいから強く打ち込めるものがほしい”と考えていました。
悪徳でもいいから、何か本当に気持を打ち込める、荒々しく立ち向って行ける、そういう対象が欲しいと思っていたが、一向に何も見出す事は出来ないでいた。
そんな耕二の満たされない気持ちは、予備学生として海軍に入隊したことで熱を帯びていきます。彼は日米戦争の開戦を機に、従軍を「自分たち若者の光栄ある義務」と感じ、軍令部で中国軍の暗号解読業務に従事することになります。1945年、広島に原爆が落とされたことで智恵子たち家族や耕二の高校時代の恩師は悲惨な死を遂げますが、耕二はただ
「広島もこれでは皆死んでしまったろう」憂鬱も腹立たしさも強くは湧かず、只来るべきものが来たという気がするだけで、耕二の心にはもはや何事も、極めて鈍くしか感ぜられなかった。
と、原爆投下を遠く離れた地のできごととして受け止めるだけなのでした。耕二はただ、戦争の勝者である連合国側が絶対的に正しく、敗者である日本は裁かれて当然であるという社会の急な価値観の転換に、大きな違和感を覚えます。物語は、終戦から3年後、広島に帰った耕二の生活を描きながら幕を下ろします。
本作を読んでいると、自然豊かな故郷で幼なじみとともにのびのびと育ち、恋心や若者らしい悩みに翻弄される耕二の学生時代の甘酸っぱい描写と、終戦後の耕二の心境を綴る暗く淡々とした描写の落差に驚くかもしれません。本作は、阿川弘之自身の生い立ちや、海軍時代の実際の経験に基づいて書かれています。圧倒的なリアリティで、戦争の惨禍が人々の心に残した傷の深さを描く名作です。
特攻隊員たちの複雑な心境を描く──『雲の墓標』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101110026/
『雲の墓標』は阿川弘之が1956年に発表した長編小説で、『春の城』と同じく、海軍予備学生の若者の青春と苦悩を描いています。しかし本作が『春の城』と大きく異なるのは、主人公が特攻隊員として出撃していくまでを描いた作品である点です。
本作の舞台は、太平洋戦争末期。京都の大学生である吉野次郎は、同級生である藤倉・坂井・鹿島らとともに、学徒兵として広島の大竹海兵団に入団します。吉野は藤倉・坂井とともに航空科に入り、やがて大分の宇佐航空隊に配属され、特攻隊員になるべく訓練を積んでいきます。
航空機から見下ろす自然の雄大さや九州の地での人々との温かい交流などに感銘を受けつつ、始めこそ特攻隊員として死ぬことに意義を見出そうとする吉野ですが、その生活の中で次第に軍への不信感や怒りを募らせていき、戦争の正当性にも疑いを抱くようになります。
一方の藤倉は軍生活の中で、この戦争に勝算などはなく、特攻隊員はただ無駄死にするだけだという確信を抱いていました。彼は出撃後、どこかの島に不時着して終戦を待ち生き延びよう──と密かに計画するものの、不幸にも飛行訓練の際の事故が原因で亡くなってしまいます。また、坂井は疑いなく特攻隊員としての任務をやり遂げ、敵機に向かっていき死を迎えます。
吉野は、最後までなかなか自分の心と戦争の正当性への疑念に折り合いをつけることができずにいます。しかし彼も、故郷に残してきた家族や失った仲間たちのことを考えながら、ひとりの特攻隊員として敵機に突っ込んで命を落とすのでした。
特攻隊を舞台にした作品では多くの場合、死というただひとつの運命に向かいながらも日本の勝利には疑いを持たず、強い信念を抱いたまま死ぬ若者の姿が描かれます。しかし本作は、吉野を中心とする学生たちの心境や苦悩を日記や書簡の形式で綴ることによって、自分の未来を自分自身で選択することのできなかった若者の無念と戦争を正当化することの醜さを、余すところなく描き切っています。
文芸評論家の福田和也は、阿川弘之の一連の戦争文学に対し、
阿川にとって戦争にかかわる想いは、いささかも観念的なものではなく、むしろ身体の側に肉化されている。
──福田和也『作家の値うち』より
と評しています。本作はまさに、生身の人間の声が聞こえてくるような小説です。
『志賀直哉』
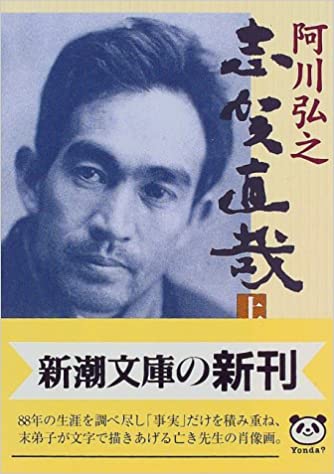
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101110158/
阿川弘之は、『暗夜行路』や『城の崎にて』などの代表作を持つ小説家・志賀直哉の“最後の内弟子”としてその薫陶を受けています。本作は、師である志賀直哉の出生から死に至るまでを、志賀の交友録や作品の評などを交えつつ書き記した伝記小説です。阿川によるこの膨大な師の記録は、第47回野間文芸賞も受賞しています。
本作は上下巻で構成されており、上巻は志賀直哉の家族や「白樺派」の盟友たちとの交流が中心、下巻では晩年に至るまでの志賀の生活と、志賀唯一の長編小説である『暗夜行路』についての詳細な分析が中心となっています。最大の特徴は、阿川自身の所感や意見よりも、志賀にまつわる数多くの資料や他の小説家・文芸評論家による評論を重視しつつ、実に詳細な調査・分析をふまえて記されている点です。同時に、弟子として
昭和二十三年から三十年までの七年間、のべつ、熱海の志賀山荘へ泊りがけで行っていた
というほどに親しく近しい立場から師を見ていた阿川ならではの愛にあふれる視点も垣間見ることができます。
本作からは、志賀がさまざまな文士たちに慕われる、率直で気取らない性格であったことが伝わってきます。志賀家は交通の便の悪い熱海にあったにも関わらず、常にさまざまな客人が志賀を訪ねてきたと言います。
また、志賀は一切の無宗教家で、散歩中に小さな石地蔵を蹴り倒してしまってからというものの家族に不幸が相次いだにも関わらず、「供養などしてよくなったと思いこむのはよくない」という理由で断固として供養を拒否し続けた──という彼の人物像をよく表したエピソードも、作中で阿川が紹介したことで有名なものになりました。
最晩年に至る章では、長年交流のあった文士・里見
つかつかと枕元へ歩み寄るなり、
「伊吾(※志賀による里見弴の呼び名)だよ」弴は言った。直哉は「伊吾」の来ているのが分ったようであった。酸素マスクの下で、荒い息をしながらしきりに口を動かし始めた。何を言わんとしているか、全く分らないのだが、弴翁は自分の片手を直哉の額にあて、もう一方の手で直哉の手を握り、
「うん、うん、そうかそうか。うん、うん」
幾度も幾度もそれを繰り返した。
本作では、志賀直哉というひとりの人物のキャラクターや信念が色濃く描かれているのはもちろん、大正から昭和に至るまでの時代情勢や文士たちの思想の変遷なども非常に詳細に綴られています。志賀直哉はもちろん、里見弴や武者小路実篤、谷崎潤一郎といった文士たちの人物像を知りたい人にとってもおすすめの1冊です。
おわりに
阿川弘之の最大の魅力は、戦争や軍生活、文人の素顔といった歴史的なテーマを取り扱いながらも、決して観念的な描写だけに終始せず、自身の実体験や資料などをふんだんに盛り込んだリアリティのある描写によって作品世界を創り上げている点にあります。
作中に用いられている旧仮名遣いやその硬質な文体のために、一見読みづらい印象を抱かれる方も多いかもしれませんが、阿川作品は決して難解で読み解きづらいものではありません。太平洋戦争前後の日本の空気や、偉人の人物像を詳細に知りたいという方には特におすすめの作家です。ぜひ、生誕から100年を迎える記念すべきこの年に、阿川弘之作品に手を伸ばしてみてください。
初出:P+D MAGAZINE(2020/12/02)

