村神様、大谷翔平、WBC……、注目度が高まる「野球」にまつわる本3選!

日本でも世界でも、熱い注目を集めている野球。実は、野球を扱った書物にも名作があるのです。野球そのものに興味が無いという方にもおすすめの、読み応え抜群な3作品を紹介します。
今年は野球がアメリカから伝来して150年を迎えたメモリアル・イヤーでした。メジャーリーグでの大谷翔平選手の二刀流、日本では村上宗隆選手の日本人年間ホームラン新記録、流行語大賞も「村神様」が選ばれて大々的なニュースになりました。来年開催されるWBCも注目が集まる野球。じつは日米の読書界でも「野球モノ」が小説やノンフィクションで伝統的に人気ジャンルなのです。そこで読めばエモい野球に材をとった名作3本を紹介します。野球に興味がない方も登場人物、物語に惹き込まれます!
マイケル・ルイス著 中山宥訳『マネー・ボール[完全版]』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)
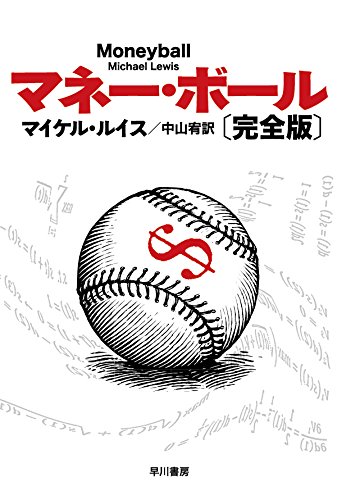
https://www.amazon.co.jp/dp/4150503877
ブラッド・ピット主演で2011年に映画化されて話題になった本作。野球界にセイバーメトリクス理論(註:野球においてデータを統計学的見地から客観的に分析し、選手の評価や戦略を考える分析手法)を持ち込んだ、オークランド・アスレチックスのゼネラル・マネージャー、ビリー・ビーンを描いたノンフィクションです。野球には打率・出塁率・防御率など様々な数値が選手を知る目安として使われています。が、ビリーは、そういった数値に「ノー」を唱え、セイバーメトリクス理論を導入するのです。我々が聞き慣れない、その理論の根拠はどういうものなのでしょう?
《打撃の評価は、選手が狙い通りに成功したケースや、得点を入れようとして入れたケースだけを対象にすべきである。ところが、これを認識している人間は驚くほど少ない。メジャーリーグが公式発表する攻撃データにしても、いちばん上に載っている(すなわち最も評価が高い)のは、得点が多いチームではなく、平均打率が高いチームだ。しかし当然ながら、攻撃の真の目的は打率を上げることだけではない》
理論を提唱したビル・ジェイムズ(註:野球に関する歴史や統計に関して広い影響力を持つアメリカ合衆国のスポーツライター)の言葉です。彼は既成の選手の力を推し量るパラメーター(註:結果に影響を与える、外部から投入される変動要素)をことごとく否定します。そのジェイムズはなんと食肉工場のガードマンが本業で、野球好きが高じ大リーグの全試合、全選手のデータを得ようと奔走、1978年に自分の論を自費出版で公開したツワモノなのです。奥さんを含め、周りから奇人変人扱いされたものの、毎年自己理論を更新することで、アメリカきっての知識人であるノーマン・メイラーや名脚本家のウィリアム・ゴールドマンに注目されます。
ジェイムズは打率より出塁率(打つよりフォアボールで塁に出ることが大事)、投球回数も投手によってまばらでデータ的に統一を欠く防御率より被安打、被本塁打数を重視しようと説いたのです。守備でボールを逸したり、落としたりするエラーも不問。なぜなら捕球をやり損なったということは、逆の見方ではボールに追いついていたのに、惜しくもミスしてしまったわけなので「問題なし」だという見解を示しました。
主人公のビリーは大学進学を希望しながらも、スカウトたちが褒めそやし、乗せられた結果、ドラフト一位でメジャーリーガーになった人物です。期待の新人だった彼は伸び悩んだ挙げ句、一流選手になれずに引退。その後はスカウトやマネジメント担当として働いてきました。球界の苦い挫折を味わった彼はスカウトがプロに求める基準(投げる、打つ、走る以外にルックスの良さも入れている)に疑問を抱き、巨額の資金によりチーム力が左右される球界の仕組み(強豪ヤンキースの予算は50億円。ビリーのアスレチックスは11億円)に対し不公平感を持っています。育てた新人選手を金持ち球団がさらっていくことに業を煮やした彼は、2002年にセイバーメトリクスを導入するのです。
開幕前にビリーは、腕の腱を痛めてキャッチャーが出来なくなったスコット・ハッテバーグやキャリアをピークアウトしたデビッド・ジャスティス、投げ方が異常に下手投げ過ぎて気持ち悪がられているチャド・ブラッドフォードを入団させます。球界や身内のスタッフからも「バカじゃないか」と評価されているのにビリーは出塁率や被安打・本塁打数を盾に譲りません。
最初は連戦連敗ですが、「これがダメだったら失業するだけ」と腹をくくったビリーは工夫(話術で安く欲しい選手を敵からトレードし、理論を選手たちに意識づけした)を重ねた結果、チームも勝ち星が増えていきます。そして球史に残る二十連勝を成し遂げるのです。腕に故障を持ち、守備の良し悪しを問わないことで一塁手にしたハッテバーグが奇跡の一打を放ちます。
「おれはやったぞ!」ではない。「おれたち、勝ったぞ!」そう叫びながら、五メートル走るごとに一歳若返り、本塁に戻ってきた時には少年になっていた。
優勝は逃すものの、ビリーはライバルチームであるボストン・レッドソックスからゼネラルマネージャーとしては破格の17億6千万円でオファーされるのですが……。
野球を金額や数値で眺める奇抜な構想、ビリーやハッテバーグ、ブラッドフォードといった登場人物の小気味良い活躍ぶりなどがノンフィクションであることを忘れさせる傑作です。
デイヴィッド・リッツ著 小菅正夫訳『ドジャース、ブルックリンに還る』(角川文庫・絶版)
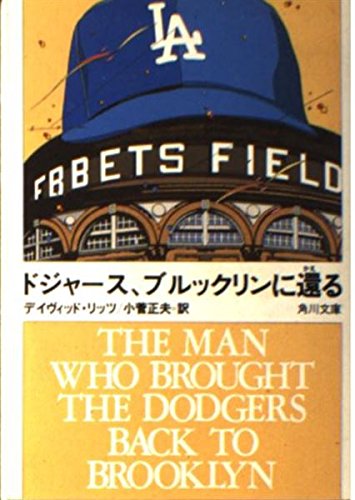
https://www.amazon.co.jp/dp/4042448011/
今もなお、野球を題材にしたエンタメ小説として内外の評価が高い本作。著者のリッツはスポーツ、音楽関係の本を発表している作家ですが邦訳はこの一冊のみです。ミュージシャンのレイ・チャールズの伝記は映画『レイ』として2004年に公開されています。リッツの特徴は対象へのファン心を熱く語るところで、本書も例外ではありません。ドジャース愛に溢れています。
ドジャースと一口に言っても、ブルックリン時代と現在のロサンゼルス時代では大きく違います。チーム創設は1883年。1940年代、名物オーナーのブランチ・リッキーに率いられたブルックリン・ドジャースはニューヨークの下町に本拠地エベッツ・フィールドを構え、ニューヨーク・ヤンキースと人気を二分していました。47年にはメジャー初の黒人選手であるジャッキー・ロビンソンを起用したことで知られています。有色人種への偏見がまだ色濃かった時代、数々の妨害に負けずリッキーとロビンソンは協力して野球の新時代を築き上げました。
そのドジャースも1957年に転機を迎えます。ブルックリン地区の再開発が決まり、ロサンゼルスに移転を余儀なくされたのです。このニュースは多くのブルックリンっ子たちを落胆させました。当時のオーナー、ウォルター・オマリーは人種差別容認の姿勢が濃い人物の上、冷徹なビジネス中心主義だったためにファンは「オマリーに売り飛ばされた」と激昂したそうです(当時のブルックリンの住民はドジャースファン以外でも「20世紀の悪人」と呼んだことでも衝撃の大きさが窺えます)。日本なら阪神タイガースが東京か千葉へ移転するというような状況でしょう。
この歴史を背景にリッツは「ロサンゼルスに去ったドジャースをブルックリンに呼び戻す小説を書こう」と思い立ったのです。主人公はドジャースをこよなく愛しているスクワットとボビー。スクワットはメジャーリーガーを目指すスラッガー、ボビーはニューヨークの名士の息子です。二人は空き地の野球で知り合い、高校卒業まで仲睦まじく成長します。ですが、メジャー入り直前でスクワットは酔ったボビーの悪ふざけが元で片脚をダメにしてしまうのです。時が流れ、宝石店で働くスクワットを、「時の億万長者」として全米を騒がせていたボビーがロサンゼルス・ドジャース買収に誘うのです。
「これこそがおれたちの待ちに待っていたものなんだ、スクワット。あんたとおれがまたいっしょにベースボール・ビジネスに復帰するというわけだよ!」
「おれにはわからんよ、坊や」頭を振り振り私は言った。
「おれにはわかってる。信用してくれ――」
「わかってる」あとを引きとって言いながら私は思わず笑った。「あんたはわれわれ二人を救うためにここに来たってんだろう」
スクワットは怪我で夢を諦めたとはいえ、実力のある野球人です。ロサンゼルスの球団を買った後は、弱体化したチームを再建するべくゼネラルマネージャーとして手腕をふるいます。けれど、オーナーであるボビーは今で言う、イーロン・マスクとドナルド・トランプを足したような人間で球団を話題にするのは得意なものの、かえってそれが仇になりチームの足を引っ張ります。ボビーの野球愛はロサンゼルスでは燃え上がらないようだと考えたスクワットは一計を案じるのです。ブルックリンへドジャースが還るニセの情報をマスコミに流そう、と。
この言葉――ドジャースが、ロサンゼルスを引き払い、ブルックリンへ帰る、という言葉を。なぜなら、それは事実だからだ。ああ、かくも美しく真実だからだ! ああ、かくも気ちがいじみていて完璧だからだ!
見事にマスコミ操作で乗せられてしまったボビーは親友にしてやられたと怒りながらも、ブルックリン帰還計画に夢中になるのです。エベッツ・フィールドを再建し、新生ブルックリン・ドジャースに相応しい、無名でもガッツのあるメンバーを加入させていきます。そして、いよいよ念願のワールドシリーズ進出! 全米の野球ファンの夢が叶う終盤へ差し掛かるのです。
奇妙な形をし薄汚れた茶色の煉瓦でできていて、見たところは要塞か、工場か、倉庫か、宮殿だ。強引に底に割り込み、街角の映画館さながら居心地よくおさまっている。へんてこな窓やアーチをくっつけ、数多くの旗をてっぺんにはためかせているが、まったくの話、そこには風格がある。(中略)この日、私たちは傾斜路づたいに左翼観覧席に出る。階段を上がり、黒く煤けた鉄梁の陰気臭い通路を抜け出し、ついに陽の光を目にし、フィールドを目にすると、背筋のゾクゾクするような興奮がよみがえり、初めての時のように胸がたかなる――すがすがしく広々とした外野とダイヤモンド、陽光きらめく青々とした芝生、内野のグラウンドはきれいに整備されている。
クライマックスでは小説の冒頭に訪れたエベッツ・フィールドに心は少年のままの中年男が球団を率いて帰還します。常勝ヤンキースに立ち向かうブルックリン・ドジャースの合言葉、WAITTILL NEXT YEAR! と共に。
皆さんにもサッカー、ラグビーなどのチームスポーツや、テニス、卓球選手、アーティストなど、「推し」がいるはず。そこには並々ならぬ想いがベースになっていることでしょう。そういった「想いのたけ」だけで想像を広げているのが本書なのです。何がなんでもドジャース推し! というファン心理に徹頭徹尾貫かれたファンタジー小説の復刊もまた、日本の野球小説好きたちの夢でもあるのでした。
ドリス・カーンズ・グッドウィン著 松井みどり訳『来年があるさ』(ベースボール・マガジン社)
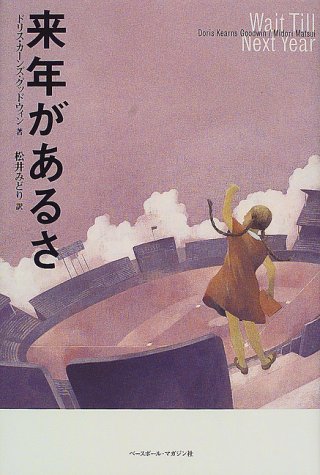
https://www.amazon.co.jp/dp/4583035772/
絶版品切になってしまった本に、時として「不朽の名作」が混じっている場合があります。この『来年があるさ』はまさに、その一冊に当たります。読後、「これって『赤毛のアン』がニューヨークに生まれていたら、こうなるよね!」と感じること請け合いです。
著者のグッドウィンはスティーヴン・スピルバーグ監督『リンカーン』の原作となった伝記を著し、ビル・クリントンやバラク・オバマといった近年のリベラル派大統領から尊敬されている歴史家です。彼女は自分が研究した歴代の指導者より、ジャッキー・ロビンソンやロイ・キャンパネラといったブルックリン・ドジャースの名選手に愛着を抱いていた自分を発見し、ドジャースの黄金時代と歩んだ少女時代を書くことにしました。
1949年、ニューヨーク州ロングアイランド。6歳のドリスが父親から真っ赤なスコアブックをプレゼントされるところから、物語は始まります。熱狂的ドジャース・ファンの父マイケルは、少年時代に両親と妹を失い、貧しいながらも努力して銀行検査官の職を得た、良き家庭人です。母ヘレンは16歳でマイケルと恋に落ちて結婚、三人の子を産んだ後は大病を患い、闘病を続けながら献身的に子育てをする知的な女性でした。長女のシャーロット、次女のジーンはどちらも周囲の人気者で看護師を目指しています。末っ子のドリスは仕事から帰った父親を喜ばせたい一心でラジオの野球中継に耳を傾け、試合を再現するためにスコアをつけることにします(註:当時はデーゲームが中心だった)。
だから私はこう信じて疑わなかった。
――パパが観そこなった試合を、この私が再現してあげられなければ、パパはわがドジャースの試合を「正しいやり方」で、つまり、「毎日欠かさず、あらゆるプレーを、イニングごとに」追うことが出来なくなってしまう。言いかえれば、この私はいなければ、野球好きのパパは一生、欲求不満ですごさなければならないんだわ――と。
おてんば娘(活動的なところから父親にバブルと呼ばれている)のドリスは思い込んだら「こう!」というタイプです。結果的には、物語の終わりであるドジャースがブルックリンを去る57年までの全試合を記録し続けるのです。
最初は父親のためでしたが、「いいかい、もうすぐ世界一きれいなものが見えてくるぞ」と連れられていったエベッツ・フィールドに魅せられ、ドジャースのジャッキー・ロビンソンやドン・ニューカムが彼女の永遠のヒーロー、野球というファンタジーの主人公に変わるのです。ファンタジーということは「悪党たち」も現れます。それはニューヨーク・ジャイアンツの面々。幼いドリスは敵チームのサル・マグリーらを「憎たらしいやつら」と呼ぶようになります。
いっぱしの野球少女になったドリスのご近所さんも野球ファンだらけ。みんな、ヨーロッパ各国から移民し、1930年代に起きた大恐慌を生き抜いた人々でした。ドリスの父親もそうだったように、つらい暮らしのはけ口、サンクチュアリが野球というエンタテインメントだったのです。当時は、野球場は「パーク」と呼ばれるだけに入場料も安く、庶民の憩いの場でした。近所の肉屋さんは全員揃ってジャイアンツ贔屓でチビのドジャース少女を「ぼろモップ(髪がボサボサだったから)」とからかい、お互いのチーム自慢を楽しみます。50年代のニューヨークには野球が傍にある暮らしがあったのでした。
さて、『赤毛のアン』のアン・シャーリーの親友にダイアナがいたように、ドリスにも心の友が出来ます。名前はエレイン、別リーグながらライバル視されるヤンキースの大ファンなのです。エレインが「ジャッキー・ロビンソンのどこがいいのよ」と言えば、「ビリー・マーチンなんか、声はかん高いし、体はまるで針金じゃないさ」などとやり合いながら、お互いのマニア度をリスペクトし合う仲です。
ドリスは近所に住む魔女のようなおばさんを恐れたり(実は庭造りにいそしむ独居老人で、ドリスは彼女の死後、あえて移民時代の質素な暮らしを続けた老婆を悼みます)、教会の教えを真に受けて列車事故現場に向かう冒険や神父に「敵チームのピッチャーなんか腕を折っちゃえ」などと祈ったことを懺悔したり、さまざまな体験をしていきます。
1951年10月3日、リーグ優勝をジャイアンツと競う決定戦、学校の昼休みに家に戻ったドリスは姉たちと母と一緒にラジオの前に陣取ります。午後は学校に戻らなくていいと、母もあっさり許すほどの大事な試合です。4対1でドジャースのリードで9回裏を迎えます。しかし、ジャイアンツは1点を返し、ワンアウト三塁のチャンスを掴むのです。
私は無意識に叫んでいた。
「ニューカムならピンチを切り抜けられるわ。降ろしちゃだめ!」
「もう限界よ」
母が反論する。
「アースキンを出すべきだわ」
しかし、マウンドまでの長い距離を歩き始めたのは、ラルフ・ブランカだった。
(中略:さらに試合は進み、一打サヨナラのピンチに)
「一巻の終わりだわ!」
シャーロットがぴしゃりと言う。
「ホームランを打って、ジャイアンツの勝ちね」
姉に食ってかかろうとしたその瞬間、私は両手を握りしめ、身を固くした。
トムソンがバットをブーンと振ったのだ。そのあと、一生忘れられない声が聞こえてきた。ジャイアンツのアナウンサー、ラス・ホッジスの、あの声が……。
「おーきな当たりです!……これはおそらく……間違いなく……!」
ジャイアンツに逆転サヨナラで優勝を奪われたドリスは「あまりの失意と屈辱感」で野球談義をしに〈ブリンマー肉店〉へ顔を出せないようになってしまいます。そんな時、意外な贈り物が届きます。
私あてに大きな赤いバラの花束が届いた。誰かから花束をプレゼントされるなんて、生まれて初めての経験だ。
〈ぼろモップ、お願いだから戻ってきてくれ〉
カードにはそう書いてあった。
〈君がいないと寂しいんだ。
――ブリンマー肉店の
友だち一同より――〉
花束をもらった感激から、ドジャース敗北の屈辱感と胸の痛みは、どこかへすっ飛んだ。
このように野球とつつましいコミュニティに囲まれて育つ彼女でしたが、アメリカの悲劇も目撃します。核爆弾の機密を敵国のソ連に漏洩させたローゼンバーグ夫妻の死刑や、共産主義の恐怖を煽り、仲間を告発させあい国を分断させたマッカーシー上院議員の「赤狩り」は少女の胸に暗い事実として刻まれていきます。
そして思春期を迎え、エレインとの友情も子ども時代を終えて大人の悩みも入り交じることになり変質していきます。さらには母の容態の悪化も……。それと同時にドジャースの選手たちも盛りを過ぎ、最後の輝きが迫ってくるのです。
1955年のワールドシリーズ。授業中、ラジオを密かに聴く生徒を情報源にクラス全員で試合の行方を追いかけます。そして念願のシリーズ制覇。喜びに湧くドリスでしたが、同じ日にティーンのカリスマだったジェームズ・ディーンが自動車事故で死ぬニュースに触れます。エレインとドリスは自分らの世代の代表を喪い、悲しみに暮れます。同時に少女期の終わりを無意識ながら感じるのです。
そして、ドジャースがロサンゼルスへ移転した58年に母ヘレンが逝去。エレインや近所もそれ以前に街を去っていたのですが、ついにドリスたちも引っ越しを決めるのです。最愛の妻を亡くした父は意気消沈し、アルコールに逃げ場を求めるようにもなっていました。その辛さを少しでも軽くするための引っ越しでした。荷造りをしながら、父と娘は語り合います。
「まだためこんでいるのかい?」
ドジャースのスコアブックの山を見ながら、父が言う。
「1949年からずーっととってあるわ。父さんが初めてスコアブックをくれたときから」
「あと一歩、という年ばかりだったなぁ。何度も何度も優勝を逃したっけ」
父が頭を振りながら言う。
「覚えてるかい。よく2人で励ましあったじゃないか。『戦い続けていれば、きっといつかは勝つさ』って。現に優勝したじゃないか。――今のわが家にも、同じことが求められてるのさ。きっと」
数カ月ぶりに、父が笑顔を見せた。
ドジャースの悲願をボビー・トムソンに打ち砕かれたあと、ブルックリンのとある会社が作ったカレンダーが、埃にまみれて転がっていた。父をそれを指さして言う。
「ほら、あれをごらん」
そこには、大きな黒い文字で、例の言葉が記されていた。
〈来年があるさ〉
野球で結びついた家族、友人、コミュニティをいきいきと描きながら、私たちにも共通する「過ぎ去った絆や思い出」を素敵な文章で綴った『来年があるさ』。ここには普遍的な文学のエモーションが溢れています。
野球ファンならずとも、読書ファンが復刻を望む「成長物語」の名著です。
おわりに
野球に材をとったノンフィクションや小説は、今回挙げた三冊以外にも名作が多くあります(山際淳司『スローカーブを、もう一球』(角川文庫)など)。また野球のみならず、皆さんの「推し」競技を扱った本を探してみてはいかがでしょう? スポーツの感動が一層深まると思います。
初出:P+D MAGAZINE(2022/12/23)

