団地を描いた映画・小説から浮かび上がる「夢・エロス・犯罪」【団地の今昔物語#1】
コンクリートの壁の息苦しさ
若松孝二監督『壁の中の秘事』
他方で同じ60年代に、団地に「あこがれの住まい」とは正反対のイメージのもとで捉える映画も登場します。そこで描かれるのは、コンクリートの部屋の閉鎖性に象徴される、人間性を疎外する〈牢獄〉のイメージです。
「ダンチ族」という言葉がはじめて登場した1958年の『週刊朝日』の記事「新しい庶民“ダンチ族”」のなかでは、団地住人へのアンケート調査をもとに、団地生活の否定的な側面として、部屋が狭いこと、近所付き合いが少ないことが指摘されていました。こういった団地生活の実感も人間性疎外のイメージと結びついているといえるでしょう。
こういった暗いトーンで団地を撮った作品として、若松孝二監督の『壁の中の秘事』(1965年)をあげることができます。
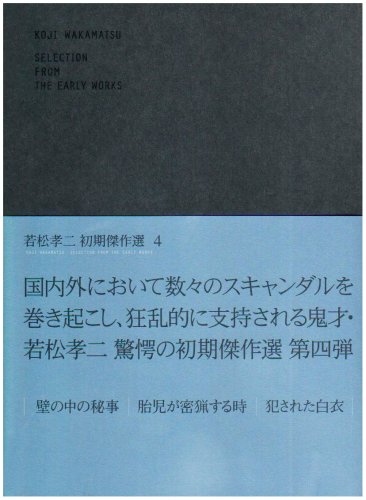
出典:http://www.amazon.co.jp/dp/B000B5M7SM
この作品では、団地に住む女・山部信子と、向かいの棟の団地に住む浪人生の内田誠の二人を中心に団地生活が描かれます。山部信子は現在団地の住居で夫と二人で暮らしていますが、学生のときには平和運動に加わった経歴をもっています。このかつての左翼女学生は、今や闘争の場を失い、団地の平板な日常のなかに専業主婦として収まっています。そんな信子の団地生活の中心には不倫があります。相手は平和運動の同志であり恋人であった男です。団地と不倫という組み合わせは、後の日活ロマンポルノ「団地妻」シリーズ(第一作は71年公開)を先取りしています。

Photo By halfrain
ただ『壁の中の秘事』では、団地と性というテーマは濃厚な政治性と絡みついて現れます。60年の日米安保闘争の敗北とそれを担った左翼活動家の日常への回帰という問題です。つまり、非日常的な政治運動に関わっていた者たちが運動に敗れ、逃げ込む先が団地なのです。ですから、団地は政治的なものとの関わりを絶たれた孤立した空間として、耐えがたい日常が待つ場として描かれます。
世相はベトナム戦争とそれへの抗議活動で盛り上がっていますが、団地にはそのことは新聞記事やテレビニュースを通して、まるで別世界の出来事のように伝えられます。この映画が団地空間のなかだけで完結し、団地の外部が映されないことも団地という場が世界から隔絶された閉鎖空間であることを物語っています。
そこにあるのは単調な反復としての生活だけです。主婦は家事をこなし、空いた時間をセックスで埋め、浪人生は受験勉強を強いられ、気詰まりを自慰で紛らわせる生活です。だからこそ浪人生は勉強部屋に仰向けになって「ああ、ベトナム行きたいなあ」と呟かざるをえないのです。
信子と愛人の団地での情交のシーンには、学生時代の信子と愛人の回想が重ねられます。かつての二人はスターリンの肖像に眺められながら抱き合っています。愛人の男は背中に原爆によって負ったケロイド状の傷跡があります。信子にとって、被爆者としての生い立ちを証すケロイドは彼に平和運動の闘士として特別なオーラを纏わせるのです。
女は団地で愛人に抱かれながら、平和運動にコミットする高揚感のなかで彼に抱かれていた往時の記憶にしがみついています。信子は団地生活の閉塞感から逃避するために、不倫と過去の記憶へと走るのです。彼女は夫に不平をこぼします。
「あなた、私の毎日がどんなだか知っているの?」
「毎日毎日、壁の中に閉じこめられて、いつ崩れるかわからないような不安のなかにいるのに。」
「あなた、ちっとも私のことかまってくれない。」
他方で、浪人の内田誠も予備校にもいかずに団地で自閉しています。家の中では家族の濃厚な気配が閉鎖空間をより狭苦しく耐えがたいものにしています。そんな彼が閉塞から脱出する回路として見出すのは「窓」です。青年は勉強部屋の窓から望遠鏡で向かいの団地の棟を覗きます。浪人生の乾いた視線に映るのは、信子と愛人の密通の現場です。
映画の終盤、誠は信子の部屋を訪れ、不義の現場を覗き見たことを告げます。恐喝者めいた態度で信子に向かう誠ですが、彼が望んでいるのは不倫をネタにした脅迫ではなく、むしろ自分の抱える閉塞感を理解し、共有してくれることのように見えます。誠は成り行きから信子とベッドで体を重ねることになりますが、経験不足から情交を果たすことができません。彼は自分の不能を信子に馬鹿にされたと思い、突発的にナイフで女を刺し殺してしまいます。
団地の閉塞感を主題にした物語は、団地青年による団地妻刺殺というスキャンダラスなラストによって閉じます。この結末は、団地住民の孤立と相互不信、団地における人間関係の不全を暗示しているといえるでしょう。そして、全編を通じて繰り返し挿入されている硬質で表情のない団地の外観やコンクリートの壁は、〈監獄〉〈牢獄〉のイメージを喚起させ、団地における人間の孤立と疎外を鮮明に印象づけています。
犯罪の温床? 孤独者の隠れ家?
横溝正史『白と黒』
『壁の中の秘事』でも団地が犯罪と結びつく場として造形されていましたが、団地が犯罪の舞台となるというイメージをいち早く描きあげたのは小説、それも探偵小説でした。横溝正史による金田一耕助シリーズの第十八作にあたる『白と黒』という作品です。この小説は、1957年11月から1958年10月の「日刊スポーツ」紙上の連載小説として世に出ました。おそらく日本文学のなかで最も早く書かれた団地を舞台とした小説といえるでしょう。
この作品が、探偵小説という大衆的な文学ジャンルで書かれたこと、しかもスポーツ新聞という戦後につくられた大衆娯楽メディアに掲載されたことは、高度経済成長期生まれの団地を描いた最初の小説の出自として、いかにもふさわしく感じられます。
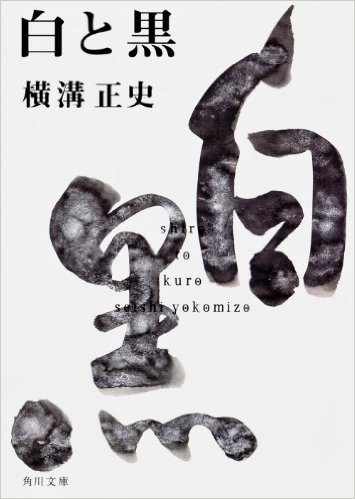
出典:http://www.amazon.co.jp/dp/404130413X
『白と黒』では、「日の出団地」という団地が舞台となります。この団地で、住民の私的でセクシャルな秘密を暴露する怪文書が出回る事件が起こります。この怪文書事件の捜査依頼をうけて探偵金田一耕助が日の出団地にやってくるのです。探偵が訪れた日の出団地は、まだ新しい棟の建設が進行しています。そして、この新しい建設中の棟で謎の女の死体が発見されます。死体が発見されるのは団地特有の構造物である「ダスター・シュート」のなかです。テクストでは団地を初めて見る探偵の視点からこの構造物が説明されます。
この二十号館の北側には入り口が五つある。その入り口を入るとすぐなかに階段があって、その階段はジグザグと稲妻型に折り曲がりながら五階まで走っている。その階段の左右に五つづつ、すなわち十世帯が住めるように部屋がくばられている。/ダスター・シュートは入り口と入り口の中間に位しており、そのシュートを中心とする左右の一世帯がそこへゴミを捨てるのだから、ガッチリとしたコンクリートづくりの箱で、そこから五階まで煙突のように、これまたコンクリートでかためた縦孔(たてあな)が走っており、それをとおて各階からゴミが落ちてくる仕掛けになっている。
(横溝正史『白と黒』角川文庫、1978年、41頁)
このダスター・シュートの地上のゴミ箱のなかに、婦人の死体が頭のほうから突っ込まれて発見されます。しかも、ここに探偵小説的な趣向が織り込まれます。発見される死体は、熱されたタールで顔面をつぶされ、「顔のない」死体となっているのです。当該の棟の屋上では事件当時、タール敷きの作業がおこなわれていました。屋上にあったタールを融かすための釜に何者かによって孔が空けられ、そこから煮えたぎるタールがダスター・シュートの縦孔をつたってゴミ箱の死体の顔の上に落ち、「顔のない」死体をつくりだしたというのです。
ちなみに、多くの団地でダスター・シュートはほとんど用いられることもなく使用禁止となったようです。ゴミの分別が義務化されたこと、高温多湿の日本ではゴミが腐敗して衛生面で問題があったことなどが使用取りやめの理由とされています。現在、集合住宅が造られるさいにはダスター・シュートは設置されることはありません。ダスター・シュートつきの団地は、公団建設ピーク期に建てられた団地に特有の年代物の光景であるといえるでしょう。

団地に現れる顔のない死体というモチーフは、被害者が団地にたどり着いた経過と考え合わせたとき、団地という場所の意味を照射するものとなります。被害者となった女性は、団地に隣接する名店街の一角で「たんぽぽ」という洋裁店を営む謎めいた美人婦人で、団地住民からは「たんぽぽのマダム」と呼ばれています。彼女は店舗を借りる際に偽名をつかっており、周囲の人びとにも自身の来歴を語ろうとしません。
しかし、物語が進展するにつれ、彼女が団地に来た経緯が明らかになります。マダムは以前神戸で夫と娘のいる生活をおくっていましたが、ある個人的な理由から結婚生活を解消しようと欲し、偽装のヨット転覆事故を計画します。偽装工作に成功し、事故で死んだ無籍者となった彼女は、自らの本名と過去を捨て新たな人生をおくるために団地へと流れ着いたのでした。
そして、小説最終盤には、マダムが偽装事故を画策した理由が同姓愛性向にあったことが明らかになります。同姓愛者が世を忍んで辿りつく場が団地だったのです。ちなみに、マダムの死体の顔がタールでつぶされていたのは、彼女が生前語っていた、死に際に及んでも自身の出自を隠しとおす死に方をするという意志を貫徹するためにマダムの隠れた協力者がおこなった工作であることが判明します。
ここで、過去を抹消して生きようとする女が逃げ込む場所が団地であるのは示唆的です。団地は氏素性の知れない過去を共有しない者たちが集まります。匿名性につつまれる団地という場は、秘密を保持したい孤独者にとって絶好の隠れ家となるでしょう。また、その秘密が同姓愛という非常に内密なセクシャリティに関わるものであることは、団地という場が私的なものを担保してくれる場であることを鋭く捉えています(この点は後に詳述します)。
このように見るならば、性の秘密を隠すために顔を灼熱のタールでつぶされた「顔のない」死体の形象は、団地に集う人びとの匿名性、個人が抱える歴史の不透明性といった特徴と通じ合うところがあるように思えます。このことは、作家がテクストに組み入れている以下の「社会心理学」的考察とも響きあっています。
人間にはいろいろさまざまなタイプがある。社交性にとみ、たやすくその環境に順応しうるタイプの人間もあれば、それに反して、容易に他をいれず、頑固に孤独を守ろうとするタイプの人間もいる。/団地のような共同社会では、後者に属するがごときソリチュード(孤独)な人間は、そこに住むことだけでも苦痛そのもののように考えられがちだが、かならずしもそうとばかりはいえない。それは団地というものは多くの家庭の集合体ではあるけれど、ひとつひとつの家庭は鍵のかかる鉄の扉によって、げんじゅうに防衛されているからである。これは従来の日本にはほとんどなかったタイプの住居ではないか。/しかし、共同社会といってもかれらはそこで、生活のかてをえているわけではない。大げさにいえばそこはかれらのネグラに過ぎない。朝起きると男の大部分と女の何パーセントかはそこを出て、それぞれちがった職場へ働きにいく、そして、夕方かえってくると、鉄の扉と厚いコンクリートの壁に守られて、外部から遮断された生活のなかに閉じこもることができるのだ。/ましてやこの日の出団地のように、まだ十分に完成しておらず、どの団地にもある集会所さえ出来ていない現状では、サークル活動なども目下よりより評議中という段階なのだから、もしそのひとが孤独を愛するならば、十分孤独のなかに閉じこもることができるのである。
(横溝正史『白と黒』、63−64頁)
『白と黒』が描き出すのは、さまざまな秘密を抱える人間たち匿名性をもとめて蝟集する団地です。その団地の匿名性は、一方で個人的来歴の不透明性ゆえに犯罪を招き込む可能性をはらむ場となります。しかし他方で、同じ匿名性は、「ソリチュード(孤独)な人間」たちにとって、社会の様々なしがらみから身をかくまう隠れ家ともなりうるのです。
(次ページ:拷問、監禁、集団売春!? 淫らに暴発する団地の性)

