滞米こじらせ日記~愛しきダメな隣人たち~ 桐江キミコ 第6話 太った火曜日①
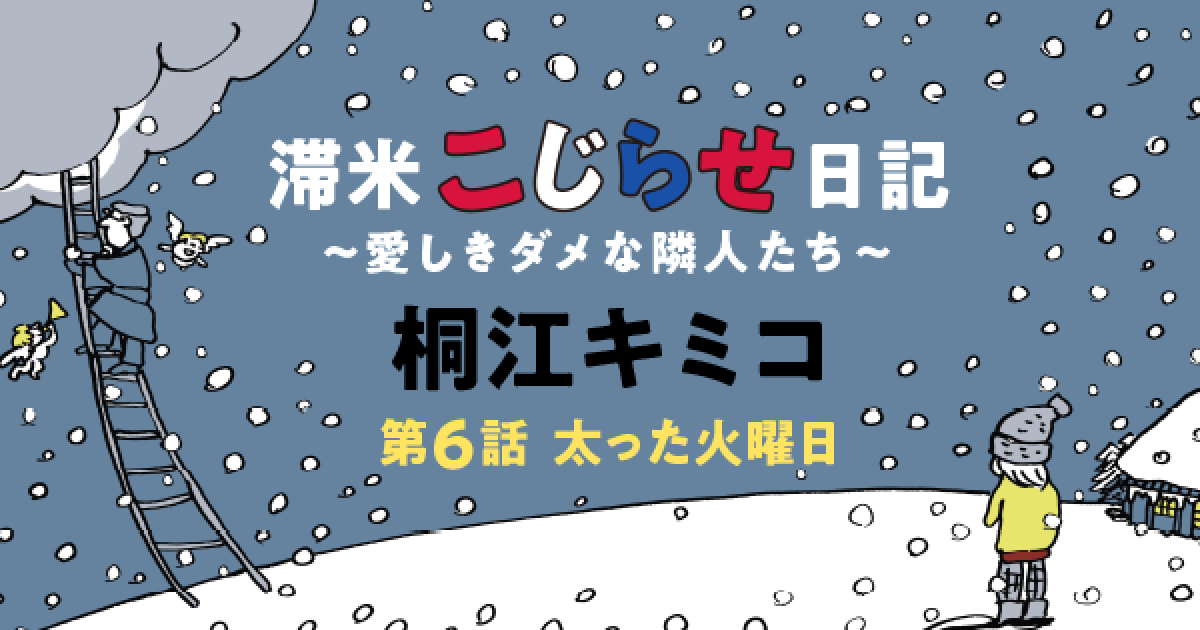
ハーレムの子供保護センターにいた日本人女性も、
いろいろな心痛を抱えて生きていた。
東京のテレビ局で働いていたころ、職場に手作りのサンドイッチを必ず持って来て、サンドイッチを食べながら、淡々と仕事をしていた、やや年配の人がいた。堅実だなと思ったのは、普通は社員食堂で食べるのに、その人は手作りサンドイッチを持ってきただけでなく、それを食パンの包装袋に入れて持ってきたことだった。どんなにあたりがガサガサしても、その同僚の周りの空気は、まるで瀞(とろ)のように静かだった。そして、同僚は、その空気の中、失礼なたとえだが、まるでカメが沼をゆっくりと泳いでいるみたいな感じで、仕事をしていた。
別に、いっしょに職場の外で何かしたということでもないのに、なぜか、ある日、同僚は、ぽろっと昔のことを話してくれた。もう30年以上前のこと、同僚が夫とまだ1歳に満たない赤ちゃんと雪深い山奥に住んでいたころのことだった。同僚は、家の後ろにある畑で野菜を育て、ほぼ自給自足の生活をしていたらしい。
ある冬の晩、隣の家に夕飯に招かれて家族ぐるみで出かけた。しかし、ちょっとした用事があって、同僚だけ家に戻った。そのとき、雪ずれのささーっという音が聞こえたので、外へ出てみると、さっきまであった隣家がなだれで流されてしまっている。同僚の時間は、その瞬間、止まった。夫と子供と隣人をのみ込んでしまった一面の雪野原を目にしたときの同僚の気持ちなんて、陳腐なことばでは表せないほどのものだったに違いない。助けを待っている、永遠と思われるほど長い長い間、深々と降り続ける雪の中を、同僚は、ひょっとしたらまだ生きているかもしれない、雪の下に埋もれたままの夫と子供、そして隣人夫婦を救い出そうと、雪をかき分けようとしたのかもしれない。でも、それが無駄な努力だと知るのに時間はかからなかったことだろう。そのときのことは記憶がぷっつり途絶えて何も覚えていない、と、同僚は、壁にずらりと並ぶモニター画面がゆれ、人々がどたばた動き回り、ニュース原稿が飛び交う、慌ただしい仕事場で、言った。
夫と子供をほんの一瞬の間に失ってからも、同僚は生き続け、時が流れ、20年たったころ、仲間が開いてくれたねぎらいの会に同僚は招かれて行った。なごやかな雰囲気の中で集いは進み、やがて仲間の前に立って挨拶をしようとしたときのことだった、同僚は、自分でもまったく予想もしていなかったのに、もう昔のことはすっかり消化しきってしまったと思っていたのに、なのに、いきなり、仲間の前でつっぷして、声を上げて子供みたいにわんわん泣いて、泣きやめられなかった、と言った。ぷっつり途絶えてしまった記憶の底に封じ込んでおいたはずの思いが、一気に噴き出してしまったのだろう。
同僚が最期を看取(みと)ることになったのは、実のお母さんでなく、ずっといっしょに暮らした義理のお母さんだったというのも、わかる気がする。子と孫を失った悲しみと、子と夫を失った悲しみという、強烈な体験を共有した2人は、おそらく当事者でしかわからない、ことばでは表しきれない思いが強い絆(きずな)になったのだろうと思う。
世の中には壮絶な人生があちこちにごろごろころがっている。そんな人生を見聞きするとき、自分の人生なんて、自分にとっては悲しいことや辛(つら)いことがじゅうぶんすぎるほどあったし、なんとかして時計の針を戻したいと思うできごとも起こったけれど、So what?(だから何なの)と言われれば、それひとことですんでしまう、取り立ててドラマのない、平穏無事な人生を、ふわふわあくびしたり、ふーたら不平を言ったりしながらここまでやって来た。我ながら本当に平坦(へいたん)な人生を歩んできたなあと思う。
- 1
- 2






