【村上春樹ライブラリー開館】村上春樹ワールドが出来上がるまで

世界中で愛され、関心を集め続ける作家・村上春樹。出身校の早稲田大学に資料の寄託・寄贈したことがきっかけで、早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)が開館。今回は、それを記念し、村上春樹が、自分自身について語るエッセイをご紹介します。
1979年に『風の歌を聴け』で、第22回群像新人文学賞を受賞してデビューを果たして以来、たくさんの物語を世に送り出してきた村上春樹。軽妙で洒脱な描写や、個性的な比喩で、人々を魅了してきました。そんな村上春樹が学生時代に通っていた坪内博士記念演劇博物館に隣接するキャンパス内の4号館をリニューアルしたのが、開館した早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)です。
村上春樹は「この場所が、文学や文化の風通しの良い国際的交流・交換の場になってくれればと願っています」と設立を記念して行われた記者会見で話しました。館内は地下、1階、2階まであり、多数の村上春樹作品(翻訳本含む)や貴重な初版本などが置かれているギャラリーラウンジ、村上春樹の書斎を再現したエリア、ジャズ好きとしても知られる村上春樹が収集したレコードの展示など、村上春樹ファンには堪らない空間となっています。
これまで、公の場にあまり姿を現してこなかった村上春樹。小説や作風については知っているけれど、村上春樹自身については、よく分からないという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、村上春樹が小説家になるまでの軌跡やライフスタイルを、エッセイから紐解いていきます。
村上春樹が小説家になったきっかけ
村上春樹は、1949年1月12日に京都で生まれました。中学生のときから、音楽を浴びるように聴き、大量の本を読んでいたそうです。その後、早稲田大学に進学をし、在学中に結婚します。アルバイトを掛け持ちしながら貯めたお金と、借金を元手に、ジャズ喫茶「ピーター・キャット」を開業。お店の切り盛りをしながら7年をかけて大学を卒業しました。
その後も、借金を返すため、寝る間も惜しんで朝から晩まで働き続けました。そんな忙しい中でも、本を読み、音楽を聞くことは、村上春樹にとって最大の喜びであり続けたと言います。(参考書籍:『職業としての小説家』)
そうして働きづめの20代も終わりが近づき、30歳を目前に控えた時のこと。よく晴れた日の午後、神宮球場で行われた野球の対戦をひとり外野席で寝転んで見ていました。バットがボールに当たる良い音が神宮球場に響き渡った、そのとき、何の脈路も根拠もなく、ふと「そうだ、僕にも小説が書けるかもしれない」と思います。
試合が終わったあと、さっそく原稿用紙と万年筆を買いに行きました。そして、お店の仕事が終わった後は、台所のテーブルに向かって夜明けまで小説を書きました。その後、おおよそ半年をかけて出来たのがデビュー作『風の歌を聴け』です。
物書きのプロセスと物語の舞台裏『職業としての小説家』
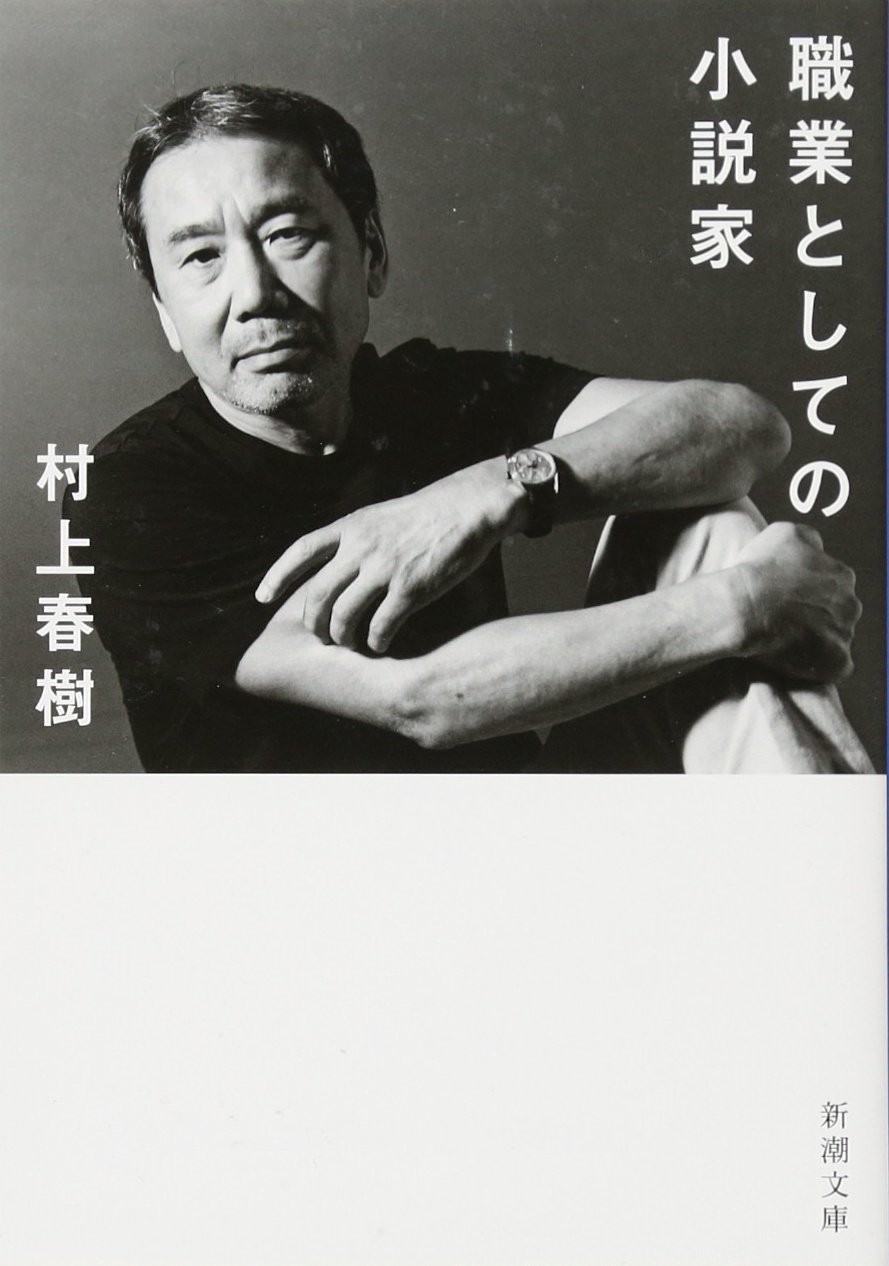
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101001693
「小説家の多くは--もちろんすべてではありませんが--円満な人格と公正な視野を持ち合わせているとは言いがたい人々です」
村上春樹は、この作品の中で、自身の考える職業としての「小説家」を、自身の経験をもとに深く推測しています。
まず、小説家は、頭の回転が早い人や聡明な人には向いていないと村上春樹は考えます。その理由について、このように綴りました。
小説を書くというのは、とにかく実に効率の悪い作業なのです。それは「たとえば」を繰り返す作業です。(中略)その「それはたとえばこういうことなんですよ」というのがどこまでも延々と続いていくわけです。かぎりのないパラフレーズの連鎖です。開けても開けても、中より小さな人形が出てくるロシアの人形みたいなものです。これほど効率の悪い、回りくどい作業はほかにはあまりないんじゃないでしょうか。
つぎに、長期間にも及ぶ孤独を支える強靭な忍耐力。これが小説家という職業人としての資質、資格なのではないかと推測しています。なぜなら、小説を書くというのは、ひとりきりで部屋にこもり、ひたすら文章をいじり、丸一日かけて、創り上げていく孤独な作業だからです。さらに、ようやく出来た1行の文章に対し誰かが「よくやった」と褒めてくれるわけでもなく、ひとりで納得し黙って頷くだけです。
長編小説ともなれば、そのような細かい密室での仕事が来る日も来る日も続きます。ほとんど果てしなく続きます。この手の作業がもともと性にあった人でないと、あるいはそれほど苦にしない人でないと、とても長く続けられるものではありません。
42年以上にわたって専業作家として、小説を書き続けてきた村上春樹だから見えてくる「小説家」という姿。本書には、そのほかにもオリジナリティーについて、どのようにして長編小説を書き上げていくのか、細かく説明をしています。物書きをしている人には、実用的な内容であり、そうでない人にとっても壮大な物語の舞台裏がのぞける貴重なエッセイです。
本書を読み始めると普段の村上春樹らしい文体でないことに気がつきます。これについて村上春樹は、「小さなホールで、だいたい30人から40人くらいの人が僕の目の前に座っていると仮定し、その人たちにできるだけ親密な口調で語りかけるという設定」とあとがきで説明しています。
小説を書くことについてだけでなく、デビューのきっかけとなった『風の歌を聴け』の裏話も収録されています。
春の日曜日の朝、編集者から「村上さんの応募された小説が、新人賞の最終選考に残りました」という電話がありました。電話に出たとき、寝ぼけていて、受話器をとったものの、相手が何を伝えようとしていたのか理解できなかったそうです。なぜなら、神宮球場で、小説が書けるかもしれないと思った時から、すでに1年近くが経っていたからです。原稿を送ったことすらも、すっかり忘れていました。原稿のコピーさえも残していなかった当時を振り返り、こう話しています。
もし最終選考に残っていなかったら、その作品はどこかに永遠に消えてなくなってしまっていたはずです。そして僕はもう小説なんて二度と書いていなかったかもしれません。人生というのは、考えてみれば不思議なものです
そのほか、小説家としてデビューする前の苦労話や、たびたび名前を出され注目を浴びてしまう文学賞についてなどのエピソードも収録されています。村上春樹が築き上げた小説家としての独自のスタイル。どのようにしてできあがったのかが、垣間見られる一冊です。
道路から学ぶ『走ることについて語るときに僕の語ること 』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/416369580X/
タイトルは、村上春樹が敬愛し、翻訳も担当した、レイモンド・カーヴァーの短編集『愛について語るときに我々の語ること』に由来しています。
「走る」ということだけではなく、村上春樹がこれまで走ってきた世界各国の様子や、ライフスタイルなども綴られている本作。村上春樹の作風は苦手という人にもおすすめのエッセイです。
走ることについて正直に書くことは、僕と言う人間について(ある程度)正直に書くことでもあった。途中からそれに気がついた。だからこの本を、ランニングと言う行為を軸にした1種の「メモワール」として読んでいただいてもさしつかえないと思う。
『風の歌を聴け』でデビューしたあとも、執筆作業をしながらジャズ喫茶の経営も続けていた村上春樹。しかし、次第に長編小説を書いてみたいという気持ちが大きくなり、執筆に集中できる環境を整えるため、繁盛していたお店を思い切って閉めることにします。
その後、長編小説の執筆作業に向けて本格的に環境を見直すことにしました。まず、ジャズ喫茶を経営していたときの夜型の生活を、朝型に切り替え、次に机で執筆しているとついつい吸いすぎてしまうたばこをやめ、健康のために走ることにしたのです。
そうして、日常的に走り始めたのが『羊をめぐる冒険』を書き終えて、専業作家として生きていくと決めた時でした。
こうして、走る小説家としても知られることになった村上春樹。走っているときにどんなことを考えているのかと、よく質問をされるそうです。それについて、このように話しています。
僕は走りながら、ただ走っている。(中略)走っているときに頭に浮かぶ考えは、空の雲に似ている。いろんなかたちの、いろんな大きさの雲。それらはやってきて、ただ過ぎ去っていく。でも空はあくまで空のままだ。雲はただのゲストに過ぎない。それは通り過ぎて消えていくものだ。そして空だけが残る。空とは、存在すると同時に存在しないものだ。実体であると同時に実体では無いものだ。僕らはそのような茫然とした容物の存在する様子を、ただあるがままに受け入れ、呑み込んでいくしかない。
よほどのことがない限り、どんなに忙しくても必ず走るようにしているそうです。その理由について、こう話しています。
日々走る事は僕にとっての生命線のようなもので、忙しいからといって手を抜いたり、やめたりするわけにはいかない。もし忙しいからというだけで走るのをやめたら、間違いなく一生走れなくなってしまう。走り続けるための理由はほんの少ししかないけれど、走るのをやめるための理由なら大型トラックいっぱいぶんはあるからだ。僕らにできるのは、その「ほんの少しの理由」をひとつひとつ大事に磨き続けることだけだ。
長い年月、物語を書き続けるということは容易いことではありません。同時に走り続けることは、村上春樹にとって、小説を書くうえでの大切なプロセスでした。そのことについて、村上春樹は、このように述べています。
僕は小説を書くことについての多くを、道路を毎朝走る事から学んできた。(中略)もし僕が小説家になったとき、思い立って長距離を走り始めなかったとしたら、僕の書いている作品は、今あるものとは少なからず違ったものになっていたのではないかという気がする。(中略)いずれにせよ、ここまで休むことなく走り続けてきてよかったなと思う。なぜなら、僕は自分が今書いている小説が、自分でも好きだからだ。
日課のランニングだけではなく、世界各地のフルマラソンやトライアスロン・レースにも挑戦をしてきた村上春樹。その姿から、何かを学ばずにはいられない一冊です。
■おわりに
「春樹節」と称されるほど、独自のスタイルが確立した文章で人々を物語に引き込んでいく村上春樹作品。そんなオリジナリティ溢れる文体を作り出した村上春樹が、日本を代表する作家になるまで、どのように生きてきたのか、いかにして小説家という職業に向き合っているのかが分かる興味深いエッセイです。
村上春樹は、世間が抱く「小説家」のイメージをこのように話しています。
自堕落な生活を送り、家庭なんか顧みず、(中略)酒に溺れ、女に溺れ、とにかく好き放題なことをして、そのような破綻と混沌の中から文学を生み出す反社会的文士——そんなクラシックな小説家像を、ひょっとして世間の人々はいまだに心の中で期待しているのではないだろうか。
(『職業としての小説家』より)
そんな「小説家」像とは異なる村上春樹の生き方。良い物語を書くため、どこまでも努力を惜しまずストイックに励む姿勢からは、生きるヒントも得られます。村上春樹を好きだという人は勿論のこと、村上春樹の独特な作風が苦手だという人、小説自体は興味がないという人にもぜひ手にとって読んでもらいたいエッセイです。
初出:P+D MAGAZINE(2021/10/08)

