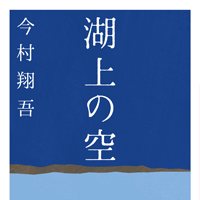思い出の味 ◈ 今村翔吾

かつて私は好物でもない食材を、必死で追い求める日々を過ごした。
京都府の南端、相楽郡和束町と謂う地がある。面積は、東京二十三区で一番大きい大田区よりも広い約六十五㎢ 。人口は約四千人。山河が大半を占め、上質な茶が採れるということ以外特筆することのない田舎町。ここが父の生まれ故郷であった。夏になると、父は車で二十分かけ、この地に川遊びに連れて行ってくれた。母が入院していた時などは、本当に飽きもせず毎日。拙著『鬼煙管 羽州ぼろ鳶組』で描いた父子の川の光景もこの日々が元になっている。
幼い私には夢があった。ヤスと呼ぶ漁具で、鮎を突いて獲ることである。和束の清流には鮎が沢山おり、夏には大人も挙ってこれを追う。だがヤスの扱いが危険である為、小学四年生まで父に禁じられていた。私は筌で小魚を獲りつつ、その日を心待ちにしていた。
五年生になってからは、もうがむしゃらに追いかけた。しかし川の流れが速く、鮎も絶望的なほど高速で泳ぐ。父は容易く鮎を獲るが、私は夏が終わっても一匹も突けなかった。父の獲った鮎を食べても旨いと感じない。むしろ腸などは子どもの私にとっては苦いだけ。つまり食べたくもないものを夢中で追ったのだ。
遂にその時が訪れたのは三度目の夏だった。穂先に鮎が刺さっていた時、私は興奮を抑えきれず、父も感嘆の声を上げた。話の流れからすれば、この時の鮎は旨かったとしたほうが収まりがよい。しかし残念ながら、やはりそうは思わなかった。私は父に大人と認めて欲しいが為、鮎を追っていたらしい。夏の終わり、「来年も来よう」と父子で川を後にしたが、中学一年生の私は何となく、これが最後ではないかと直感して、二度三度振り返ったのを覚えている。父は今尚健在だが、果たしてその通りになっている。父と川を訪れるのは、私が大人になる為の儀式であったかと思えるほどに。
夏の終わり鮎を食す。舌でほどけるようなきめの細かい白身、そしてほろ苦い腸の味も旨いと思うようになった。そんな時、決まって思い出すのは川からの帰路、茜を借景にするほど存在感を放つ、広く大きな父の背である。