夏目漱石の”日本初”まとめ【没後100周年】

言わずとしれた日本文学の巨人、夏目漱石。彼が残した様々な「日本初」を題材に、その後世への影響力を探ります。
夏目漱石が世を去ってから100年の歳月が経った2016年。今年は没後100年、来年は生誕150年と記念イヤーが続くこともあり、漱石に関する番組の放送や記念展が次々と企画されています。
文学ファンならずとも、日本人で漱石の名前を知らない人はまずいません。漱石が近代文学を確立した功績は計り知れず、また後世の文学や思想に多大な影響を与えていることからもわかるとおり、日本を代表する文学の巨人と言っても過言ではないのです。
今回はそんな漱石に関係する「日本初」について、広く知られているものから意外と知られていないものまでをご紹介します。
日本初の帝大英文科◯◯から◯◯になった漱石

漱石は最初から作家として活動をしていたわけではありません。23歳で帝国大学(現在の東京大学)英文科に入学した後、大学院に籍を置きながら教師として働いていました。更に1年間という短い期間に愛媛の中学校に赴任していた経験は、「坊っちゃん」創作時のヒントとなっています。その後、英文学研究をより進めるため、漱石は文部省のイギリス留学生としてロンドンに渡ります。
このロンドン留学で“近代化への疑問”を感じることとなった漱石は、神経衰弱に陥りながらも1903年に帰国し、帝国大学英文科の講師を担当します。それまでは外国人が担当していた英文科の講師として、漱石は日本人で初めて教鞭を振るうこととなったのです。
前任は怪奇文学で知られる小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。大人気だった講師の後任というプレッシャーに悩む漱石を歓迎する雰囲気は無いどころか、生徒には「田舎高等学校教授あがり」と陰口をたたかれます。授業が厳しかった漱石と生徒たちとの間に生じた溝は埋まらないと思われましたが、シェイクスピアの作品について論じた講義が大評判になり、他の学科の生徒も聴講にやってくるほど大反響を呼ぶこととなるのでした。
そして講師を務める傍ら、高浜虚子の勧めから「吾輩は猫である」を雑誌「ホトトギス」に発表。この作品が高い評価を得たことは、漱石のその後の人生において大きな転機となります。
1907年、漱石はついに講師を辞職して朝日新聞社へ入社し、小説記者となりました。出社の義務は無く、年2回程度の新聞連載小説を書くという小説記者として、漱石は新たな道を歩み始めます。

日本で初めて◯◯制度を整えた漱石

漱石は現代の作家にも大きく関わる制度、印税の仕組みを整えています。それまでの作家が得られる収入は、出版社が買い取った1作品単位の原稿料のみ。「坊ちゃん」の原稿料は148円(現在の価値にして約50万円)だったと知られていますが、もしも作品が人気になり、増版が決定したとしても作家は売り上げを全く貰えず、得をするのは出版社だけだったのです。
漱石はそんな状況を変えようと動きます。記録によると、「坊っちゃん」や「草枕」が収録された作品集『鶉籠』について、初版の印税は1割5分、第2版以降は2割、6版以降(後には4版以降)は3割と、かなり事細かに要求していることが分かります。更に、最終的に3割となる印税は当時では破格の割合であり、出版社からはあまり良い反応をされませんでした。
漱石がこうまでして印税制度を整えようとしたのは何故だったのでしょうか。その背景には、弱い立場だった作家の収入を安定させようとしたことが考えられます。漱石自身もまた、教授を辞めてまで作家になろうとした際には「せっかく帝大の講師だったのに。そんなに身を落としてまでやりたいことなのか」と大きな批判を受けていたのです。
どんなに素晴らしい作品を著したとしても、作家が得られる対価は最初に出版社から支払われる原稿料のみであり、貧しい日々を過ごすことは避けられませんでした。そんな作家の未来に貢献することは、漱石にとって悲願だったのではないでしょうか。
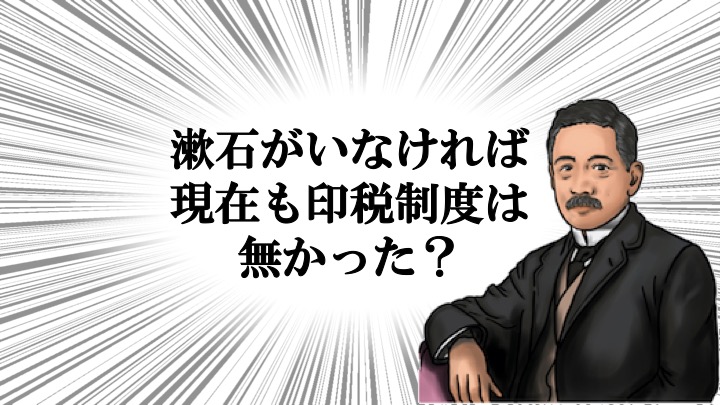
日本に初めて◯◯を伝えた漱石

1909年、漱石は南満州鉄道総裁を務めていた中村是公と共に満州旅行をし、この記録を「満韓ところどころ」という旅行記に残しています。この旅行に同行した中村是公は第一高等中学で知り合った親友であり、「こころ」や「吾輩は猫である」に登場するキャラクターのモデルになっているという話もあります。漱石は中村を「ぜこう」、中村は漱石を本名の金之助から「金ちゃん」と呼んでいたことから2人が親しい仲であったことが窺えますね。
この「満韓ところどころ」の興味深いところは、中国人がとある遊びをしている様子が描かれている箇所にあります。
二階が荷主の室だと云うんで、二階へ上って見ると、なるほど室がたくさん並んでいる。その中の一つでは四人で博奕を打っていた。博奕の道具はすこぶる雅なものであった。厚みも大きさも将棋の飛車角ぐらいに当る札を五六十枚ほど四人で分けて、それをいろいろに並べかえて勝負を決していた。その札は磨いた竹と薄い象牙とを背中合せに接いだもので、その象牙の方にはいろいろの模様が彫刻してあった。この模様の揃った札を何枚か並べて出すと勝になるようにも思われたが、要するに、竹と象牙がぱちぱち触れて鳴るばかりで、どこが博奕なんだか、実はいっこう解らなかった。ただこの象牙と竹を接ぎ合わした札を二三枚貰って来たかった。
「満韓ところどころ」より
「4人で将棋の駒ほどの大きさの札を並べ替えて行う勝負」という表現から、この時漱石が見たものは麻雀だと考えられます。初めて目にした異国の遊びについて「実はいっこう解らなかった」と言いながらも、「札を2、3枚貰ってきたかった」と興味を示しています。
日本に麻雀を紹介した記録としてはこの「満韓ところどころ」が最古のものだと言われています。
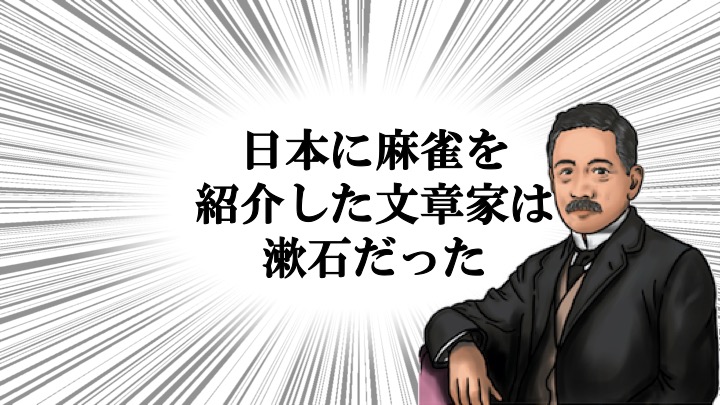
漱石が1000円札の顔になったのは◯◯の象徴?

漱石といえば、1000円札の顔というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。これも、日本初の出来事として触れておかなければなりません。1881年に神功皇后が描かれて以来、紙幣には政治に関わった人物の肖像画を使うのが当たり前となっていました。それは国が戦争や恐慌で不安定になった時にこそ先導してくれる政治家が、人々から高い評価を得ていたことが影響しています。
そんな傾向が変わったのは、紙幣に文化人の肖像画を使用すると決めた1980年のことでした。イタリアではガリレオ、イギリスではニュートンといった文化人が紙幣に描かれるようになったという国際的な傾向もありましたが、日本国内でも相次ぐ政治スキャンダルから、利権に無関係の文化人の方がお札の肖像画として好ましいのではないかという意見が国民の間に醸成されていったのです。当時、肖像画の候補には漱石の他に芥川龍之介、正岡子規、森鴎外、新渡戸稲造、岡倉天心といった人物の名前がありました。
そこから最終的に「国際性のある人物」として外国の見聞を日本に伝えた福沢諭吉、国際交流に尽力した新渡戸稲造と共にロンドン留学経験のある漱石が選ばれ、1984年に文化人の肖像画が使用された紙幣が発行されたのでした。
文化人の肖像画が使われたのは、日本が平和で経済的にも豊かになった象徴とも言えるでしょう。
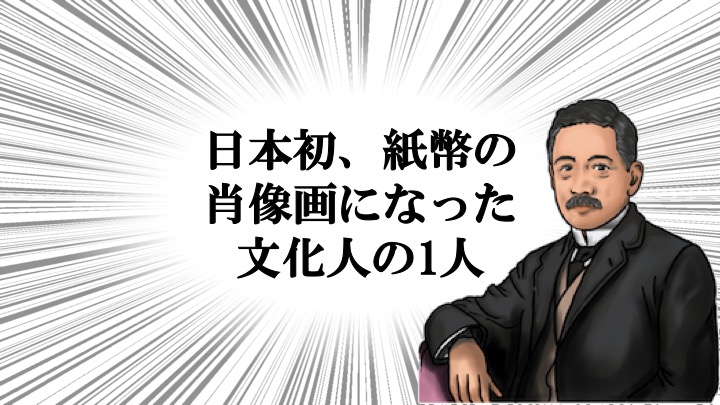
「和製漢語」職人、漱石
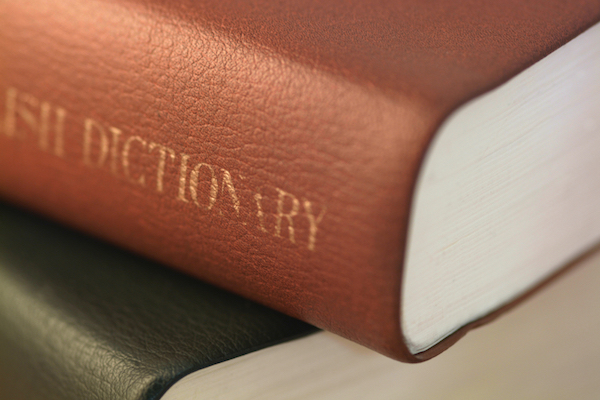
また、漱石は西洋の言葉を訳すために和製漢語を作った人物でもあります。当時、日本の文筆家たちは西洋の書物を翻訳する際に漢字を使用して新しく言葉を作り上げていました。森鴎外や福沢諭吉と共に、漱石もこの和製漢語を数多く作った人物の1人だったのです。
また、「肩こり」という言葉は漱石による造語として考えられており、漱石の「門」のなかにこのような表現があることが根拠とされています。
指で圧してみると、頸と肩の継目の少し背中へ寄った局部が、石のように凝っていた。
「門」より
しかし、「門」より以前にも「肩が凝る」、「肩が張る」という表現が使われていたことが判明しているため、「肩こり」は漱石が作った言葉だと断定することはできません。
このように漱石が初めて作ったとされる造語は複数存在すると言われています。ただ、どれも漱石より古い用例があるため、はっきりとしたことは未だ分かっていません。
判明しているのは、「浪漫」について「教育と文芸」で「適当の訳字がないために私が作って浪漫主義として置きました」と述べていることから漱石による言葉だということです。漱石は現在でも使われている「浪漫」という表記を、初めて日本語に落とし込んだのです。
関連記事:日本の翻訳文化って、どこがすごいの?【教えて!モリソン先生 第2回】
おわりに
漱石が作家として活躍した期間は僅か9年でしたが、丁寧な心理描写や時にユーモアに溢れた作品は人気を獲得し続けています。それだけでなく、近代日本語の礎を築き、後世の日本文学を更に実りあるものへと発展させた漱石は、現代に生きる私たちに新鮮な印象を与え続けているのでしょう。
それまで日本に強く根付いていた慣習を変え、日本に新たな情報や当時としては考えられなかった物語を提供した漱石。そういった視点から考えると、漱石は日本を生まれ変わらせた文豪とも言えるのです。
初出:P+D MAGAZINE(2016/05/13)

