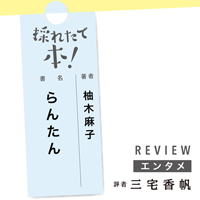インタビュー 柚木麻子さん 『BUTTER』
オリジナルレシピを見つけるまでの話だとも言えるんです。
柚木麻子さんが、現時点での彼女の最高傑作ともいえる作品を発表した。長篇『BUTTER』は、実際に起きた事件をヒントに作り上げられたフィクション。著者自身がこれまでにも取り上げてきたモチーフの詰まった集大成的な作品になっている。
あの連続不審死事件がきっかけ
交際していた男性が次々と不審な死を遂げていることが発覚、物的証拠のないまま無期懲役を言い渡されて控訴審を控えている女、梶井真奈子。週刊誌記者の町田里佳は拘置所の彼女に手紙を書き、取材を試みる──柚木麻子さんの新作『BUTTER』のあらすじを読めば、多くの人は二〇〇九年に発覚した首都圏連続不審死事件を思い浮かべるだろう。この四月に容疑者である木嶋佳苗の死刑が確定したが、当初から柚木さんはこの事件に関心があった。
「記事を読んでいるうちに、料理のことで傷つく人がたくさんいる気がしたんです。彼女は料理教室でパンを焼いたり、死んだ男の人たちに料理を作っていましたが、一緒にパンをこねてそのパンを食べたり人に配ったりしただろう人たちもショックだっただろうし、“料理教室に通うのは婚活のため”“男の人は胃袋でつかめ”“料理の上手な女は家庭的”といった、ありがちな言説に傷ついて、料理が嫌になっちゃった人もいっぱいいるだろうなと思って」
実際に同様の料理教室にも体験取材をした柚木さんにしてみれば、教室は真面目に料理を学ぶ場で、婚活やマウンティングなど寄せ付けない雰囲気であったし、彼女自身「料理は好きだけれども私は家庭的ではないです」ときっぱり。そしてもうひとつ、裁判傍聴記などを読むうちに気になったことがあった。
「彼女がお料理教室に通ったのは、もしかしたら女友達を作るためだったのかもしれない。そう思った時、事件のことがいろいろ見えてきたんです。以前、北原みのりさんが著作の中で、もし、世間でいわゆる「毒婦」と糾弾された、あの人やこの人に女友達がいたら……と書いていらしたことが、『ナイルパーチの女子会』を書く時の出発点でしたが、今回も女友達のことは考えようと思いました」
事件を追う記者とその親友
手紙でレシピのことを尋ねたことがよかったのか、里佳はついに面会を許される。梶井真奈子の人物造形に関しては、
「現実に被害者の方がいるので、どう書くかすごく迷いました。それで、読んだ関連書籍のことや彼女のブログのことは一回、全部忘れることにしました。“私はホリー・ゴライトリー(『ティファニーで朝食を』のヒロイン)”“許せないものがふたつあって、それはフェミニストとマーガリンです”といった台詞は私の創作です。梶井真奈子、カジマナのほうがガーリーというか、子どもっぽいかもしれません」
梶井が三十五歳、里佳が三十三歳という年齢設定にしたのは、
「実際に事件が発覚した時の彼女がそれくらいの年齢だったんです。それと、里佳とカジマナそれぞれ、援助交際が社会問題になった時代のまさにど真ん中に高校生だった年齢にしたくて。前述の北原さんも著作で指摘されていましたが、実際の事件も思春期に自分たちの身体に価値があると知らされた世代だからこそ、起きている。ただ、作中に出てくる北陸新幹線の開通時期やバター不足の時期に合わせて微調整はしています」
面会を重ねながら指示通りに料理を作り、レストランに足を運ぶ里佳。もともと痩せぎすだった彼女も、バターたっぷりの食を堪能するうちに、次第に脂肪をまとっていく。
「女性上司の指示で主人公がランチを食べに行く『ランチのアッコちゃん』のように、命令されて何かを食べに行く話にすることは決めていました。それが可能な存在ということで、記者という職業にしたんです。それも会社の中でものすごく圧をかけられていて、まわりに同性の仲間のいない女性にしたくて、週刊誌の記者という設定にしました」
実際に、元、もしくは現役の女性記者にも取材したところ、
「編集部に同性の先輩がいないと言うんです。みなさん、結婚か出産か身体を壊したのを機に編集部を離れていく。それくらい仕事が過酷なんです。情報提供者の男性との関係に女性としての見返りを求められていると悩む人もいるし、セクハラの経験もある。そういうことは里佳の経験として書きました」
そんな環境の中、里佳は梶井と弟子と師匠のような関係になっていく。
「今の時代はみんな確固たるものを持てずに悩んでいるから、声の大きな人に従いやすいんですよね。“あなたは本当の贅沢を知らない”と言われると、そうなのかなと思ってしまう」
そこから二人の関係性も状況も二転三転していく構成が実に見事。里佳は梶井の過去を知るために彼女の故郷の新潟を訪れることになるが、そこに里佳の学生時代からの親友で主婦の伶子がついて来るあたりから、物語の方向性は予想もつかないものになっていく。
「実際の彼女は北海道出身。近所に酪農家があって、だからバターが好きだったんでしょうね。それをこの小説で新潟にしたのは、たまたま友達が住んでいて地元の美味しいものを教えてくれると言ってくれたので(笑)。雪が降る阿賀野市を歩き回りましたし、牛の乳しぼりも経験しました」
酪農家の取材体験は大きかったようで、
「牛乳はもともと牛の血液なんだということに思うところがありました。それに、牝牛は闘わないという話が面白かった。牝牛は一回放牧すると牝牛同士で序列を決めて、それ以降は決して揉めないそうです。女の子がグループで住み分けていると言うと怖いといわれるけれど、実は気を使いあっているだけですよね。それと同じだなと思って」
対照的なのが、作中で何度も言及される『ちびくろ・さんぼ』だ。
「さんぼを襲う虎たちは牝ですよね。さんぼがやっつけたわけではなく、勝手に揉めて、ぐるぐる回ってバターになるんです」
親友同士の心の変化
取材旅行についてきた親友の伶子が、その後驚く行動に出て、物語に深く関わってくる。
「伶子は何をやらせてもできる人。現在は仕事を辞めて主婦ですが、家事をやらせてもアートの域。家事が完璧な人って、実はものすごく才能があってクリエイティビティにあふれているんですよね。伶子もそう。でも彼女自身は、自分に納得していないんです。私は伶子がすごく好きで、『風と共に去りぬ』のメラニーをイメージしていました」
いわずと知れた名作で、主人公のスカーレットが思いを寄せるアシュレイと結婚するのが地味なメラニーだ。南北戦争の混乱の中、類まれなほどの懐の深さで生き抜いていく善良な女性でもある。スカーレットは彼女をずっと馬鹿にしているが、メラニーは彼女を崇拝している。
「あの小説でも実は一番変わっていて、一番なんでもできるのがメラニーですよね。この小説でも、カジマナに立ち向かえる唯一の女の人が伶子だと思います。里佳がカジマナの影響でどんどん身体が大きくなりながら強くなっていくのに対し、伶子はどんどん小さく、ピュアでイノセントになっていくことも表したかった」
ちなみに、伶子の愛犬の名前がメラニーなのはその象徴だ。では、里佳はスカーレットなのだろうか。
「里佳は女子校時代、王子様として存在していて、だから自分の女性性をあまり出さないようにしてきた人。ですが、スカーレットよりだいぶソフトです。どちらかというと煮え切らない優男のアシュレイに近いでしょうか(笑)」
やがて伶子も里佳も、人生のひとつの局面を迎えることになる。物語は里佳の情報提供者である通信社の編集委員である篠井、同僚や恋人、さらには母親、伶子の夫の亮介なども絡んで人間模様に広がりを見せ、互いに少しずつ支え合っていく姿が印象に残る。
「誰かが誰かを完全に救済することは難しいですよね。でも、逃げ場になってあげることはできる。駆け込み寺のような存在になることはできるんですよね」
彼らの関係性は、新しいコミュニティの形を提示しているようにも読める。ある場面で、“家庭的な女”というものに関して、里佳が言う言葉にはっとする。
〈これだけ家族の形が多様化している現代で、そんなのもう、なんの実態もないです。そんな形のないイメージに振り回され、男も女もプレッシャーで苦しめられている〉
それが事件の本質ではないかと里佳は問う。
「ほとんどの殺人は家族原理主義によるものともいわれていますが、この婚活殺人もそうですよね。結婚しなくちゃいけないという意識があるから起きてしまう。でも、女の人は男の人を立てるべきとか、男の人には肉じゃがだ、なんて言っているのは、結局相手をきちんと見ていないということ。相手の体調が悪化しようが、相手が仕事や人間関係で悩んでいようが関心がなく、それよりもお金や、結婚するかどうかばかりが大事だという。そういう人と一緒の空間にいると、本当に死んじゃうことはあると思うんです。私は実際に起きた事件を自分が裁く気は全然ないんですけれど、ただ、一緒にいるだけで相手から生きるエネルギーを奪うタイプの人はいろいろな場にいるな、とは思いました」
つまり梶井の食生活に合わせようとして体重をふやしていった里佳も、同様の危険があったというわけだ。
「里佳は、死んでしまいそうなほど悩んでいる時に、“助けて”と人に言えること、そして野菜を茹でてタッパーに入れて保存することができた。それさえできたら、人は生きていける」
もちろんそれは、健康管理ができるかどうか、という問題とは少し違う。
「自分の適量を知る、ということだと思います。最近は料理のレシピでも、“塩少々”と表記すると“きちんと分量を書いてくれないと失敗するじゃないか”とクレームがくるそうです。でも、失敗を繰り返さないと、自分にとっての適量は分からない。いろいろ食べて試して、何が自分に合うのかを探していくことが大事。それは食だけに限らず、広くライフスタイルについていえるのではないかと思います。人と自分では適量が違うのだから、たとえばファッショニスタは体重をコントロールする努力をしたっていいし、里佳のような人は、メイクはおざなりで夜中に何か食べてもいい。人が良いと言っているから自分もする、というところから自由になれたら。だからこの小説は、自分にとっての適量を見つけて、オリジナルレシピを見つけるまでの話だともいえるんです」
世の中の多くの人がやっているから自分もやる、ということでは適量は分からない。そして、
「異性であれ同性であれ、相手のことを聞くことが大事じゃないでしょうか。人として向き合うこと。世の中がこれだけ多様化しているのだから、一人ひとりと話さなきゃいけないんだなと感じます。みんなが適量でオリジナルレシピを作って、いろんなレシピの交換ができるようになったらいいなと思います」
終盤、七面鳥を焼いてみんなで食べ、翌日自分なりのアレンジを施してまた食す場面がある。それは柚木さん自身の経験でもあるという。だからこそ、そこで描かれる充足感には説得力がある。
現在取り組んでいるのは下流老人の話だという。世の中の既存の価値観に、どんな問いを投げかけてくれるのか楽しみだ。