新川帆立さん『元彼の遺言状』
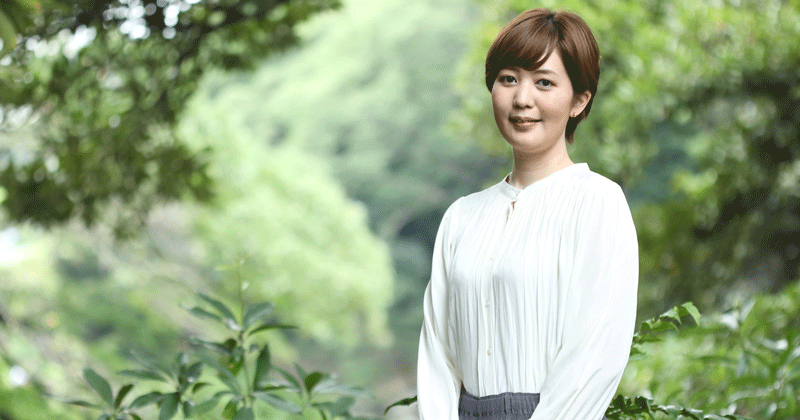
女性が憧れる女性を書きたかったんです
昨年、第19回『このミステリーがすごい!』大賞で大賞を受賞した新川帆立さんの『元彼の遺言状』がいよいよ刊行に。金の亡者、でも憎めない女性弁護士が、元彼が残した謎めいた遺言状の真相に迫っていく。自身も弁護士として働いてきた新川さん、その創作の裏側にはどんな思いがあったのか。
女性弁護士が知った元恋人の奇妙な遺言状
「書くことが楽しくて、その楽しいことを仕事にできてすごく嬉しいです」
と、昨年『このミステリーがすごい!』大賞で見事大賞を射止めた新川帆立さん。1991年生まれ、弁護士でもある大型新人が送り出すデビュー作『元彼の遺言状』は、女性弁護士・剣持麗子が主人公。学生時代の元彼であり大手製薬会社の御曹司、森川栄治が死亡、彼が残した遺言は、「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」というなんとも奇妙な内容だった──。キャラクターも謎も時にコミカルなストーリー運びも非常に魅力的、まさに大型新人の登場である。
「本を読むのは好きで自分でも書きたいと前から思っていたのですが、実際に書き始めたのは2年前くらいからです。3年前に山村正夫記念小説講座、通称・山村教室に入ったんです。私は宮部みゆきさんが好きなのですが、山村教室の前身の教室に宮部さんが通っていたと知り、間違いないだろうと思って。でも、最初の1年間は仕事が忙しくて幽霊部員みたいなものでした。それで2年前から小説を書く時間を作ってちゃんと学び始めました」
自身は純文学も好きで読んでいるが、書く側としては「分かりやすいものを」という意識でエンタメ寄りの作品を執筆。
「1年目に形式も分からないまま書いた小説がファンタジー寄りの変わった小説になったのでどの新人賞に出したらいいか分からなくて。『このミステリーがすごい!』大賞はいろんな作品を出していて、奇抜だからといって落とすことはないだろうと応募したんです。そうしたら一次で落ちて、ちょっと悔しかったんですよね。打倒宝島社を誓い(笑)、ミステリーに取り組むことにしました」
そこから『このミス』大賞の過去の選評を読み、自分なりに条件を考えた。
「キャラクターを立てる、全体的に派手に華やかにする、ミステリーとして大きな謎を用意する、読者が読んだことのないような新しい要素を入れる、現代的なテーマなど新しい要素を入れる、その5つくらいが必要だなと思いました。キャラクターについては、自信を持って深いところが書けるのは同世代の女性なので、今回は年代も職業も自分と同じ女性を主人公にしました。それに、女性が憧れる女性を書きたかったんです。というのも男性が書くミステリーって、男性に都合のよい美人ばかり出てくる印象があって。現実の世界だけじゃなくて小説の世界でも、女性は花を添える役割を担わされている。そういう作品も市場で必要とされていると思いますが、自分が一生懸命仕事して家に帰って小説でも読もうかなと思った時にそういうものを読むとぐったりするというか。それで、普通の女性にとっても楽しいものを書きたかった」
わがままで強引、稼ぐことにこだわる痛快な女性主人公
女性の憧れる女性というが剣持麗子はかなり自信家で強気な性格。年収2千万円だが、まったく満足していないどころか、まだまだ稼ぎたい、稼げると思っている。こうした女性像にしたのは単にキャラ立ちさせたかったからだけではない。
「もともと『風と共に去りぬ』のスカーレット・オハラが好き。ああいう、わがまま放題だけど憎めない主人公にしたかったんです。そういう人物の行動のモチベーションは現代で考えるならお金だなと考えました。女性が自立するには経済的自立が一番大事だし、自分で稼いでやる、と思って一生懸命働いている女性は全国にたくさんいるのに、エンタメ小説はそういう存在を無視していると感じています。女性のお仕事小説と呼ばれるものでも、素直ないい子が頑張って、メンター的な男性と恋愛っぽくなるというパターンがありますが、〝仕事も恋も頑張るぞ〟ではなく、もっとゴリゴリに働いてゴリゴリに経済まわしている女性は実際にいる。だから、主人公のモチベーションも恋愛ではなく、自立して、ほしいものを手に入れる、というところを起点にしたかった」
かといって、いわゆる〝女を捨てている〟タイプでないところも自然だ。
「仕事と恋愛って二者択一じゃないですよね。今は女性としての楽しみを持ちつつ働いているのが当たり前なのに、どうしてもエンタメ小説だとキャリアウーマンとなると肩ひじ張っていたり、さばさばしていたりする形で描かれやすい。でも、現実はその先をいっているという思いがありました」

しかし麗子の金に対するこだわりは、額が桁違い。栄治の遺言を知った知人男性から、犯人として名乗りを上げるので代理人になってほしいと依頼されるが、成功報酬を見積もって「たかだか十億」と言って渋るくらいだ。
「その点については、読者にとって身近にするか夢を見る方向にするかのどちらかだと思いますが、せっかくなので後者を選びました。現実は大変なことが多いので、辛いことを辛いまま書いても面白くない。それに中途半端なお金の亡者ではなく、すごい額にしてしまえばいやらしくない。読者に笑ってもらって、明日一日元気に過ごしてもらえたら。現実はヨーグルトを買うにしても220円のものか240円のものかで悩むんですけれど(笑)」
それにしても森川栄治はなぜあのような遺言を作成したのか。彼は本当に殺されたのか、その場合犯人は遺産をもらえても、警察に捕まるのではないか。
「別の文脈で、文化人類学のポトラッチという、贈答慣行を意味する言葉を知ったんです。人にプレゼントを贈ることは善いことに思えるけれど、もらいすぎると人は返さないといけない気になる。あげる側は相手を支配するためにプレゼントしている。何かを与える、もらうというのはハッピーなことばかりではないんだなと思ったことから、遺言の内容で復讐を果たそうとする話が書けないかなと思ったんです。そういうことを考えていた頃、何年も連絡をとっていなかった3つ前の彼が突然〝元気?〟って連絡してきたんです。変なことするなと思って、元彼が不慮の事故で亡くなったら悲しいだろうか、お葬式に行くんだろうかと考え始めて、これは小説の内容として面白いな、と」
それにしてもこの遺言は実際に成立するのか。読者が消化不良を起こさないよう、作中で疑問点を解消しているところも配慮を感じさせる。
「ありえなそうだけれどなくはない、ギリギリのラインを攻めました。ミステリーの賞に出すためには新しさがないといけないと思い、あえてハッタリ芸で勝負に出ましたが(笑)、一応弁護士としてあからさまな法的誤りがあってはいけない。一生懸命考えたので、解釈として微妙なところもありますが、あからさまな噓はないはず。細かい確認作業もしましたが、それを小説に書いても難しくなるので、分かりやすさと正しさの中間をとったような形です」
結局、知人の依頼を引き受けた麗子は、彼を犯人に仕立て上げようとする。ここも、ミステリーとしてはなかなかない設定だ。
「探偵役が犯人を捜すという設定がミステリーの基本なので、ミステリーとしての新しさを考えました」
さらに栄治が、過去の恋人たちにも遺言を残していると判明、麗子も当事者となって森川家と関わりを持つ。一族や栄治の他の元彼女など、多くの人物が登場するが、みな個性豊か。
「話の長さに比して人物が多いと言われるまで自分では気づいていなかったのですが、自分が、こういう人がいたら面白いだろうな、と思う人を考えていきました。分かりやすいようにデフォルメして色をつけたイメージです」
だからこそ、みなが印象に残り、みなが何か怪しく思えてくる。女性も多いが、麗子と対立したりいがみあったりする展開にならないのも読み心地がいい。
「そこは意識しました。女の敵は女という言い方がありますが、それは噓だと思っています。私が働いて暮らしている生活圏ではそんなことは全然起きなくて、みんな立場の違う相手を尊重して建設的に接している。小説で女同士のドロドロしたものが描かれていると、現実とのギャップを感じていました。そうではなく、私に見えている世界を書きたかった。男性に関しても、嫌な奴に見えてもどこか愛されポイントや笑えるところがあるように考えました」
小説家を目指しながら、司法試験に合格
プロフィールによると、16歳の頃に夏目漱石の『吾輩は猫である』を読んで感銘を受け、作家を志したという。
「ユーモア系の小説を読んだのはそれがはじめてで、自分もこうした、笑える話が書きたいと思いました。それですぐに創作を始めたわけではなかったのですが」
心の中では小説家を目指しながら、東京大学法学部に進学し、司法試験を受け、弁護士となったというわけだろうか。
「文才があると言われたこともなかったし、出版不況と聞いていたし、自分にとって作家を志すのは茨の道だと分かっていたんです。かつ、人が夢を諦める一番の理由は経済的な事情だと思うので、まずは経済的な基盤を作ろうと考えました。国家資格のある専門職につけば生活に困ることはないだろうと、医学部を受験したら落ちたんですが、たまたま後期試験で医学部以外の学部になら進学できることになり、それで法学部に行って弁護士になろうと思いました。さしたる志もなかったので、いざ弁護士になって事務所に入って働き始めたらしんどくて」
残業時間が多く小説を書く暇もなかった。そのため転職して企業所属の弁護士となり、小説を書き始め、そしてデビューを果たした。最終選考日は「気になって何も手に付かないので」宿坊に泊まり、寺で写経をしていたという。エピソード豊富な新川さん、プロ雀士としての活動歴もあるのがユニーク。聞けばなんと、プロテストでは首席だったのだとか。
「高校生の時に囲碁部に入っていて、部活の友達から麻雀を教わったらそっちのほうが向いていると気づいて。大学時代は麻雀に青春を捧げました(笑)。でも若い女の子が麻雀をやっていると、男性から舐められたり、失礼な態度をとられたりすることが多いんです。こちらの本気度を示すために司法試験が終わってからプロ資格を取りました。プロとして活動のこだわりはなくて、趣味としてやっていることのひとつの到達点なんです」

目指したものはとことん極める性格のようだ。もちろん小説も。
「じつは会社に、今は小説に集中したいとお願いしたら、今年から休職させてもらえることになりまして。駄目だったら戻っておいで、って言ってもらえました。本当に人に恵まれていますね、私。今年は挑戦の年なので頑張ります」
今後についてはまず、本作をシリーズ化する予定だという。
「応募した段階で続篇のことはまったく考えていなかったので、シリーズ化を提案された時はどうしようかと思いました。でもひねりだして(笑)、今、3作目まで構想があります。2作目は今年秋までには出したいです。これをシリーズとして大事にしつつ、いろんなものを書いていきたい。アイデアは沢山あるのに技術が追いつかないのがもどかしいのですが、少しずつ幅を広げていきたいです」
新川帆立(しんかわ・ほたて)
1991年2月生まれ。アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身、宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業。弁護士として勤務。司法修習中に最高位戦日本プロ麻雀協会のプロテストに合格し、プロ雀士としても活動経験あり。作家を志したきっかけは16歳の頃、夏目漱石の『吾輩は猫である』に感銘を受けたこと。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/宝島社)
〈「WEBきらら」2021年2月号掲載〉







