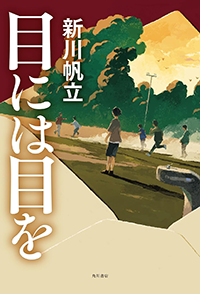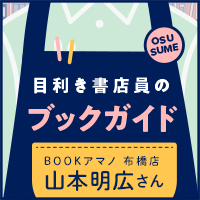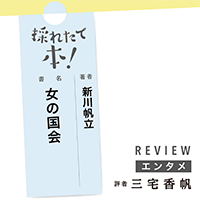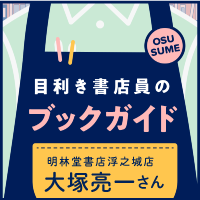新川帆立『目には目を』◆熱血新刊インタビュー◆
復讐は難しいからこそ

紀元前18世紀に発布されたハンムラビ法典の一節で、「歯には歯を」という言葉を伴って語られることも多い「目には目を」。この一節は、被害者による復讐の権利を謳うものではなく、加害者への過度の復讐を抑える意図があることはよく知られている。だが、復讐された加害者の家族の側には、被害者によって家族が加害されたという現実が残る。ならば今度は、こちらが相手に復讐しても良いのではないか……。新川帆立の『目には目を』は、そうした連鎖の可能性を物語の核に据える。
「きっかけは単純だったんです。自分の文体が軽いとよく言われるから、重たいものを書こう、と」
文体を重くするのではなく、題材を重くする、という選択が興味深い。
「おそらく作家の文体って本人のキャラクターと紐付いているので、作品によってちょっとずつ変わってはいるものの、大きくは変えられないものなんですよね。私の文体で軽い題材を書くと、大人が読むには軽すぎて物足りなく感じてしまうのかもしれない。むしろ重たい題材のほうが向いているのかもしれなくて、普通に書くと重くなりすぎる題材も、自分の文体で書けば逆に読みやすいのかもしれないと思ったんです。それを自覚的に実践したのが、身体に重度の障害を負った主人公が司法試験突破を目指す『ひまわり』という作品(2024年刊)であり、今回の『目には目を』でした」
少年法の問題を扱うことにした背景には、編集者からの刺激があったという。
「打ち合わせで私が昔、定時制高校の法務部で働いていたという話をしていたら、編集さんから定時制高校の話を書きませんかと言われたんです。ただ、自分の体験と距離が近い話になってしまう気がしたので、広く教育というものをテーマにしてみるのはどうかなぁ、と考えました。教育でリーガルものだと少年法絡みかなと思い、少年院を主な舞台にするという着想が芽生えました。それと同時に、少年法にまつわる一般的な感覚として、悪いことをしても未成年だからという理由で裁かれないのは、被害者からすると納得できないというものがありますよね。被害者やその家族は相手に復讐したいはずで、〝本当に復讐したらどんなことが起こるんだろう?〟と考えてみたかったんです」
〝甘栗〟をたくさん書きたいと思っていたんです
〈彼は人を殺し、人に殺された〉(「序章 墓地」より)
ルポルタージュ形式が採用された本作は、彼──少年Aを巡る事件の真相を、ライターの「私」が当事者への取材を通して解き明かしていく。当時15歳10か月だった少年Aは、少年Xに暴行を加えて死亡させた。少年法に守られたAは1年3か月をN少年院で過ごし、17歳の春に退院した。それから半年と少しの後、土木作業員として働いていたAを殺害したのは、田村美雪という女性だった。警察に自首をした彼女は、Aに殺されたXの母だった。「死には死をもって償ってもらおうと思ったんです」。裁判時の被告の発言から「目には目を事件」と呼ばれるようになった事件には、幾つもの謎があった。例えば、被害者遺族が少年Aの居場所を知るには、少年院でAと共に生活していた、少年Bによる密告が不可欠だった。Bは誰なのか、なぜそのような行動を取ったのか?
本格ミステリーの必要十分条件の一つは、物語の冒頭部で、全編をかけて解き明かすべき「謎」が提示されることにある。冒頭わずか6ページで「謎」が掲げられる本作は、社会派ミステリーでありながら、本格ミステリーとしての佇まいを兼ね備えている。それは、題材選びから来る必然だったと著者は言う。
「私の文体は軽めなので普通のノンフィクションなどよりも読みやすいかなと思いつつ、今回取り上げた題材を、構造的な工夫など何もなしで書いてしまうと、読み進めるのがしんどくなってしまう。苦い薬を飲み下してもらうためのコーティングとして、ミステリーの要素が大事だなと感じていました。重い題材だったからこそ、期せずしてミステリー度合いが他の作品よりも高くなったんです」
前半部は、N少年院ミドリ班の6人への取材とルポルタージュがメインだ。
「猟奇犯罪犯の少年についてはあえてテンプレートっぽく書いたんですが、他の5人に関しては、子供は無垢で残酷で……というフィクションでよく描かれがちな少年犯罪者像からは距離を取りました。デビュー前まで弁護士として法律の仕事をしてきた自分が納得できる、こういう子なら現実にいる、と思えるリアリティのラインを目指したんです。ミステリーにしてはナマっぽいというか、あまり〝犯人〟っぽくない子たちになりました」
その言葉通り、多くの少年たちは偶然、境界線を超えてしまっている。深い害意を持って行動したわけではないからこそ、警察が来た時に、ある少年は予想外のリアクションを取った。少年が発した言葉を、「私」は実直に記録する。〈警察官の姿を見て、大坂君は「あちゃー」と思ったという。そこから先の流れは「マジで刑事ドラマみたい」だった〉。ナマっぽい、と感じる描写だ。
「東野圭吾さんの『手紙』という小説で、お兄ちゃんが空き巣に入った家でいろいろ盗んだ後、ダイニングに甘栗があるのを見かけて、〝そういえば弟が甘栗好きだったな〟と思って取りに行くんですよ。その行動のせいで被害者と鉢合わせして、相手を殺してしまう。甘栗なんて、コンビニで買えばいいじゃないですか。弟に対する謎の優しさからわざわざ危険を冒して取りに行って、取り返しのつかない事態を起こしてしまう。犯罪者ってこういう不合理な動きをするんだよなと、とてもリアリティを感じるシーンなんです。ミステリーのために作られた犯罪者像ではないんですよね。私もこの作品では、少年たちがどこかで本当に生きていると感じてもらえるような、〝甘栗〟をたくさん書きたいと思っていたんです」
復讐してしまったところから始まるミステリー
6人のうち誰が殺された少年Aで、誰が密告した少年Bなのか──。後半では「そこも謎だったのか!」というサプライズが連鎖し、物語は二転三転を遂げる。
「ミステリーのどんでん返しは、キャラクターの多面性と連動すると思うんです。ミステリーを面白くするためにはキャラクターの多面性が必要になるし、キャラの多面性をエピソードで入れようとすると、どんでん返しになる。自分が書いていて飽きないために、無理やり引っくり返して自分を驚かせる、という時もあるんですけどね(笑)」
実は、社会派にして本格ミステリーである本作は、もう一つのサブジャンルを包含している。エンターテインメントの世界でよく目にする、復讐モノだ。
「ミステリーで人を殺害する動機って、だいたい復讐だったりするんですよね。真相に辿り着いてみたら、動機は復讐でしたと明らかになって終わるミステリーはよくあるんです。でも、本当に復讐してしまったところから始まるミステリーはあまりない。ここから始めれば、自分なりの新しい物語が書けるんじゃないかという予感がありました」
書き進めるうえで根底にあったのは、「復讐は難しい」というリアリティだった。
「今野敏さんの空手塾で、要人を守るボディガードの仕事をされていたという師範代の方から聞いた話が印象に残っていました。加害者が相手を攻撃するうえで、銃が精神的に一番楽で、次に刃物がしんどくて、手で殴りかかる時は一番ストレスがかかるそうなんです。他人に強い害意を向けるのは相当難しいことだし、人ってなかなか凶悪にはなれないんですよね。だから、復讐って現実ではなかなか起きないし、この小説の中でも〝こういう状況であるならば……〟というリアリティラインを探りました」
そうした想像力が、復讐モノのお約束を排除し、新しい人間ドラマを呼び込んだのだ。
「復讐は難しいということは、人間の善性を象徴しているかもしれないなと思ったんです。悪くなろうとしても悪くなりきれない人間の姿を描くことで、逆に人間を肯定的に捉えることができる。人間ってもしかしたらこういう存在かもしれないというところまで想像するのは、ノンフィクションではできない、小説だからこそ表現できたことかもしれないなと思うんです」
重大な罪を犯して少年院で出会った6人。彼らは更生して社会に戻り、二度と会うことはないはずだった。だが、少年Bが密告をしたことで、娘を殺された遺族が少年Aの居場所を見つけ、殺害に至る──。人懐っこくて少年院での日々を「楽しかった」と語る元少年、幼馴染に「根は優しい」と言われる大男、高IQゆえに生きづらいと語るシステムエンジニア、猟奇殺人犯として日常をアップする動画配信者、高級車を乗り回す元オオカミ少年、少年院で一度も言葉を発しなかった青年。かつての少年6人のうち、誰が被害者で、誰が密告者なのか?
新川帆立(しんかわ・ほたて)
1991年生まれ。アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身。宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し、2021年に『元彼の遺言状』でデビュー。他の著書に『倒産続きの彼女』『剣持麗子のワンナイト推理』、「競争の番人」シリーズ、『先祖探偵』『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』『縁切り上等!』『女の国会』『ひまわり』などがある。