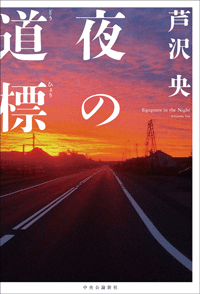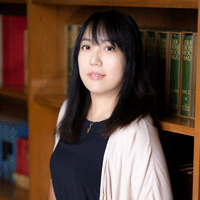芦沢 央さん『夜の道標』

自分が抱いていた恐怖や問題意識と繫がりました
作家生活十周年を迎えた芦沢央さんの新作『夜の道標』。一九九〇年代に起きた殺人事件をめぐり、容疑者の男、男を匿う女、彼らに関わる二人の少年、調査を進める刑事の姿から炙り出されるものとは。この時代、この人物設定だからこそ切り込めるテーマに勇気を持って挑んだ痛切で衝撃的な一作だ。
出発点は、自身の恐怖と問題意識
「この話を書かないと、私は前に進めないと思いました」
と語る芦沢央さん。作家生活十周年を迎えた彼女の新作『夜の道標』は、一九九〇年代に起きた殺人事件を描き、その真相に愕然とさせられるミステリ作品。
「ずっと、自分にとって怖いものを見つめるために小説を書いてきたところがあります。私の作品はイヤミスと言われがちですが、私自身は嫌な話を書いてやろうと考えたことはなく、ただ自分が怖くて仕方ないから、その怖いものを見つめるしかなくて書いている部分がありました。今自分が正しいと思うものを守れているのは、ただ運がいいだけだという思いがあって。でもだんだん、「今自分が正しいと思っているもの」が本当に正しいのかということも揺らいできたんです。ここ数年、どんどん価値観がアップデートされていて、かつて容認されていたことが断罪されるケースも増えていますよね。価値観がアップデートされるのはもちろんいいことですが、その際に取り返しがつかなくて振り落とされたり、踏みにじられたりする人もたくさんいる。私も、過去に書いたことについて弾劾される日がくるかもしれない、何より自分自身が許せなくなるかもしれないと怖くなってきたんです。そうした恐怖と問題意識に向き合ってみたのが、今回の作品です」
一九九六年、横浜市内で殺人事件が発生。被害者は塾の経営者、戸川で、容疑者は彼の元教え子で現在三十代の阿久津という男。しかし事件から二年経った今も、阿久津の行方は杳として知れない。実は阿久津は中学校で同学年だった長尾豊子に偶然再会し、彼女が一人で暮らす一軒家の半地下の部屋に匿われていた。
「最初は、匿う人と匿われる人の関係性を書こうと思ったんです。匿われる人はどれだけ嫌な状況でもそこにいるしかないけれど、匿う人は、匿い続けるかどうかも一方的に決められるという関係のアンバランスさがある。もともとは匿われる側が優位な関係でも、匿われる状況になったら立ち位置が逆転するのではないか、とその歪さに関心がありました。でも、もし匿われている人が逃げたいと思っていなかったら、追い詰められるのは匿う側なんじゃないかと思ったんです。じゃあ、そもそもその人はなぜ匿われることになったのか、というところから発想が広がりました」
そこに、以前から問題意識があった事柄が結びついたという。それについては、ネタバレになるのでここでは明かさないが、被害者の戸川が経営していた塾が、学校の勉強についていけない子ども、知的発達・情緒に障害を持つ子ども、不登校の子どもなどを受け入れる個別指導塾だったことが意味を持ってくる。
「母は昔、戸川先生のような個別指導塾をやっていたことがあるんですが、母から聞いて衝撃を受けた話があったんです。これはいつか書かなければと思っていましたし、最近自分が抱いていた恐怖や問題意識と繫がりました」
殺人犯の男を匿う女性と、彼を追う刑事、そして二人の少年
視点人物は複数いる。豊子、阿久津を追う刑事の平良正太郎、さらに二人の少年だ。少年の一人、小学生の橋本波留は父親に放置されているうえ、時折強要されて当たり屋をしている。彼はたまたま豊子の家の庭に入り込み、半地下の小窓から阿久津に食料を分けてもらうようになる。もう一人の少年は波留のバスケットボールチームの仲間、仲村桜介で、波留が車にぶつかった現場に居合わせた彼は、自分が名前を呼んだせいで事故が起きたと思い込み、自責の念に苦しんでいる。
「それぞれが見ている景色、考え方、守りたいものがどう絡み合って、どんな光景に繫がっていくのか見たいという思いがあり、複数視点という形式にしました。少年たちを登場させたのは、匿う人と匿われる人の関係に第三者が入り込んできたらどうなるか、という発想からです。この話って最後まで誰かが誰かを誤解したままだったりするんですが、それは完璧なコミュニケーションが成り立っていないからなんですよね。それでも関わり合おうとする姿が書きたかった」
それぞれのパートで、書き方を変えた。
「桜介のパートは、幼い感情がダダ漏れですよね(笑)。波留については前半では感情を表現する言葉はなるべく書かず、彼が見ている情景の描写を中心にしました。正太郎パートは警察小説として心情より事実と分析をメインにしました。ここでは組織内の軋轢も書きたかった。豊子のパートでは、彼女がその場所で感じること、思い出すことを掘り下げました。特に彼女に関しては、エンタメとして書くと損なわれるものがあると思ったので、抑制をきかせました」
中学時代、同級生のいじめの現場に介入した阿久津を見かけた豊子は、それ以来ずっと彼のことを気にかけていた。離婚し、両親も他界した今、彼女は実家で一人で暮らしており、阿久津を匿うのに問題はない。
「第一稿を書き上げた後、視点人物のパートごとに分け、改めてその人の背景や造形を探っていったのですが、一番直したのは豊子のパートです。彼女はパート先の惣菜屋で計算的にサボったり、周囲のちょっとした悪を許容している人物。最初、離婚理由を元夫のモラハラにしていたのですが、そうして元夫を一方的な悪者にすると、彼女が悪を糾弾する側の人になるんですよね。それで離婚理由を変えました。終盤に彼女の気持ちが変わっていくまで、豊子の性格や心情は丁寧に書きたかったんです」

物語の舞台が一九九〇年代であることにも、重要な意味がある。
「今回は時代がわかる固有名詞や、今との倫理観、価値観の違いも盛り込みました。特に時間をかけて考えたのは、お笑いのシーンです。昔笑えたものが、今は笑えなくなるというのは、如実に倫理観の変化を表していると感じていて。親が子どもを殴ることや、いじめの概念もここ数十年で大きく変わったし、一九九〇年代なら普通に職場で煙草を吸っていたりもする。そうした価値観の違いを背景の中で丁寧に積み重ねていくことは、この作品にはすごく大事でした」
この小説では疑似家族を礼賛したくなかった
阿久津と波留は少しずつ、交流を深めていく。父親に虐待されている波留にとって阿久津は唯一の頼れる大人でもある。
「今回、疑似家族についてすごく考えました。波留と阿久津ってある種の疑似親子ですよね。そして、阿久津にとって、戸川は疑似親だったわけです。エンタメフィクションではよく疑似家族が魅力的に描かれますが、疑似親子を礼賛する話にはしないでおこうと考えました。疑似家族だからこそできることがあり、本当の親子だからこそしてしまうことがある。両者を同じ評価軸で比べるのはフェアではないと思うんです。これは血縁関係があるかどうかという話ではなく、人生のどこかの期間だけ関わるか、その子の一生に責任を持っているかという話です。自分が死んだ後もこの子は生きていかなくてはいけないと考えるから選べない、あるいは選んでしまう選択肢がある。そこにこそ、この登場人物が生きづらさを感じる要因があると考えています」
では、阿久津と戸川はどのような関係だったのか。戸川を知る人たちはみな、彼を人格者だと証言する。そんな彼を本当に阿久津が殺したのか。平良や相棒の刑事は、犯人は別の人物ではないか、あるいは思いもよらない事故ではないか、とも考えるが、それは読者も同じだろう。
終盤、阿久津が戸川について語る場面がある。少年の頃、夜道をそれぞれの自転車で走っていた時、前を行く戸川が曲がり角などで手で合図をしてくれたというのだ。タイトルはこのシーンから浮かんだ。
「少年の頃の阿久津が、あの手が指す方向に行けば間違いがない、と思ったという場面です。私はいつも書き上げてからタイトルを考えるんですが、今回その際に浮かんだのがこの場面でした。正確には、私自身が幼い頃に見ていた母の背中です。母は自転車で先導する時、次に右に曲がるとか、左に曲がるとかを腕で合図をしてくれたんです。あの力強い腕の記憶に重なるようにして、「夜の道標」という言葉が落ちてきました。道路標識って、一般的に説明なくみんながわかるものとされていますよね。でも、私は免許を取らなかったこともあり、何となくはわかっても正確な意味を知らないものがあったりします。社会に生きる人間として、知らなくてはならないものを知らないままでいるような不安と申し訳なさがあって。世の中には、そんなふうに、誰でも理解できるとされている道標的なものがたくさん存在する。そのある種の暴力性や、取り残される感覚について考えたいと思ったんです。もちろん、タイトルには戸川先生が彼の人生の〝みちしるべ〟だったという意味もありますが、私の中では〝みんながわかるものとされている道路標識〟という意味合いが強いので、〝どうひょう〟という読み方にしました」
タイトルを考える際に映像が浮かんだというように、執筆の際、頭の中には鮮明な映像があったのだという。
「今回初めて、最初に絵コンテ的なものを描いたんですよ。今までは場面が浮かぶとすぐ言語化していたんですが、頭の中に浮かんだ映像の構図をそのままに棒人間で描いてみたら、イメージが阻害されないと気づいたんです。何だかわからないけれど絶対にこのシーンだ、というイメージがいくつもあって、登場人物について掘り下げていく中で「だからこのシーンだったのか」と発見していった感じというか。感覚としては、このシーンは何なんだろう、という謎を解くために物語を探っていった感じなんですよね。自分が考えた物語というより、頭の中に最初からありながら、断片的なシーンとしてしか見えなかったものを掘り出していった感覚があって、そういう意味ではこれまで書いてきた長編の中で一番書くのが楽しかったかもしれません」
なんとも意外な新たなる挑戦
読者を打ちのめす、挑戦と勇気の詰まった本作を書き上げた芦沢さん。作家デビューから十年、自身の変化を感じるところはあるのだろうか。
「ずっと書きたいことをがむしゃらに書いていましたが、ここ数年で、何を書くかよりもどう書くかに意識がシフトしてきました。何を書かないか、どこまで文章を削ぎ落とせるかを考えるようになったというか。これは短編を書く機会が多かったこととも関係している気がします。そうすると小説の読み方も変わってきたんです。今まで読んで、ただ〝すごい〟とだけ思っていた小説でも、どういう挑戦をしていて、何を抑制していて、何がどう機能しているのかを分析するようになりました。読む本も変わってきていて、特にデビュー後は現代の国内作家のエンターテインメント作品ばかり読んでいたのですが、今は翻訳小説やいわゆる純文学といわれる作品を中心に読んでいます。こんなやり方があるんだ、と気づかされることの連続で、今はとにかく小説について考えるのが楽しくて仕方ありません。自分ももっともっと、いろいろなものをいろいろなやり方で書いていきたいです」
では次回作は? と聞くと、意外な舞台が飛び出してきた。
「今は一九八〇年代から二〇一〇年代にかけてのパレスチナの話を書いているんです。私が高校三年生の時にアメリカ同時多発テロが起きて、あまりに何もわからなかったので、大学では史学科に進んで中東史を専攻しました。ただ、四年間学んで結局わかったのは、自分は何もわからないということだけで。だから卒業後も論文や専門書を読み続けてきました。自分にとっては小説執筆とは関係ない個人的な課題だったんですが、それを話したある方から〝小説で書いてみたら〟と言われて。それで、小説として一個人の生活を書くという視点で資料を読みはじめたら、これまでいくら読んでもわからなかったことが一気に繫がりだしたんです。これは本当にもう、自分自身が少しでも理解を深めたいという気持ちで書いています」
他にSFにも挑戦してみたいという。まだまだ自身の世界を広げていきそうだ。
芦沢 央(あしざわ・よう)
1984年東京都生まれ。2012年『罪の余白』で第3回野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。『火のないところに煙は』が第7回静岡書店大賞を、『神の悪手』が第34回将棋ペンクラブ大賞文芸部門優秀賞を受賞。『汚れた手をそこで拭かない』が第164回直木賞候補。著書に『悪いものが、来ませんように』『許されようとは思いません』など。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野 剛)
〈「WEBきらら」2022年9月号掲載〉