寺地はるなさん『川のほとりに立つ者は』
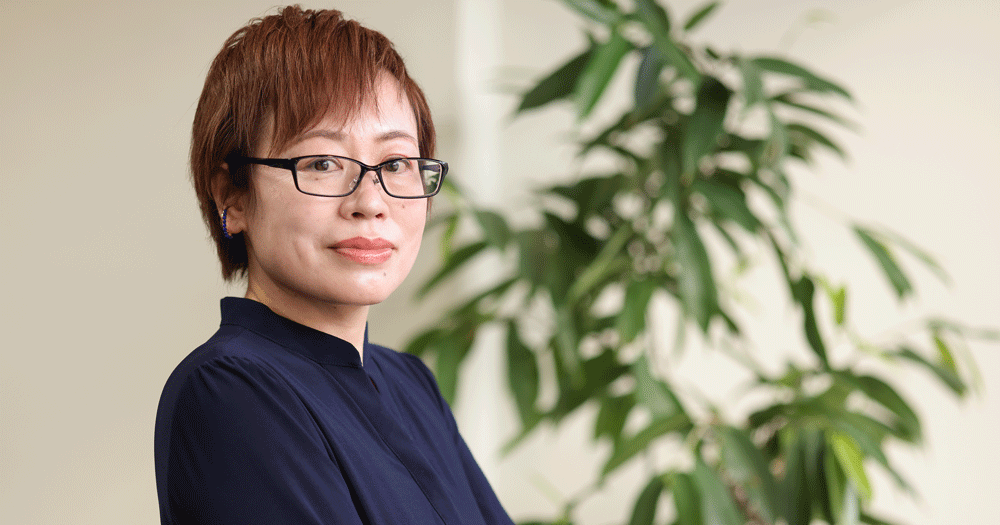
書いているのは、答えじゃなく問い
読んだ人の数だけ答えがある
小説のなかで、今の時代だからこそ考えたい問いかけを放ちつづける寺地はるなさん。新作『川のほとりに立つ者は』もまた、恋人の秘密を知った女性の、心の軌跡が丁寧に描かれるなかで、読者にもさまざまな発見をもたらしてくれている。読んだ人にとって大切な一冊になるであろう、本作の執筆のきっかけは。
怪我で意識不明の恋人が、自分に隠していたこととは
川のほとりに立つ者は、水底に沈む石の数を知り得ない。
寺地はるなさんの新作『川のほとりに立つ者は』を読み終えたら、作中に出てくるこの言葉を痛いほど実感するはずだ。自分も含めて誰もが、川のほとりに立つ者なのだ、と。
「雑誌連載時のタイトルは、『明日がよい日でありますように』だったんです。コロナ禍で世の中が暗くて、みんな不安そうだったし私も不安だったので、よいことがあるといいよね、みたいな気持ちでつけたタイトルでした。でも単行本にする時、このタイトルだと明るい話だと思われそうな気がして。それで、私からタイトルを変えていいですかと編集者にメールしました」
大阪でカフェの店長として雇われている原田清瀬は二十九歳。恋人の松木圭太とは、彼が何かを隠していると気づいた清瀬が一方的に怒り、さらに新型コロナウイルスの感染が広まったことで、しばらく顔を合わせていない。そんな折、松木が怪我をして意識を失い、入院したとの連絡が。聞けば松木と一緒に幼馴染みの岩井樹も倒れていたというが、いったい何が起きたのかが分からない。合鍵を使って松木の部屋に入った清瀬は三冊のノートを見つける。そこには手紙の下書きらしき文章が拙い文字で綴られていた。松木自身は達筆であるため、清瀬は彼が誰かに文字の書き方を教えていたのだと考える。松木の隠し事とは、このことなのか──。
「最初は、小学生の子どもが漢字の書き取りに時間をかけているのを見て、自分が小さい頃に焦ると鏡文字を書いてしまったりしていたな、と思い出して。自分の場合、パソコンを使うようになって不便は感じなくなったんですが、あれはなんだったんだろうと思い、ディスレクシア(識字障害)について調べてみたんです。フィクションでディスレクシアが出てくる時って、文字がグニャグニャ曲がって見えたり、黒い丸に見えたりすると表現されていることが多いですが、それは極めて稀で、本当は人によって違うらしいんです。そうしたことに興味を持った、というのがこの小説を書いたきっかけのひとつでした」
ただ、当事者はこんなに大変だ、ということが書きたかったわけではない。
「そうではなく、その人の周囲にいる人が、障害の名前でその人を見てしまう、というところを考えたかったんです」
物語は、松木の入院を知ってからの清瀬の日々や、その半年前の松木の日常が綴られ、小説内小説や日記、手紙などが挿入されていく。〈川のほとりに立つ者は、水底に沈む石の数を知り得ない〉は、松木の部屋にあった『夜の底の川』という小説のなかに出てくる一節だ。
「いろんな人が書いた文章を小説のなかに書く、というのを一回やってみたかったんです。それを書くのが楽しい、という私の気持ちだけで(笑)」
松木と岩井が入院している病院で、清瀬は弁当店を営む岩井の母親や岩井の交際相手、まおと出会うが、まおはなぜか「松木が悪い」と主張。また、勤務先のカフェでは、遅刻が多く複数の作業を要領よくこなせないタイプのアルバイト、品川に悩まされている。一方、松木視点のパートでは、半年前から怪我をするに至るまで、何があったのかが少しずつ明かされていく。
「恋人が意識を失くした状態だという連絡が来て、さてどうする、というところまでしか決めずに書き始めました。何人かの登場人物が決まると、自然に話が浮かんでくる、という感じでした」
さまざまな考え方が交錯
清瀬は友人の篠井から、「松木にたいしてちょっと遠慮があった気がする」と言われる。いつも人に気を遣い、そのせいで感情を消化できずに爆発させることがある、と指摘されるのだ。松木と喧嘩したのも、そうした性格によるところが大きかったのだろう。
「清瀬は私が今まで書いてきた主人公のなかでは屈託がないほうだと思います。温かい家庭で育って、友達にも恵まれて。それゆえの残酷さみたいなものがあると思うんです。話が通じる相手に囲まれて育ってきたぶん、相容れない人間がいた時、相手と意見をぶつけあう、という経験が極端に不足しているというか。いろんなタイプの人と、いろんなコミュニケーションの取り方をする、という経験値がそんなにないから、意見を違えた時に黙ってしまうタイプです。もともとの性格もあると思いますが、たとえば支配的な親に育てられた子どもが、人の顔色をうかがって黙ってしまう、というのはすごく分かりやすい。でもそうではない場合もあるかなと思ってこうした人物を書きました」
では、松木はどうか。彼視点のパートがあることで、読者は彼が清瀬に言えなかった事情にも納得できるのだが……。
「松木もちょっと、女の人を下に見ているところがあるんです。本人も周囲もそれを自覚してはいないけれど、読者にはそれが感じられるようにしようと意識して書いた気がします」
この小説ではいろんな考えの人を書きたかった、と寺地さん。読み進めるうちに、相反する意見どちらにも納得してしまうところがある。
「ひとつの考え方がすべてのケースに適用できるかというと、そうではないなと思っていて。だから一人の人のなかにも矛盾した考えがいっぱいあるのが自然ですよね。そういうことが書きたかったのかもしれません」
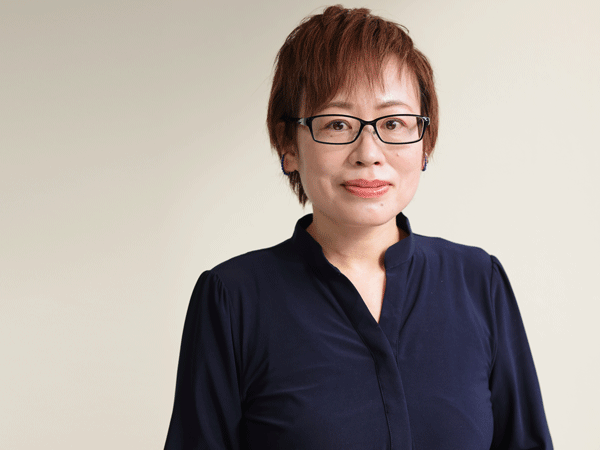
たとえば作中、障害を隠していた人物が、「そのことを知ると相手はただの『障害のある人』っていうカテゴリでしか見なくなる」と語る場面がある。確かに、診断名を知って相手への態度を変えるのはどうなのか、と思わせる。一方、作中に登場する、子どもがディスレクシアだと気づかずにいた母親に対しては、医師に診断してもらっていれば何かが違ったのではないか、と思ってしまう。
「このなかの誰の行動が正解、ということはないんですよね。みんなどこか正解で、どこか間違っている。ディスレクシアの子どもに対して母親が〝できなくてもいいよ〟と否定しなかったのは優しさや愛ではあるけれど、それが正解でもないと私は思うんです。私も〝あなたはあなたのままでいい〟と思いますけれど、でもそれは、何も努力しなくていいよ、ということではない気がする。やっぱり努力は必要で、でもどういう努力が一番いい方法なのかが人によって違う。たとえば字が書けない子でも、書いて覚えるのが向いている子もいれば、それが向いていない子もいるらしいんです。できないならできないままでいい、ではなくて、自分ができる方法を考えよう、というのがいいんじゃないかなと私は思います」
悪気はない人間の独善性への疑問
一方、誰かしらの独善的、あるいは時に無神経な側面がうっすらと見えるところも。たとえば、「女性を守りたい」と言う善良な男性が登場するが、その言葉の裏側にどんな身勝手な思いが潜んでいるのか、後半に辛辣に指摘されていて痛快なほどだ。
「前作『カレーの時間』でも、男は女の人を守るものだと思っている祖父を書いたんですが、読者に伝わらなかったなと思って。あれは読んだ人に、守るってどういうことなのか、なにをもって守っていることになるのか疑問を持ってほしかったんですが、男性読者から〝おじいちゃんカッコいい〟みたいな感想をいただいてしまって。それで今回も、そのことについて書きました」
他には、ある人物がモラハラ男の話を聞いて、「まあなんか、理由があるんやろな、その男にも」と発言して冷ややかな目を向けられる場面がある。
「あれは、ふと思い出したことがあって。知人の女性が仕事の取引先にパワハラみたいなことをされて、別の男の人に〝パワハラじゃないか〟と相談したら、〝パワハラする側にも事情があると思う〟と言われたそうなんです。彼女からその話を聞いて、私は事情があっても駄目なものは駄目でしょう、という話をしました。そこは公平さを発揮しちゃ駄目なんじゃないか、って思うんです。でも、中立で、公平で、両方の立場を汲み取れる人間でありたい人って多いですよね。私もできれば中立な立場の人間でありたいし、どちら側にも事情があるということも分かります。でも、駄目なものは駄目だと言うことも大事。今石を投げられている人に対して、投げる側にも事情があるなんて、そんなこと言ってる場合ではないですから」
書いているのは「結論」ではなく「問い」
登場人物たちのちょっとした言動、ちょっとした会話に心揺さぶられる本作。
「誰かを糾弾するためではないし、こういうやり方がベストだよって書いた本でもないです。みんなそれぞれ、この人はこうでした、というのをひたすら書いた本になったのかな、って思います」
人はひとりひとり違う。人との接し方について、こうすればよい、といった絶対的な法則があればラクだろうが……。
「こういう属性の人にはこうするのが正解、なんてものはないんですよね。やっぱり人と接していると、必ずどこかで相手を傷つけることはあると思う。そういう意味で、加害者になりうる自分に耐えなきゃいけないのかな、って考えたりするんです。私たちは、分からなさとか、失敗するかもしれない不安を、耐えなきゃいけない。だって、分かりやすい属性がない人でも、〝これを言われたら傷つく〟というのは、ひとりひとり持っているじゃないですか。なんの配慮もなく接していいわけじゃないですよね」
人間関係の難しさを改めて感じるわけだが、
「だからといって、〝そんないろいろ考えなきゃいけないなら、何も言えなくなっちゃうよ〟とは言いたくないんです。それって、〝最近はなんでもセクハラだって𠮟られるから、何も言えなくなっちゃうよ〟って言っている人と同じですよね。そんな、なんでも言えるか何も言えないかのどっちかしかないような、ゼロか100かに分かれるものではないと思っています」
人と人とが関わり合うことの難しさを浮かび上がらせつつも、その先の希望を感じさせてくれる本作。
「小説を書き始めた頃は、物語にはある程度の結論みたいなものが必要だと思っていたかもしれません。よく〝作品にこめたメッセージは〟って聞かれますし。だから以前はわりと、結論めいたものをひねり出していたんですけれど、最近は、自分はそういうタイプではないのかも、と思うようになりました。自分が書いているのは答えじゃなくて、問いなんだな、って気づいたんです。きっと、読んだ人の数だけ答えがあるんだろうなって思います」
つまりは読後の感想に、その人自身が表れるということ(もちろん、どんな本でも、それは言えるのだけれども)。あなたはこの作品を読んだ後、どんな思いを抱くだろう。
寺地はるな(てらち・はるな)
1977年佐賀県生まれ。大阪府在住。2014年『ビオレタ』で第4回ポプラ社小説新人賞を受賞し、デビュー。20年度「咲くやこの花賞」文芸その他部門受賞、21年『水を縫う』で第9回河合隼雄物語賞を受賞。著書に『声の在りか』『雨夜の星たち』『ガラスの海を渡る舟』『カレーの時間』などがある。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/浅野 剛)
〈「WEBきらら」2022年12月号掲載〉




