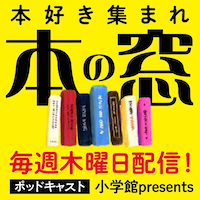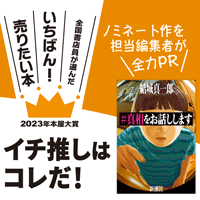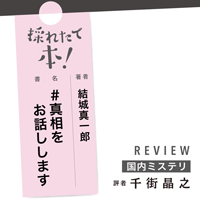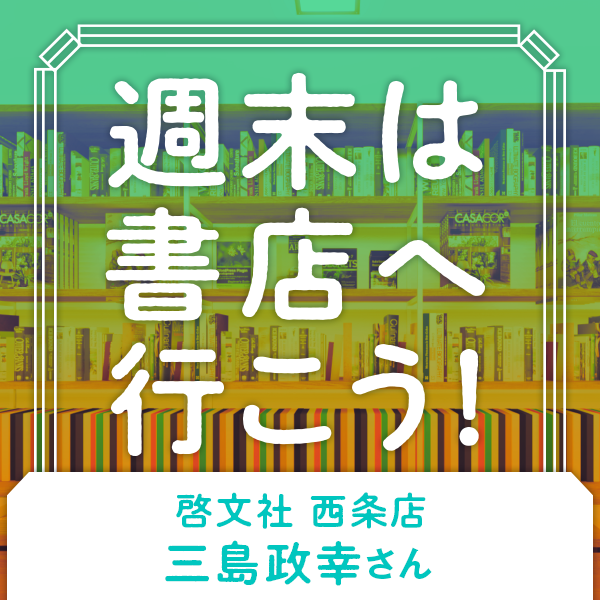結城真一郎さん『どうせ世界は終わるけど』*PickUPインタビュー*

価値観のどんでん返し!
100年後に小惑星が地球に衝突する世界
地球への小惑星の衝突が確実視された世界が舞台。というと終末モノを思い浮かべるが、結城真一郎さんの新作小説『どうせ世界は終わるけど』はちょっと違う。というのも、物語の始まりの段階で、衝突は100年後とされているのだ。近くもなく遠くもない未来の滅亡を心の片隅におきながらの日常は、人々の人生や価値観にどんな影響を与えるのか。これは、そんなドラマを描く連作短篇集だ。
「最初に、編集者さんから〝今までとは違うものをやりましょう〟という提案があったんです。もともと人類滅亡や小惑星衝突といった舞台設定が好きだったので、じゃあそれをやりたいなと思って。ただ、この設定はもうたくさん書かれているので、従来の作品とずらした部分がほしいと思いました。これまでの作品は基本的に、主人公たちが滅亡の当事者になる話が多い。だったらそこをずらせばいいのではないか、と。かといって1000年後と言われても他人事感が強すぎる。自分事と言い切れないけれど他人事として無視するわけにもいかないくらいの設定として、100年後にしました」
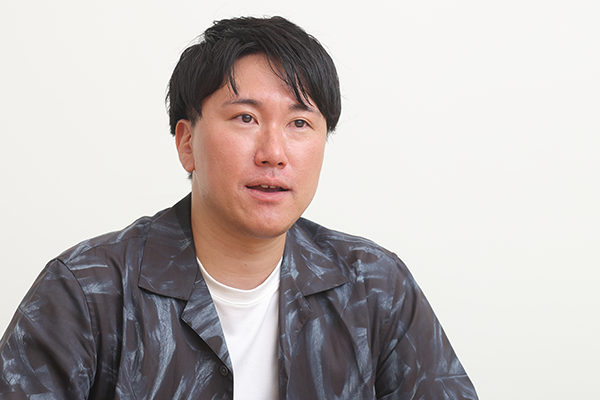
そもそもなぜ人類滅亡や小惑星衝突といった設定に惹かれていたのか。
「僕は『アルマゲドン』や『ディープ・インパクト』といった映画や、伊坂幸太郎さんの『終末のフール』をリアルタイムで楽しんできた世代ですし、やはり単純に、スケールの大きな設定には理由なく惹かれます。それと、4、5歳の頃、いずれ地球や宇宙そのものが滅びるということをすごく考えて、漠然とした虚無感や恐怖で夜眠れなくなる時期がありました。なので、昔から、そういうことに対する興味関心はすごくあったと思います」
謎やひっかかりが用意された群像劇
収録されるのは6篇。各短篇で、少しずつ時代は進んでいく。
「時間が進むにつれ、世の中の状況も少しずつ変わっていくはず。その変化を書こうと思いました。ただ、衝突する時期があまりに近づくと結局当事者の話になってしまうので、100年の期間のすべてを書く必要はないと考えていました」
第一話「たとえ儚い希望でも」は、自殺した女友達・日向の葬式に出席した「私」が、彼女と過ごした高校時代を振り返る話だ。二人が高校1年生の時に人類滅亡の危機が発表されたが、日常は大きく変わらなかった。なにしろ100年後には、同時代のほとんどの人はもう死んでいるのだから。そんな折、「私」は教科書に挟まれた「怪文書」を見つけ、日向に相談したのだった──。「怪文書」の送り主は誰か、4年後になぜ日向は死を選んだのか、複数の謎を含みつつ話は展開する。この第一話で最初に考えたのは、種の存続についてだったという。
「やはり100年後に世界が滅びるとなった時、多くの人がまず向き合うのはその問題だと思いました。そこから発想を広げて、気づいたらこういう話になっていました(笑)」

高校生の話がなぜ種の保存の問題と繫がるのかは、終盤に見えてくる。
第一話だけでなく、本作は全篇、ミステリー的な手法が用いられている。
「なにかしら謎や秘密があって、それがつまびらかになった瞬間にちょっと景色が変わる話を意識していました。やはりミステリーの賞でデビューした人間としては、それは忘れずにいたいんです」
第二話「ヒーローとやらになれるなら」は、就職活動で苦戦する青年、村井が主人公。彼は集団説明会の会場で、高校が一緒だった諏訪部という女性と再会。彼女は、自分にとって村井はヒーローだと言う。しかし彼にはそこまで言われるほどのことをした記憶はなく……。
人々の小さな勇気が連なれば世界だって動かせる、そう素直に信じさせてくれる内容だ。これまでの、痛烈な皮肉が詰まった結城作品とはかなりトーンが違う。分かりやすい表現でいうと、これまでの作品を黒結城とするなら、本書はまさに、白結城。
「今までが黒過ぎたというのはありますね(笑)。これまでと違う作品を書くという約束事があったので、ある程度意図的にこういう話にしました。でも、自分も懐疑的な目で世の中を見てはいますけれど、ここで書いたような世界であってほしい気持ちは根っこにあるんです。その気持ちをそのまま素直に書いたという感じです」
いい話が続くのかと思いきや、第三話「友よ逃げるぞどこまでも」は殺人事件が絡む話だ。厭世的になり独りで生きると決めた男、「私」が暮らす無人島に一人の男がやって来る。二人の奇妙な共同生活が始まるが、ある時「私」は男が刑期満了の前日に脱走した殺人犯、永瀬ではないかと疑い始める。そんな「私」に、彼は自分の正体と事情を明かしたうえで言う。「逃げるのも立派な戦いってことだよ」──一般的によく言われる「逃げずに戦え」とは反対の価値観を示すのだ。
「僕自身は記憶になくて親から聞いた話なんですが、僕が幼稚園生くらいの頃、女の子が泣いていて周りが〝泣かないで〟と言っている時に、僕だけが〝泣きたい時は泣いていいんだ〟みたいなことをその子に言ったそうなんです。親から何度もその話をされて、そういう発想が僕の中にあるんだということが根付いていました(笑)。なので、〝逃げるのも戦いだ〟という発想は僕だけの固有のものではないですけれど、そういう一般的ではない考え方をテーマに一本書こう、というのがこの話の始まりだったと思います」
この話は、男の正体や、彼が「逃げるのも戦い」と言う理由が明かされた後で、さらにちょっとした驚きが待っている。
原体験や心象風景をアレンジ
「今話していて思ったのですが、今回は自分の原体験や心象風景をアレンジした、というのが全篇に共通しているかもしれません」
と、結城さん。では、第四話の「オトナと子供の真ん中で」はどうか。これは小学6年生のサッカー少年、蹴斗がクラスの真面目女子、山路と家出をする小さな冒険譚だ。
「編集者と話していて、子供の目線の話も入れようということになって。それで、子供の頃にしか味わえない一瞬のきらめきや感動みたいなものを心象風景から引っ張ってきた気がします。僕は家出をしたことはないですけれど、近所の下水道を探検したり、雑木林のなかに秘密基地を作ったりしていた時、〝自分はすごいことをしている〟みたいな感覚がありました。大人になった今はもうああいう気持ちを味わうのは不可能なので、それに対する憧憬みたいなものが入っていますね」

蹴斗は、息子がサッカー選手になると信じて疑わず、進路にもあれこれ口を出してくる父親に対して苛立っている。
「これも半分実体験です。小学生の頃、僕は水泳選手になりたかったんですけれど、親に中学受験をしろと言われ塾通いを強いられたんです。その選択が間違っていたと思わないですし、親に感謝はしていますが、当時は親の意向で自分の進路が捻じ曲げられたような気がしていました。この短篇はその状況を若干入れ替えた形です」
ちなみにこの第四話では、小惑星衝突は80年後に迫っている。クラスで卒業制作にタイムカプセルを作ろうという話になった時、山路のとある発言で教室が微妙な空気になるのがこの世界ならでは。
「この小説の世界においてはたぶん、それまで当たり前にやっていたのに、だんだん〝それはやるべきでない〟という論調になってくるものが出てくる。第四話の時点でタイムカプセルはギリギリのラインかなという気がします」
他にも、少しずつ時代の流れを感じさせる変化が描かれていく。そして迎える第五話「極秘任務を遂げるべく」は、親子の話だ。主人公の「俺」は、離婚した元妻と暮らす小学3年生の娘から「パパは宇宙飛行士」だと勘違いされている。娘を落胆させたくなくてその話に乗っかり、隕石を粉砕する極秘任務に就いていると噓をついた「俺」だったが、娘がそのことを作文に書くと言い出して大慌てする。
「僕は漫画『宇宙兄弟』の大ファンなんです。今回のこの小説の世界では宇宙飛行士の選抜基準ってどうなるだろう、と考えたところから着想しました。この父親の心配事のように、人類滅亡と比べたら小さなことかもしれないけれど当事者にとっては大問題という場合はある、ということも考えていました。それと、こういう世界だからこそ主人公が一歩踏み出す、という話を書きたかったんです」
いちばん書きたかった一言
第六話「どうせ世界は終わるけど」は、母親の話。小学生の息子が学校に行かなくなり、日中どこかに出掛けるようになって一週間。ある日、彼の後をつけてみると……。
この最終話では、これまでの話の重要人物たちが姿を見せる。
「他の話の登場人物が最後になんらかの形で関わってくることは決めていました。それぞれが生きてきた何年間かの足跡がちょっとだけ見える形にしたかったんです」

その楽しみを持たせつつ、息子の行動の謎や、親子関係の背景でも読ませる。終盤の母子の会話のなかで、『どうせ世界は終わるから、好きに生きたほうがいい』という言葉に対して息子が発する疑問にははっとさせられる。
「最終話では、ミステリー的などんでん返しではないけれども、ある種価値観のどんでん返しみたいなことがやりたかったんです。それがあの一言であり、たぶん自分がいちばん言いたかったことかなと思います。今回書きながら気づいたのは、100年後に滅びる世界と今自分たちが生きている世界はそんなに変わらない、ということでした。我々の世界は100年後に滅びるとは宣告されていないけれど、先行きに対する不透明感や閉塞感があるし、結局みんな死ぬのは間違いないじゃないですか。その発想からたどり着いたのが、あの言葉だった気がします」
息子が放つ一言は、表面的にきれいにまとまった表現の穴をついてくる。しかしそれは皮肉や絶望を感じさせるものではない。その前向きな価値観の反転は、きっと読み手の心にも響いてくるはず。
「今この世界を生きる人にとっても、一歩踏み出す後押しになる話にしたかったし、そうなっていたらいいなと思います。今回、いろんな境遇の人やいろんなエピソードを書いたので、どの話も自分にはまるで関係ないです、という人はたぶん一人もいないと僕は思っています。今この時代を生きている人たちに向けた話だということは、これまで書いてきた小説と変わりません」
結城真一郎(ゆうき・しんいちろう)
1991年神奈川県生まれ。東京大学法学部卒業。2018年『名もなき星の哀歌』で第5回新潮ミステリー大賞を受賞しデビュー。2021年「#拡散希望」で第74回日本推理作家協会賞〈短編部門〉を受賞。同作を収録した短編集『#真相をお話しします』がベストセラーに。その他の著書に『プロジェクト・インソムニア』『救国ゲーム』『難問の多い料理店』がある。