『平場の月』の著者 朝倉かすみおすすめ4選

2019年、『平場の月』で第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞候補にもなった朝倉かすみは、若くはない人たちの結婚生活や恋愛の諸相を描いた小説で知られています。そんな著者のおすすめ小説を紹介します。
『夫婦一年生』結婚一年目は夫婦にとっての正念場
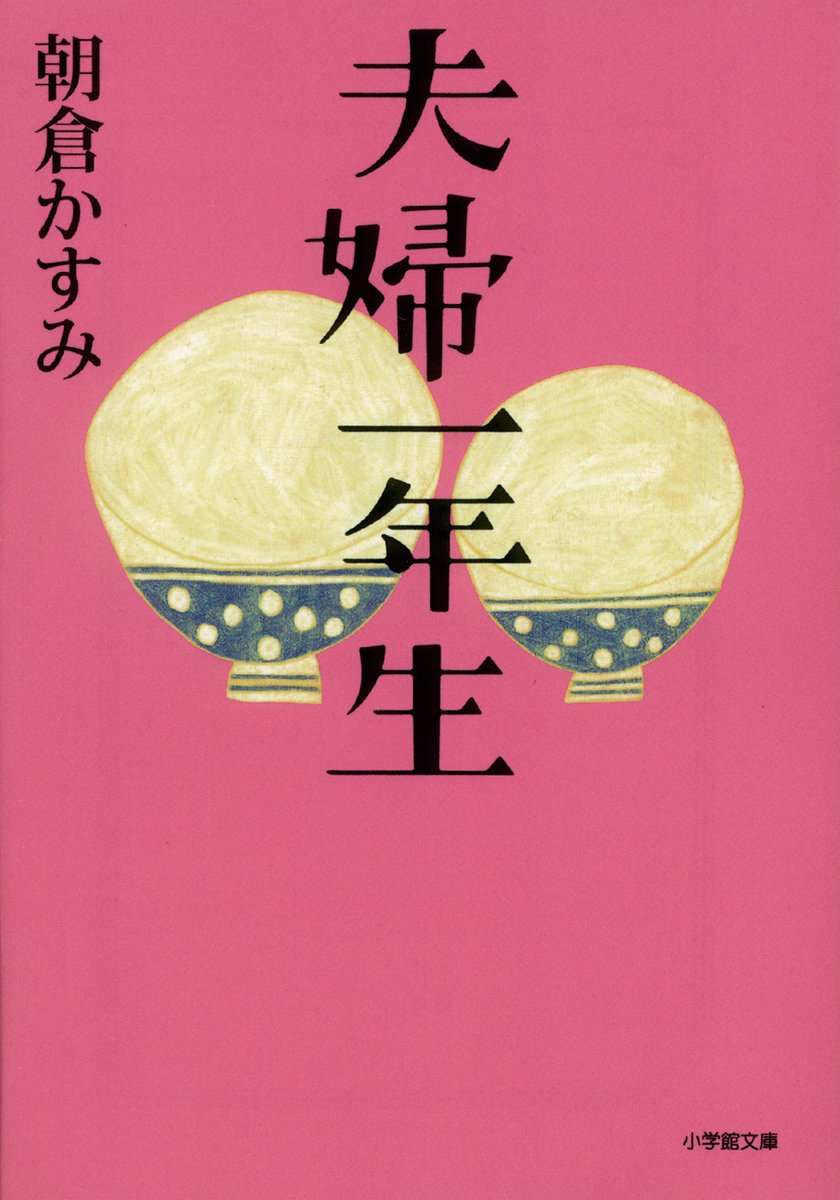
https://www.amazon.co.jp/dp/4094084932
32歳の
結婚前に心に誓ったことがあった。
仕事から帰ってきたばかりの朔郎に機関銃のように話しかけない。
会社員だった頃、青葉が母にやられて難儀した事柄だった。帰宅するやいなや、母は青葉に「きょうの1日のできごと」を迂遠 かつ脈絡なく話しかけてきた。空腹だし疲れているし、青葉は相槌を打つのも億劫 だった。青葉にしてみれば、お座敷が2度かかったようなものである。会社お座敷では、気に入らないことがあってもぐっと堪えて愛想よくするし、しなくちゃいけない。ひと息つけるはずの自宅でも愛想をもとめられるのは勘弁してもらいたかった。
しかし、札幌に友人がなく、仕事もしていない青葉は、日中は話し相手がいません。最初の誓いも虚しく、夫に話を聞いてもらいたい寂しさを持て余しています。
他に、新婚の人にとっての「あるある」がコミカルに描かれます。結婚祝いをくれた人たちへ、新婚旅行の土産を買う際に、高価なものをくれた人にはそれ相応の品をお返しするとして、どう見ても贈り手の自己満足としか思えない縄文土器のような壺をくれた人へのお返しは、どの程度のものにするのか、とか、料理が苦手な青葉の作った夕飯に対して、夫が「心がこもっている」と誉めるときは、「美味しくない」の婉曲表現で、上司が部下をおだててから注意事項を切り出すという常套手段に似て、かえって苛立つ、などです。
青葉は、主婦の近所付き合いにも戸惑います。おすそ分けをする際、ブランド物の袋に入れて持ってくる見栄っ張りの主婦がいて、彼女は、相手によって袋のランクを使い分けており、隣家にはシャネルの袋なのに、うちはGAPの袋だから軽く見られている、などと青葉が言い募っても、それは夫には勘弁してほしい、女の世界の悩みだったりします。
小さな諍いはあっても、おおむね順調だった夫婦生活ですが、新婚数カ月のときに、ついに青葉の堪忍袋の緒が切れます。それは、朔郎の両親が札幌に泊りがけで遊びに来るということで、朔郎はそのことを急に言い出し、色々と準備に追われる青葉に、「普通でいいよ」言い放ったこと。嫁として「普通で」いられるはずなどないのに、夫は何も分かっていない様子です。
(朔郎父母とは)両家顔合わせの食事会の前に、挨拶に伺ったのが最初だった。自分でいうのも面映ゆいが、好印象をあたえたはずだ。青葉は、そもそも、ひとに対して自ら好かれに行くタイプではない。好くも嫌うも向こうの勝手、と思っている。「勝手」は「自由」といい換えたほうが当たりはきっと柔らかだ。けれども、青葉は「勝手」のほうを使いたい。なぜなら、こちらが相手を好いたり嫌ったりするのは、こちらの勝手であるからだ。そこに「自由」ということばを使用すると話がややこしくなる気がする。うまくいえないが、正当化される感じがするのだ。青葉はべつに自分の気持ちを正当化しなくてもいい。「勝手」で充分だ。しかし、朔郎父母には好かれたかったし、青葉もかれらを好きになりたかった。
青葉は少ない準備期間で、無事、朔郎の両親をもてなせるのか、そして夫婦仲は修復できるのでしょうか。
『幸福な日々があります』教授夫人の生活に息苦しさを感じた46歳の女性が、夫と別居を決意

https://www.amazon.co.jp/dp/4087453480/
別れたい妻に対し、理由を問う夫。稼ぎがよく穏やかな夫に非はありません。離婚したい確たる理由を言えない森子は不利ですが、言葉にできない心の澱が沈殿しています。それは例えば、次のようなことです。
夜のニュース番組を一緒に観る。モーちゃん(夫)はコメンテーターの言を、自分の意見をまじえてわたしに解説してくれた。モーちゃんの説明を聞いているうち、見通しがよくなったような気がした。あくまでも「ような気がした」だけだ。見通しがよくなった、と言い切ってしまうと、わたしはモーちゃんと同じまなざしで世の中を見ていることになる。夫のまなざしで世のなかの大事を見る妻に育っていくのには抵抗があった。わたしの理想は、夫婦それぞれの目で物事を見て、それぞれの頭で考えた意見が、期せずして一致する、という状態だ。(中略)うまくいえないけれども、ふたりでテレビを観ることも、わたしにとっては夕ごはんを作ったり洗い物をしたりするのと似たようなものだと感じる部分があった。仕事とまではいかないけれど、それに準ずる感じがどうもするようなのだった。
2人は、しばらく別居して冷却期間を置くことを決めます。森子は、風呂なしの安アパートを借りて掃除婦のパートを始めることに。祐一は自分が恥をかかされたと言うのに反し、森子は、くたくたになるまで身体を動かしてぐっすり眠れる毎日が心地よく、家事も自分1人のためなら手抜きもでき、自分はこういう暮らしがしたかったのだと気付きます。
そんな折、祐一の姪の結婚式があり、祐一側の親族には別居のことを知らせていないため、森子は、「夫婦然」として出席してほしいと頼まれます。仲睦まじい夫婦を演じることで、仲はもとに戻るのか、それとも……。
長年一緒に暮らした配偶者に対する、入り組んだ微妙な感情を描いた1冊です。
『平場の月』人生の悲喜こもごもを経験した50代の元同級生の恋愛の行方とは

https://www.amazon.co.jp/dp/4334792650/
青砥の内側で、須藤は損なわれなかった。それが愉快だった。どんな話を聞いても、そこにどんな須藤があらわれても、損なわれないと思った。
若い頃の恋愛は、相手によい面を見せようと見栄をはりがちですが、50年生きて、青砥自身もそれなりにいろいろな経験をしたので、かつて憧れていた須藤の負の面を知ってもそれで相手に幻滅することはありません。ふたりは、時々会って食事をする仲になります。青砥は年収350万円弱、須藤は200万円に遠く届かないという「平場の庶民」である「元男子」と「元女子」は、いつも外食というわけにもいかず、ある日、須藤は、自分のアパートで「家飲み」しようと誘います。「もういい大人なんだからいいじゃない」と言う須藤に対し、「分別のある大人だからこそ、そういうことはしたくない」と言う青砥。ただし、須藤の言う「家飲み」はその言葉以上の意味はなく、先回りして淡い期待を抱いていた青砥は肩透かしを食らう羽目に。この辺りのやりとりは、初々しく微笑ましいものです。
ある時、青砥は、内視鏡検査を受けた須藤から、進行性の大腸がんだと告白されます。
がんについて、須藤は全部を言っていない感触があった。核心をはぐらかされているようで、もどかしかった。言わないから訊けないのか。訊かないから言えないのか。青砥が須藤と親友だったら、たぶん、こうではなかっただろう。恋人同士でも、こうではないはずだ。この関係をどう扱っていいのか、どう名付けたらいいのか、棚上げしているうちに、須藤を大事に思うきもちのカサが増えていった。
手術を受け、人工肛門をつけた須藤は、あっけらかんとそのことを話します。若いときなら異性にするのはためらうような話もでき、互いの弱みもさらけ出せるようになるのは、年齢を重ねることのよい面かもしれません。けれど、互いの人生が抱えているものの重みを考えれば、若い頃のように気持ちだけで突っ走れないのも事実。金銭面の問題もあります。手術に際し、生活保護を受けるか妹から借金するか悩む須藤に、自分も人に援助できるほど余裕がないことに忸怩たる思いを抱く青砥。
病は、2人の関係にどのような変化をもたらすのでしょうか。
『静かにしないさい、でないと』「普通」という言葉の持つ暴力性

https://www.amazon.co.jp/dp/4087468836/
内海さんは個人的に普通をFと呼んでいる。内海さんは「普通」という言葉が大大大嫌いだ。大多数という状態にあぐらをかいて、いいたい放題いえ、やりたい放題やれるF者たちには
端倪 すべからざるものがあり、瞠目 に値すると手持ちの難しい慣用句を用いて皮肉る。内海さんだって見かけが(せめて)Fゾーンに入っていたとしたら、B(ブスのこと)にたいそう親切そうに振る舞える。あなたが思うほど傍はあなたの容姿を気にしていないとか、一生食べられる資格を取ったらどうだと助言を連発できる。陰で嗤うこともできる。
内海は、ある人との出会いを機に、「Fゾーン」入りを果たすべく、美容整形外科で「ボツリヌス・トキシン」を注入し、ワキガを治そうと思い立ちます。
内海とは反対に、自分が普通であることに悩む女性も登場します。三姉妹の長女である彼女は、世話のかかる妹たちに比べ、成績も容姿も何もかもが平凡であったため、両親から見過ごされがちで、「普通」という呪縛から抜け出したいと願っています。
私たちが何気なく使っている「普通」という言葉に傷つく人がいることを思い知らされる短編集です。
おわりに
大人になれば達観していろいろなことを見られるようになると、若い頃は思うものです。けれど、実際その年齢になってみると、あまり進歩がなく、同じようなことで傷つき悩んだりする自分がいます。これは、多くの人が実感することではないでしょうか。朝倉かすみは、そうした人々のありようを肯定し、愛おしさを込めて描く作家です。その小説は、きっと読者の心に寄り添ってくれるでしょう。
初出:P+D MAGAZINE(2022/06/09)

