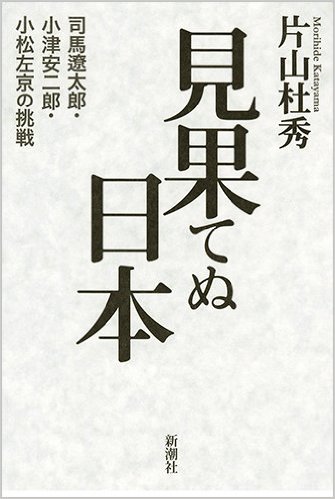『見果てぬ日本 司馬遼太郎・小津安二郎・小松左京の挑戦』
平山周吉●雑文家
持たざる国が陥っている泥沼に一条の光
見果てぬ日本 司馬遼太郎・小津安二郎・小松左京の挑戦
片山杜秀著
新潮社 1800円+税
装丁/新潮社装幀室
原節子が亡くなった年に、その「父親」笠智衆の存在を通して「日本」を考える、示唆に富む名著が出現した。
片山杜秀の『見果てぬ日本』は、といって別に映画の本というわけではない。「持たざる国」日本が陥っている終わりなき泥沼に、一条の光を見つけようという積極果敢な試みである。SFの小松左京、歴史小説の司馬太郎、映画の小津安二郎、この三人を読み解くことで、昭和から平成の日本の困難が徐々に明らかになってゆく。その手際はスリリングにして、構想力にれ、語りはエネルギッシュである。
ハイリスク(核分裂型原発)を引き受けて、万博的未来を創出しようと決断した小松。豊葦原瑞穂国の農民気質を騎馬民族と海人のロマンで挟み撃ちする司馬。そして何よりも、支那事変に召集され、大陸での二年間の軍隊生活から、ぎりぎりのところで現われる「本物の人間だけを描こうとする映画作り」をした小津。その小津にとって、自作の画面に欠かせない人物として浮上したのが笠智衆だった。
貧弱な肉体の日本兵がなぜ世界で一番強いのか。一挙手一投足にも無駄を省き、体力を温存し、いつ来るかわからない決戦に備える。無愛想で、不器用で、ぶっきらぼうで、何かに耐えている。それでいて魅力的な人間が笠智衆だった。「日本という国全体の体力不足」に見合う人物像が小津にはどうしても必要だったのだ。非常時にも、平時にも。
小松と司馬は、希望の出口を未来と過去にそれぞれ求めた。その果敢で壮大な文明論は魅力的であるがゆえに、隘路につきあたる。「出口なし」の大前提を引き受ける小津=笠智衆の「省力法」にこそ、かぼそい突破口がある。著者はそう語っている。
小津だけでなく、司馬も小松も戦争体験を深化させることで、各人の世界を築けた。ちゃらい平和観や戦争論が跋する平成日本で、そうした強な思考を生むのは、それ以上に細い道である。
(週刊ポスト2016年1.1/8号より)
初出:P+D MAGAZINE(2016/01/13)