【著者インタビュー】原 尞『それまでの明日』
「ハードボイルドとは何か」を日々問い続け、14年ぶりに待望の長編小説『それまでの明日』を上梓した、直木賞作家・原尞氏にインタビュー!
【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】
14年ぶりに沢崎が帰ってきた! 真のハードボイルドに挑み続ける直木賞作家、渾身の一作
『それまでの明日』
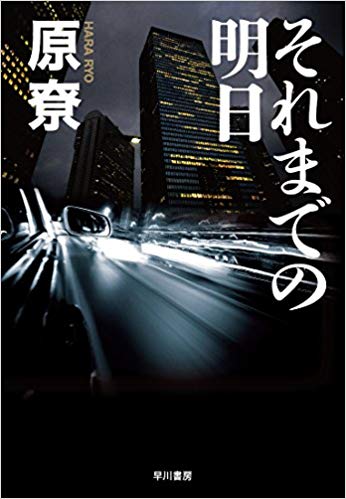
早川書房 1800円+税
装丁/早川書房デザイン室
原 尞

●はら・りょう 1946年佐賀県生まれ。九州大学文学部美学美術史科卒。フリージャズピアニストや脚本執筆等を経て、88年『そして夜は甦る』でデビュー。「素人が送りつけたこの作品を見出してくれたのが菅野編集長でした」。89年、沢崎シリーズ第2作『私が殺した少女』で直木賞、91年に初短編集『天使たちの探偵』で日本冒険小説協会大賞最優秀短編賞。本書は95年『さらば長き眠り』、04年『愚か者死すべし』に続く長編第5作。鳥栖在住。167㌢、54㌔、B型。
僕の頭の中の主人公には顔すらなく、彼が人や世の中を見る視線だけがある
西新宿の外れで探偵業を営む、〈沢崎〉の初登場から30年。このほど14年ぶりの最新作 『それまでの明日』を上梓した原尞氏(71)は、大のチャンドラー好きにして、寡作の人でもある。
「先日もサイン会で年輩の読者から釘を刺されました。『次作も14年後なら、さすがに僕は生きてないよ』って(笑い)。お待たせして申し訳ないとは思う一方、男の美学とか建前に留まらない本当に面白いハードボイルドを書くには、14年はギリギリ常識の範囲内とも思う。チャンドラーも確か、長編は7作だけですしね」
物語は、金融会社〈ミレニアム・ファイナンス〉の新宿支店長を名乗る依頼人〈望月皓一〉が忽然と姿を消し、彼が調査を依頼した赤坂の料亭〈業平〉の女将〈平岡静子〉も既に故人であることが判明するなど、のっけから不穏な気配が。しかも本書は「ハードボイルドとは何か」を日々問い続ける作家の、14年を費やした一つの答えでもあった。
*
著作は88年のデビュー作『そして夜は甦る』以来、僅かに6作。前作『愚か者死すべし』以降をシリーズ第2期と位置づけ、「謎解きよりハードボイルド重視」の姿勢を打ちだした原氏を、佐賀県鳥栖市で兄が営むジャズバー、「コルトレーン・コルトレーン」に訪ねた。
「僕がどうも違和感があるのが、推理物の主人公が終盤になると必ず名探偵に変身すること。謎を複雑にすればするほど、名探偵度も上がってしまうんです。
例えば『長いお別れ』の面白さが、事件や謎解きより、主人公の言動にあるように、僕はハードボイルドの神髄は難問に答え続ける姿勢にあると思う。つまり誰のいかなる問いにも真摯に応え、常に最善を尽くす姿勢がその小説をハードボイルドたらしめるとすれば、沢崎に天才性は必要ないんです。むしろ僕は彼を非常識なほど普通な男として描いている。デビュー以来そんな私の背中を押してくださった今は亡き早川書房の菅野圀彦編集長に、本書は捧げた作品でもあります」
ここ〈渡辺探偵事務所〉の元経営者を看取り、看板を継いだ沢崎の許に、〈紳士〉な依頼人・望月が訪ねてきたのはある年の11月。彼は融資を検討中だという老舗料亭の女将の調査を依頼し、自宅の電話番号を書いた名刺と着手金30万円を置いていった。
が、調査を始めて程なく当の女将はとうに死亡し、融資の予定自体ないことが判明。しかも望月とは一向に連絡がつかず、やむなく勤務先を訪ねた矢先、事件は起きる。銃を持った2人組によるサラ金強盗である。
「実は構想に唯一初めからあったのがこの強盗事件で、そこで沢崎ではなく、別の人物を活躍させたら面白いというのが出発点でした。
ヒントになったのはギャビン・ライアルのマクシム少佐シリーズ。砂漠に取り残された戦車の奪還作戦でも彼は戦車の専門家じゃないから後ろで最小限の指示を出す、その出し方が絶妙なんですよ。僕は読者としての経験は誰にも負けない自信があるし、その経験を有効活用するのが僕なりの書き方なので」
本書の沢崎は得意の減らず口(!) で邪魔ばかりし、代わりに危機を凌ぐのが、求職者と企業をITで繋ぐ若き起業家だ。取引相手の望月の留守を待つ間、人質に取られた〈海津〉である。
「『長いお別れ』にもレノックスという相棒が出てくるでしょう。まあ彼の場合は大酒呑みで困った男だけど、外見も中身も〈ハンサム〉としか言い様のない好青年海津と、携帯すら持たない50代の沢崎が組むことで、思いもしない展開が生まれた。僕自身、最後の一行までどう転ぶかわからない小説が好みでもあるし、果たしてそれがハードボイルドたりうるか、自分でも書き終えてみるまでわからないところがあるんです」
一行一行手探りで書くしかない
以来、海津は沢崎を慕うようになるが、望月は依然消息不明。さらには新宿支店の金庫で見たあるはずのない大金の正体や、沢崎と因縁の深い暴力団〈清和会〉の影など、複雑に絡む糸は後半もなお、ほどける兆し一つ見せない。
また新宿署の天敵〈錦織〉らとの丁々発止は本作でも健在。「会話=ハードボイルドの神髄」をまさに地でゆく沢崎は、暴力を憎み、寡黙に見せて実は面倒見の良いところも魅力の一つだ。
「彼の場合、唯一の武器は減らず口だったりしますし、個人的にはある書店員さんの『一々面倒臭いオヤジだ』という意見に感心しました。確かに殴るより言葉で切り返す方が手間もかかる。その方が会話的には豊かになるとはいえ、面白いこと言うなあと思って(笑い)。
ただし僕自身は彼にやりこめられる側に近く、自分の対極にいる沢崎がどんな人間かを知りたくて、彼の物語を書いてきました。そもそも一人称の主人公が自ら魅力を語るはずもなく、僕の頭の中の沢崎には顔すらない。あるのは彼が人や世の中を見る視線だけ。沢崎ならこう言わないとか、わからないものを一行一行、手探りで書くしかないから、面白くてやめられないんです」
誰に対してもフェアで、よくも悪くも言葉を尽くす普通の男がこうも格好よく映るのは、効率や結論ばかりを求めがちな時代のせいか。表題の「それまで」が何を示すかはラストに譲るとして、鮮やかな謎解きもどんでん返しもない代わりに、彼の愚直なまでの率直さが残像を刻み、書き手の思いすら代弁する、一行一行を噛みしめて読みたい、ザ・ハードボイルドである。
●構成/橋本紀子
●撮影/国府田利光
(週刊ポスト 2018年4.13号より)
初出:P+D MAGAZINE(2018/08/09)

